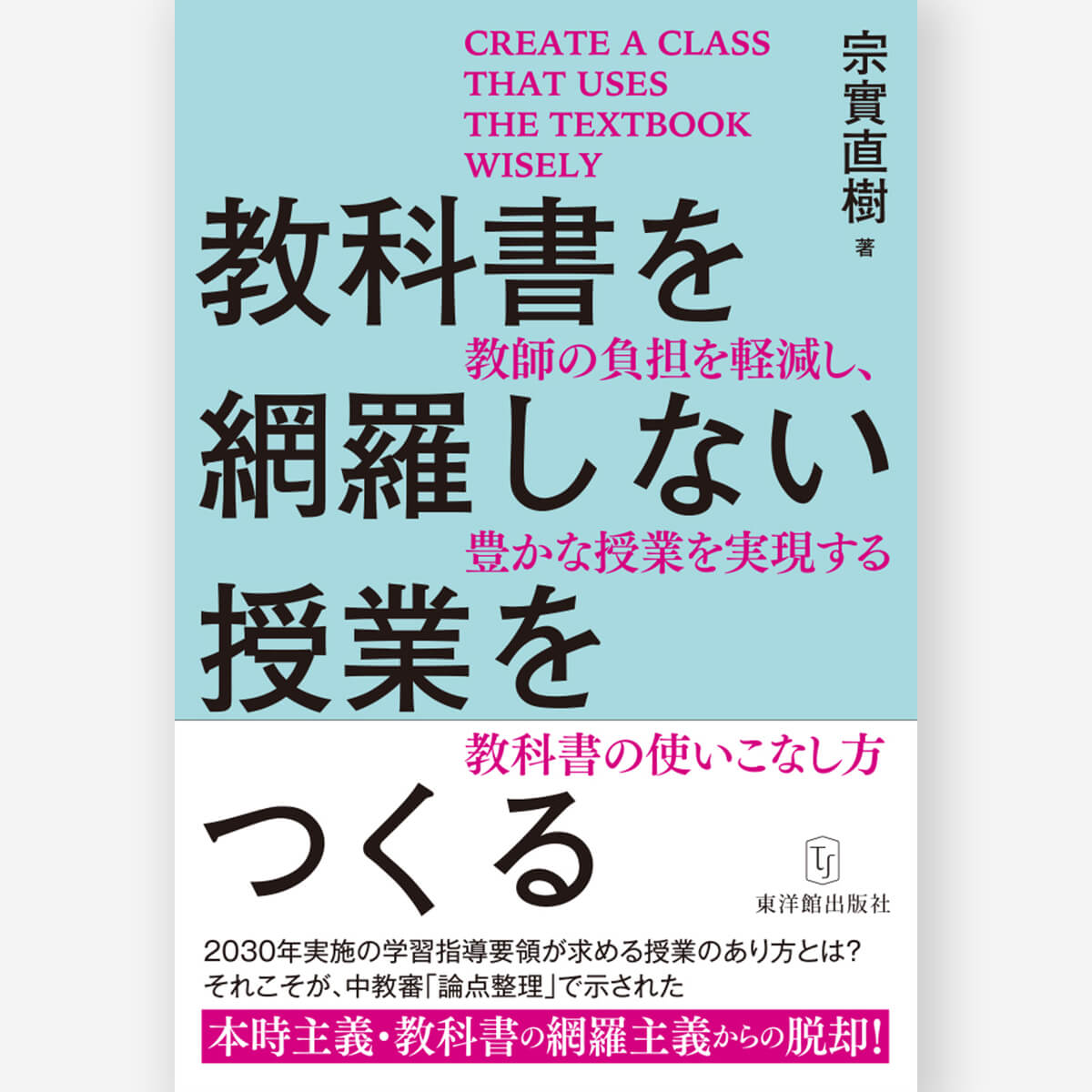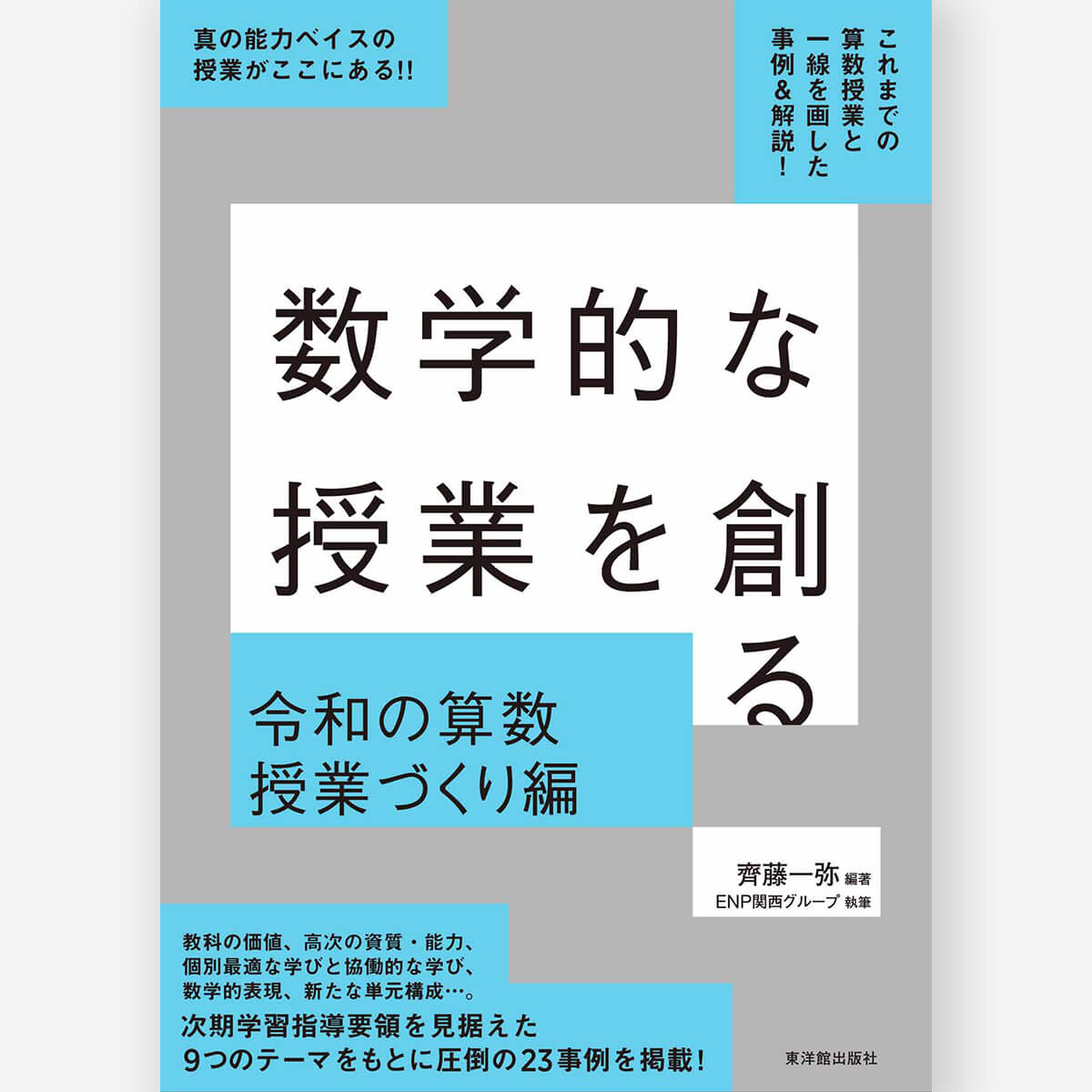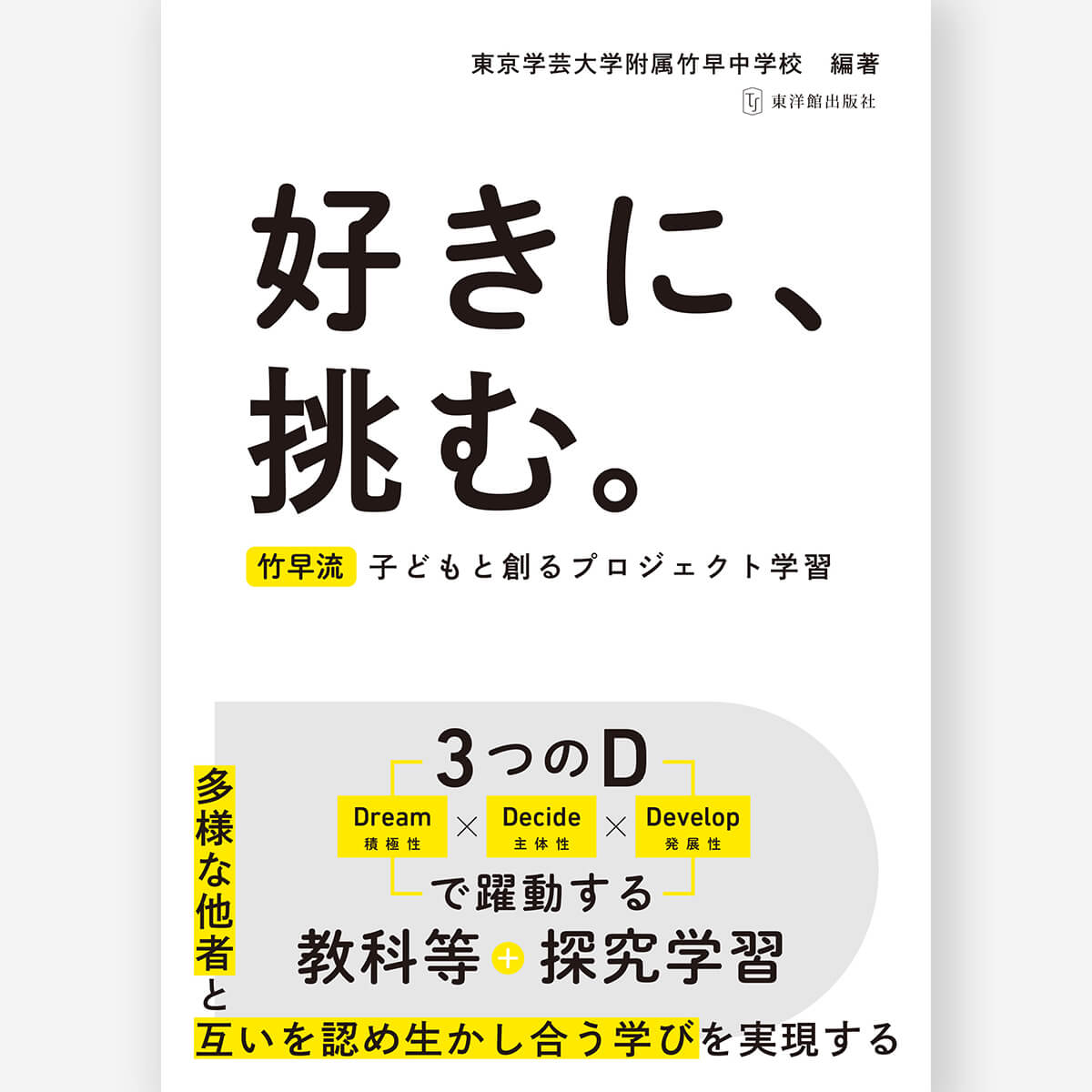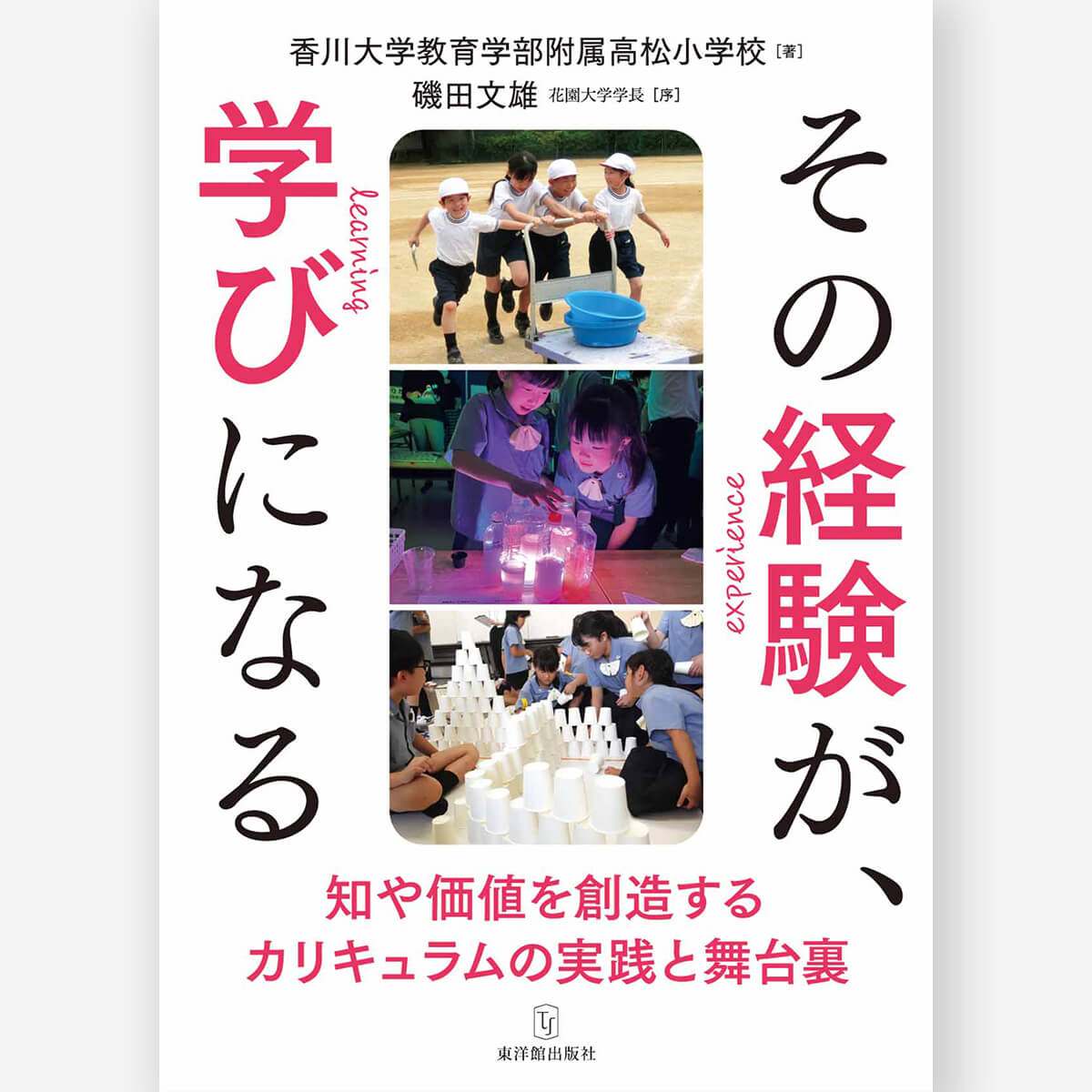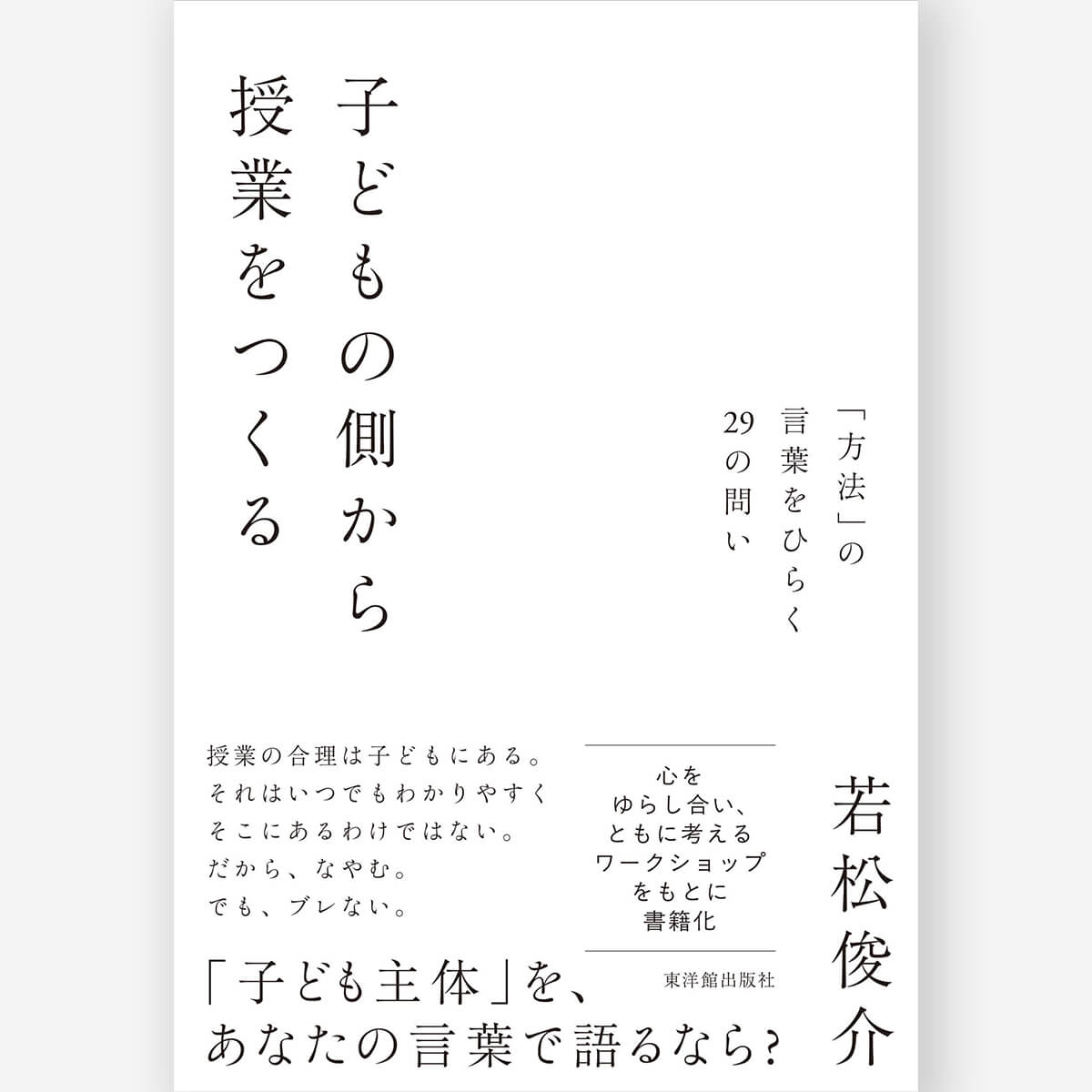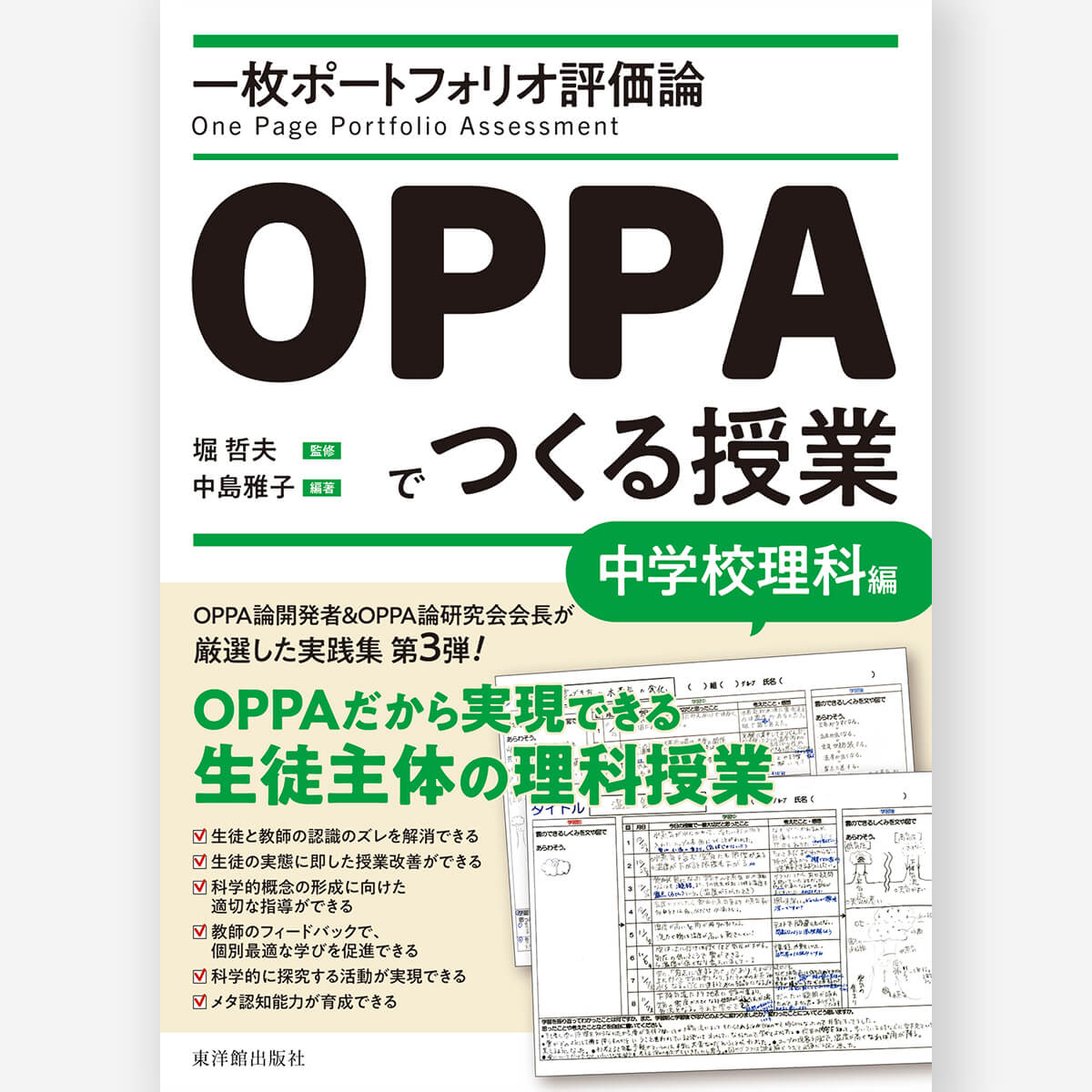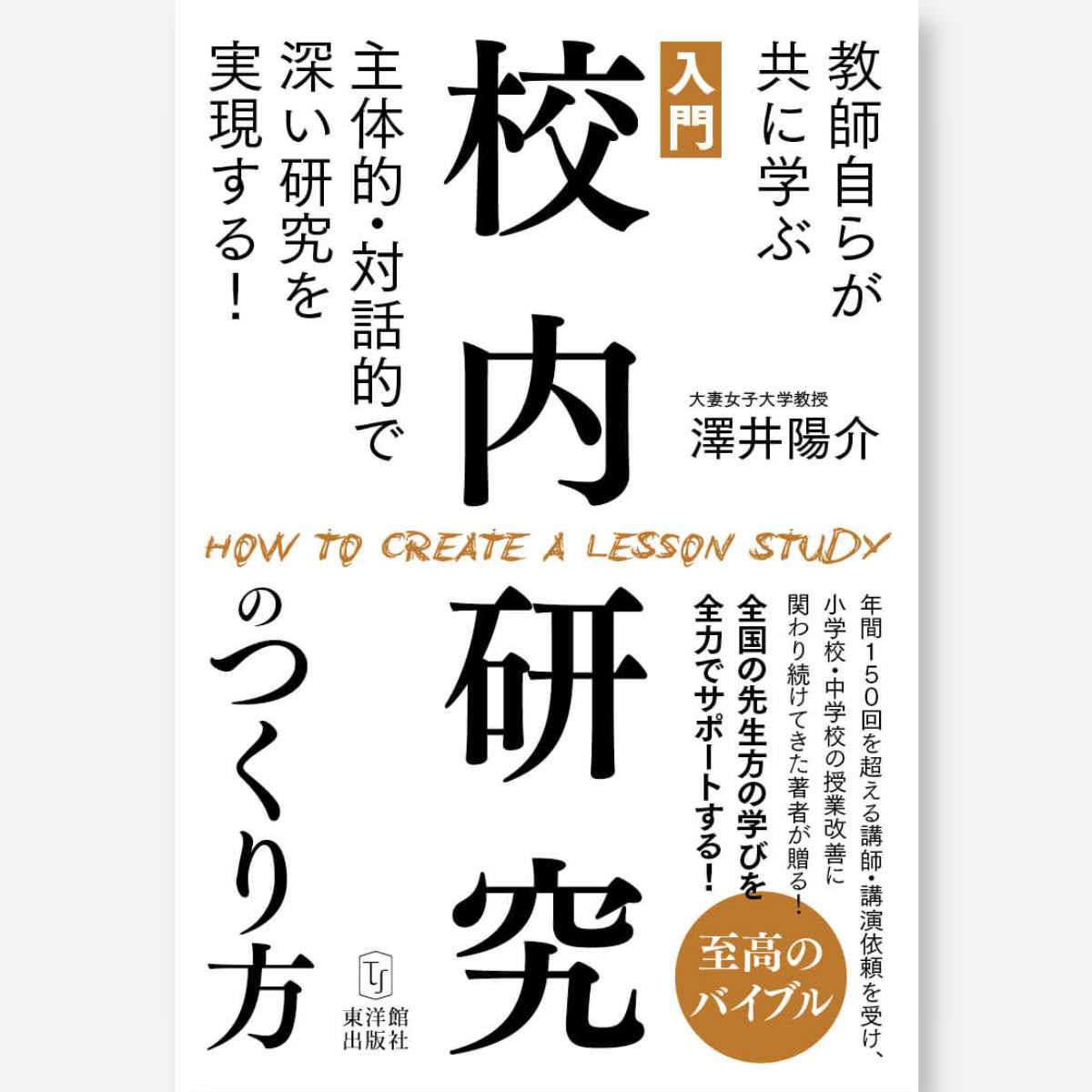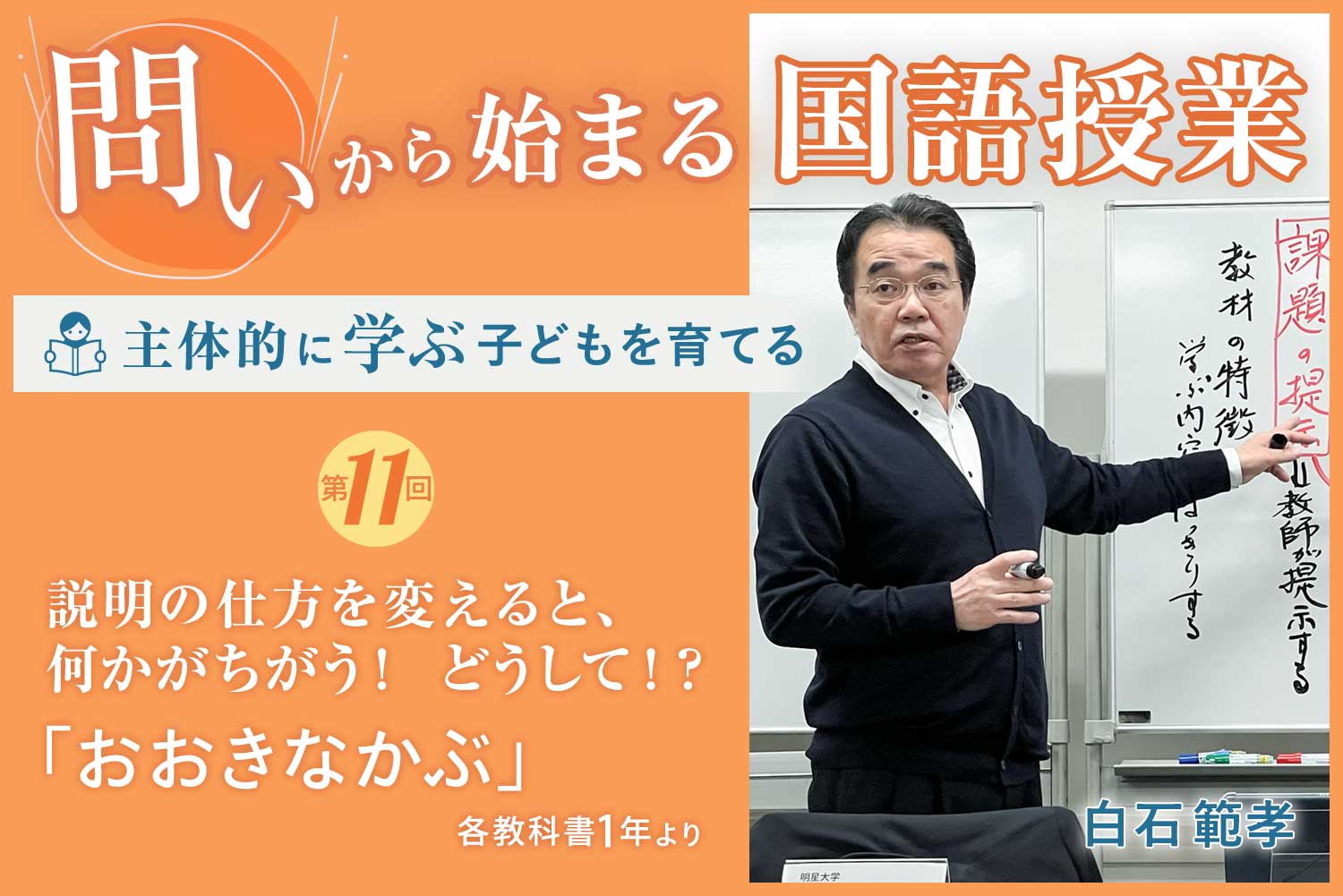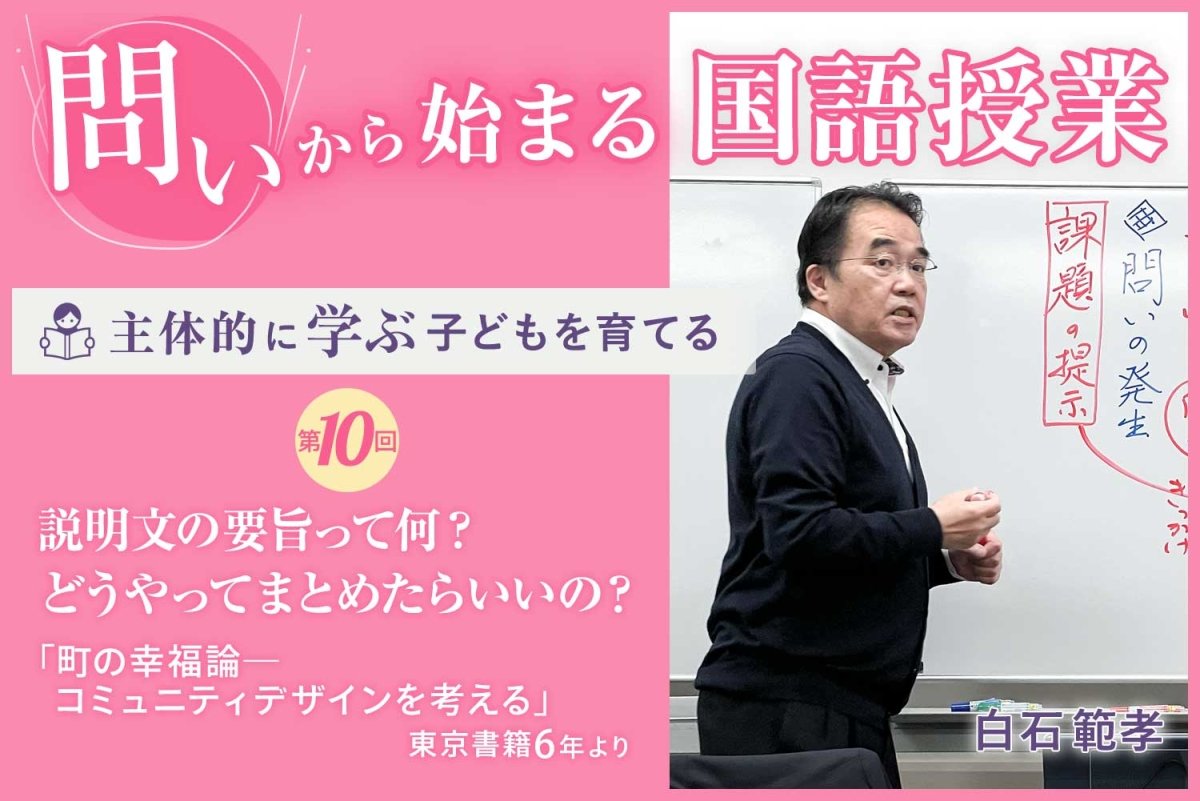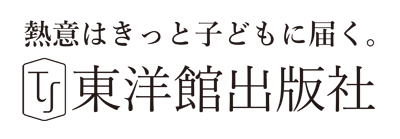〈 鹿毛雅治先生インタビュー 後編 〉連載第7回目は、鹿毛雅治先生へのインタビュー後編をお届け。前編は、子どもたちを見取る上で、「ポイントを求めるのではなく教師のスタンスが大切」というお話で終わりました。
後編では、子どもたちが生き生きと学ぶための教師サイドの「スタンス」について深掘りし、「居方」や「構え」、それを意識するための授業研究の在り方、教師自身の学び方に焦点化していきます。
マインドレスとマインドフルネス
近年流行している「マインドフルネス」というのは、瞑想法のような形で広まっていますがもともとの発想としては、実は心理学に基盤があって、「注意の向け方」の話なんです。注意の向け方として、「マインドフル」と「マインドレス」の両方があって、どちらも注意を向けている状態であって、決して「無」の状態ではないんです。「今ここで何が起こっているか」に注意を向けることが、マインドフルな状態ですよね。それに対して、「今ここ」よりも、何らかの「あるべき姿」だとか、「こうしなきゃいけない」だとか、そういったとらわれや観念を前提にして今に向き合っているのが、マインドレスな状態です。 ですので、我々の日常生活は、いつもマインドフルというわけではないんです。例えば朝、車で通勤している人は、運転している最中、「今日はあれをしなきゃいけないな」などと「今ここにないこと」についてあれこれ考えてしまうでしょう。「今ここ」に目を向けるなら、例えば「木々がちょっと色づいてきたな」と秋を感じたり、ちょっと窓開けてみると「風が涼しくなってきたな」とか、そういった「今ここ」に、注意を向けるメンタリティーになりますよね。同じ車を運転しているときであっても、注意の向け方として精神衛生上は、マインドフルであったほうがいいということなんですよね。「1日何分瞑想しなさい」ということよりも、基本的にはそういった、注意の向け方に関する心理学的な発想なんですよ。 この話は、教師にも言えることなんじゃないかと僕は思っています。教育目標があるがゆえに、教育評価の枠組みが常に頭の中にあって、「この子はさぼっているんじゃないか」などと思ってしまい、授業において教師がマインドレスな状態になってしまっている。 マインドフルな状態はその逆で、「この子は今、何をしようとしているのかな」と、その子の「今ここ」に注意を向けることです。評価の枠組みによってその子を見ると「良い」「悪い」で判断しがちになる。そういった固定観念を取り払ったときに初めて、「子どもに向き合っている」というメンタリティーになるのではないでしょうか。 もちろん、これを言うのは簡単なんだけれど、とても難しいことですよね。実際問題、授業には「ねらい」がありますからね。ですから、マインドフルとマインドレスの両方が教師に必要なわけですが、これまであまりにもマインドレスな状態が良しとされ、全てが語られすぎてきた。学習指導案もその代表でしょうが、常に「目標」を念頭に置いて、今を見なくてはいけなかった。けれど、子どもの人生の「今ここ」は目標のために存在しているわけではないし、それじゃあ子どもにとっても窮屈です。先生方が少しでもマインドフルな気持ちをもっていれば、先生も子どもに「共感」をしながら、教室で突発的に起こる事柄を、みんなで一緒に笑ったり、不思議がったりできる。そんなふうに授業を過ごせるようになれば、それはみんなにとって楽しいことですし、ひいては先生のメンタルヘルス上も好影響でしょう。
プロの教師として、子どもと共に居合わせる以上は、マインドレス的な要素としての「先を見通す」ことも必要ですがそれを当たり前とするのではなく、授業における「教師の“居方”」こそが問われています。僕は、先生が机間指導の際に何を見ているのかというのがすごく気になるんですよ。「真面目にやっているか」「ちゃんとたくさん書き込んでいるか」監視してまわっているのか、違うのか。優れた先生って、そこで「この子は何を考え、何を書こうとしているのか」という、「今ここで起こっていることの意味」を、見取ろうとします。つまり、子どもがちゃんとやっているかどうかという「動き」をチェックするのではなくて、「この子は何を書くんだろうな」と思ってじっとたたずんでいたり、あるいは、一生懸命書いている子のところで「なんでこの子はこんなに一生懸命考えているのかな」と思ったり、その子の中で起きている事柄に対してマインドフルに注意を向けているんです。
――けれど、その先で、それを「どう解釈するか」というところで、間違えてはならないですね。
いや、何をもって「間違い」であるのかという点も、よく分かりませんよ。子どもへの解釈が「合っているか、間違っているか」なんていうことが、そもそも存在するのかどうかも分からない。けれど、ただ見ているだけではない「見取り」ですから、その先に問われるものはありますよね。 評価においては、先ほど言ったような、「教師側が思い描いたものに当てはまっているか」的なマインドレスな状態でも、見ているには見ているんですよ。けれど…、それだけですかね?
――それだけではないですよね。先ほどの「切実さ」ということで言えば、「その子にとって」どうなのか。
そう。「その子にとって」その表現が、どういう意味をもつのか、という観点ですよね。子どもが思ってもみないようなユニークなことを書いていて、これは面白いなぁ…って思ったりすることって僕にはすごくあるんですけれど、それは必ずしも、「本時のねらい」と照らすと当てはまらないのかもしれない。けれど、これはそんな次元の話ではなくて、その子が今ここで文化的に発揮しているクリエイティブな営みというのは、たとえ本時のねらいとは合わなかったとしても、教育上ものすごく大事なことじゃないですか。
――今のような、教師の構えやスタンス、教師の居方みたいなところは、学校の先生方とどれくらい共有できていると感じておられますか?
これもまた、こういった話を聞いたからといって、すぐに分かるようなものでもないんですよね。
――確かに。実際に体験してみなければ。
そう。我々には頭では分かっていてもできないことというのがあって、やはり積み重ねで、心理学で言う態度形成というものを図らなければならない。教師の根元にあるような力量というのは、極めて態度的であって、その先生の経験の蓄積、履歴によって培われるものだと思うんです。そもそも教師になる前から、そういったものは形成されていて、そこにさらに教師としての経験が積み重なって出来上がっていくわけなんですが、重要な体験の一つとして、やはり各学校で行われる授業研究がありますね。
人間の学びの本性
――子どもの学びも、先生方の授業研究も、意味のあるオーセンティックな「場」にする。あとは、長い目で見られるようにならないといけないですね。
そうです。だからね、教育の結果なんて、そんなすぐに表れるものじゃないんですよ。育まれる力が大きな力であればあるほど、長期間の継続が必要です。例えば、「学びに向かう力」にしても、1時間、1日、1学期という単位で培われるようなものではなく、切実に課題に向き合うような体験の繰り返しによって、子どもたちにそういった大きな力がつくんですね。だからこそ、すぐさまそれを評価するというのは難しい。点数をつけて通信簿をつけて、本末転倒にもそれが目的となった授業をする…それが評価なんだという、あまりにも根強い教育評価への固定観念を変えなくてはならないと思います。評価はそれだけではなくて、むしろ「見取り」と「フィードバック」だと思うんです。見取ったことに対して言葉掛けをしたり、それを自分の授業にも生かしていくこと。そのことを「指導と評価の一体化」と言いますけれども、これは目の前で生じる個別具体的な現象なので、ハウツーでどうにかなることではありません。ハウツーというものはあくまでも参考程度に過ぎず、それよりも、授業を創る主体である先生方一人一人がどう考えるかが、本当に大切です。自分への自信は自分でつくらなくてはなりません。
子どもに主体性を求める以上は、先生方もまた主体的に自身で考え、「こうすればうまくいく」といったハウツーを鵜呑みにしない。先ほど(編集注:インタビュー前編)、「オーセンティックな学びは教育環境に働きかける際の切り口の一つ」と言いましたが、そのように、我々がやっているような研究の成果は、概念整理や発想の切り口に力点を置いていて、あくまでも先生方の心を動かすための情報提供なのです。単純なハウツーの提供ではありません。
AIの発展によって、「答えを出すこと」に関して人間はもうAIにはかなわなくなりました。否応なく、答えよりも「問うこと」が大事な時代になったということです。翻って考えると、問うということは楽しい体験です。答えを覚えることが求められる授業よりも、問いが求められる授業のほうがワクワクするじゃないですか。そして、それがオーセンティックな課題であればあるほど、自分事であるから「問いたくなる」ということです。人間の学びの本性からすると、このような教育のほうが望ましく、むしろ時代がついてきたと言えますよ。
(構成:東洋館出版社 河合麻衣)
一生の問い
――先ほど「切実さも程度の問題」とのことでしたが、そういったちょっとした「投げかけ」とした工夫もありえるし、あるいは、もっと緊迫した課題もありえるでしょうし、そのあたりはグラデーション的であるという理解でいいですか。
そうです。今みたいな例もあれば、長期的に単元レベルで言えば、この前見た、小学校の国語科の実践でしたが、その学校には、「通学時のバスの中で本を読んではいけない」という、子どもたちがみんな「なんでそんな決まりなの?」と不満に思っている校則があったんですね。そこで、「それがおかしいと思うんだったら、そのことを副校長先生に訴えてみたらいいんじゃないか」と、意見文を書くことになっていったんです。先ほどはウクライナ侵攻を例に出しましたが、間接体験でも共感とイマジネーションによって切実さには一歩近づくことができるのだけれど、この事例の場合は、まさに直接体験なんですよね。子どもたちにとって、日々学校に通っている当事者としての直接的な問題意識からくる切実な課題なんです。「何でこれが禁止されているのか」「じゃあ、校則自体をもっとよいものにしていこう」「変えていこう」と自分事として取り組む。先生も、切実な課題だからこそ、国語の授業としては「意見文を書く」という教科の学習目標にもっていけるわけですよね。その場合、単元としては、例えば特定の先生を想定して、「この先生にはこういうアプローチがいい」とか、あるいは「じゃあ自分たちのクラスだけじゃなくて、全校のみんなの意見をアンケートで聞いてみよう」と発展していきますから、もはやこの学びは一過性のものではなくなっていきます。
つまり、切実な課題にも、一過性のものがあるかもしれないけれども、単元を貫く問いとなると一過性ではなく、むしろ次々と「問いが生まれてくる」んです。「どんな意見文だったら説得的か」という問いが生まれてきたように。学びが「切実」であれば、自発的に問いが生まれてくる。この事例のように、持続的に学びを深めるような学習プロセスが生まれてくると、その切実な問いは単元を貫き、あるいはもっと長期間にわたって、「一生の問い」になる可能性すらあります。
この世界情勢の中で、「平和って何だろう」と、まさに今、切実に多くの人が考えているのではないかと思いますが、そうした「一生の問い」をもったとき、日常生活の見え方が変わりますよね。ニュースの見方だって変わりますし、その日限りの一過性のものではなくなっていく。自分事になっていくとは、そういう、心も体も能動的に動き出す状態のことです。
――それって、すごくパーソナルな部分が関わりますか。
基本的には個人的なことだと思うんですよ。同じ授業を受けていても、例えば先ほどの美術の授業でも、お家の人を驚かせようとして、多くの子は「どうしようかな」と考えるかもしれないけど、シラけている子もいるかもしれません。同じ場であっても、個人差があるという点は、教育環境を考える上で検討しなきゃいけない最重要のポイントの一つですね。
同じ場であっても、同じように人が動くわけではないんです。いいんです、それで。そのうちに友達やその場に巻き込まれる可能性もありますし。そんなに性急にみんなの心が動くように働きかけようと堅く考えなくてよくて、むしろ環境のダイナミズムに委ねて、先生は「モニター」しながら、その場・そのときの適切な働きかけをすればいいんですよ。
この話は「見取り」ということと関係してきます。私たちが授業を見ていると、「子どもたちの心が動いてるな」「あ、ここでノってきてるな」とかって、感覚的に感じることがあると思うんですね。それを単に、感覚的に受け止めるだけじゃなくて、そこで「見取る」ということです。つまり、「この子は何に心が動いてるのか」「何をしようとしているのだろうか」といったことを、ぼんやりと見ているのではなくて、その姿を「解像度」高く把握することで、その子が向かおうとしていることや疑問に思っていること、こだわっていることを捉えなくてはなりません。プロなんですから、単に漠然と「意欲的に子どもの目が輝いている」とかではなくて、「一体何がどうして目が輝いているのか」を絶えずモニターし、捉える。それが見取りでありアセスメントです。
それが「教育的瞬間」なのであれば、即座に取り上げて、子ども一人の姿をみんなにとってのヒントとなるように、臨機応変に共有してあげたりすることもあるでしょう。
「ポイント」でなく「スタンス」
――「モニター」するに当たっては、まずはどんなところを気にかけるといい、というのはありますか。
これはよくあることなんですけれど、あんまりそういうことを具体的に考え過ぎると、逆に、視野狭窄のような状態になってしまうんですね。教育の世界って、「見取りのポイントは何ですか」「じゃあこことそこを見取りなさい」みたいなことになりがちなんです。そのとおりにすればうまくいく、みたいな簡単なことではないので、基本的には、ポイントではなくて「スタンス」が大事だと思うんですよね。個別具体的な場で逐一どうするかということではなく、授業に向かい合う際の「構え」です。
仕事柄、たくさんの授業を見ますが、子どもたちが意欲的に取り組んでいる授業における先生のスタンスって、子どもに何かが起こることを見守るというものです。そういった先生方の共通項としては二つあって、一つには、子どもを信用することですね。子どもを信用して委ねて任せるスタンスでいれば、子どもたちはそんなに変なことはしません。任せてみるというスタンスでいるのは、子どもをそもそも信じてないとできませんよね。
もう一つは、子どもの姿を面白がるということ。子どもに対する好奇心が旺盛で、子どもたちの学びや気付きに対して「子どもって面白いよね」という話で盛り上がれるようなメンタリティーです。そういう二つの構えは、言い換えれば教師の心理的余裕、でもあります。ハウツー的なことでは全くない、このような「構え」が、子どもたちのいい姿との相乗効果で、一緒にいい授業を創り出しているという事実を、身に染みて感じています。
鹿毛雅治(かげ・まさはる)
慶應義塾大学教職課程センター教授。著書に『授業という営み:子どもとともに「主体的に学ぶ場」を創る』『子どもの姿に学ぶ教師:「学ぶ意欲」と「教育的瞬間」』(ともに教育出版)など多数。最新刊に『モチベーションの心理学:「やる気」と「意欲」の心理学』(中公新書)。