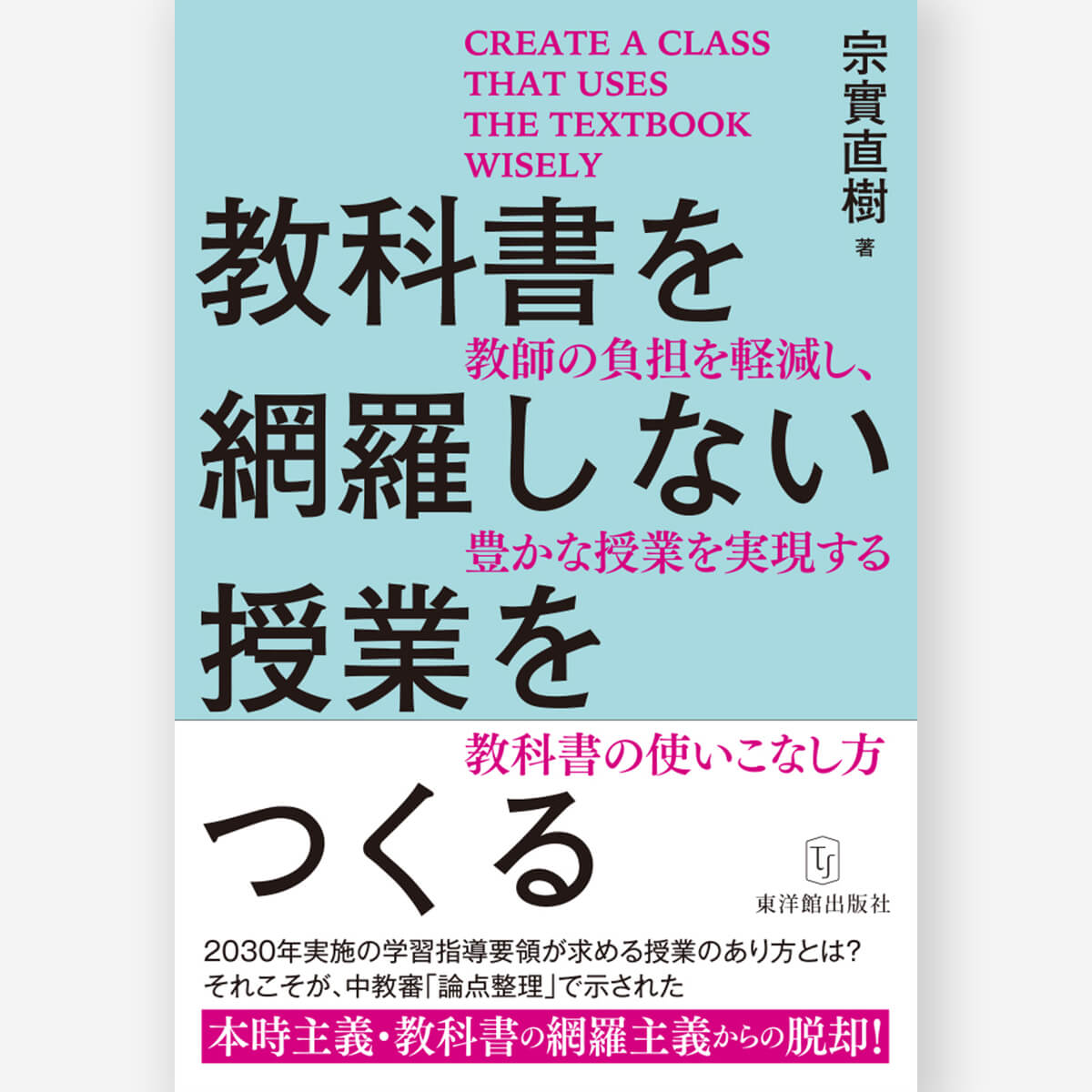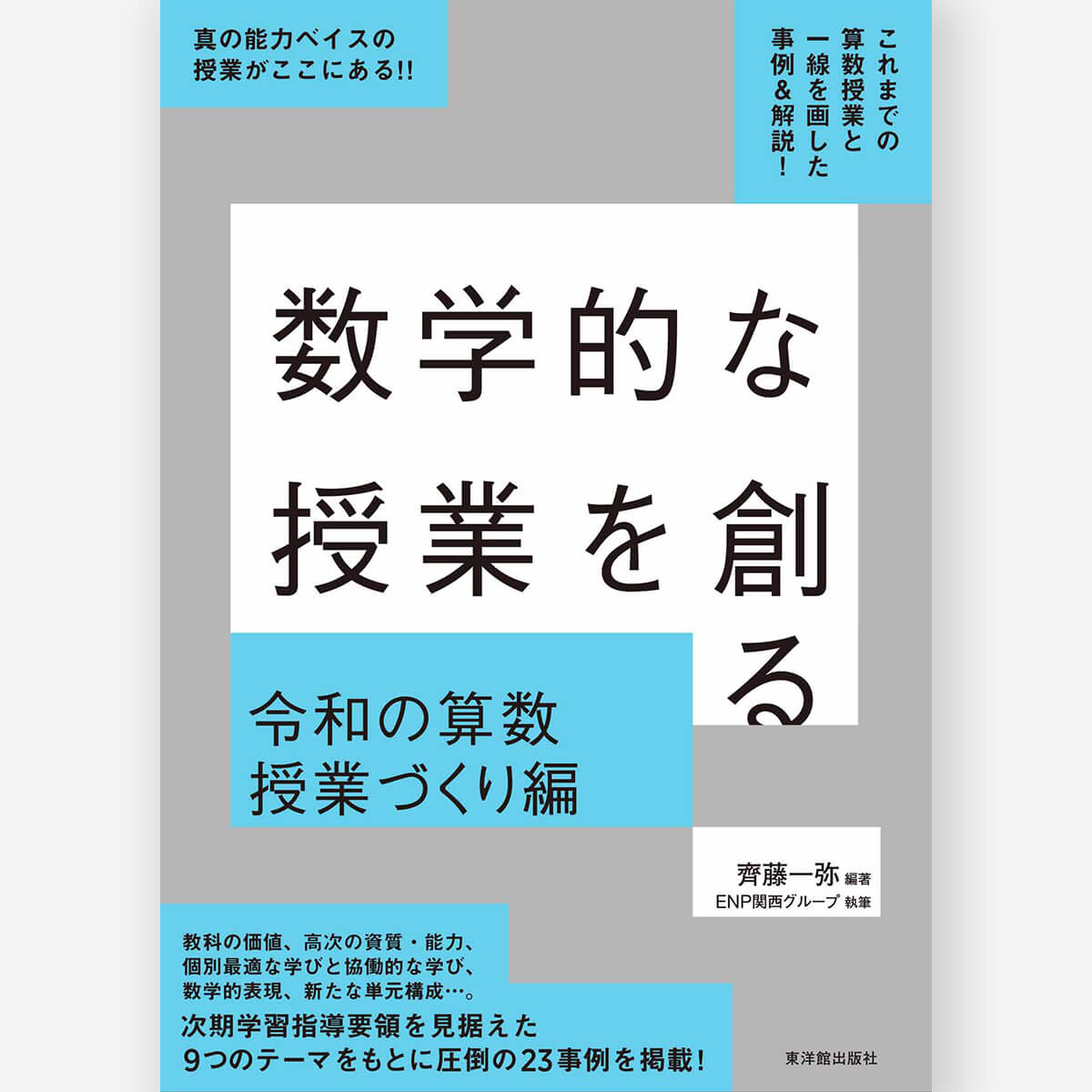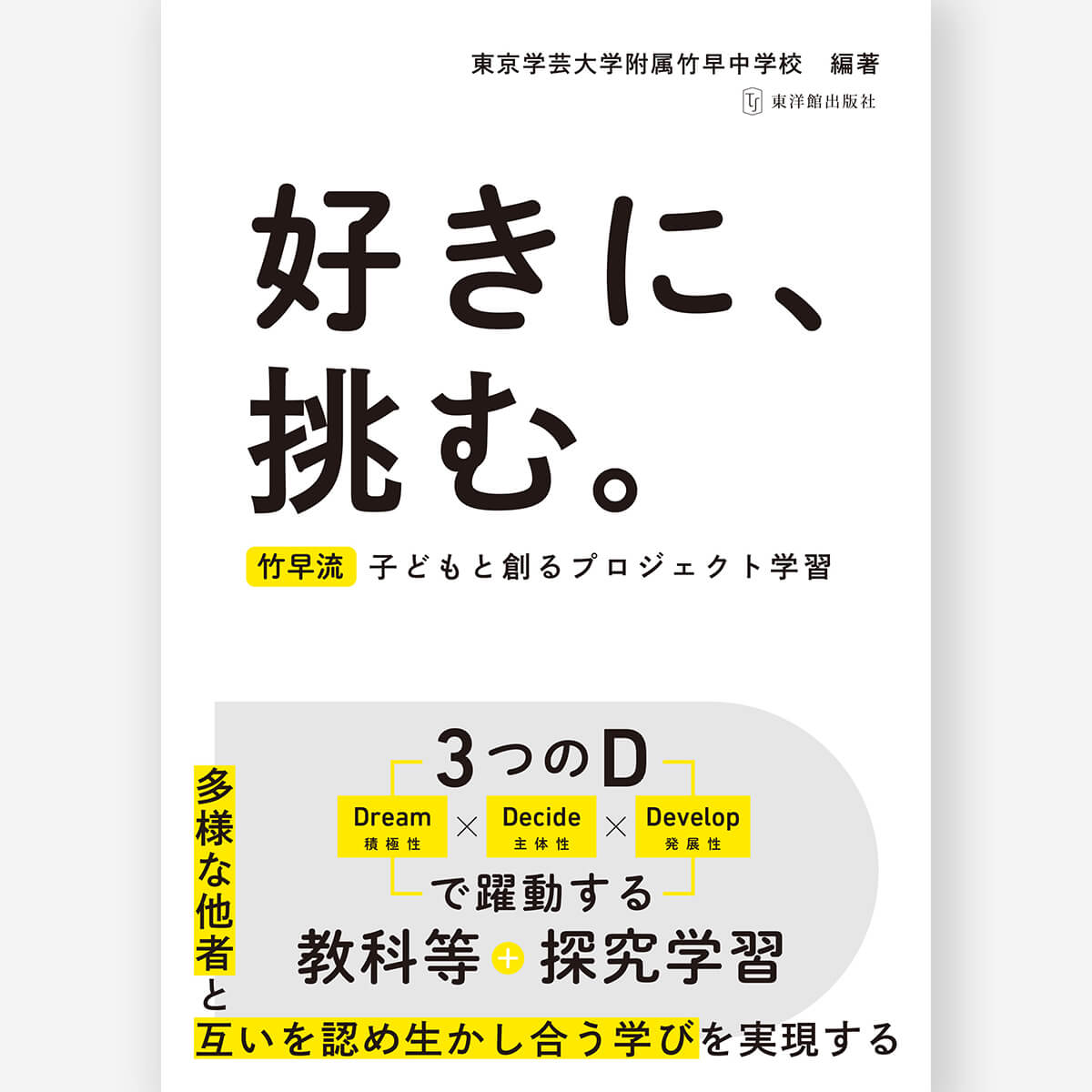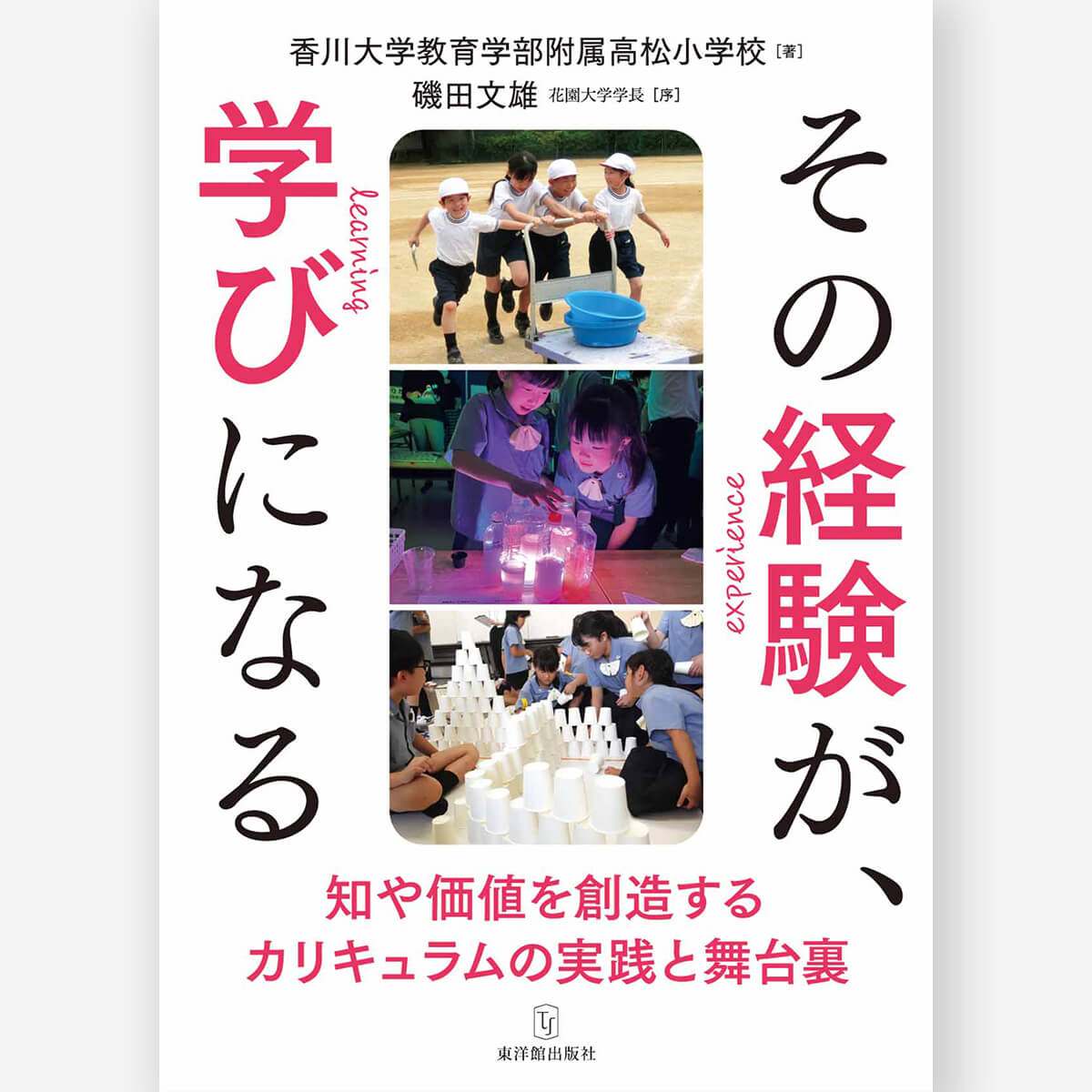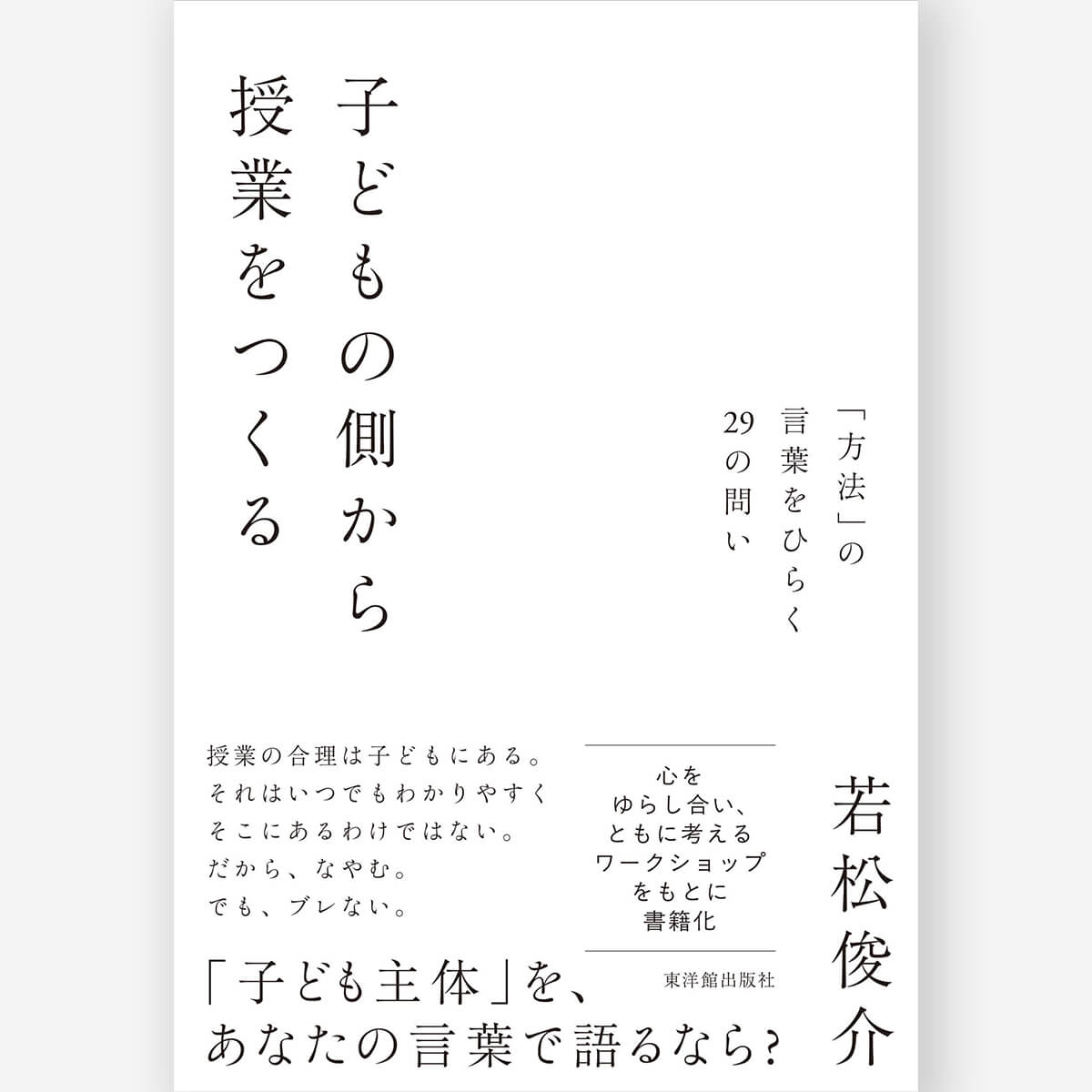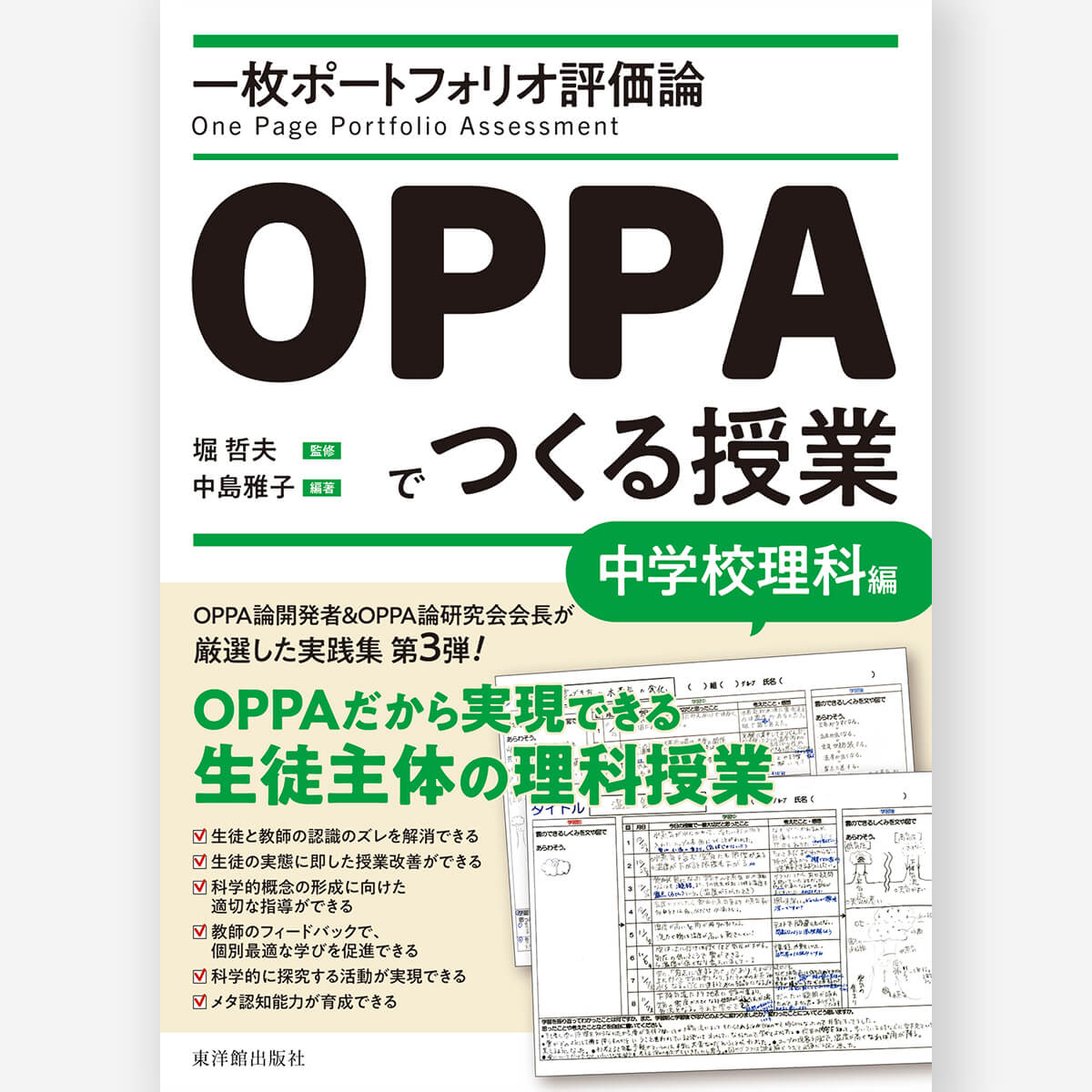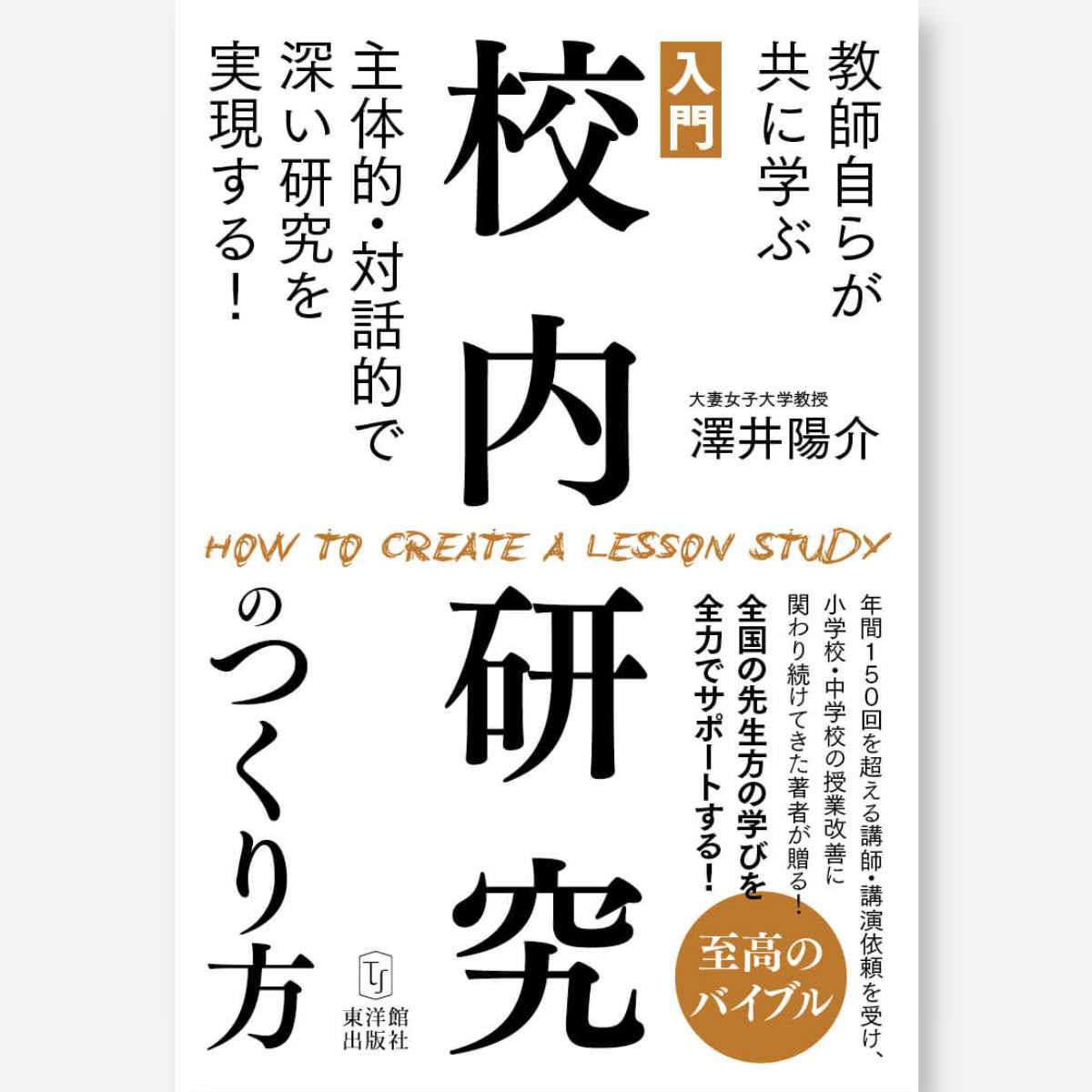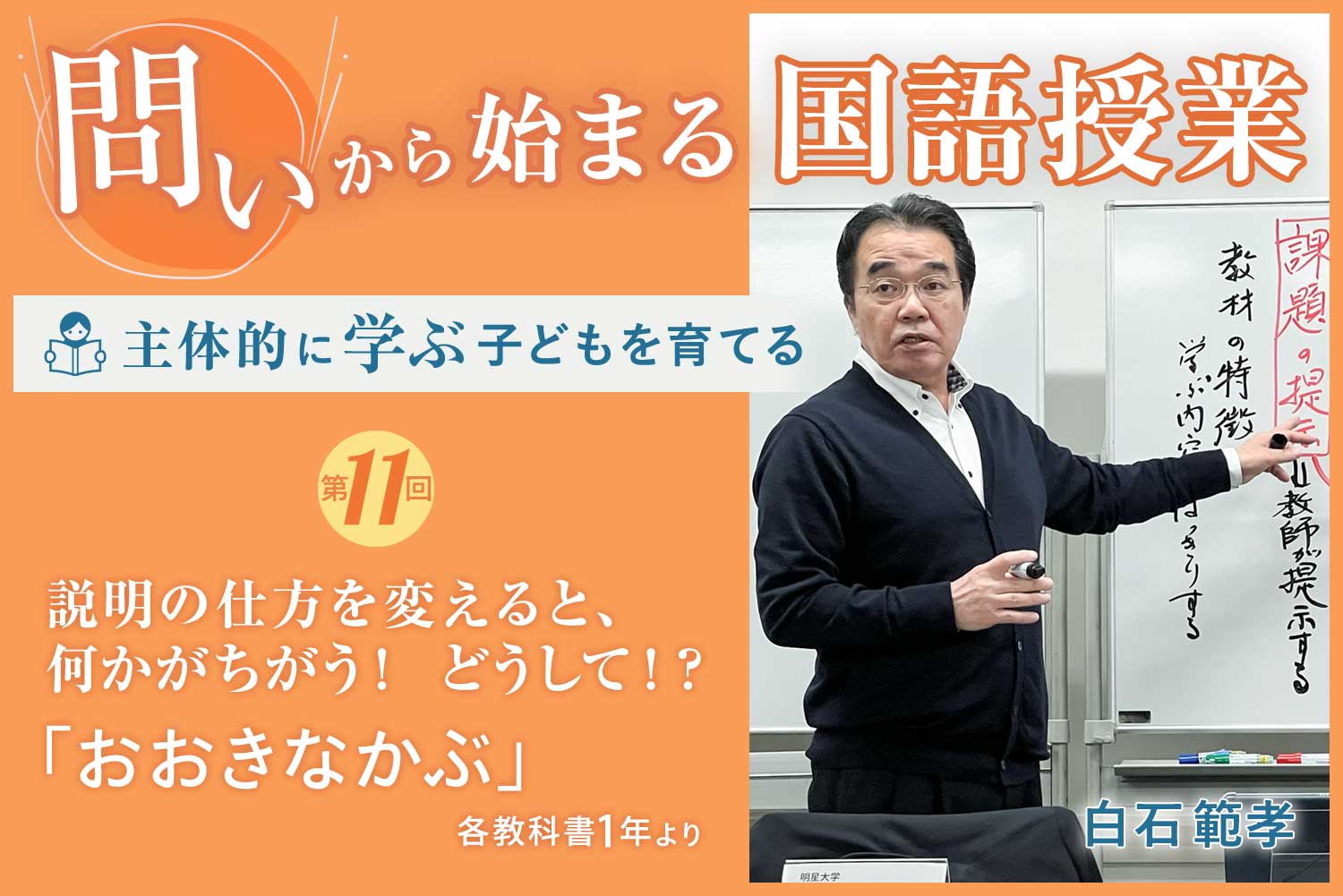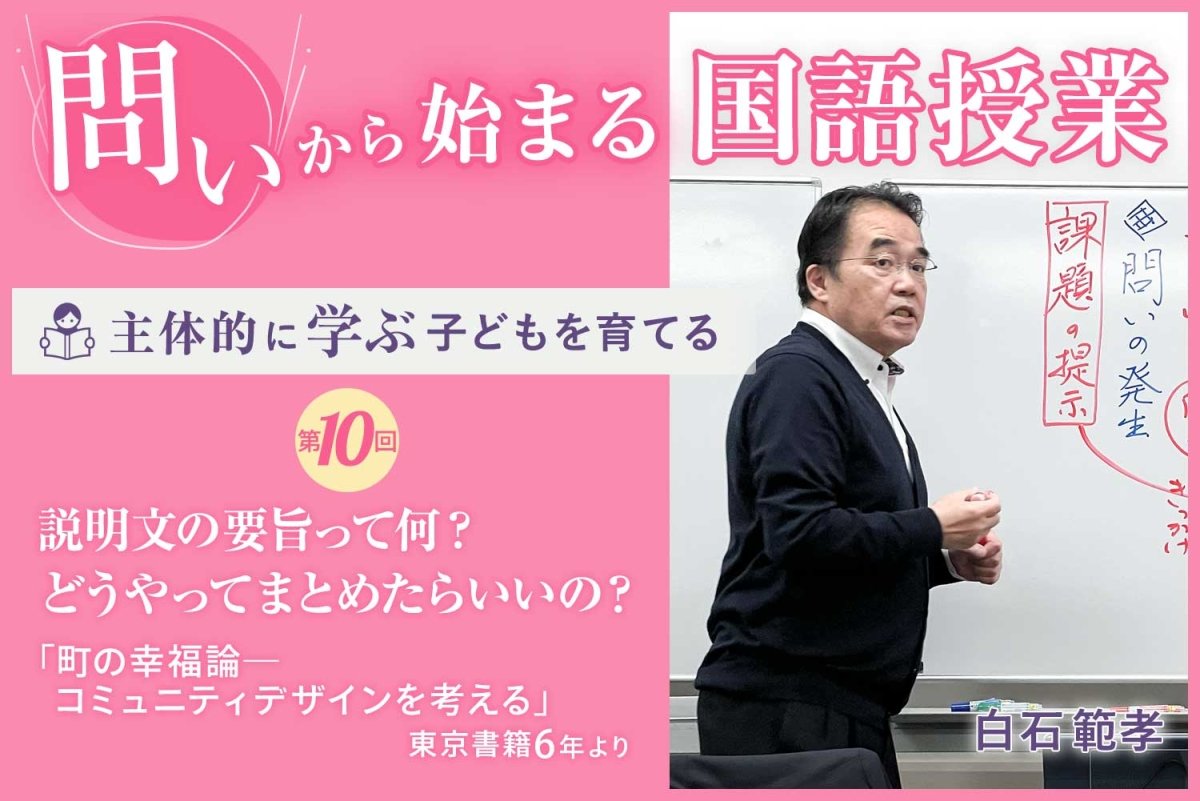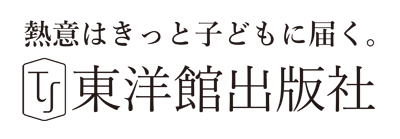〈 鹿毛雅治先生インタビュー 前編 〉 「オーセンティックな学び」が、子どもたちの学びの在り方に与える効能はさまざま。さらに多面的に考える必要がありそうです。第6回目となる今回は、動機づけや教育心理学がご専門の慶應義塾大学の鹿毛雅治教授に、子どもたちの学びへの意欲のメカニズムや教育環境づくりについてお聞きしていきます。
「いてもたってもいられなくなる」という気持ち
――鹿毛先生の専門領域の意欲や動機づけという視点から見ると、「学びがオーセンティックである」というのは、子どもの中でどういうことが起きている状態を指しているのか、というところからお聞かせいただければと思います。
オーセンティックな課題に向き合っているとき、おそらく人の内部では、「切実な心理状態」になっていると思うんですよね。切実だから前向きに取り組む、という意欲が生じる。
切実さ、とは何かと言えば、最近よく使われるようになった言葉として「自分事」という言葉があります。対義語は「他人事」ですね。
例えば、まさに現在のことで言えば、戦争が起こる前は、ウクライナという国に関して私も含めてですが恐らく他人事だったわけですよね。けれども、ロシアによるウクライナ侵攻が起こり、報道を通して、爆撃の様子や家族が亡くなった方々の声、あるいは日々いつ攻撃されるか分からないような状況を目の当たりにしたときに、一步、ウクライナという国が自分事に近づくわけです。そう考えると「切実さ」というのは、程度の問題でもあるかもしれません。前までは全くの他人事で、ウクライナという国の知識もそれほどなかったところから、映像による間接情報だけれども、クローズアップされることで、切実さの程度が増していく。いてもたってもいられなくなる。その理由は、「共感」と「イマジネーション」が働くからです。「自分だったら」と想像を働かせると、切実に気持ちがシンクロするような心理状態になる。一言で言えば「共感システム」が活性化して、「自分だったらどうだろう」「これは他人事ではない」と、心が動くわけです。一步、自分事になったとき、何かしたくなる意欲でもって、例えば寄付をするなどの実際のアクションや、あるいはそれ以前にもっとウクライナという国について調べたくなるといった主体的な学びが起こってきたりするわけです。
太陽型アプローチ
――そのような「共感」や「イマジネーション」が生まれるような教育環境というのはどういうもので、また、どうやってつくっていけるものなのでしょう。
「いてもたってもいられなくなるような気持ち」みたいなものも程度の差がありますが、動機づけの一つのメカニズムなのだと思うんですね。つまり、非常に激しいものの場合もあれば、そうじゃない場合もありますが、いずれにしても、ある出来事に対して「心が動いて体も動く」わけですから、モチベーションそのものですよね。
そのような「場」をどういうふうにデザインするかというポリシーには、大きく二つあります。寓話『北風と太陽』の北風型アプローチと太陽型アプローチ。旅人のコートを脱がす競争をするとなったとき、北風は冷たい強い風を吹かせると、旅人はむしろ着込んでしまう。けれど、太陽は大気を暖めることによって、おのずと旅人がコートを脱ぐようになる、ということで太陽が勝つわけですね。この「おのずと旅人がコートを脱ぐ」というのがポイントです。北風はとにかく外圧によって旅人を思いどおりにさせられると思っていたわけだけれども、人間はそういう存在ではなくて、むしろ寒い北風だったら着てしまう。つまり、北風は人間の理解が浅いわけですよね。それに対して、太陽は人間とは何かという理解が優れていて、人間は暖かいとコートを脱ぐ、という人間の主体性を理解していたから、人間に直接的に働きかけた北風に対し、太陽は環境に対して間接的に働きかけたわけです。
「教える」という行為は、何か説明したり、指示したり、発問したり、教師側が主語になって何かをすることだと考えがちだけれども、これから子どもの主体性を基に教育環境を整えていく際には、「こうしろ、ああしろ」と子どもに指示することによる働きかけでは不十分で、むしろ太陽型アプローチに基づいて環境を整備し、「環境を通じて教育する」という発想をもちたいですね。「環境」とは、物理的な環境もあれば、教材などももちろん含まれていて、それらを工夫することを通じて、「おのずと」子どもが活動するようにデザインしていく。
「オーセンティックな学び」は、その教育環境デザインにおける一つの切り口です。
教育環境の一部として、オーセンティックな課題を用意する場合に、真正であるということはそれだけで、「学ぶ必然性」や「切実さ」を感じやすくさせます。意欲的に取り組みやすくなる。なぜかというと、「オーセンティックでない課題」というものが学校には溢れているからです。「学校課題」と言われるものなのですが、学校という場でしか通用しないような課題で、教育を行っていることが実は多いわけですよね。分かりやすい例で言えば、旧来的な「避難訓練」って、全くオーセンティックではないですから、切実さも必然性も生まれず、自分事にはなりません。ですから、だらけた気持ちで参加してしまって、訓練の時間が無駄になってしまう。大人だけが、なんだかやったつもりになっている。切実感の生まれる形で工夫の余地は、あると思うんですけどね。
これが、教科の学習であってもそうです。「トマトの授業」(※編集注:島根県立大学の齊藤一弥先生の実践。あらゆる品種のトマトの実物を比べながらお買い得を決める、5年生「単位量当たりの大きさ」の授業。小野健太郎『オーセンティックな算数の学び』p.82-83に詳しい)がそうであるように、自分事に一歩でも近づいた課題であれば、心が動くから、やる気になる。
私の知っている美術の実践例で、造形活動で、本物そっくりの食べ物の塑像(そぞう)を作るという課題がありました。それを「作ってみよう」と単に先生から投げかけるのではなく、「お家の人が、冷蔵庫をのぞいたときに、びっくりするようなもの作ってみよう」というふうに投げかけたんだそうです。そうすると全然「つかみ」が違いますよね。そこには、まさにイマジネーションがふくらむ。その場面を想像して、「うちの家族だったらこういうの作ると驚きそうだな」と思うことで、心が動く。心の中が活性化することでアイデアも浮かんでくるわけです。これは「投げかけ」ですから、「ああしろ、こうしろ」とは言っていません。北風を吹かせたわけじゃないんですね。少し、太陽型アプローチで投げかけただけで、みんなが「どうしよう?」とワクワクして、「俺だったらこう作る!」と隣の子と話し合ったりする「場」が学級に出来上がる。それぞれ具体的なアイデアが出てきて、意欲的に造形活動に取り組めるようになる、という仕組みなのですね。
一生の問い
――先ほど「切実さも程度の問題」とのことでしたが、そういったちょっとした「投げかけ」とした工夫もありえるし、あるいは、もっと緊迫した課題もありえるでしょうし、そのあたりはグラデーション的であるという理解でいいですか。
そうです。今みたいな例もあれば、長期的に単元レベルで言えば、この前見た、小学校の国語科の実践でしたが、その学校には、「通学時のバスの中で本を読んではいけない」という、子どもたちがみんな「なんでそんな決まりなの?」と不満に思っている校則があったんですね。そこで、「それがおかしいと思うんだったら、そのことを副校長先生に訴えてみたらいいんじゃないか」と、意見文を書くことになっていったんです。先ほどはウクライナ侵攻を例に出しましたが、間接体験でも共感とイマジネーションによって切実さには一歩近づくことができるのだけれど、この事例の場合は、まさに直接体験なんですよね。子どもたちにとって、日々学校に通っている当事者としての直接的な問題意識からくる切実な課題なんです。「何でこれが禁止されているのか」「じゃあ、校則自体をもっとよいものにしていこう」「変えていこう」と自分事として取り組む。先生も、切実な課題だからこそ、国語の授業としては「意見文を書く」という教科の学習目標にもっていけるわけですよね。その場合、単元としては、例えば特定の先生を想定して、「この先生にはこういうアプローチがいい」とか、あるいは「じゃあ自分たちのクラスだけじゃなくて、全校のみんなの意見をアンケートで聞いてみよう」と発展していきますから、もはやこの学びは一過性のものではなくなっていきます。
つまり、切実な課題にも、一過性のものがあるかもしれないけれども、単元を貫く問いとなると一過性ではなく、むしろ次々と「問いが生まれてくる」んです。「どんな意見文だったら説得的か」という問いが生まれてきたように。学びが「切実」であれば、自発的に問いが生まれてくる。この事例のように、持続的に学びを深めるような学習プロセスが生まれてくると、その切実な問いは単元を貫き、あるいはもっと長期間にわたって、「一生の問い」になる可能性すらあります。
この世界情勢の中で、「平和って何だろう」と、まさに今、切実に多くの人が考えているのではないかと思いますが、そうした「一生の問い」をもったとき、日常生活の見え方が変わりますよね。ニュースの見方だって変わりますし、その日限りの一過性のものではなくなっていく。自分事になっていくとは、そういう、心も体も能動的に動き出す状態のことです。
――それって、すごくパーソナルな部分が関わりますか。
基本的には個人的なことだと思うんですよ。同じ授業を受けていても、例えば先ほどの美術の授業でも、お家の人を驚かせようとして、多くの子は「どうしようかな」と考えるかもしれないけど、シラけている子もいるかもしれません。同じ場であっても、個人差があるという点は、教育環境を考える上で検討しなきゃいけない最重要のポイントの一つですね。
同じ場であっても、同じように人が動くわけではないんです。いいんです、それで。そのうちに友達やその場に巻き込まれる可能性もありますし。そんなに性急にみんなの心が動くように働きかけようと堅く考えなくてよくて、むしろ環境のダイナミズムに委ねて、先生は「モニター」しながら、その場・そのときの適切な働きかけをすればいいんですよ。
この話は「見取り」ということと関係してきます。私たちが授業を見ていると、「子どもたちの心が動いてるな」「あ、ここでノってきてるな」とかって、感覚的に感じることがあると思うんですね。それを単に、感覚的に受け止めるだけじゃなくて、そこで「見取る」ということです。つまり、「この子は何に心が動いてるのか」「何をしようとしているのだろうか」といったことを、ぼんやりと見ているのではなくて、その姿を「解像度」高く把握することで、その子が向かおうとしていることや疑問に思っていること、こだわっていることを捉えなくてはなりません。プロなんですから、単に漠然と「意欲的に子どもの目が輝いている」とかではなくて、「一体何がどうして目が輝いているのか」を絶えずモニターし、捉える。それが見取りでありアセスメントです。
それが「教育的瞬間」なのであれば、即座に取り上げて、子ども一人の姿をみんなにとってのヒントとなるように、臨機応変に共有してあげたりすることもあるでしょう。
「ポイント」でなく「スタンス」
――「モニター」するに当たっては、まずはどんなところを気にかけるといい、というのはありますか。
これはよくあることなんですけれど、あんまりそういうことを具体的に考え過ぎると、逆に、視野狭窄のような状態になってしまうんですね。教育の世界って、「見取りのポイントは何ですか」「じゃあこことそこを見取りなさい」みたいなことになりがちなんです。そのとおりにすればうまくいく、みたいな簡単なことではないので、基本的には、ポイントではなくて「スタンス」が大事だと思うんですよね。個別具体的な場で逐一どうするかということではなく、授業に向かい合う際の「構え」です。
仕事柄、たくさんの授業を見ますが、子どもたちが意欲的に取り組んでいる授業における先生のスタンスって、子どもに何かが起こることを見守るというものです。そういった先生方の共通項としては二つあって、一つには、子どもを信用することですね。子どもを信用して委ねて任せるスタンスでいれば、子どもたちはそんなに変なことはしません。任せてみるというスタンスでいるのは、子どもをそもそも信じてないとできませんよね。
もう一つは、子どもの姿を面白がるということ。子どもに対する好奇心が旺盛で、子どもたちの学びや気付きに対して「子どもって面白いよね」という話で盛り上がれるようなメンタリティーです。そういう二つの構えは、言い換えれば教師の心理的余裕、でもあります。ハウツー的なことでは全くない、このような「構え」が、子どもたちのいい姿との相乗効果で、一緒にいい授業を創り出しているという事実を、身に染みて感じています。
(構成:東洋館出版社 河合麻衣)
鹿毛雅治(かげ・まさはる)
慶應義塾大学教職課程センター教授。著書に『授業という営み:子どもとともに「主体的に学ぶ場」を創る』『子どもの姿に学ぶ教師:「学ぶ意欲」と「教育的瞬間」』(ともに教育出版)など多数。最新刊に『モチベーションの心理学:「やる気」と「意欲」の心理学』(中公新書)。