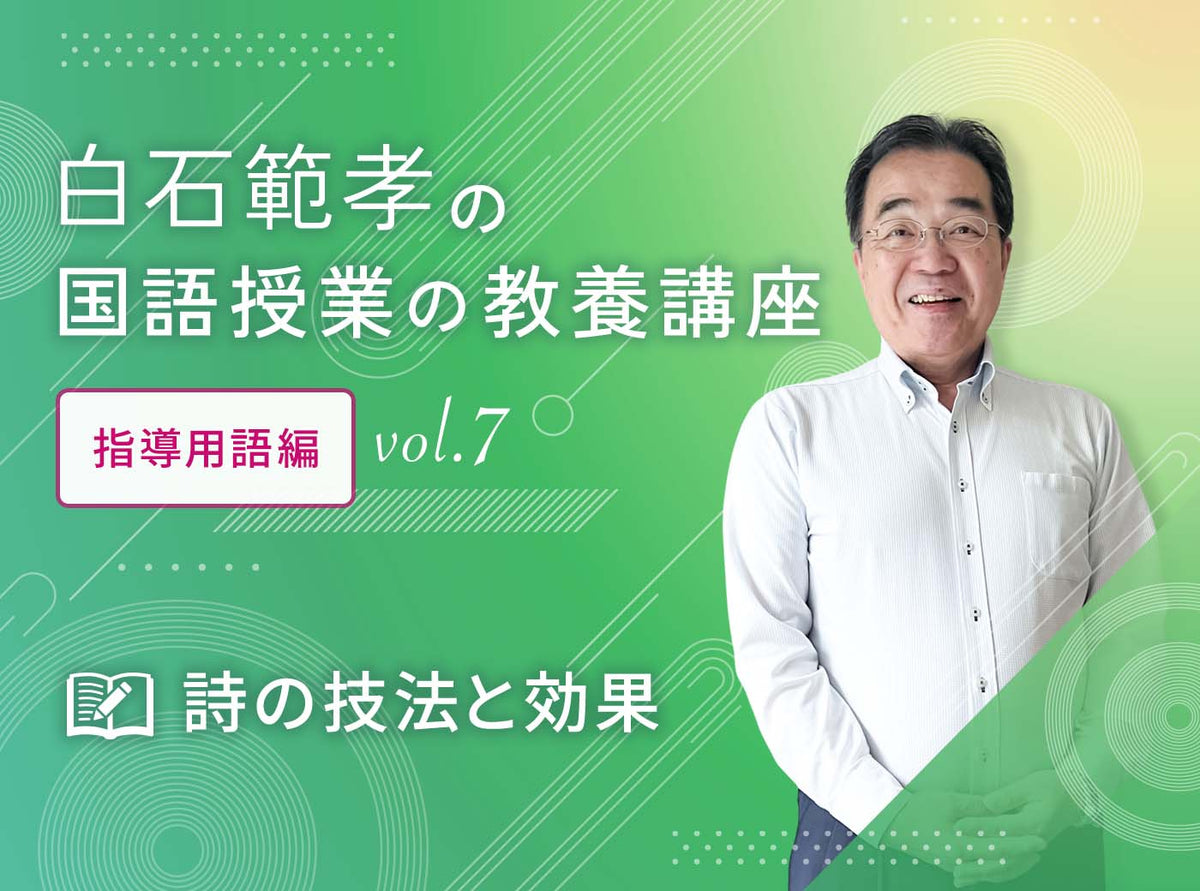
詩の技法と効果
|
|
国語授業における詩の読みは、感性によって読むもの――と思っていないでしょうか。
また、「どうやって詩をつくったらよいかわからない」という子どもに対して「自分の気持ちをよく考えてごらん」といった曖昧な指導をしていないでしょうか。
今回は、詩とは何なのかということや、論理的に詩を読んだり創作したりすることにつながる「技法と効果」について考えてみます。
「詩の世界」というのは、どんな世界がどのように描かれているのでしょうか。
詩は、人間が五感を通してとらえた世界が描かれています。
詩は、この5つの感覚で感じ取ったことが言葉によって、表現されているのです。
詩は、五感を通してとらえたことや、それによる心の動きを伝えるために、一般の文章よりも多くの「技法」を用います。
「技法」を用いることによって、「効果」が生まれるのです。
この連載のVol.3で、北原白秋の「落葉松」という詩を取り上げました。
なんだか、寂しい感じ、もの静かな感じがします。
決して、楽しい感じはしません。
読んだ人が誰もが、このように感じるのは、詩人がある仕掛けをしている、つまり、技法を使っているのです。
その技法が「五七調」です。
五七調を使うことによって、「寂しい感じ」「もの静かな感じ」という「効果」が生まれているのです。
詩で用いられる技法には、様々なものがあります。
そのうちの主なものについて、効果と共にまとめると、次のようになります。
| 技法 | 効果 |
| 繰り返し |
|
| 律 |
|
| 頭韻、脚韻 |
|
| 擬声語 |
|
| 擬態語 |
|
| 比喩 |
|
| 擬人法 |
|
| 倒置法 |
|
| 対句 |
|
| 体言止め |
|
どんな技法が使われているのかを明らかにすることによって、作者が何を表現したかったのか、どんな世界を描こうとしたのかをとらえることができます。
もちろん、自分で詩を創作する際にも、効果を考えながら技法を用いることによって、自分が描こうとしている世界を明確に読者に伝えることができます。
では、実際に試してみましょう。
歌にもなっている有名な詩「夏は来ぬ」ですが、どんな技法が使われているのか、探してみてください。
この詩は、各連3行の5連構成になっています。
まず、音数を見てみると次のようになっています。
| 第一連 |
|
| 第二連 |
|
| 第三連 |
|
| 第四連 |
|
| 第五連 |
|
〈律〉
どの連も、1行目と2行目は五七調、3行目は七五調です。
このため、3行目の七五調の明るさが強調されます。
〈繰り返し〉
「夏は来ぬ」と言う言葉が、題名も含め、繰り返し登場します。
しかも必ず各連の3行目の最後の5音です。
〈律〉でも見た通り、この最後の5音は明るさが強調されています。
これらのことから作者は、「とうとう夏がやって来た」という喜びを、この詩で表現しようとしていることがわかります。
*
「感性の世界」ととらえられがちな「詩」の学習ですが、今回説明した、
などの視点で読んでいくことによって、「詩を論理的に読む」ことや、「詩を論理的に創作する」ことも可能になるのです。
*
今月は、「詩の世界」と、「技法と効果」について考えてきました。
次回は「要点・要約」についてご説明する予定です。
また、一緒に学びましょう。
