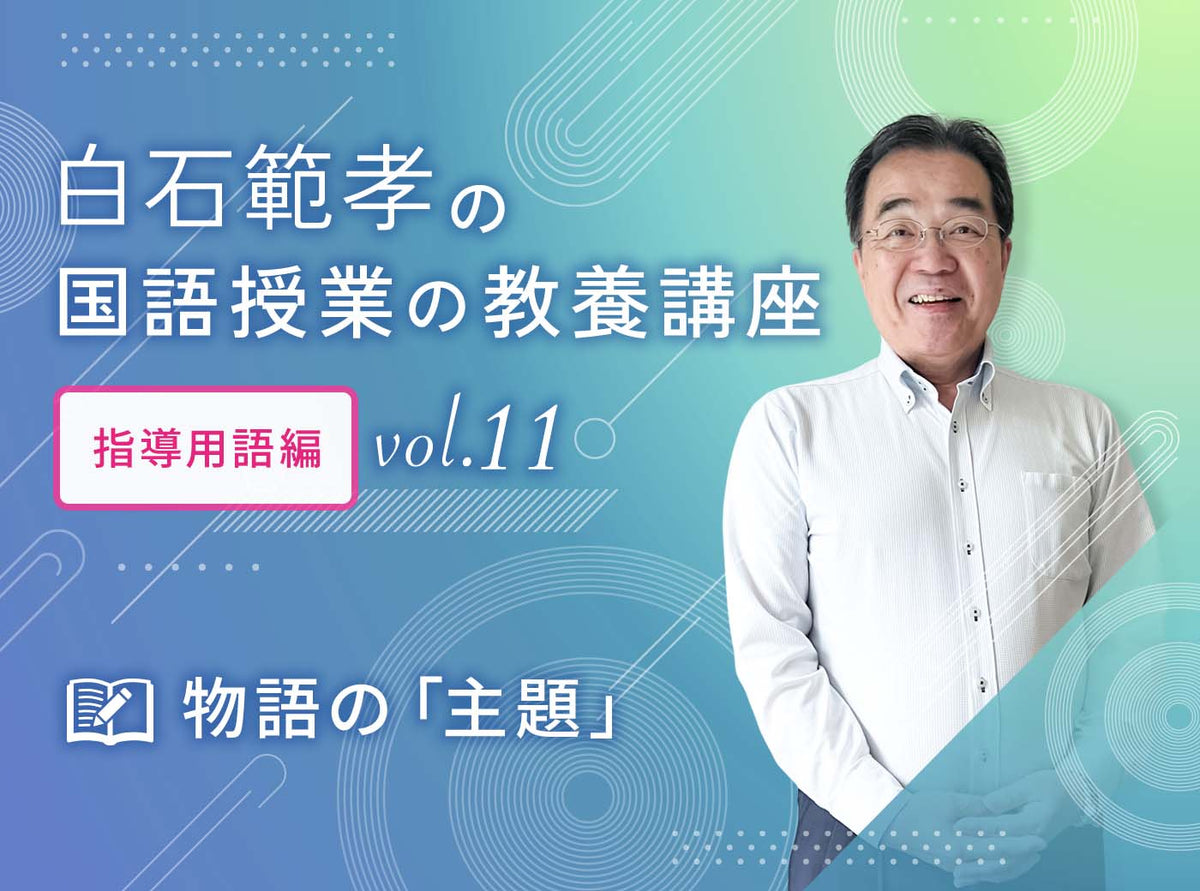
物語の「主題」
|
|
説明文の学習では「筆者の主張」や「要旨」をとらえることが重視されます。
物語において「説明文の主張や要旨」にあたるものは「主題」です。
ところが、現在、小学校の物語の学習において「主題」をとらえることは行われていません。
学習指導要領に「主題を読む」という言葉は見当たらないのです。
その理由は、「主題」について、いまだ未解決の大きな議論があるからです。
今回は、その「未解決の議論」から話を始めたいと思います。
物語の「主題」をめぐる「未解決の議論」とは、
物語の「主題」は、「物語の中にある作者の意図」なのか、「作者の意図に関わらず、読者に任せられるもの」なのか。
というものです。
詳しく見ていきましょう。
【主題についての考え方①】
「主題は作品の中にある作者の意図である」
作品には、作者の意図や考え、メッセージが表現されている。
これは、作者が主題を意識して表現したものである。
よって、主題は、作品の中に作者の思想として存在している。
つまり、「主題は作品の中にある」。
【主題についての考え方②】
「作者の意図に関わらず、主題は読者に任せられるもの」
主題とは、作品を読んだ読者一人ひとりがもつテーマである。
読者が物語から自由にイメージをふくらませ、感想をもったり、メッセージを感じ取ったりすることにより、とらえるものである。
つまり、「主題は読者自身に任される」。
主題については、以上の2つの考え方が議論されてきました。
しかし、決着がつかないまま、現在に至っています。
その結果、小学校の国語の学習において「主題」は扱われず、学習指導要領にも「主題を読む」という言葉は見当たらない――というわけです。
私は、小学校の国語の学習においては
主題は、作品の中にある作者の意図である。
とすべきだと考えています。
なぜなら、「主題は読者自身に任される」とすると、子どもがとらえる主題が一人ひとり違ってしまいます。
授業は拡散し、何が主題なのかを学ぶ学習は成立しなくなってしまいます。
よって、「小学校の国語の学習の中で学ぶ『主題』」を次のように定義した上で、主題について考えていきたいと思います。
小学校の国語の学習における、物語の「主題」
作品の中にある作者の思想内容のこと。
それは、作品の中から自然に見いだされるもの、あるいは、作者が意識して表現の中心としたものである。
「主題を読む」とは、作品の表現を通して、作者の意図を探ることである。
物語の中にある作者の意図は、物語の叙述から読み取ったものでなければなりません。
叙述から離れた感想や想像を根拠としてしまったのでは、作者の意図ではなくなってしまうからです。
叙述から読み取ることができることのうち、次の3つが、主題をとらえるための大切な手がかりとなります。
[手がかり1 クライマックス]
この連載でも繰り返し述べてきたように、物語とは「中心人物の変容を描いたもの」なので、作者の意図、つまり主題は、中心人物の変容にもっとも強く込められているといえる。
したがって、中心人物の変容点である「クライマックス」の一文をとらえることが、作品の「主題」をとらえることにつながっている。
[手がかり2 中心人物のこだわり]
「中心人物のこだわり」とは、中心人物が物語の中でもち続けた思いや願いのこと。
「こだわり」が成就したりしなかったりすることが、中心人物の変容と深く関係している。
「中心人物のこだわり」をとらえるためには、物語の中で繰り返されている言葉に着目する。
[手がかり3 象徴]
物語の「象徴」とは、題名や物語の中のキーワードが象徴しているもの。
三人称客観視点で描かれた物語の中には、中心人物の心情が語られず、中心人物の変容がとらえにくいものもあるが、そのような物語の場合は、題名や物語の中のキーワードが何を「象徴」しているのかを明らかにすることで、「主題」をとらえる。
「主題」をまとめるときに注意が必要なのは、主題とは物語の中に描かれている「具体」ではなく、作者が物語の中で描いたことを抽象化したものだということです。
そのために、次の2つのステップでまとめるとよいでしょう。
②の抽象化した文章を書く際には、「人は……である。」という文型で表現するとまとめやすくなります。
『海の命』(立松和平 作/光村図書・東京書籍6年)を例に、「主題」のまとめ方を、手がかり1~3に沿って具体的に見ていきましょう。
[手がかり1 クライマックス]
『海の命』のクライマックスの一文は、「水の中で太一はふとほほえみ、口から銀のあぶくを出した。」。
その直前まで、「この魚をとらなければ、本当の一人前の漁師にはなれない」と思っていた中心人物・太一が、瀬の主を殺さないという決断をした――つまり大きく変容したのが、この一文なのである。
このことから「本当の一人前の漁師になる」「瀬の主であるクエを殺さないという決断」などが、「主題」と深く関わっていることがわかる。
[手がかり2 中心人物のこだわり]
太一のこだわりは、本当の一人前の漁師になること。
ただし、どんな漁師が「本当の一人前の漁師」なのかは、クライマックスの前後で異なる。
[手がかり3 象徴]
この物語は、題名の「海の命」が象徴しているものが、「主題」と深く結びついているものと考えられる。
これら3つの手がかりをもとに、この物語で描かれていることをまとめると、次のようになります。
「村一番の漁師」として成長するとは、自然の恵みを守りながら漁をすることであり、クエを殺したり、魚をとりすぎることではない。
このことを、物語の世界から離れて抽象化すると、次のようになります。
人は、自然の恵みの中で生きているのであるから、自然と共生して生きていくべきである。
これが、『海の命』の主題となります。
*
今月は、物語の『主題』について見てきました。
今回、主題をとらえるための手がかりを3つあげましたが、これらの手がかりをとらえるために、これまでの連載で述べてきた様々な読みが土台となることは、言うまでもありません。
小学校6年間の国語の学習によって習得してきた物語の読みの力の集大成が、「主題」をとらえる読みに結びつくのではないでしょうか。
*
次回は、説明文の「要旨」についてご説明する予定です。
また、一緒に学びましょう。