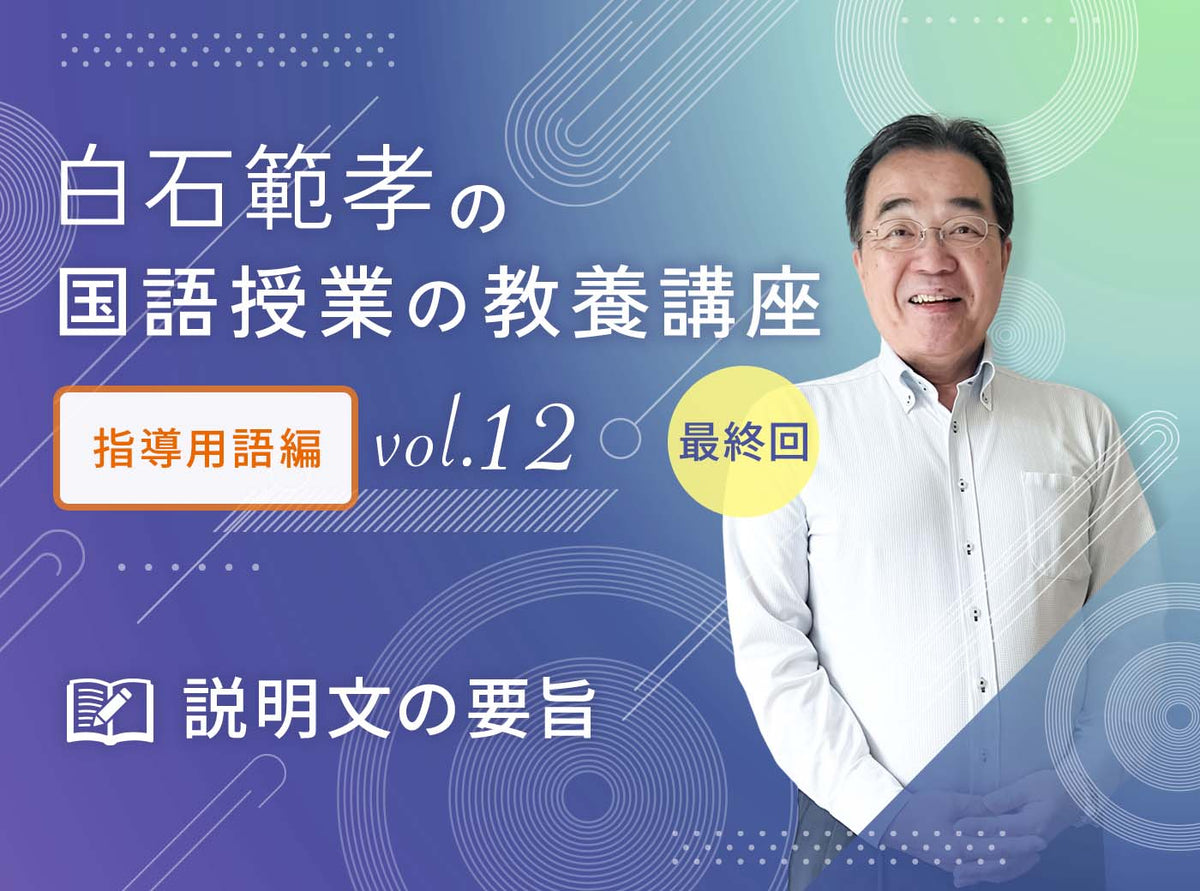
説明文の要旨
|
|
この連載の本年度の第6回(2024/10/3公開)で、「説明文のまとめ・筆者の主張・要旨」について説明し、要旨について、次のように定義しました
【説明文の要旨】
「まとめ」「筆者の主張」から、筆者が最も述べたいこと。また、「筆者の主張」を抽象化したもの。
また、「筆者の考えの中心となるもの」と表現することもあります。
今回は、この連載の締めくくりとして、改めて「要旨」について考えてみることを通して、説明文の読みの学習において大切なことは何なのかを考えてみたいと思います。
この連載でも繰り返し説明してきましたが、説明文の基本三部構成は次のようになっています。
〈はじめ〉…「話題」「課題」の部分
〈なか〉……「具体例」「事例」の部分
〈おわり〉…「まとめ」「主張」「要旨」の部分
説明文の中には、「まとめ」や「主張」「要旨」がないものもあります。
説明文の読みの学習では、「まとめ」「主張」「要旨」が明確に区別されていないことも多く見られます。
しかし、この3つが表しているものが異なる以上、その区別の方法を明確に示すことが必要です。
このうち「まとめ」は、〈なか〉で示された「具体例」「事例」の共通点や相違点などをあげてまとめています。
具体例・事例よりも一般化されています。
「主張」は、「まとめ」を踏まえた「筆者の考え」です。
「まとめ」よりも抽象化されていますが、そこで述べられていることの内容は「具体例」「事例」をもとにしたものをこえません。
「要旨」は、「筆者の主張」を一般化し、〈なか〉であげた「具体例」「事例」の範囲をこえて述べられるものです。
したがって、「筆者の主張」よりも抽象化されたものだといえるでしょう。
このように見てくると、「主張」は「まとめ」よりも抽象的ですが、「要旨」よりは具体的だといえます。
説明文の中の「抽象」には、様々な段階のものがあることがわかります。
説明文は、このような「具体」と「抽象」の行き来によって論が展開されていきます。
そして、「まとめ」→「主張」→「要旨」となるにしたがって、抽象度が高くなっていくといえるでしょう。
〈なか〉で示された「具体例」「事例」をどこまで抽象化、一般化しているかによって、「主張」と「要旨」を区別することになります。
なお、「要旨とは、筆者の主張を抽象化したもの」を、「抽象的な言葉で書かれている部分」ととらえないよう注意してください。
「未来につなぐ工芸品」(光村図書 4年下)を例として、具体的に見ていきましょう。
「未来につなぐ工芸品」は、7つの段落で構成され、基本三部構成は次のようになっています。
「未来につなぐ工芸品」の基本三部構成
〈はじめ〉①、②段落
〈なか〉 ③~⑥段落
〈おわり〉⑦段落
〈おわり〉である⑦段落には、「まとめ」「主張」「要旨」が述べられています。
それぞれを区別して明らかにしてみましょう。
⑦段落を文ごとに書き出すと次のようになっています。
[1文目]わたしは、工芸品をのこすことは、日本の文化やげいじゅつ、そして、かんきょうを未来につないでいくことになると考えます。
[2文目]だから、みなさんにもぜひ、工芸品を手に取ってみてほしいと思います。
[3文目]そして、工芸品にみりょくを感じたら、「一人の職人」になって、先生や友達、家族に自分がどう感じたのかを伝えてみてください。
1文目は、これまでの➀~⑥段落の内容をまとめた「まとめ」になっています。
2文目は、1文目の「まとめ」を踏まえた、筆者の希望が述べられています。
したがって、2文目は「主張」です。
1文目、2文目は工芸品の魅力について述べていますが、3文目は、「工芸品の魅力」から一歩進め、「その魅力を『一人の職人』として伝える側に立ってほしい」という筆者の思いを述べています。
これらのことから、「未来につなぐ工芸品」の⑦段落は、次のようになっていることがわかります。
「未来につなぐ工芸品」⑦段落
[1文目]…まとめ
「工芸品をのこすことは、日本の文化やげいじゅつ、そして、かんきょうを未来につないでいくことになる。」
[2文目]…主張
「工芸品をのこすために、ぜひ手に取ってみりょくを感じてほしい。」
[3文目]…要旨
「あなたも、工芸品のみりょくを多くの人々に伝える『職人』になってほしい。」
「要旨」は、「筆者の考えの中心」でもありますから、この文章で筆者が最も言いたかったことは「あなたも、工芸品のみりょくを多くの人々に伝える『職人』になってほしい。」だとわかります。
もう1つ、「和の文化を受けつぐ ~和菓子をさぐる~」(東京書籍 5年)についても、同様の方法で見てみましょう。
「和の文化を受けつぐ ~和菓子をさぐる~」の基本三部構成
〈はじめ〉①段落
〈なか〉 ②~⑮段落
〈おわり〉⑯、⑰段落
「未来につなぐ工芸品」では〈おわり〉が1段落だけで構成されていましたが、「和の文化を受けつぐ」では、⑯、⑰段落の2段落で構成されています。
「和の文化を受けつぐ ~和菓子をさぐる~」の⑯、⑰段落
⑯段落
[1文目]このように、和菓子の世界は、知るほどにおくが深いものです。
[2文目]長い間をへて、それぞれの時代の文化に育まれ、いく世代もの人々の夢や創意が受けつがれてきた和菓子には、おいしさばかりでなく、伝統的な和の文化を再発見させてくれるようなみりょくがあるといえるでしょう。
⑰段落
[1文目]わたしたちの毎日の生活の中には、和菓子に限らず、筆やろうそく、焼き物やしっ器、和紙、織物など、受けつがれてきた和の文化がたくさんあります。
[2文目]そこにどんな歴史や文化との関りがあるのか、どんな人がそれを支えているのかを考えることで、わたしたちもまた、日本の文化を受けついでいくことができるのです。
⑯段落は、「このように」という接続語ではじまっていることからもわかるように、〈なか〉で述べられた「具体例」の「まとめ」です。
また⑯段落の2文目の後半では、「まとめ」を受けて筆者の考えを述べているので、「主張」です。
和菓子のみりょくを、〈なか〉の「具体例」から一般化して述べていますので、「まとめ」よりも抽象化されていることがわかります。
⑰段落に入ると、「和菓子に限らず……」と、和菓子以外の日本の伝統文化全般に話を広げます。⑯段落で述べたことをさらに一般化し、抽象化します。
したがって、⑰段落で述べていることが「要旨」だとわかります。
整理すると、次のようになります。
「和の文化を受けつぐ ~和菓子をさぐる~」の「まとめ」「主張」「要旨」
まとめ
「和菓子は、長い時代を経て、それぞれの時代の文化に育まれ、いく世代もの人々の夢や創意が受けつがれてきた。」
主張
「和菓子は、おいしさばかりでなく、伝統的な和の文化を再発見させてくれるような魅力があるといえる。」
要旨
「和の文化について、どんな歴史や文化との関わりがあるのか、どんな人がそれを支えているかを考えることで、日本の文化を受けついでいくことができる。」
これらのことから、この文章で筆者が最も言いたかったことは「和の文化について、どんな歴史や文化との関わりがあるのか、どんな人がそれを支えているかを考えることで、日本の文化を受けついでいくことができる。」だとわかります。
説明文の学習では、「筆者がこの文章でもっとも言いたかったことは何でしょうか。」といった課題が示されることがよくあります。
そして、説明文の内容を読み解くことによって、この課題に対する答えを導き出そうとします。
しかし、小学校の国語の学習は、内容をとらえるための「読みの力」を子どもたちが獲得することが大きな目的の一つです。
「読みの力」がまだ十分に身についていない子どもたちに内容を読み解くことを求めるのは、おかしな話だと私は思います。
今回のように、
「筆者の考えの中心となるもののことを『要旨』というよ」
「『要旨』は、こうやってとらえるんだよ」
という説明をすれば、子どもたちはその教材だけでなく、ほかの説明文の読みでも使うことのできる「読みの力」を獲得することができます。
それが、「汎用的な読みの力」であり、子どもたちがこれからの人生でずっと役立てていくことのできる力です。
そういった「汎用的な力」を獲得することが、国語に限らず、小学校のすべての学習に共通して大切なことなのではないでしょうか。
私の連載は「国語の学習」をテーマにしたものでしたが、小学校で何を教えていくべきなのかを考えるきっかけにしていただければと思います。
これからも、ずっと一緒に学んでいきましょう。