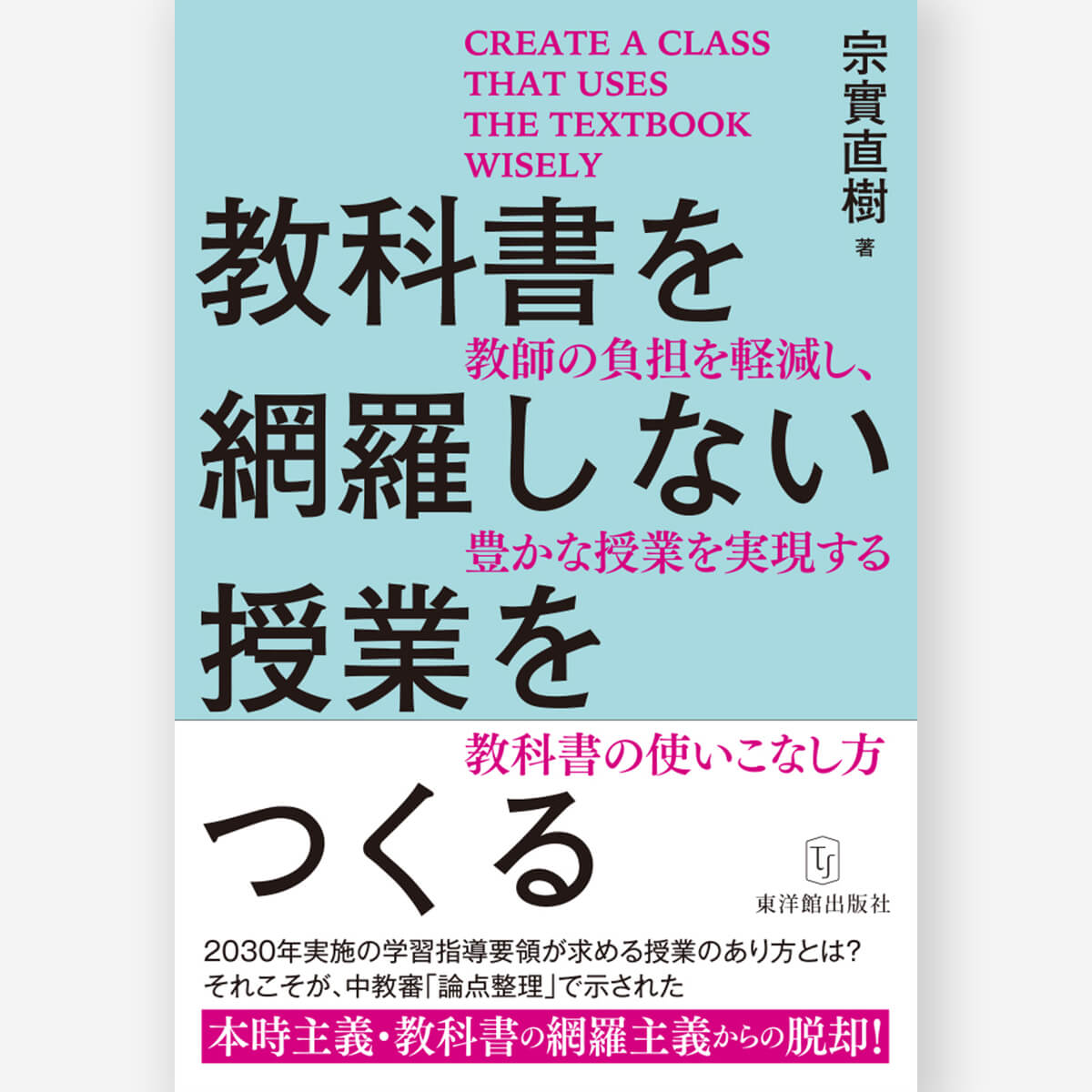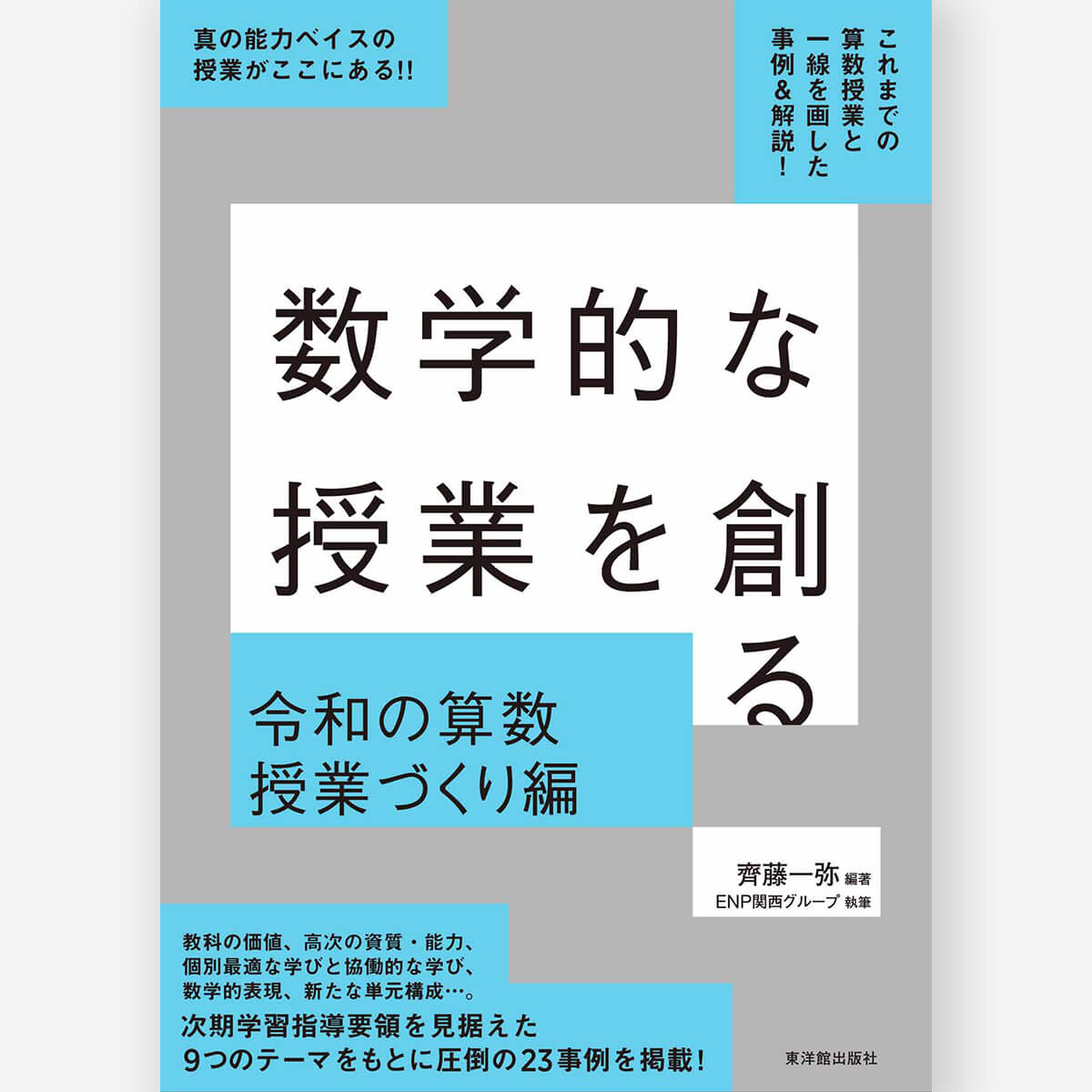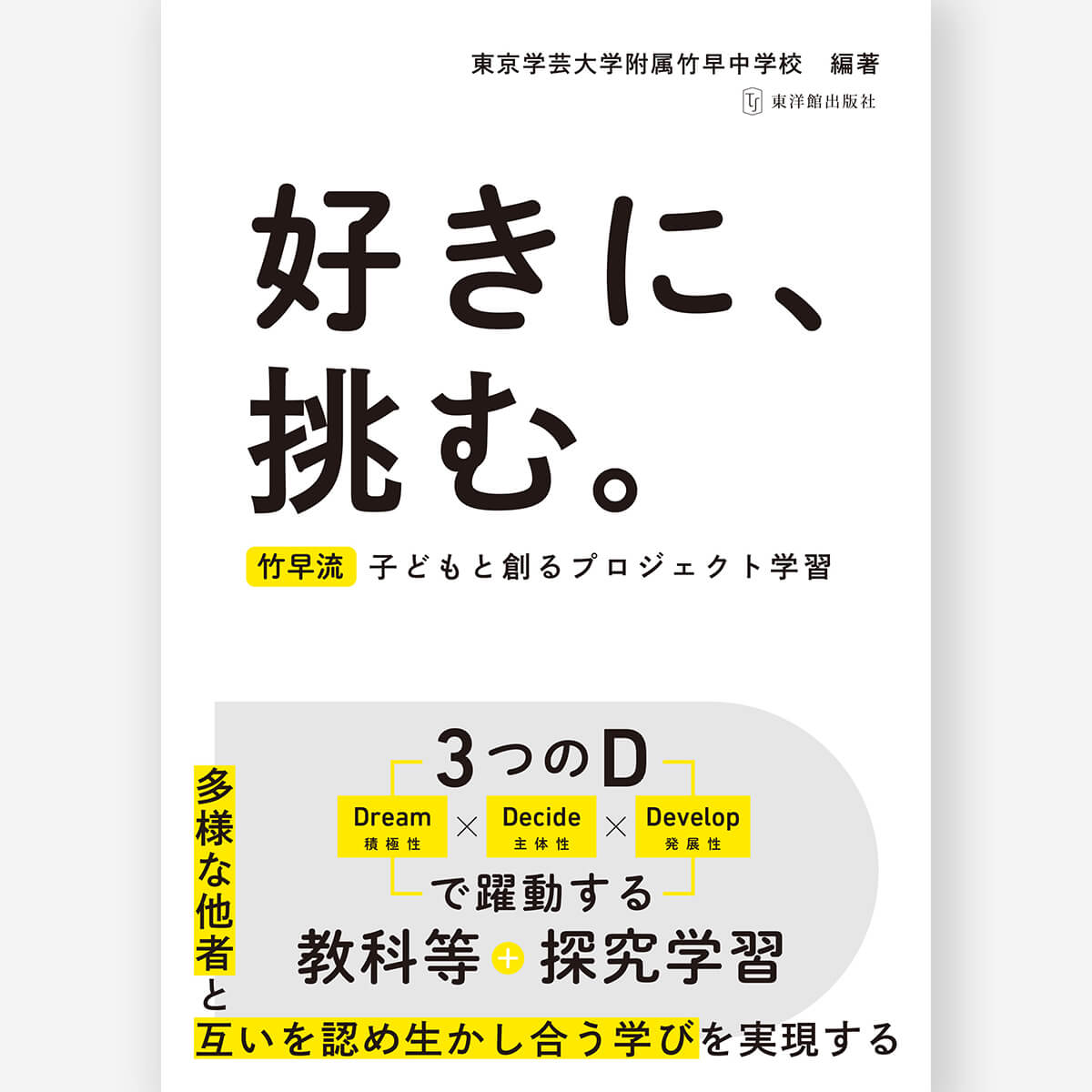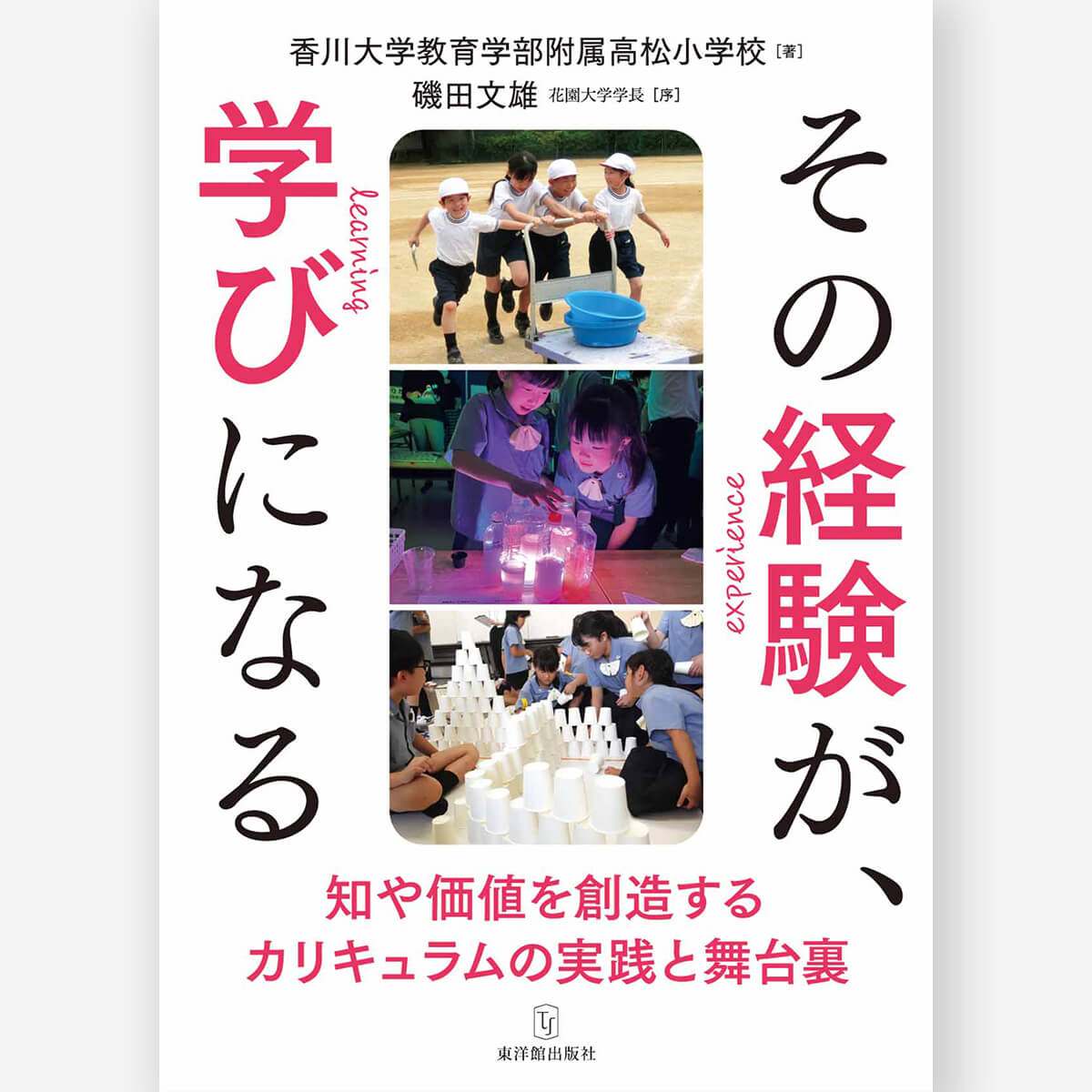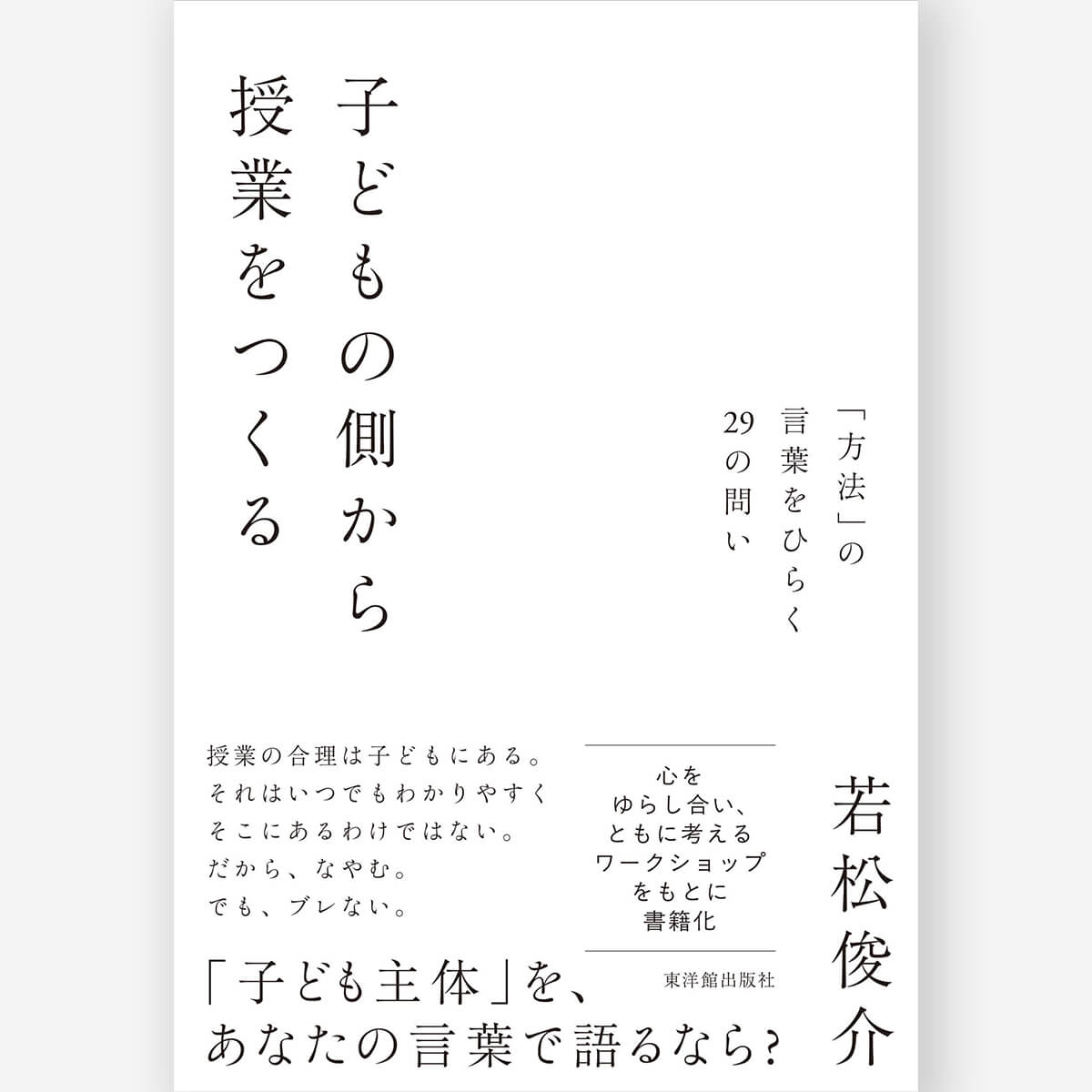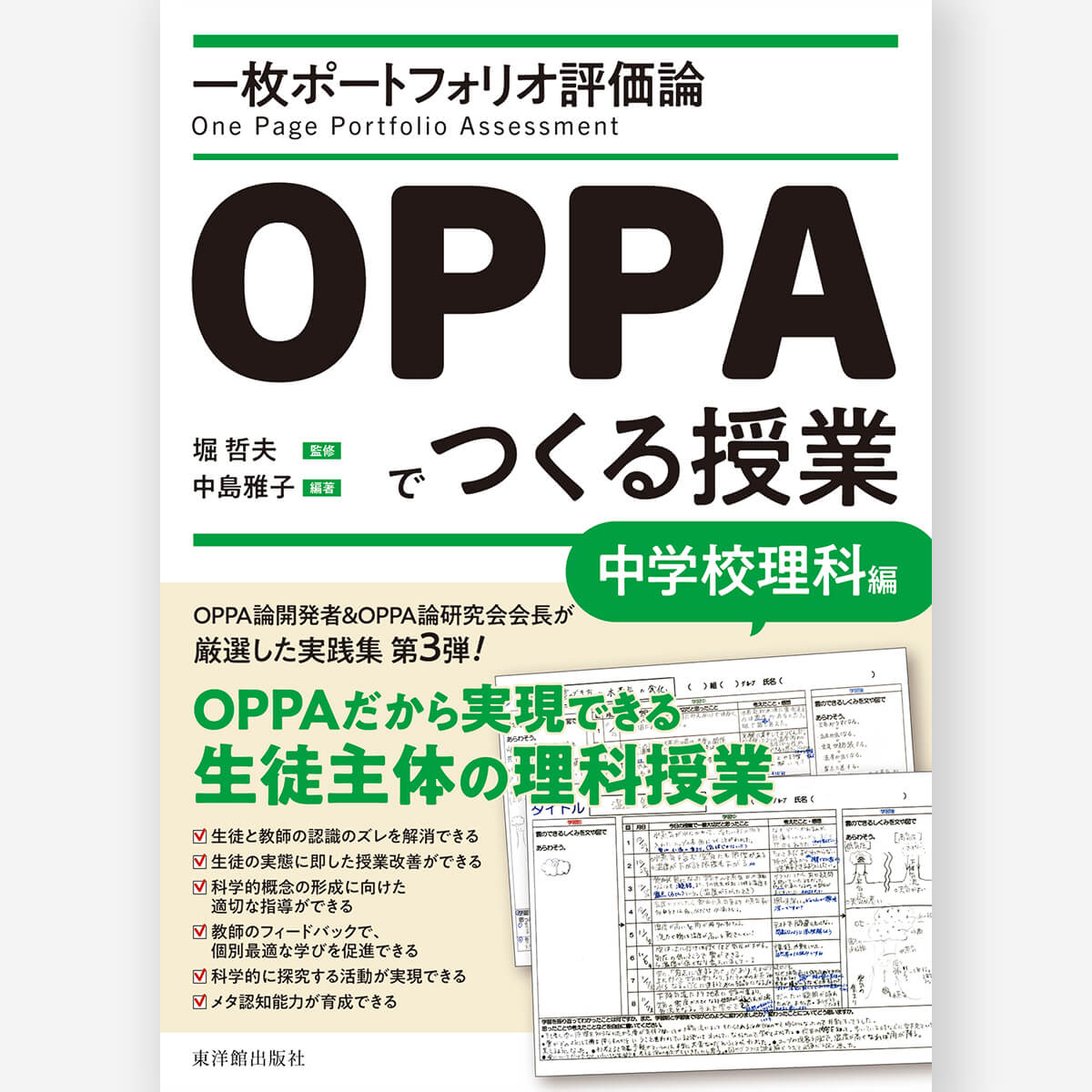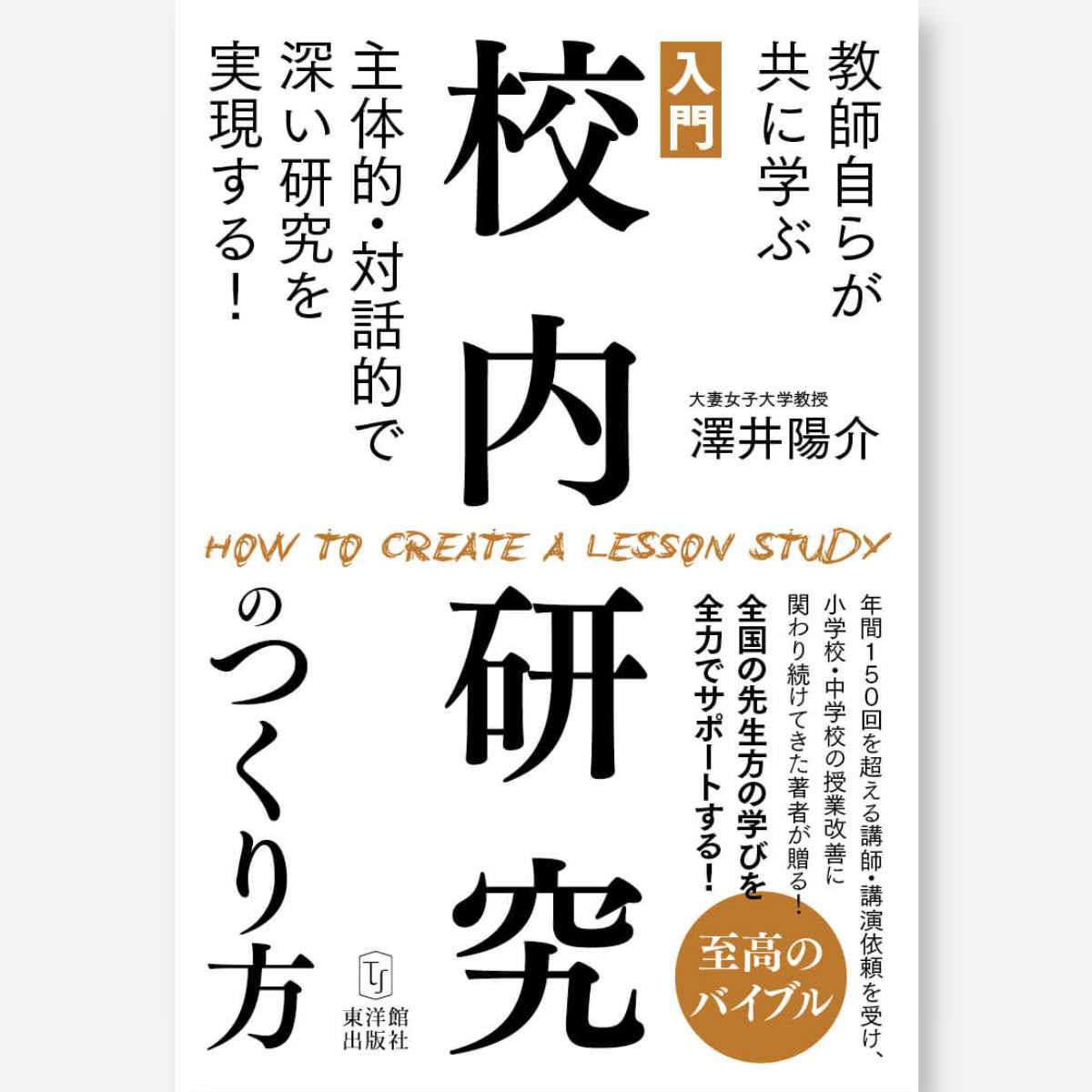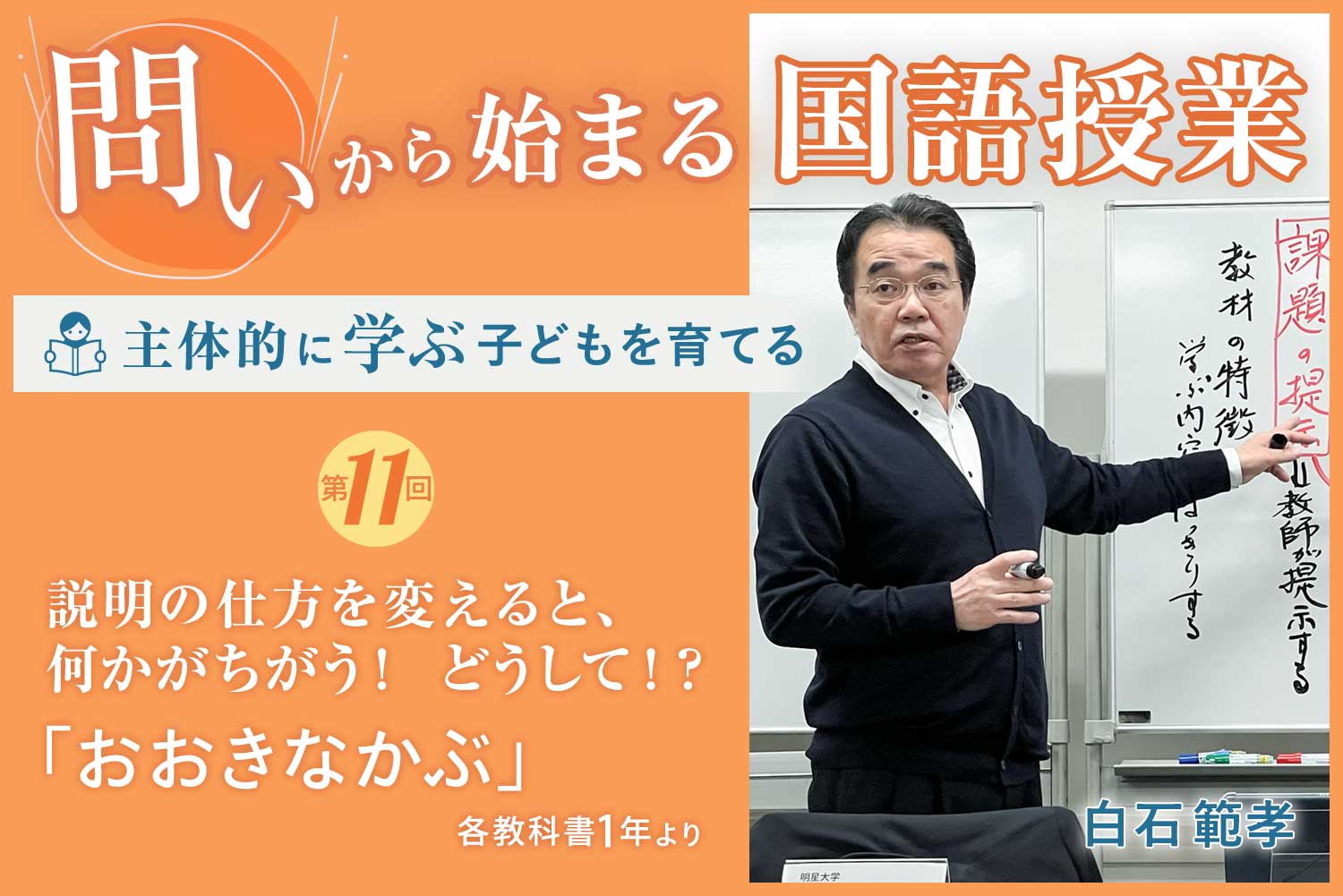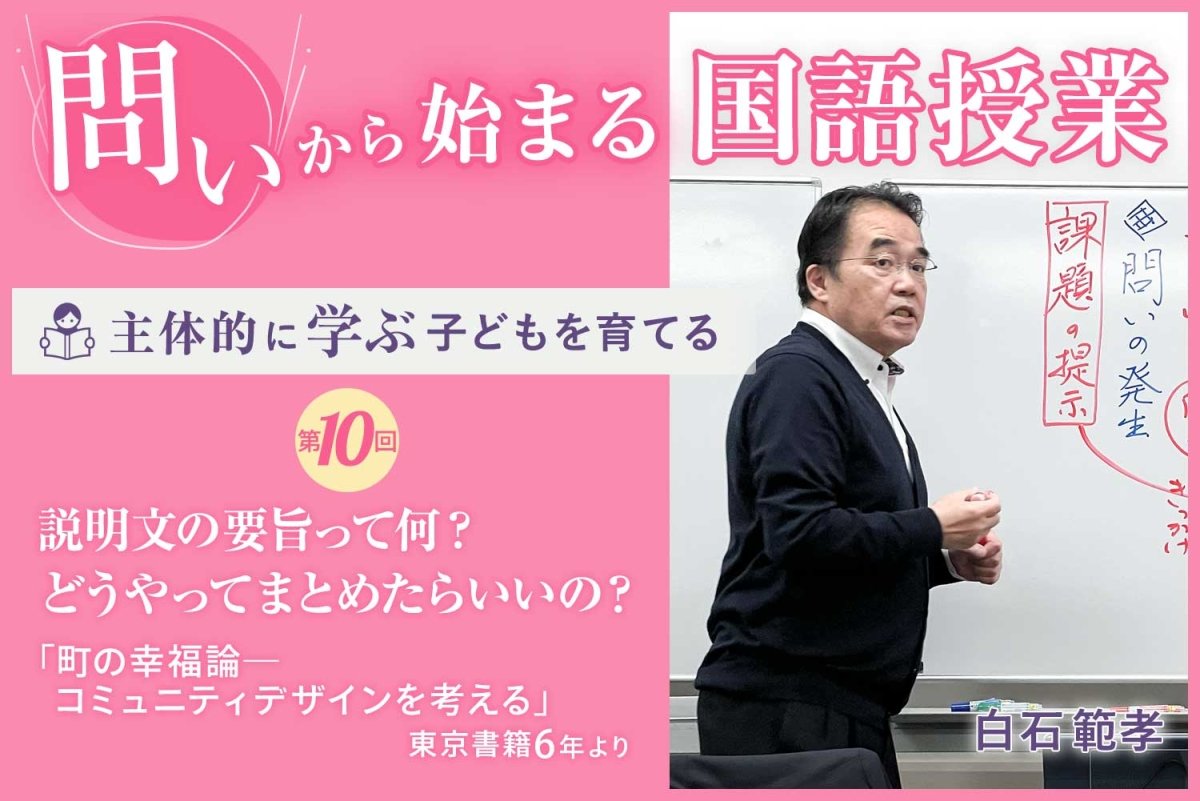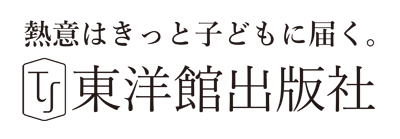資質・能力を育成する学びの鍵として、「オーセンティック(真正な/本物の)」という概念があります。
教育分野でたびたび耳にするこの概念、子どもの姿や授業場面としては具体的にどのような様子をイメージしていけば、理解が深まるのでしょうか。
基本的な考え方を探るため、上智大学の奈須正裕先生に教えていただきました。
状況に埋め込まれた学習
――「オーセンティックな(真正な/本物の)学習」という言葉を、教育界隈で耳にすることがあります。奈須先生のご著書『「資質・能力」と学びのメカニズム』(2017、東洋館出版社)でも、その重要性が述べられていますが、いまいちど、この概念について教えてください。
近年の学習研究は、人々の直観や常識に反する事実を数多く見出してきました。その代表格が、学習の転移は簡単には生じないというものです。
たとえば、2007年度の全国学力・学習状況調査では、同じ平行四辺形の面積に関する知識を用いれば正答できる問題であるにもかかわらず、授業で教わった通りの尋ねられ方をするA問題の正答率が96%だったのに対し、図形を地図中に埋め込んだB問題では正答率は18%まで低下しました。B問題を巡って日本中の先生方が頭を悩ませてきた、しっかりと「習得」させたのに意外なほど「活用」が利かないというこの現象は、学習の転移が簡単には生じないという人間の学習の原理の現れにほかなりません。
転移が簡単に生じないのは、学習や知性の発揮が本来的に領域固有なもので、文脈や状況に強く依存するからです。単に知識を学べばよいのではなく、どのような文脈で学んだかが、「活用」が利くかどうかやその範囲など、学ばれた知識の質を大きく左右するのです。 従来の授業では、習得した知識がどんな場面でも「活用」できるように、つまり転移が生じるようにとの配慮から、むしろ一切の文脈や状況を捨象して純化し、一般的命題として教えてきました。しかし、これは間違いでした。何らの文脈も伴わない知識は、同じく何らの文脈も伴わないA問題のような特異な状況を除けば、現実の意味ある問題解決はおろかB問題にすら転移しません。近年、大学入試の問題も変わりつつあり、A問題のような出題は激減しています。断片的な知識の詰め込みでは、もはや受験も突破できないのです。
ならば逆に、具体的な文脈や状況を豊かに含み込んだ本物の社会的実践への参画として学びをデザインすれば、学ばれた知識も本物となり、現実の問題解決に生きて働く、つまり転移するのではないか。これが、オーセンティックな学習の基本的な考え方です。
解けない問題
――本物の社会的実践への参画として学びをデザインすることによって、具体的にはどのような変化が、子どもたちの姿として見られてくるのでしょうか。
従来の授業では、たとえば、割り算を教えた後の適用題に、割り算で解ける問題ばかり出題してきました。子どもは何も考えず、割り算を実行します。これではドリルと同じで、今日学んだはずの割り算という新たな数理の意味理解にはほとんど貢献しません。
そこで、割り算で解ける問題に加えて引き算で解ける問題、さらに「140人の子どもがバスに乗ります。バスの運転手さんは35歳です。何台のバスが必要ですか?」のような解けない問題も出題します。子どもたちは140を35で割ったり、解けないことに気づいて「引っかけじゃないか。ずるい」と不満げに言うでしょう。しかし、それでいいのです。
解けない問題を出すのは、現実世界の問題解決では、そもそもこの問題が解決可能かどうかから判断しなければいけないからです。あるいは、
「先生、このままでは解けません」
「バス1台が何人乗りかを教えてくれれば解けます」
と言える子どもにしたいのです。なぜなら、それこそが割り算を理解しているという状態にほかなりません。どのような問題場面にどのような理由で適用可能なのか、適用条件は何で、どのような変換を施す必要があるのかまで伴っていてはじめて、知識は自在に「活用」が利くようになるのです。
心配しなくても、子どもたちはすぐにポイントをつかみ、勉強や問題解決に対する構えまで変化させてきます。なぜなら、それが学習や知識の本来の姿、つまりオーセンティックなことは子どもにも直感的にわかりますし、その方が断然いいと感じるからです。
“教材”としての教師の背中
――日々の授業としては、どのような展開がありえるでしょうか。まずはじめに心がけておきたいことなどを、教えてください。
実生活・実社会のリアルな文脈で教科を学ぶ授業に加えて、「科学する」理科、「文学する」国語、「アートする」美術など、学びの文脈や状況を各教科の背後にある本物の文化創造の営みになぞらえていく授業づくりもまた、オーセンティックな学習を生み出します。
たとえば、理科の実験では操作の不正確さや測定誤差、実験材料のばらつきなどにより、多少なりともデータが荒れるものです。とりわけ、子どもは操作に慣れておらず、いい加減に取り組んだりもして、法則性が見出だせないほどに不安定になることがよくあります。
しかし、だからといって苦し紛れに「本当はこのグラフはまっすぐになるんですよ」などとしてはいけません。それはデータの無視や捏造であり、最も反科学的な態度だからです。というわけで、ここは徹底して科学的な態度で臨みたいと思います。
たとえば、「みなさんのデータをグラフにしてみましたが、このグラフからは何のきまりも関係も見出せそうにありません。ですから、この2つの間には何の関係もないというのを、クラスの結論にしていいですか」と尋ねるのです。子どもたちはあわてて「先生、教科書には関係があると書いてあります」と言うかもしれません。
「教科書にどう書いてあろうが、実験結果は関係のないことを示しています。みなさんが一所懸命に、しっかりと正確にデータを取った結果ですからね。ほかはどうか知りませんが、2組としては関係がないということにするしかないでしょう」
「いや、先生、もしかすると、僕たちは実験でミスをしたかもしれないし」
「そうですか。ミスをしたということであれば、話が違ってきます」
「先生、私たちの班はちょっとふざけていたので、それも結果に影響したと思います」
「それでは、このデータは信用できませんね。どうすればいいと思いますか」
「できれば、もう一度真面目に、しっかりと実験をして、正確なデータを取りたいです」
「そうですか。どこでミスをしたのか、見当はつきますか。そして、今度はふざけないで実験ができますか。できそうであれば、来週、もう1回挑戦してもいいです」
翌週の実験では、子どもは大真面目に、そして万事慎重にことを運ぶでしょう。すると、データは見違えるようにきれいに整ってきますし、今度はきまりも無理なく見出せます。と同時に、それでもなお、データに少々の荒れは残るのです。
子どもたちは不思議がったり残念がったりしますが、この厳然たる事実が、実験という近代科学が確立してきた知識生成の方法の真実です。このことを受け入れ、なぜそうなるのかを理解し、だからこそ「誤差の処理」に関する精緻な方法論が存在することを知り、なるほどと納得すると共に、さらに深めていきたいと願うでしょう。
その教科の「見方・考え方」を子どもが感得する簡潔にして最善の方法は、教師がその身体や言語を駆使し、「見方・考え方」という抽象を、子どもにもわかる多様な具体的現れとして教室で体現することです。子どもにとって最大の教材は、教師の背中なのです。
「学びの質」が明確になって初めて意味を成す“教育方法の選択”
――今月末には、武蔵野大学で教育心理学の視点から教科教育(主に算数)の研究を進めてきた小野健太郎准教授の初めての単著『オーセンティックな算数の学び』が刊行されます。小野先生は奈須先生のもとでも長らく学んでこられた研究者ですが、本書での小野先生の提案を、どのようにお感じになられましたか?
オーセンティックな学習に関して部分的な紹介や解説はこれまでにもありましたが、特定の教科を取り上げ、さらに現実の授業づくりを通してオーセンティックな学習の原理と実際について詳述した著作は、我が国では本書がはじめてかもしれません。
まず、豊富な実践事例と、そこに立ち現れる多様な子どもの姿、その深く的確な解釈のすべてが、大いに参考になるでしょう。とりわけ、事例の多くは教科書などオーソドックスな教材を足場にしているので、いくつかのポイントを着実に押さえることにより、現在の授業からオーセンティックな学習へと向かう筋道や手立てが無理なく理解できると思います。
また、どうすれば算数の学びがオーセンティックになるかという教育方法学的な問いとともに、そもそも算数・数学とは何かという教育内容論的な問いに多くのページを割いている点が、本書の大きな特徴でしょう。読者はもっと直截に方法や技術について知りたいかもしれませんが、目指すべき子どもの学びの質が明確になってはじめて、用いるべき教育方法の選択や決定が根拠をもちます。その意味で、この複雑で困難な作業は不可欠でした。
具体的には、フィクションとノンフィクションという言葉を手がかりに、算数・数学の世界の構造的把握を試みるという斬新な提案ですが、とてもわかりやすく、説得的です。なにより、そこから質の高い学習や授業を生み出す具体的な論理や手立てが生み出されているわけで、その意味でもこの試みは大いに奏功していると言えるでしょう。
本書の刊行が、オーセンティックな学習の普及と発展に寄与することを願っています。
[参考文献]
奈須正裕『「資質・能力」と学びのメカニズム』2017年、東洋館出版社
国立教育政策研究所教育課程研究センター『平成19年度 全国学力・学習状況調査解説資料(小学校 算数)』2007年