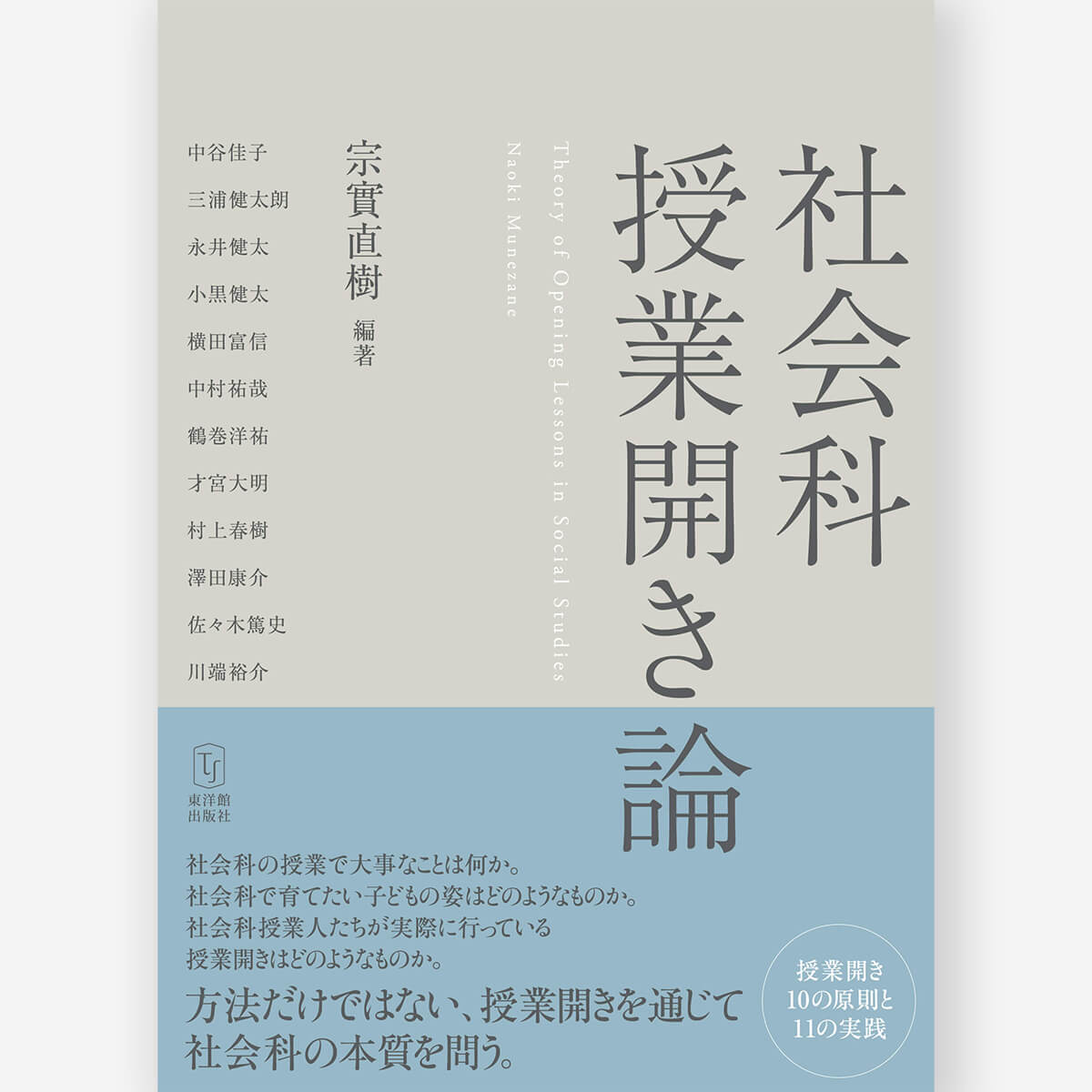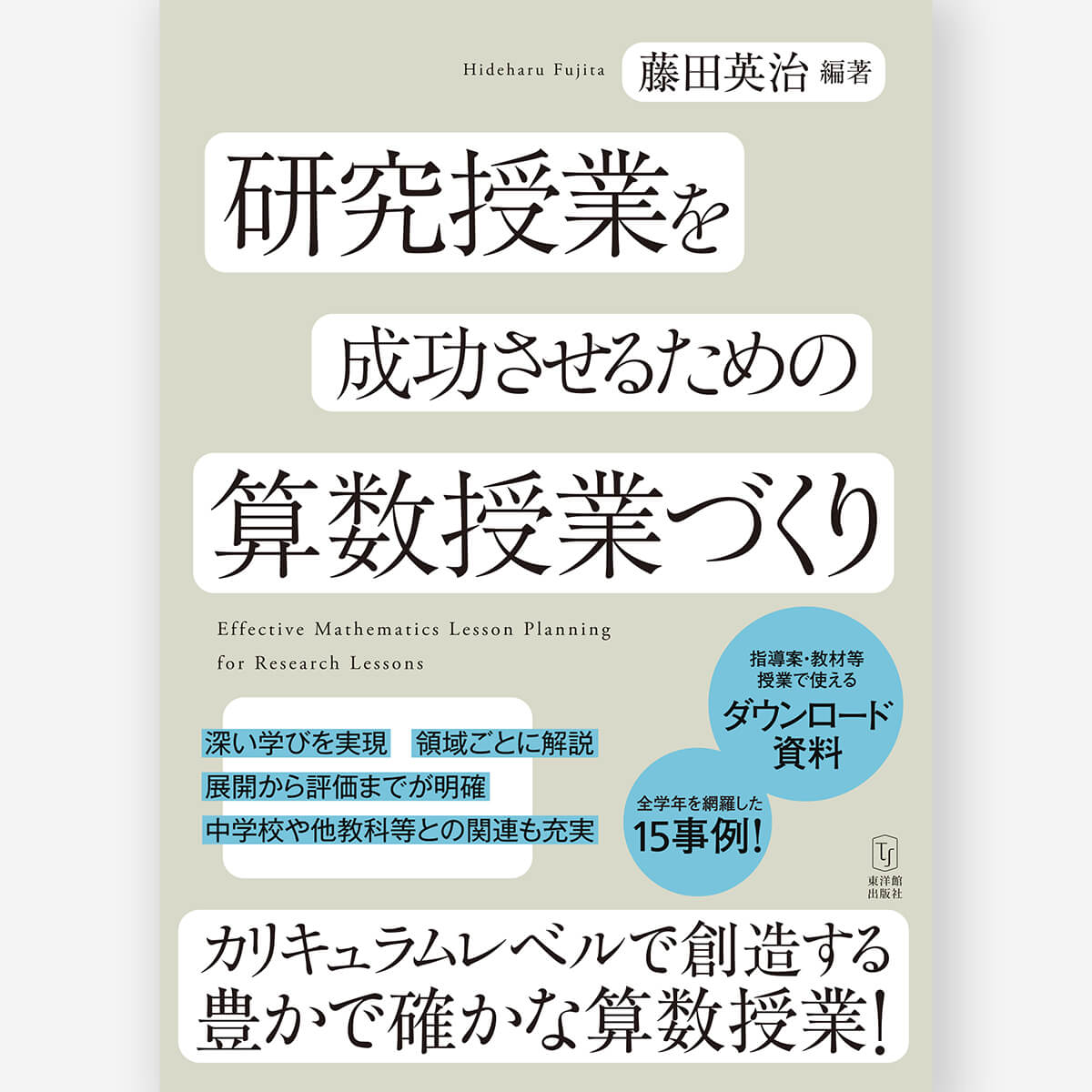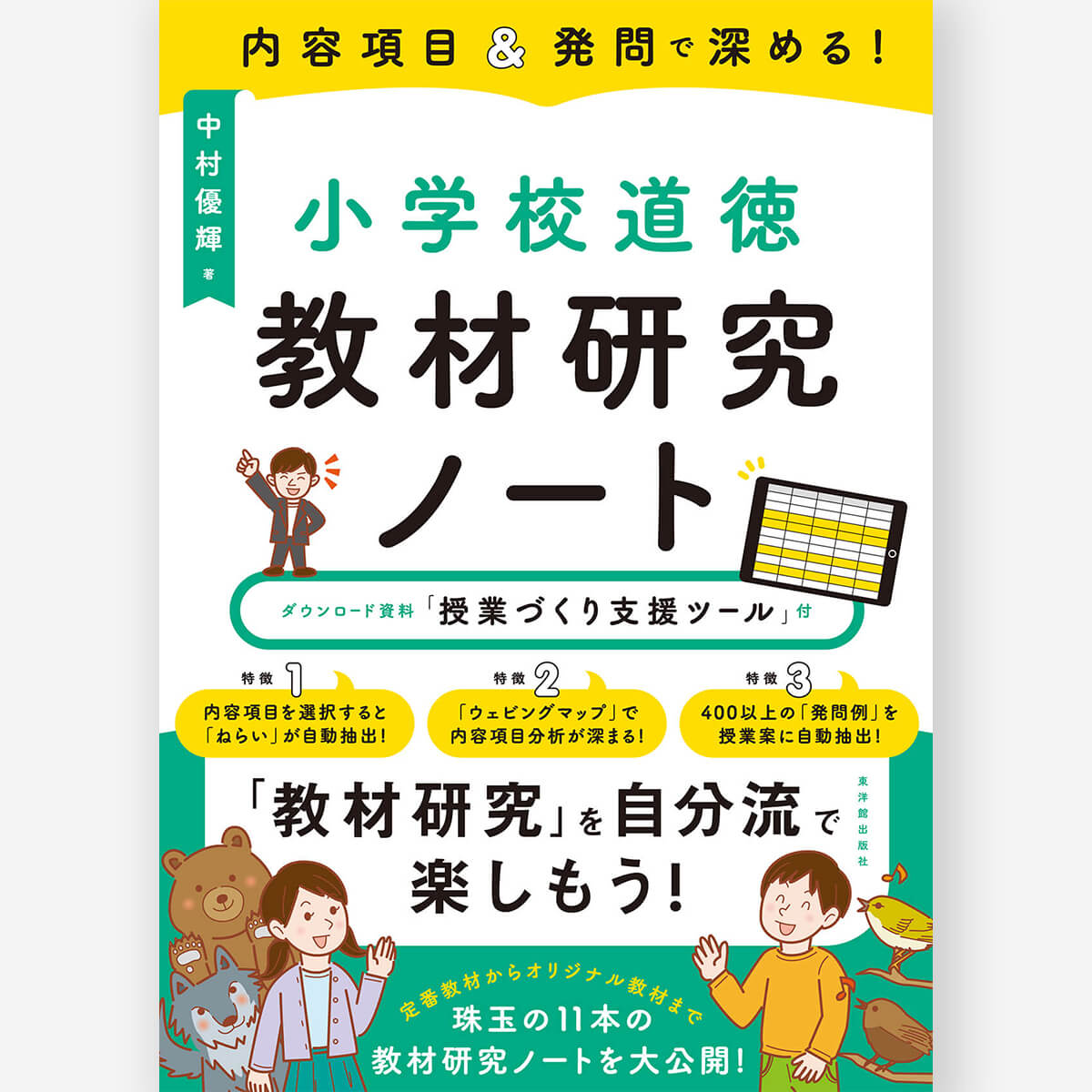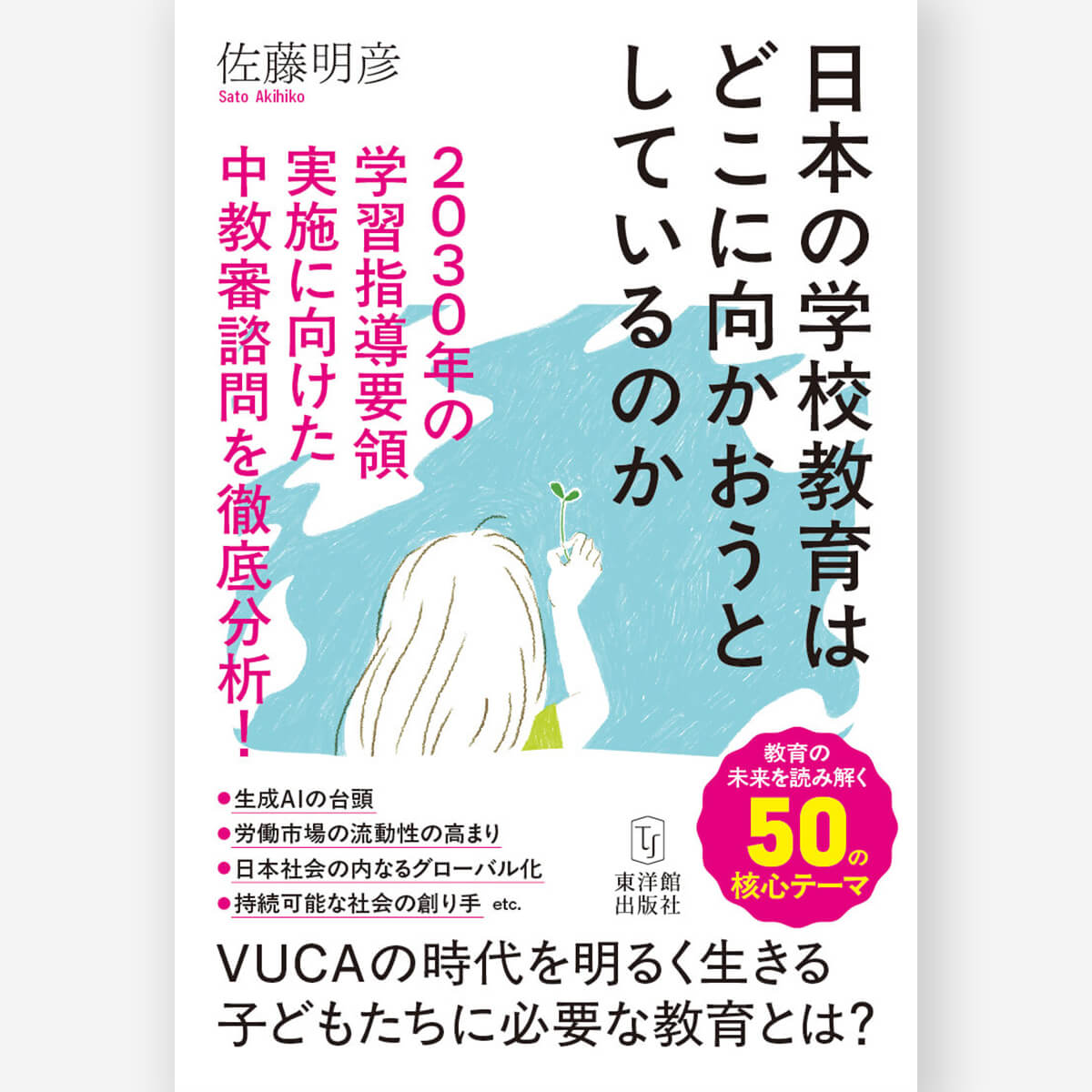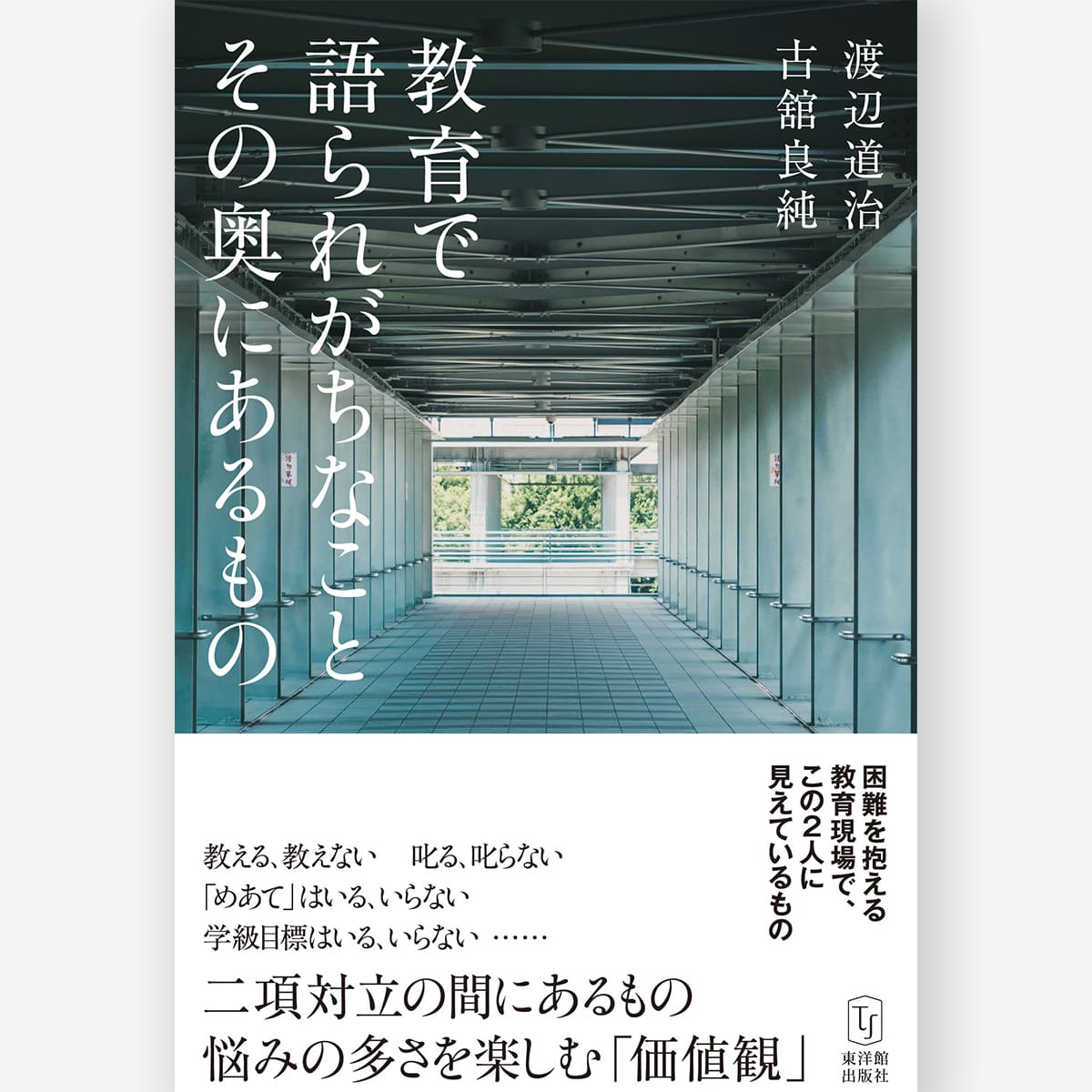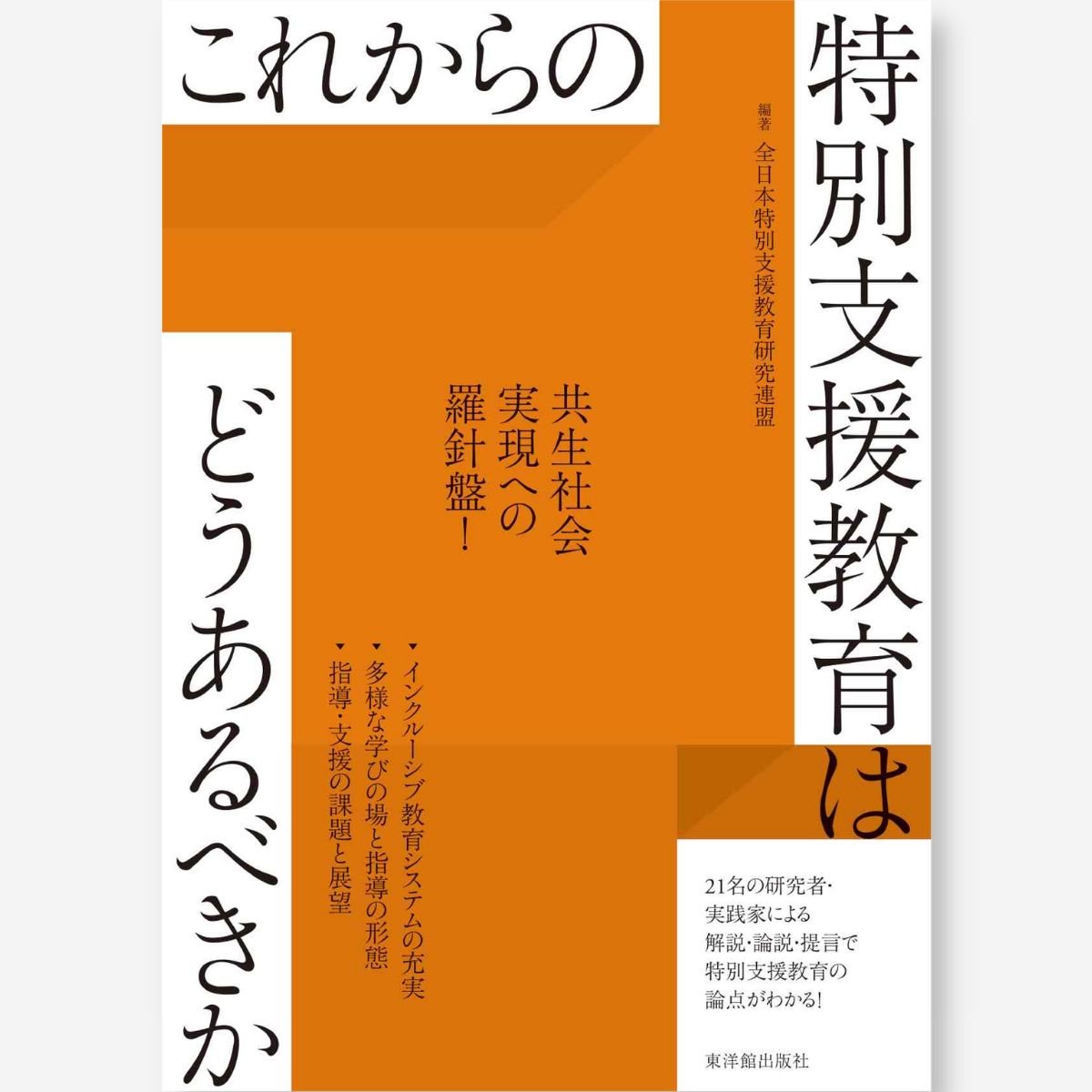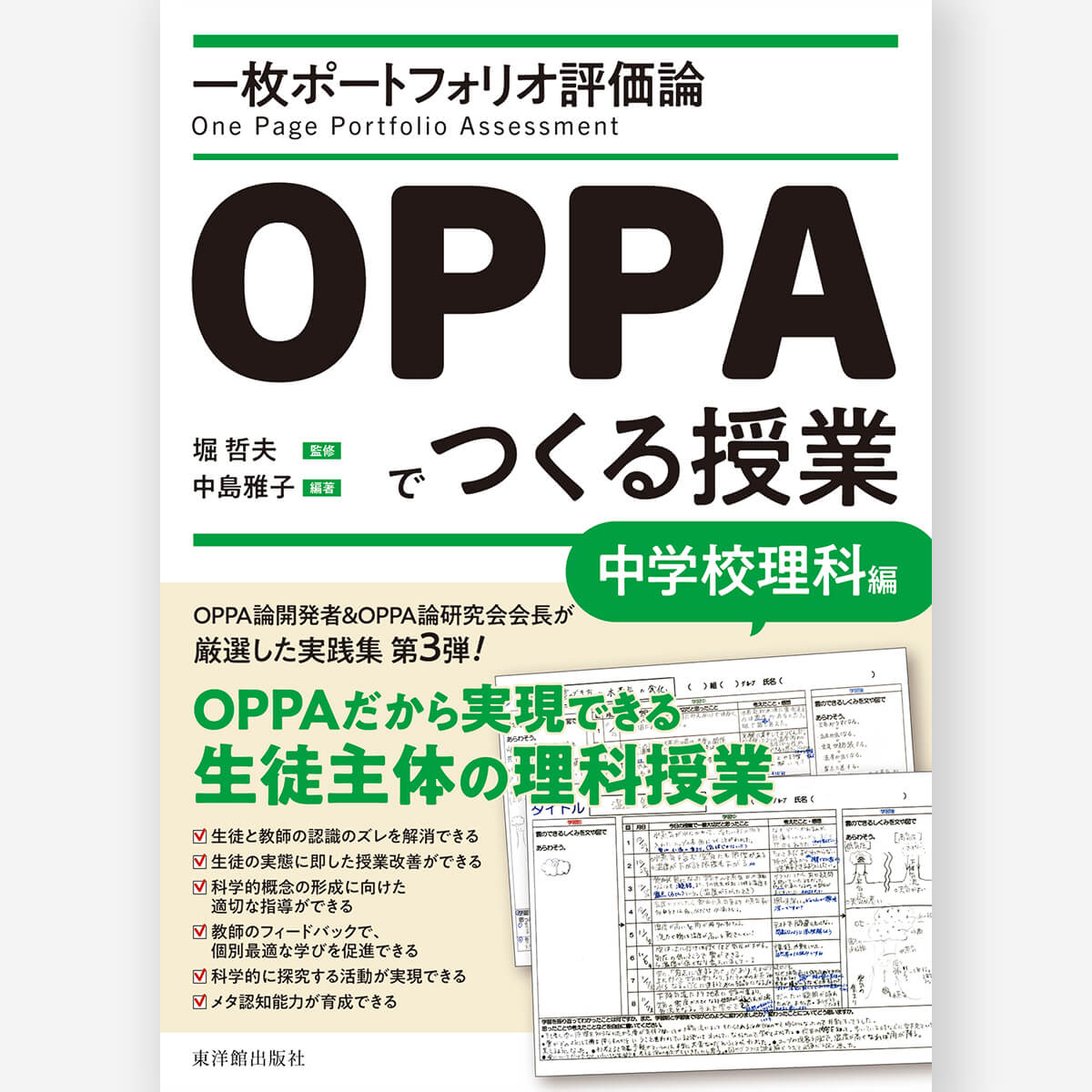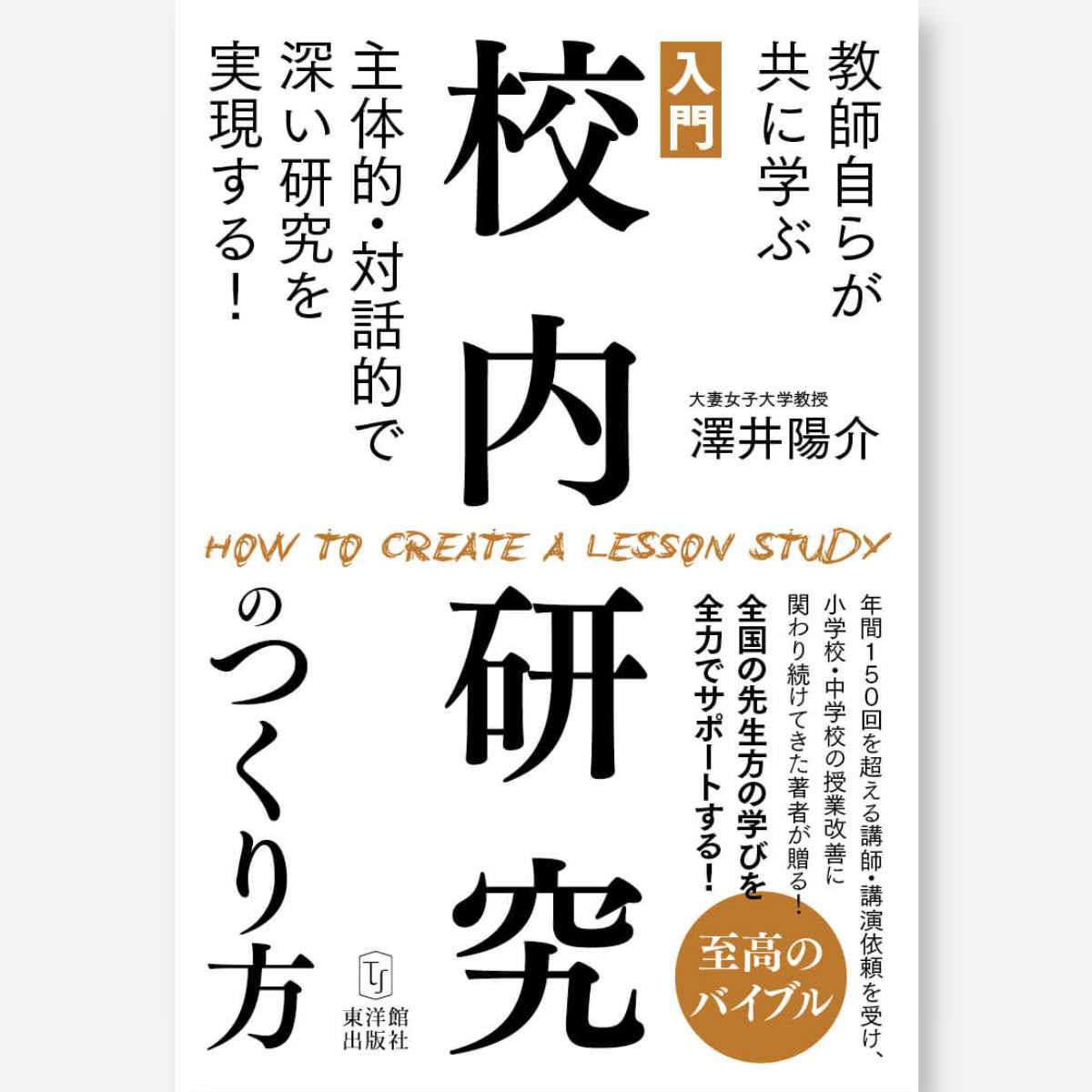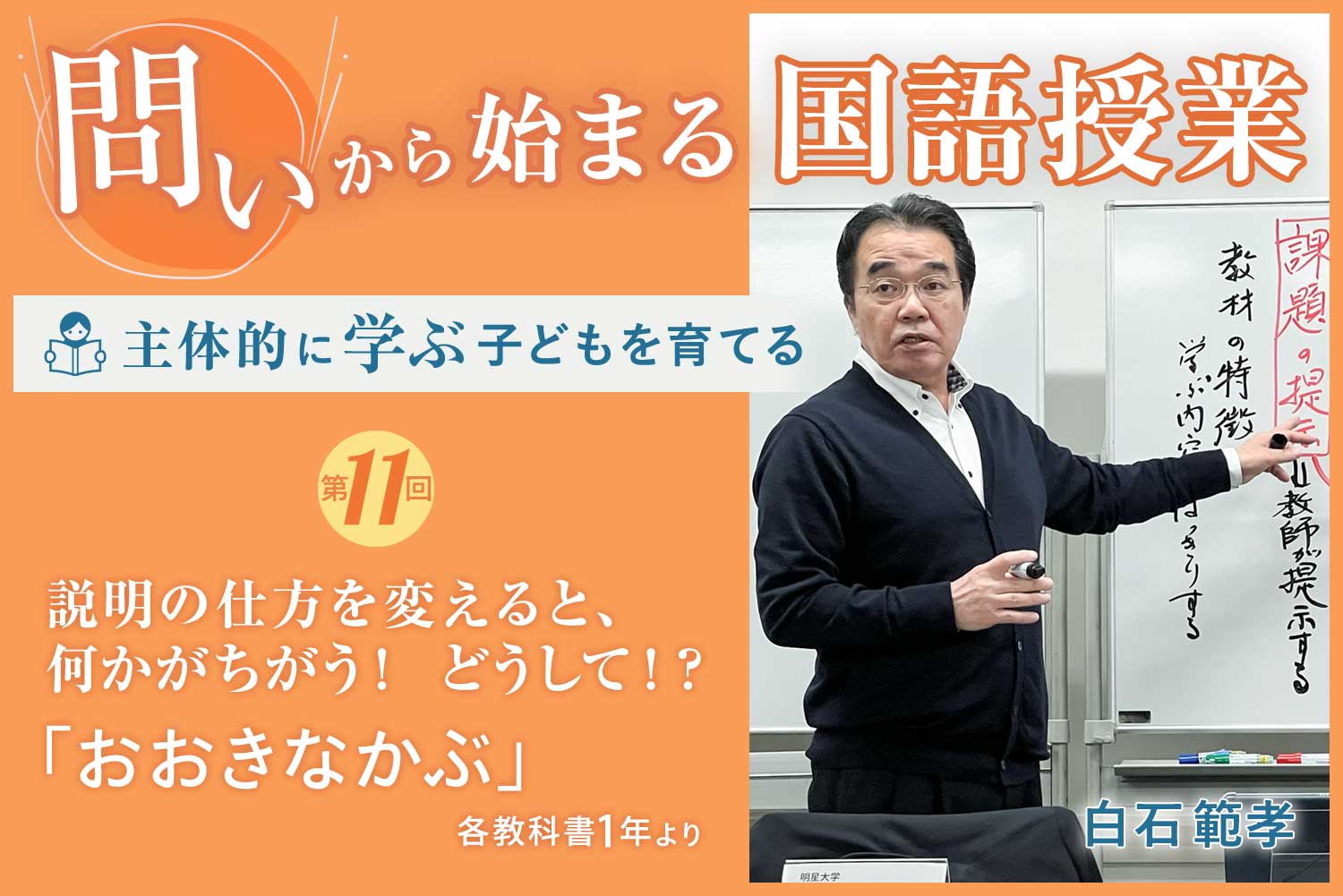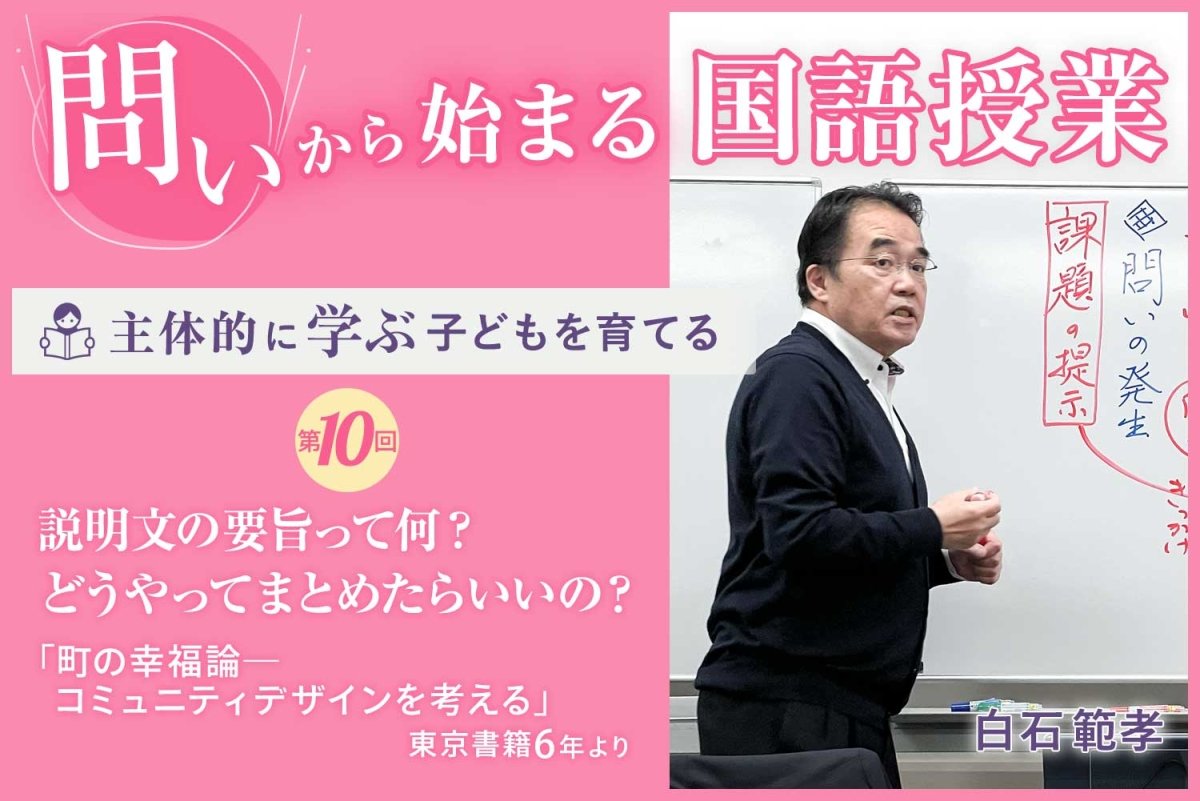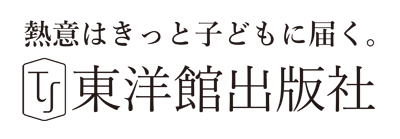「思いがけなくうまくいった」オンライン授業
大学でのオンライン授業が始まったのは、だいたい2020年の春からです。1月から先生方は必死になってリモート授業のためのコンピューターリテラシーを身につけていった。そして、4月からオンライン授業が始まった。当初はトラブルがたくさんありました。でも、1か月くらい経ったところで、だいたい順調に回るようになった。
それでも、オンライン授業では、教える側にも教わる側にもいろいろと不満が多いだろうと僕は予測していたんです。8月ぐらいになって、大学の先生たちとご一緒する機会があったので、「オンラインどうです?」と訊いたんです。すると、意外なことに、「思いがけなくうまくいっている」というお答えを頂いた。ちょっと驚きました。どこがうまくいったのかを伺うと、脱落者が減ったということでした。
ふつう、4月から授業が始まって5月の連休明けぐらいで、履修者の2、3割は脱落します。授業に興味が持てない、授業についてゆけないので脱落する。それぐらいの歩留まりだということを前提にして僕たちは授業をしていました。ところが、オンラインでその歩留まりが良くなったというんです。
授業を休むと、学生のところに先生からメールが来る。その日の配布物や宿題が添付ファイルで送られてきて、先生から「今日はこんな授業をやりました。質問があったらメールしてください。また来週」というくらいのコメントがついている。でも、その程度の定型的な呼びかけでも、学生にとってはけっこう親身に感じられるらしく、翌週は出席する。
学生からすると、「先生に個体識別された」ということがけっこう安心感を与えるらしいんです。ふつう大教室の授業なんかだと、教師はまずほとんど学生を個体識別していません。中学高校の場合と違って、学生の固有名を覚えるということは諦めている。授業の後に教壇まで質問に来たり、オフィスアワーに訪ねてきたり、際立って面白いレポート書いたりする学生だと名前を覚えますけれど、100人のクラスで半期の講義をして、名前を覚えるのは、せいぜい数人です。でも、オンラインだと教師と学生が一対一で繋がるチャンネルがある。だから、教師に固有名詞で呼びかけられる。その結果、脱落者が減った。レポートの提出率が上がった。そして、期末試験の成績が前年度より高くなった。
オンラインは対面授業ができなくなったことの代替手段だったはずだったけれど、場合によってはこちらの方がうまくいった科目もあった。その話を聴いて、僕はこれまで大学の教師は何をしていたんだろうといささか深刻な疑問を抱きました。
オンライン授業から見えた反省
大学というのは、これまで学生に対してずいぶん冷たかったのではないかと思ったんです。何回が授業に出て、それきりになった学生について、僕たちはフォローアップするということをしなかった。ゼミの場合は、ずっと休んだりすると、友だちに「あの子どうしたの?」って訊いたりしますけれど、大教室の授業ではやりません。そもそも大学というのは主体的に学ぶところだという前提がありました。自分に興味のあることはいくらでも学ぶことができる。本もあるし、研究施設もあるし、聴きたいことがあればいつでも研究室のドアは空いている。学ぶ意欲のあるものは大学の提供する学術的リソースをいくらでも享受することができる。
でも、それは逆から言えば、廊下で先生の袖をつかんで質問するとか、オフィスアワーに研究室のドアを叩くとかして、自分から積極的に動くことができない学生には学ぶチャンスが閉ざされるということです。高等教育は「自学自習」だというのはまさにその通りなんですけれども、それだと、知的能力も高いし、好奇心も旺盛なのだけれど、ちょっと引っ込み思案で、先生にいきなり話しかけるというようなことができないという学生を学びの機会から遠ざけることになっていた。こちらから少しでも手を差し伸べたら手をつかんできそうな学生を僕たちはケアしてこなかったんじゃないか……、そういうことに気がつきました。
「大学は主体的に学ぶ者のための場所だ」というのはもちろん正しいのです。でも、ちょっと冷たくはなかったか。あと一押しすれば、「主体的に学ぶ」気になりそうな学生へのサポートが足りなかったんじゃないか。そのことをオンライン授業で脱落者が減ったという話を聴いて、反省しました。
本当に「身体性がある」教育とはなにか
僕は自分のことを学生に対してかなり親切な先生のつもりでいたんですけども、それでもケアが足りなかったという気がしました。ゼミでも、十何人かのゼミ生の中で、食い付いてくる学生が一人でもいれば上出来だと思っていた。それくらいに期待のハードルを下げておかないと、こちらも疲れちゃうし、学生だって気重だろうと思っていたからです。でも、教育者として、僕は「学習弱者」に対してはかなり冷たかったかも知れません。教師の側からのあとわずかの働きかけがあれば学ぶ意欲が賦活されたかも知れないのに、「主体的に学べ」という大義名分を掲げてその手間を惜しんだのではないか。
僕は学校を辞めて10年になりますけども、そのことに退職10年後になって気がつきました。それがオンライン教育から僕が得た教訓の一つです。「謦咳に接する」とか「身体性の教育」とか言っていても、実際にかたわらにいる学生に対して手を差し伸べなかったら一緒にいる意味がないです。だから、「オンラインには身体性がない。対面なら身体性がある」というような単純な二項対立に落とし込んではいけないと思います。いくら対面で授業しても、教師の側に学生たちを個体識別して、脱落しそうになったら手を差し伸べるという気づかいがなかったなら「身体性がある」とは言い切れないからです。
(本記事の小見出しは、編集者が追記しました。)
教育を支える出版社として
1948年の創業以来、教育書の専門出版社として、主に学校教育に関わる出版活動を続けて参りました。学術書から実用書まで、教育書という分野において確かな地盤と実績を築いてきたという自負があります。
一方で、社会の大きな変化と、それに合わせた学校教育を含む教育情勢の変化も感じて参りました。創業前年の1947年には最初の学習指導要領が作成されました。当時はまだ「試案」という形で、戦争を省みる言葉とともに、子どもの興味や関心を大切にする児童中心主義の教育観が打ち出されました。
それから約70年が経ち、変わらない本質的な部分は現代に引き継がれつつも、全国の小中学校の9割以上に一人一台端末が配備され、授業風景が大きく変わろうとしています。学校から目を転じてみると、生産年齢人口の減少や科学技術の革新、地球規模での気候変動といった今まで人類が経験したことのない局面に直面しています。そのような変化の時代において、未来を生きる子どもたちのために、教育を支えるすべての人のために、何かまだできることがあるのではないだろうか――そのような思いから、本シリーズを新たに2022年より刊行いたします。