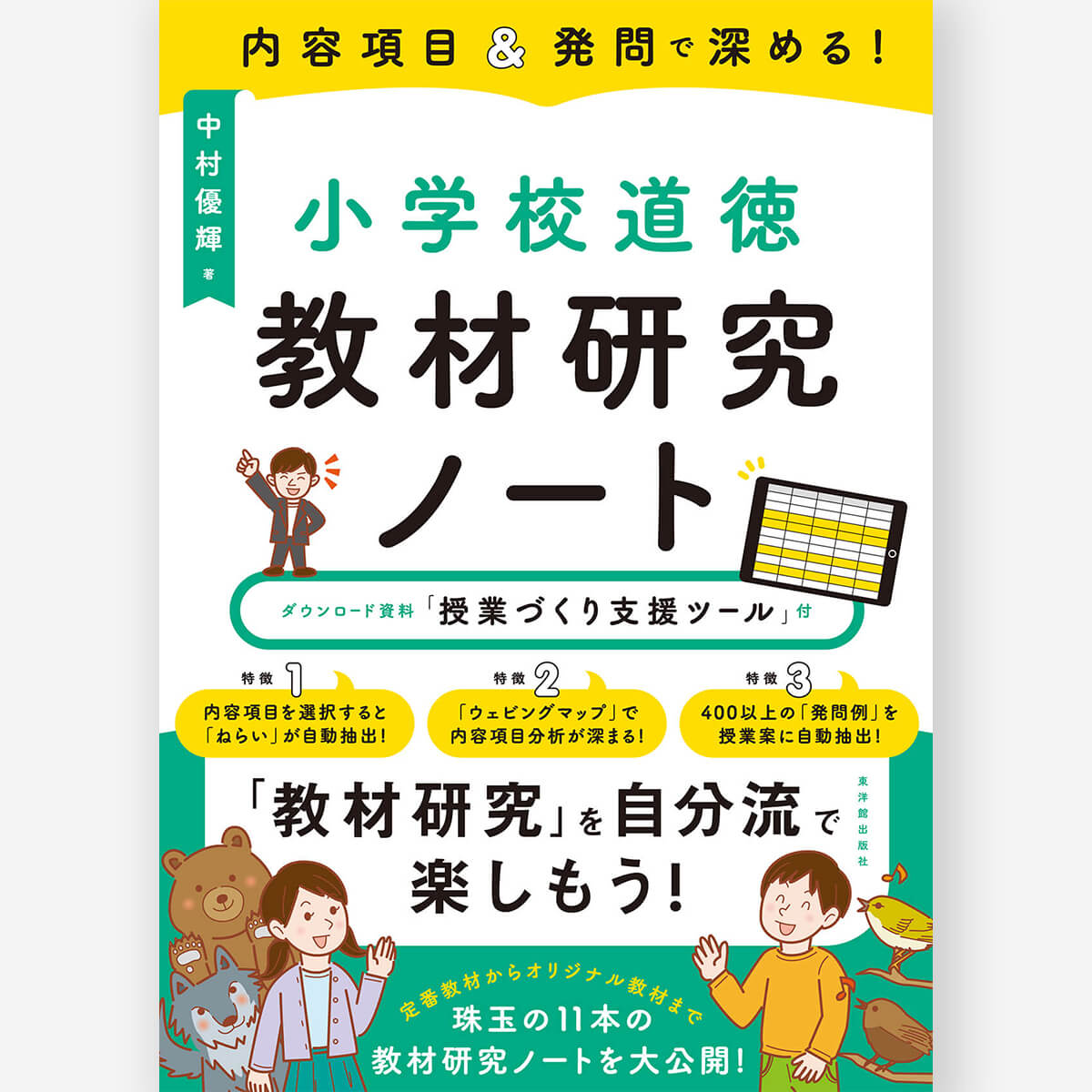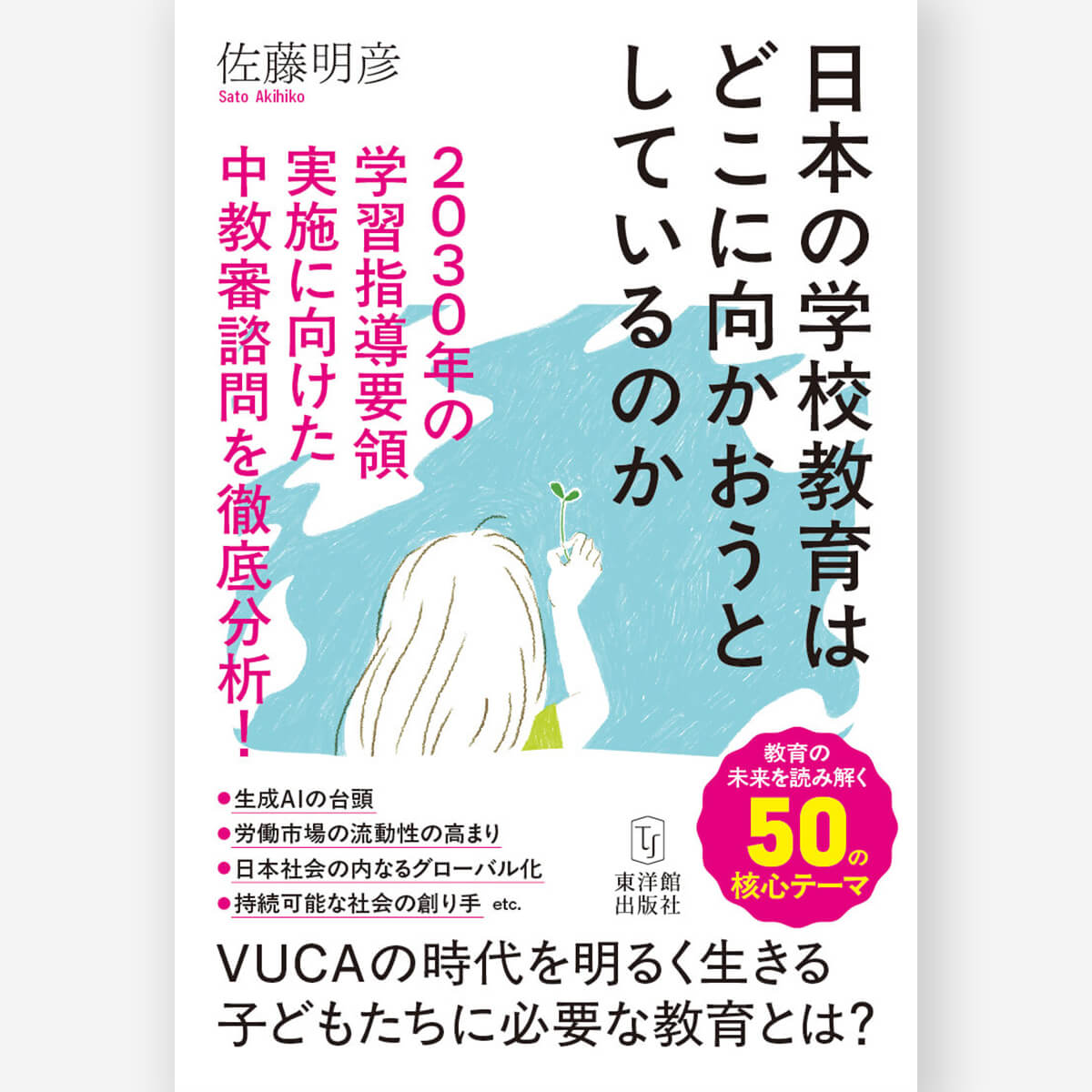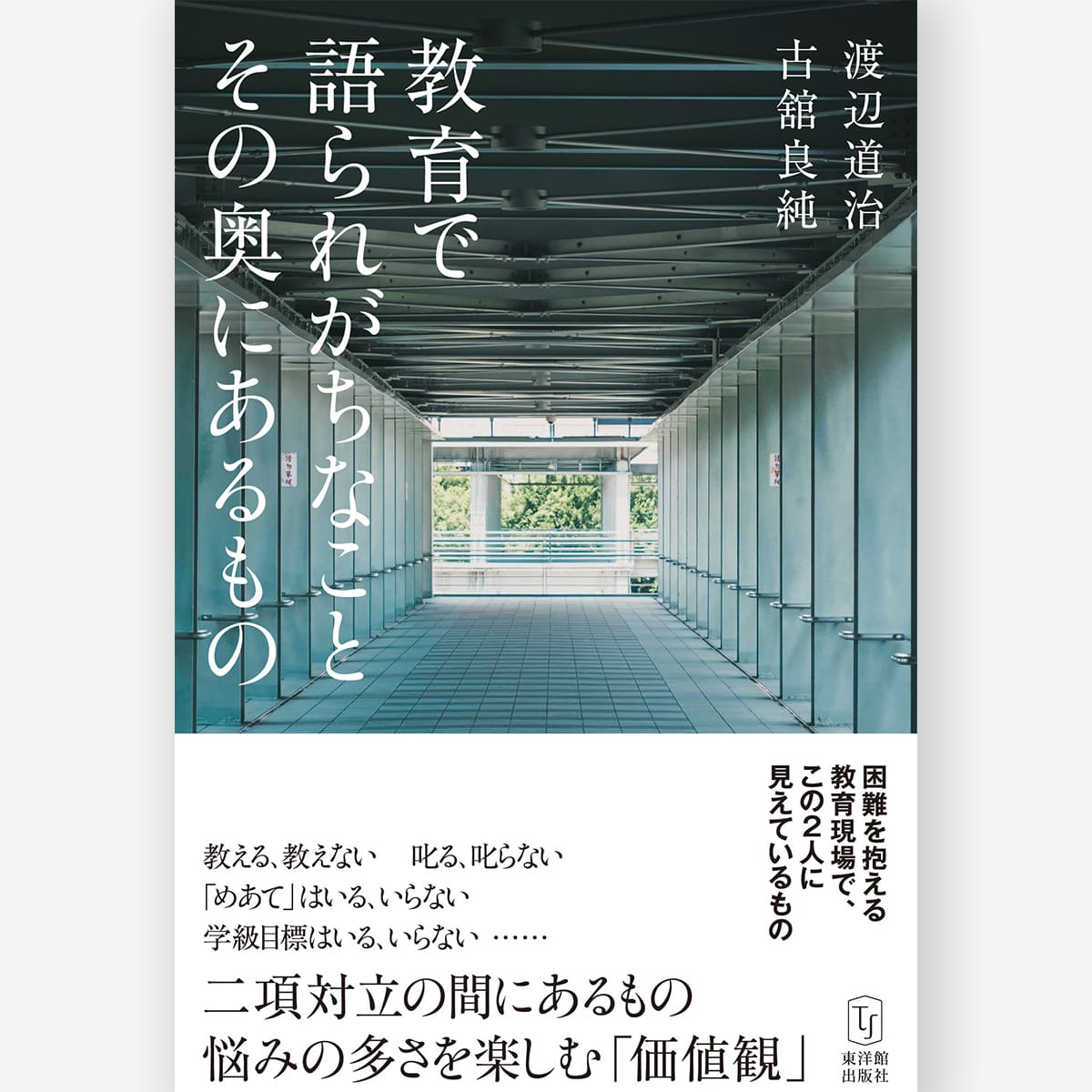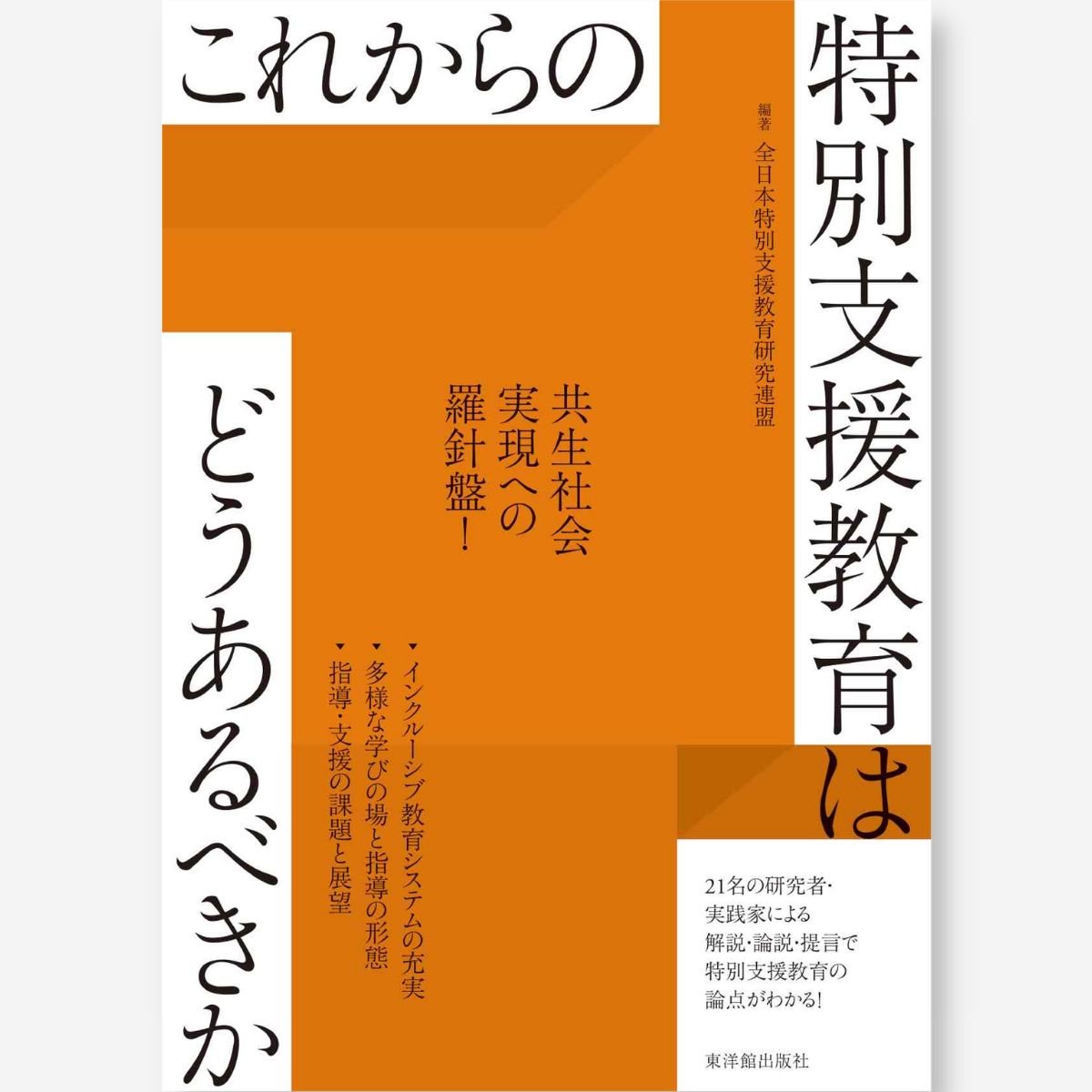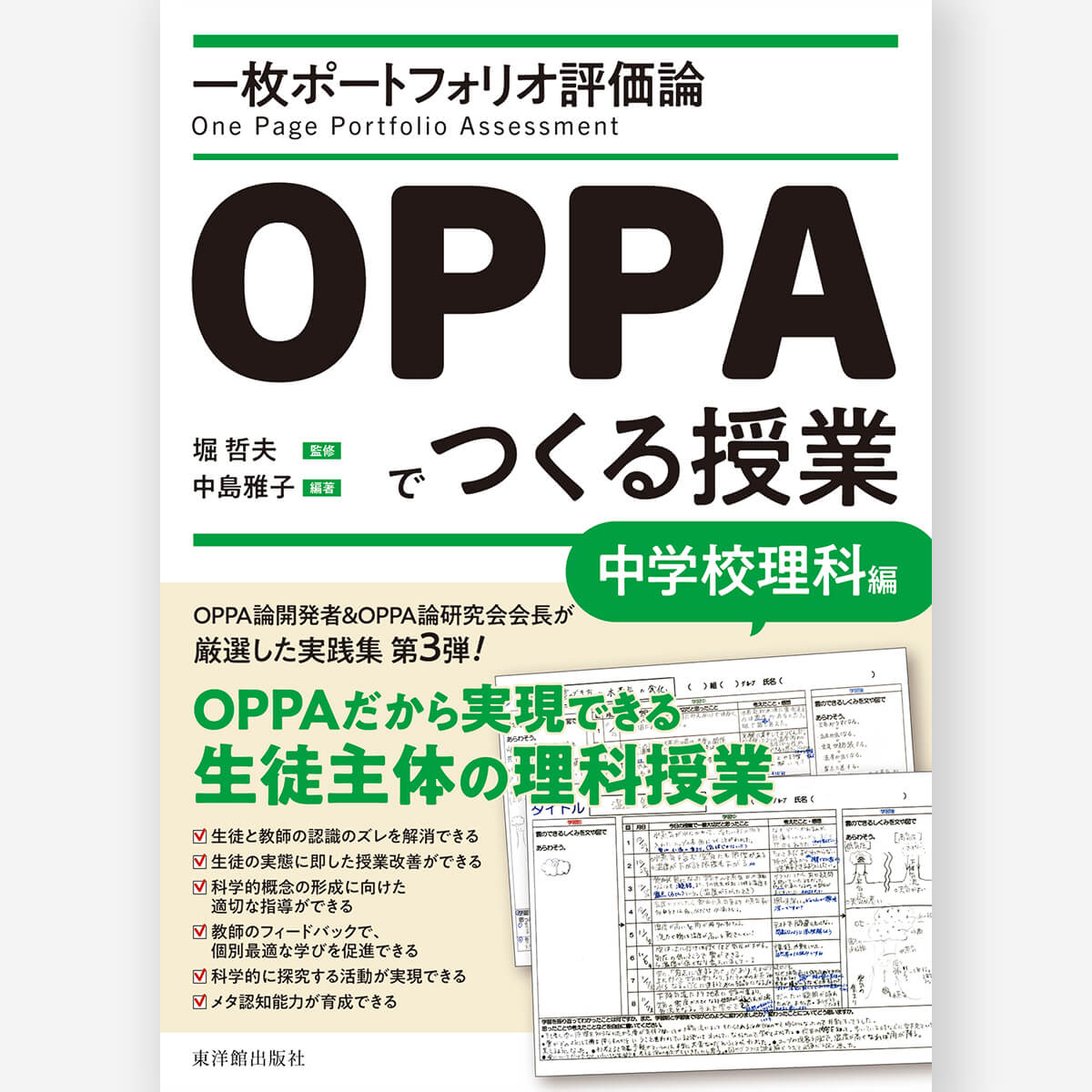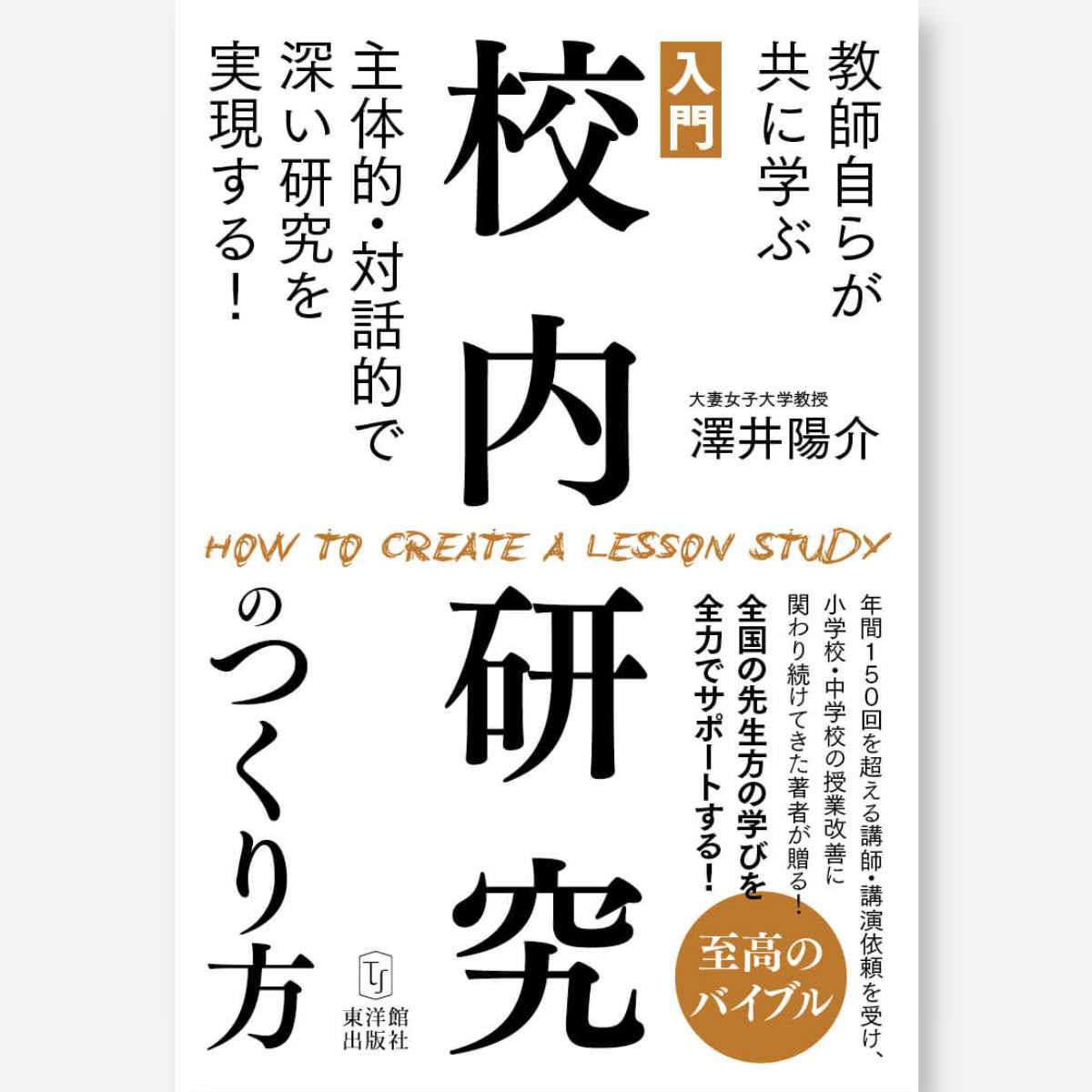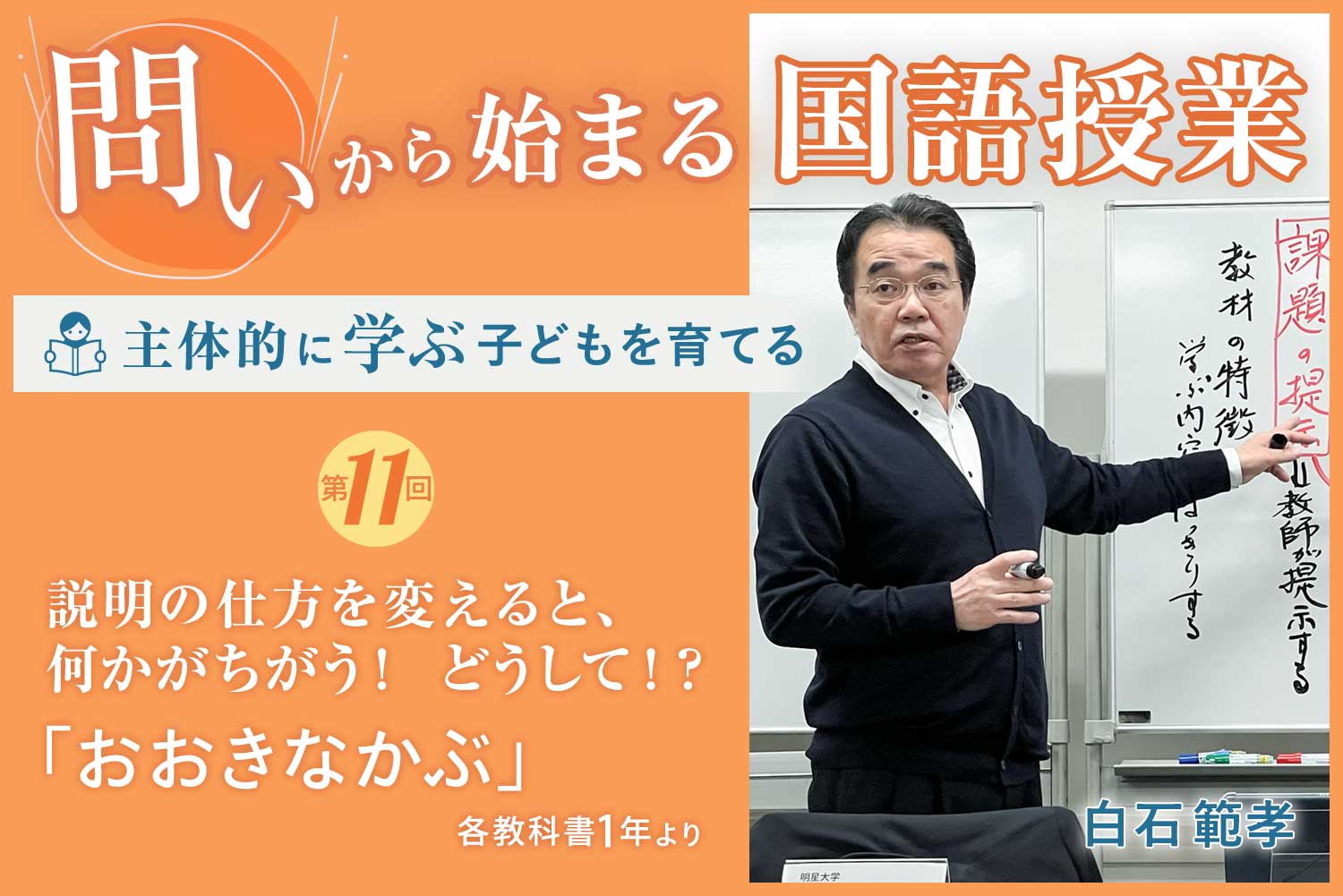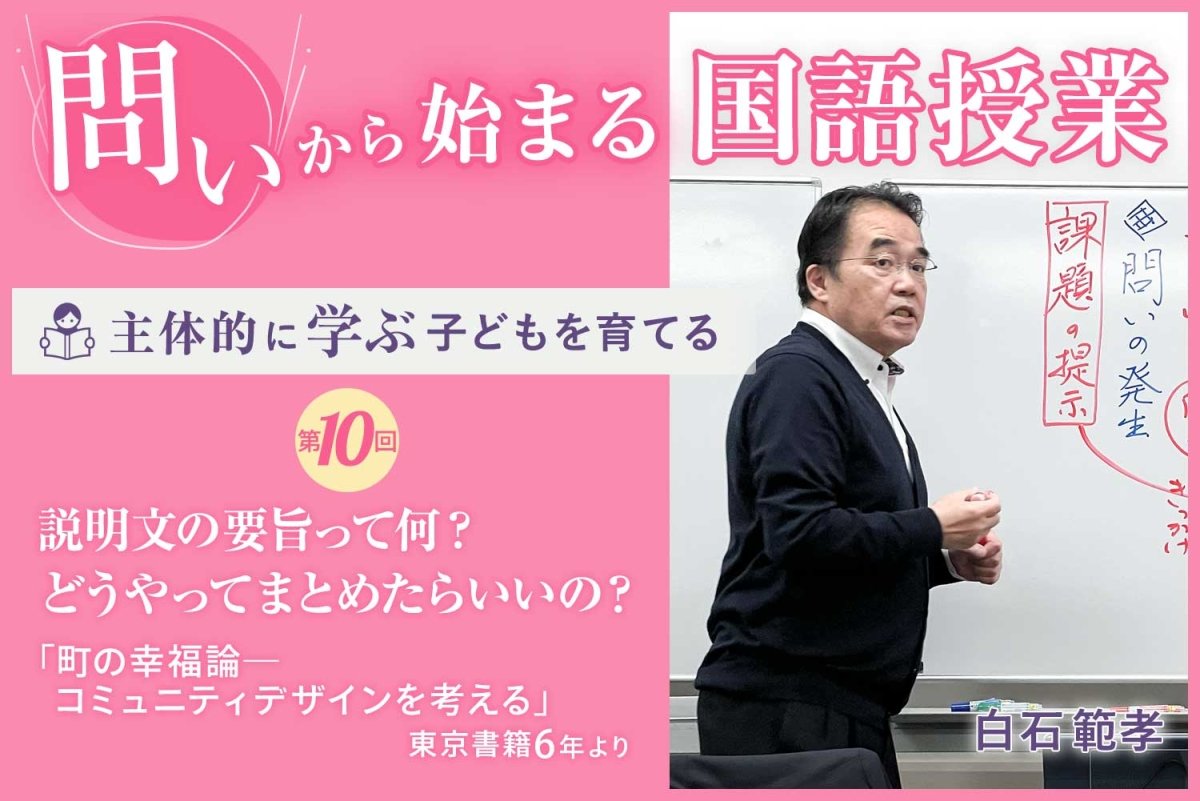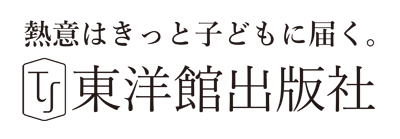子どもの健康と教育が最も守られている国
国際NGOセーブ・ザ・チルドレンが発表したグローバル・チャイルドフード・レポート2021によれば、子どもが健康と教育の面で最も保護されている国別ランキングで、シンガポールは世界186か国中1位であった(日本21位)。
医療が発達しているシンガポールにおいて、例えば5歳から11歳までの30万人以上の子どもを対象とするワクチン接種が2021年12月に始まったことからもわかるように、子どもの健康が守られているのはもちろんのこと、教育の面でも才能ある子どもには最良の教育機会を提供しつつ、低学力の子どもに対する学習促進と支援体制が非常に充実している。その成果もあって、国際学力調査ではシンガポールが常に上位を占めてきたことは周知の通りである。
「実験国家」ともよく呼ばれるシンガポールは、その経済的豊かさを背景に、国の未来を支える人材を育てるべく、教育に膨大な国家予算を投入し、独自の人材育成システムを築き上げてきた。本書では、日本を含む東アジアとも欧米とも異なる、シンガポールの教育制度、とりわけコロナ禍と関連するその特徴を解説する。そのうえで、なお残る課題、そして気になる今後の展望と方向性について説明し、日本への示唆を論じる。
日本とこうも違う教育の特徴
ここではまず、シンガポールの特徴的な2つ教育制度を紹介しよう。1つ目は学校長の高い裁量権と教職の高い社会的評価であり、2つ目は世界トップレベルのICT教育の環境整備と実践である。
(1) 校長の高い裁量権と教職の高い社会的評価
各国の校長と教員を対象としたOECD国際教員指導環境調査(TALIS 2018)の結果から、シンガポールの校長裁量権が日本の場合よりはるかに高いことがわかる。とりわけ、学校内の予算配分に関しては、シンガポールでは校長の判断によって決定されることがほとんどである。同国では、学校教育の各段階の「出口」に全国共通試験があり、よって教育の質と効果をチェックすることができるため、学校の運営と管理に関しては校長の裁量権が広く認められているのである。例えば学校内の学級編制を自由にしたり、適宜必要な予算をつけて学校独自の学習プログラムや部活動を強化したりすることが可能であり、学校運営におけるフレキシビリティが非常に高い。
また同調査より、教職に対する社会的評価もシンガポールでは日本の割合より倍以上高いことが明らかになっている。このような教職への評価は、その職の専門性への信頼性の高さに由来する。
校長裁量権の高さおよび教職への社会的評価の高さは、コロナ禍における学校運営を進めるうえで非常に重要であることは間違いない。
(2) ICT教育も世界トップレベル
さらに、コロナ禍に対応した持続的な学校運営を行っていくためには、ICT教育の環境整備と効果的な実践がカギを握ることは論をまたない。
シンガポールは1990年代からICT産業を国の基幹産業の一つと位置づけ、教育分野においてもICTの活用を強く推進してきた。その狙いとして、児童生徒に対する学習指導の面だけでなく、教員の仕事の効率化と負担軽減も挙げられる。四半世紀前から教育現場へのICT導入が本格化した同国では、低所得層へのパソコン配布や購入支援に加え、学校では紙の教科書を全く使わない授業も展開されてきた。
TALIS 2018の調査結果からも、同国において学校のICT環境整備が進んでおり、指導のためのICT利用の公的研修を受けたと答える教員の割合が非常に高いことがわかる。また、2018年に実施されたOECD生徒の学習到達度調査によれば、効果的なオンライン学習サポートのある学校で学んでいる生徒の割合が参加国平均で約5割、日本では3割以下であったのに対して、シンガポールにおいてはその割合が9割であることも明らかになっている。
それでも多くの課題に直面
シンガポールは、2002年から2003年にかけて流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)による影響で学校閉鎖を経験した国である。そのときの経験を生かし、新型コロナウイルスが2020年1月にこの国へやって来たとき、学校現場ではすでに準備が始まっていた。
SARS以降、一斉休校をせざるを得ないような事態が再び起きることに備え、ネットを利用した学習形態であるeラーニングをより充実させ、年1回以上の全校自宅学習日や自宅教育活動を実施してきた。
さらに2018年からは、教育省に開発され、全国の学校に導入されたオンライン学習プラットフォームの活用も進められてきた。もっとも、校長の裁量権の高さから、学校によっては独自に違うシステムを使っている場合もある。
オンライン学習プラットフォームでは、子どもは各々自宅あるいは校内の所定場所から自分のペースと力に適した学習プログラム(簡単なクイズもある)を受けることができ、教員は彼らの学習進度をモニターできるようになっている。
だが、有事に対する「学校教育のレジリエンス」が強そうなシンガポールにおいても、次のような課題が浮かび上がっている。
(1) コロナ禍に対応した学校運営と学習活動
コロナ禍の影響で、シンガポールの2020年度スクールカレンダーは変更され、学期が短縮ないし延長となったり、学期間休暇が前倒しされたり、追加休暇が設けられたりした。なお、各教育段階において、低学年の学期末試験が中止になったり、最終学年の修了試験については時期の延期や試験問題範囲の変更などの配慮も行われたりした。
また、コロナ禍の感染状況が悪化するとすべての学校が完全な自宅学習になったり、改善すれば分散登校になったり(例えば、重要な卒業修了試験を控えている最終学年だけは毎日の登校が許可され、その他の学年は週ごとの自宅学習と登校を繰り返す)、状況が落ち着いたら全児童生徒の登校が再開されたりしていた。
以上の措置により、学校の規模、学年、クラスや学校内感染状況などによる差はあるものの、例えば小中学校では例年なら年間登校日数の200日が平均約150日になったという報告もある。
(2) 教職員、部活動顧問および保護者への配慮と支援
シンガポールでは2020年3月から15万人の教職員を対象とした接種を開始したことからも、教員が必要不可欠なエッセンシャルサービスを提供する重要な専門職と位置づけられていることがわかる。
また、2020年の4月に最初の全国一斉休校期間が始まる前に、学校はすでに2月から準備を整え始め、児童生徒は事前に教科書と必要な学習資料を自宅に持って帰ることができた。なお、前述したオンライン学習プラットフォームでは教員同士による意見交換や指導教材の共有などもできるため、仕事負担の軽減につながったことが調査でわかった。一斉休校への対応について、20年前のSARS発生当時と今とを比較して、「ワークシートの提供から授業の提供へ」と評する記事もあった。
一方、同国の学校では、部活動の顧問はその競技や分野のプロが務める場合がほとんどであり、各学校はそれぞれのニーズに合わせて教育省が管理する人材登録バンクからコーチやインストラクターを選考し契約を結ぶことになっている。コロナ禍の影響で部活動が中止ないし制限される中、部活動顧問への雇用面での支援体制も設けられた。
また、両親ともエッセンシャルサービスに従事している子どもや、自宅にオンライン学習の環境が整っていない子どもは、自宅学習期間中であっても登校して学校で授業を受けることができる支援が行われた。さらに、在宅勤務の親とパソコンを共有できない子どもや、そもそも必要な機器がない家庭の子どもには、パソコン、タブレットやネット接続機器が無料で学校から貸し出された。
また、同国は学校給食制度がないことから、低所得層の児童生徒には学校の食堂で食べ物を買うための電子マネーが給付された。これらの子どもは登校できなくても、地下鉄駅などでスマートカードを使って電子マネーをチャージでき、学校外でも食事することができる措置がとられた。
(3) 浮き彫りになった主な課題
このように、ICT教育を推進してきたシンガポールといえども課題が山積している。本書で詳しく述べる家庭間格差と教員間格差のほかに、同国で生じている学校間格差が校長の裁量権の高さに由来することが興味深い。聞き取り調査の対象者は以下のように語る。
「自宅学習期間中に、私の学校では毎朝ブレックファーストセッションというZoomでのクラス交流集会があり、また週に必ず数回はリアルタイムのZoom授業を行って、子どもたちの様子を観察したり、落ち込んでいる子や元気のない子がいたらケアをしてあげたりしていますが、別の学校に勤めている友達の教員の話によると、その学校ではリアルタイムのZoom授業をまったく行わないそうです……校長の教育観と実行力によって差はありますね……」
校長裁量権の高さゆえに実態に合わせた機動的な支援を可能にしたことが、かえって学校間の対応格差を広げてしまうという、極めて難しい課題を抱えている。
この危機を契機に教育を巨視的に考える
世界には、いまだに休校が長引いている国もあります。またワクチン接種・PCR検査等にみる南北格差も鮮明です。2021年末現在においても、ユネスコによれば世界には1千万人(0.7%)の児童生徒が休校によって学習の継続が保障できない状態にあります注1。ユネスコの同統計によると宣言後の2020年3月16日の時点では、6667万人(42.3%)であり、国全体の一斉休校は109カ国に及んでいました注2。その1月後には117カ国とさらに増え、1億人を超える児童生徒が登校できなくなります。この時点から編者が最も懸念したことは、アフリカ、南米、アジアと北米、オセアニア、欧州、東アジアの一部との学習権の格差拡大にありました。
マスク外交から、ワクチン外交へと格差が鮮明になることは、現在の国際情勢から予測され、デジタル教育への切り替えにも、デジタル先進国のノウハウが輸出されることになり、教育という極めて内政・文化にかかわる事項にまで踏み込んだ教育産業の貿易「新たな植民地化」が強まることに危惧したからです。本書でパンデミック宣言後の、各国の初動を明らかにすることで、そこでみられた教育課題は、近代化の象徴である公教育(学校)の長所と短所を浮き彫りにしました。その内実は、受益者側である子どもや保護者、学校に携わる教職員、教育行政官、教育研究者などの声として第1部(全26章)にまとめました。より政策動向と教育行政に焦点を当てた8か国(ドイツ、スペイン、スウェーデン、フランス、イギリス、シンガポール、ブラジル、日本)については第2部に収めました。2部構成とすることで学校現場から研究者まで読者層を広げ、パンデミックがもたらした未曾有の教育危機に世界の教育現場はどう立ち向かったのか巨視的で複眼的に考えることを試みました。
注1 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse (2021年12月30日閲覧)
注2 例えば、ユネスコのこの統計において、日本は国からの要請であったため、全国休校の国として数えられていない。



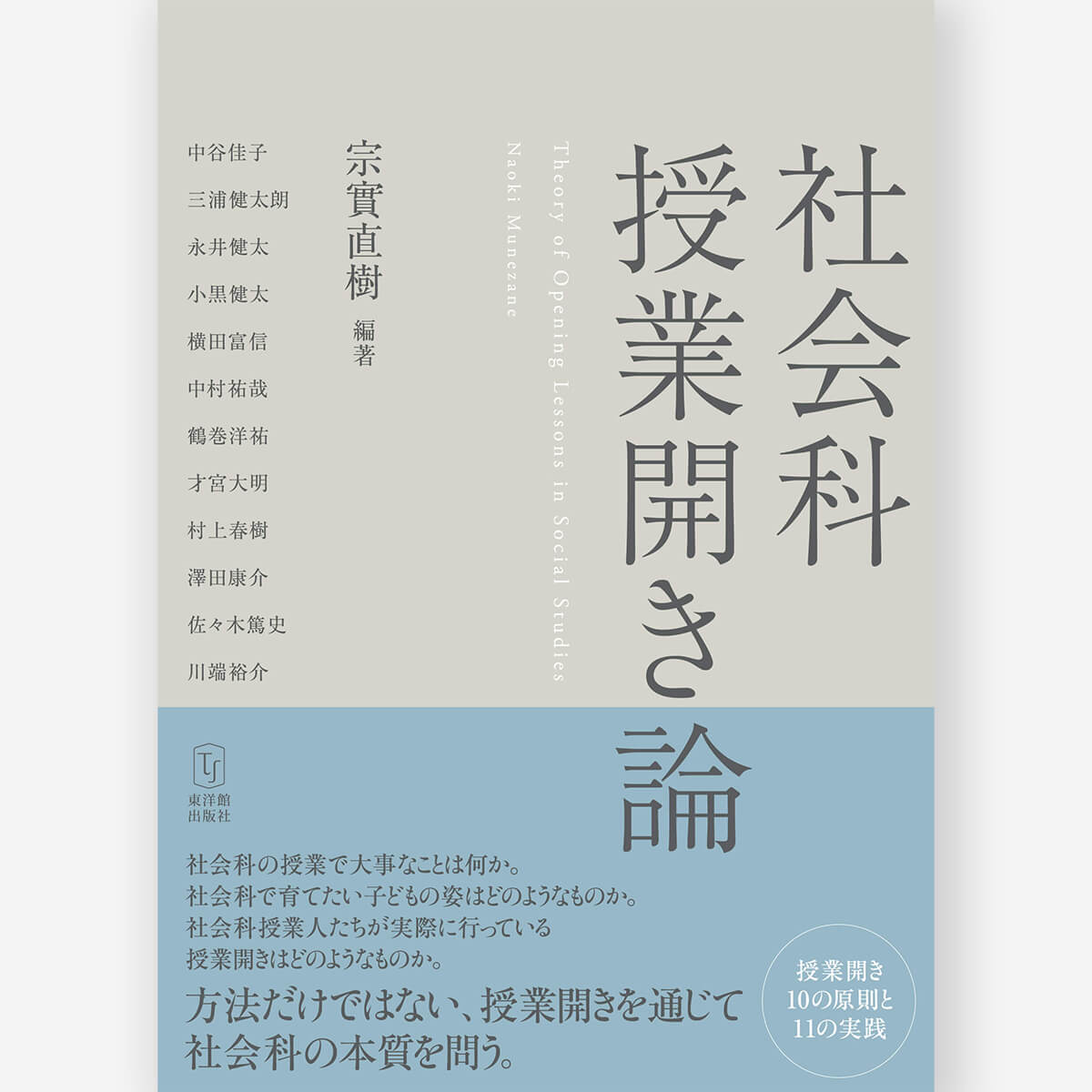
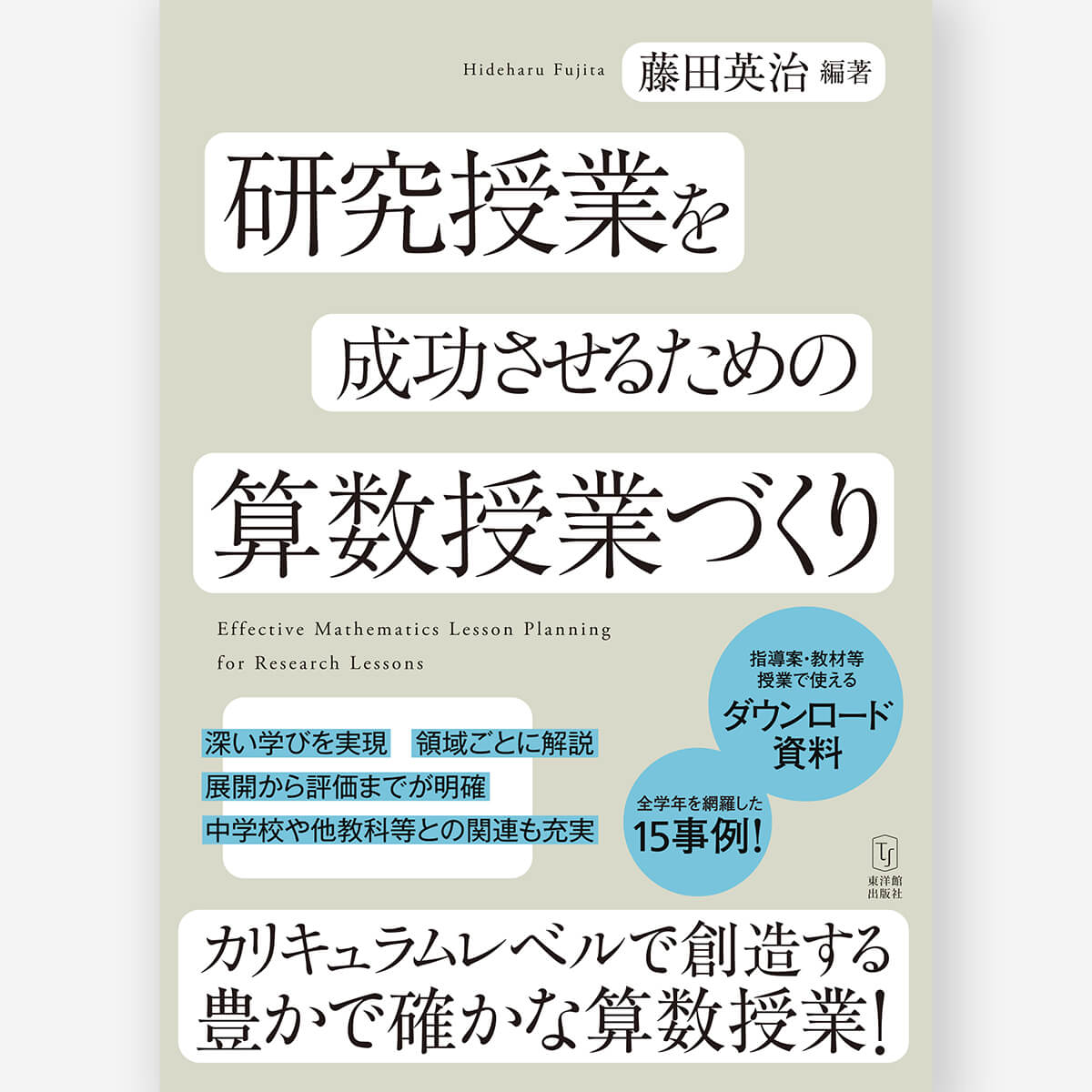
![[小中英語]学習者用デジタル教科書を活用するために知っておきたいこと―子どもを“真ん中”にした授業をつくる! - 東洋館出版社](http://www.toyokan.co.jp/cdn/shop/products/product-203055.jpg?v=1708564599&width=1200)