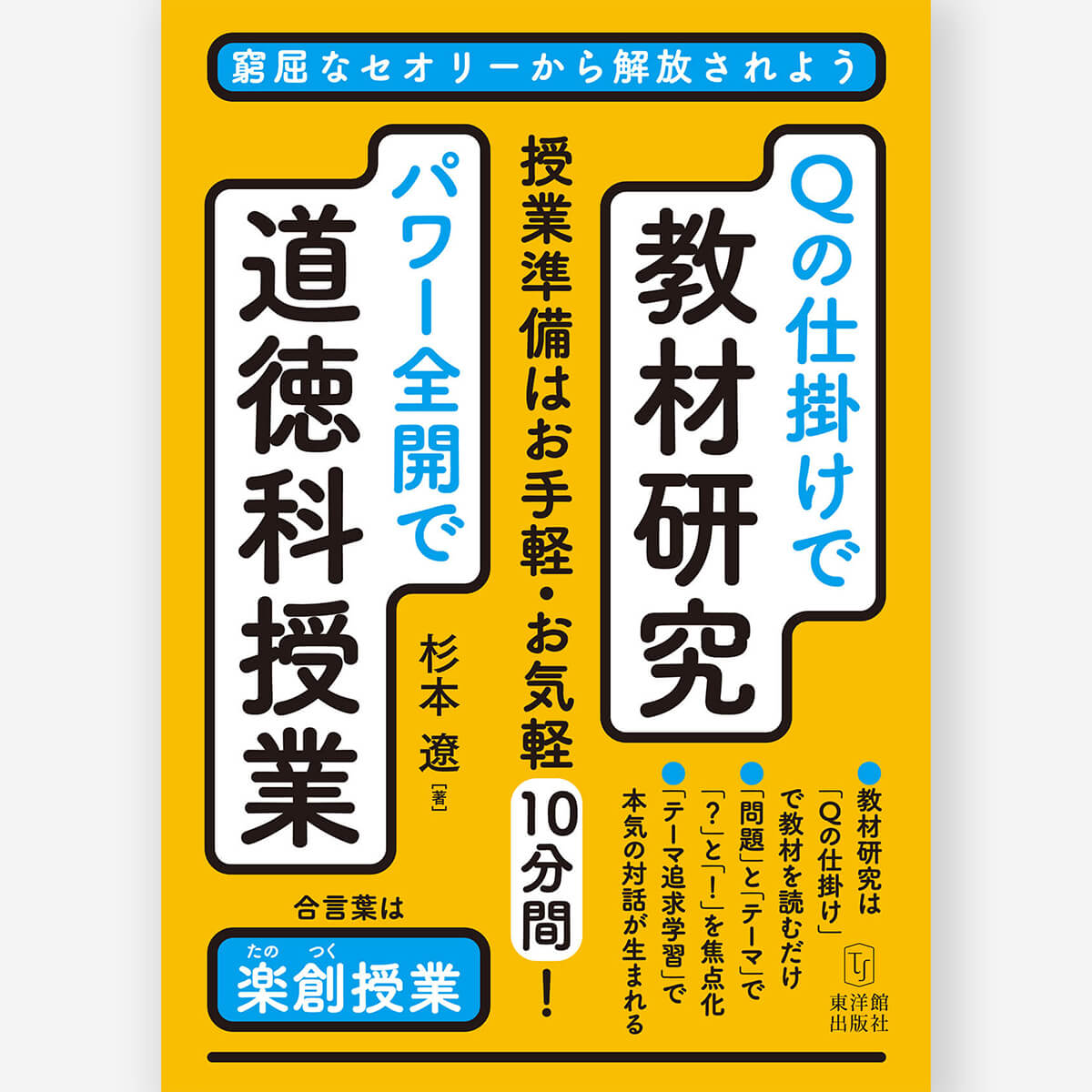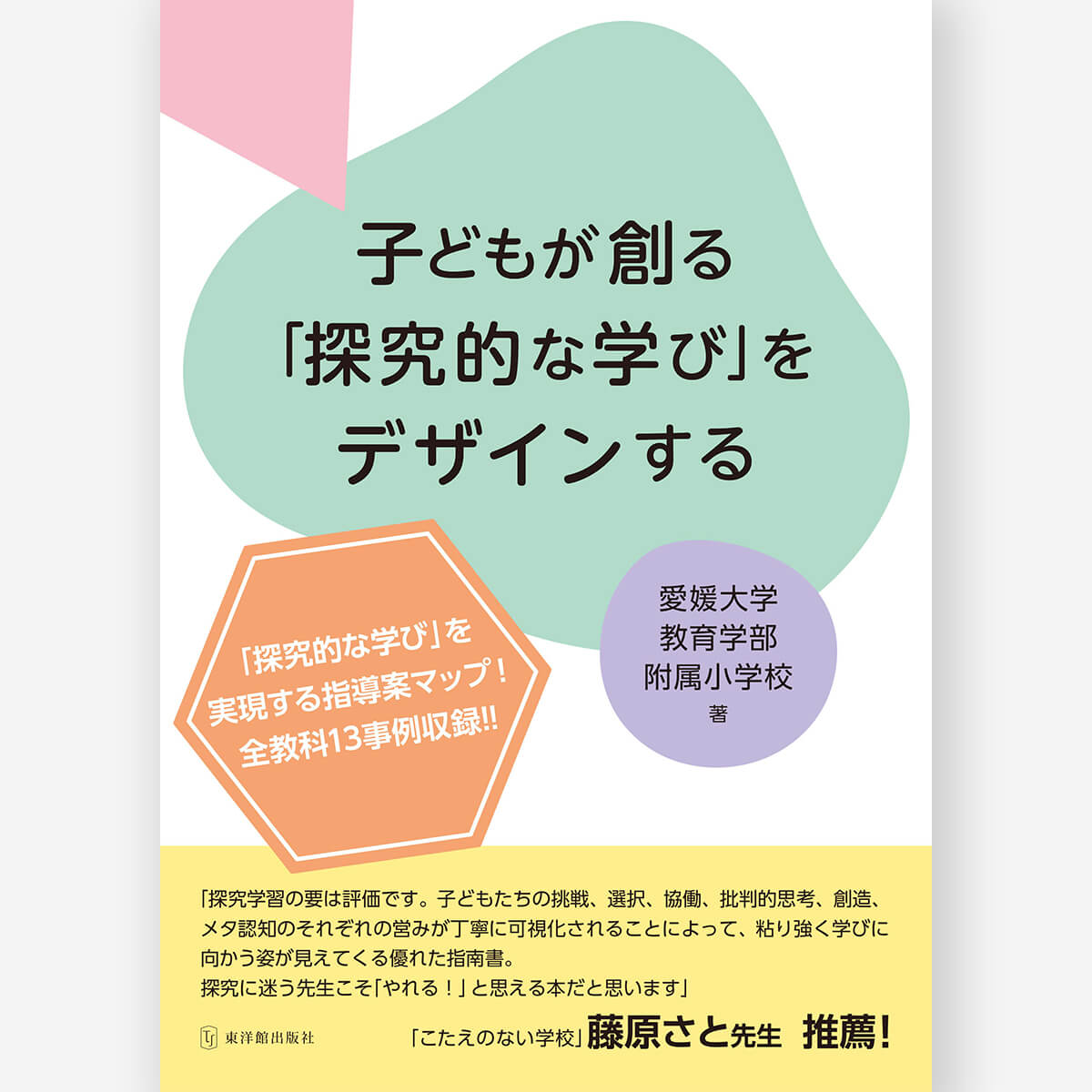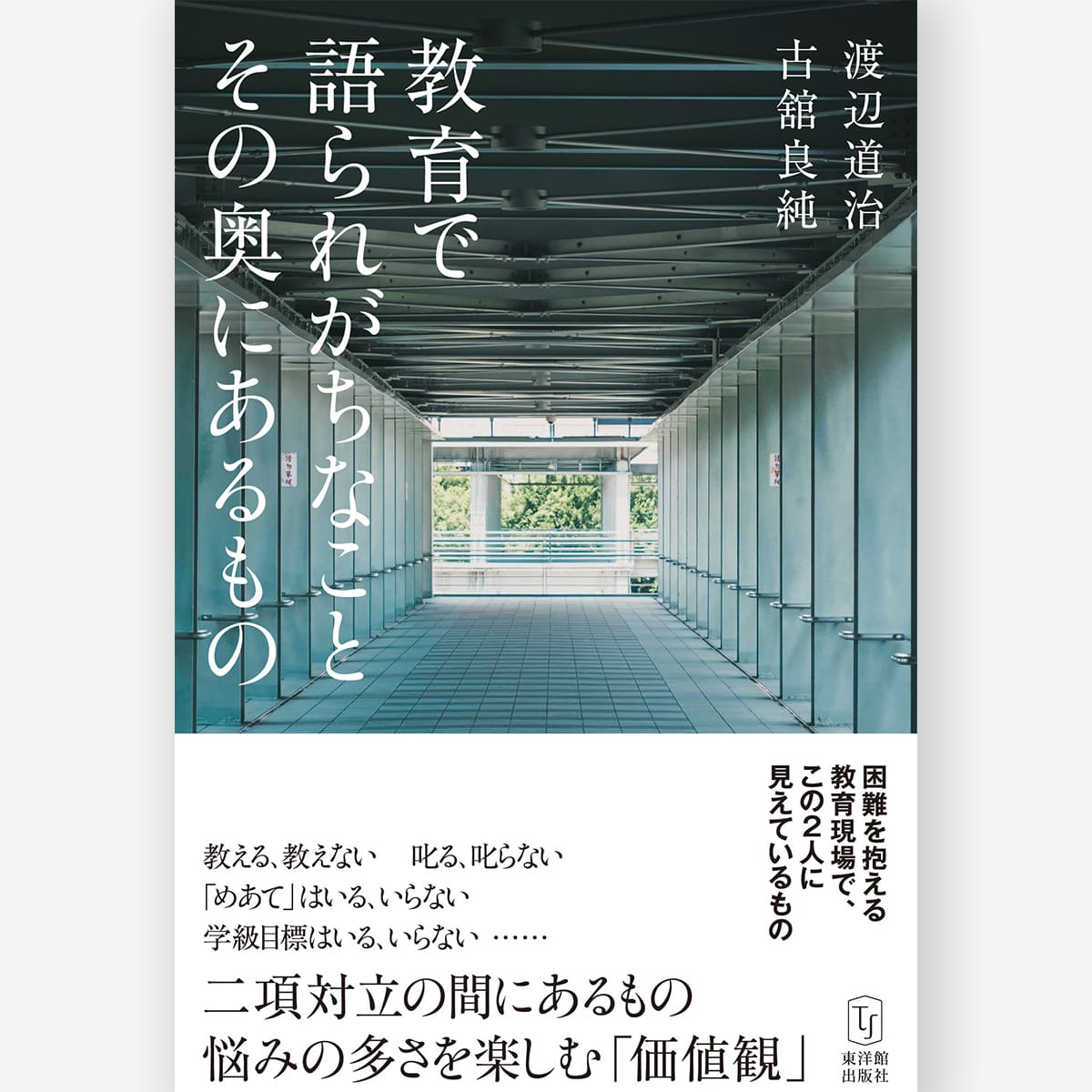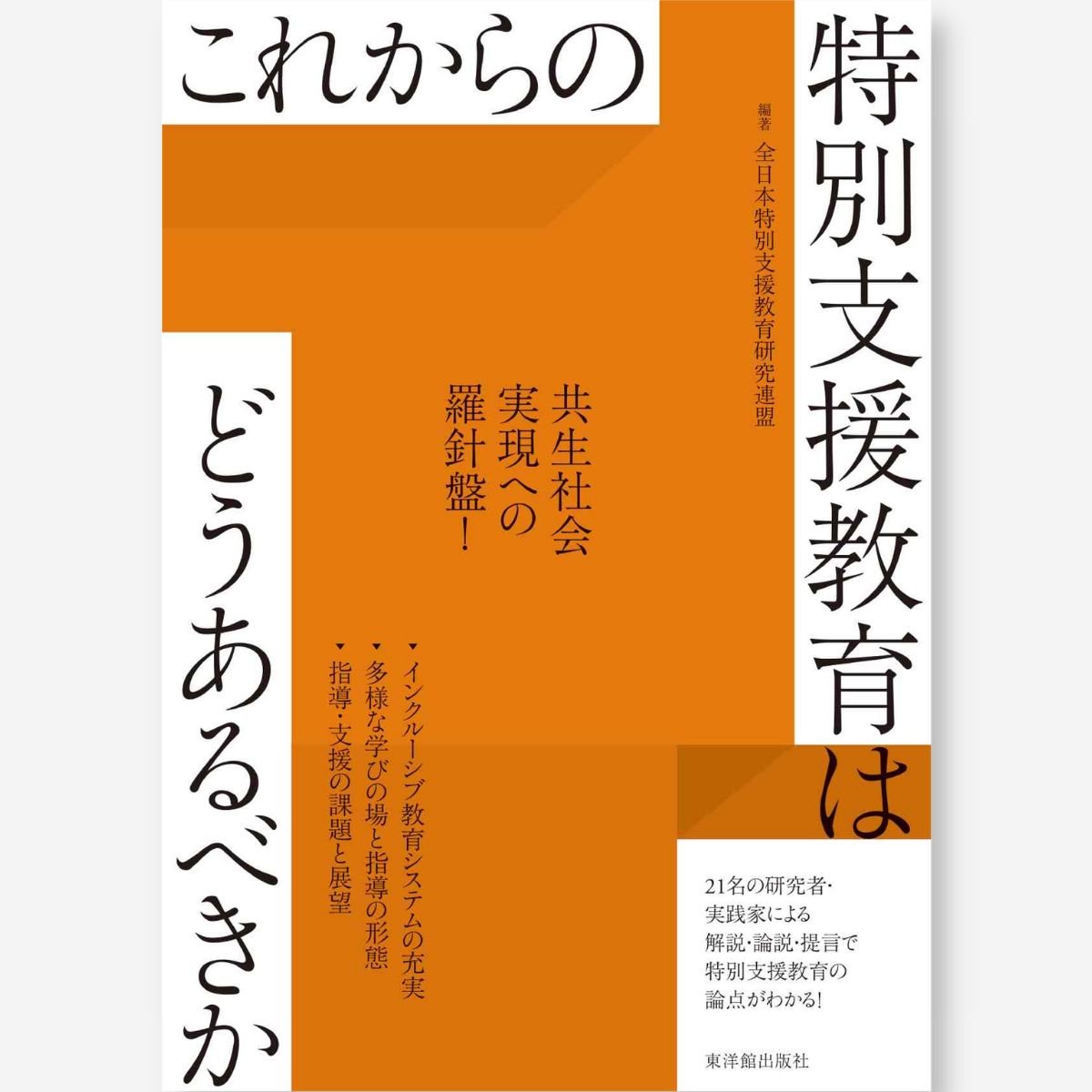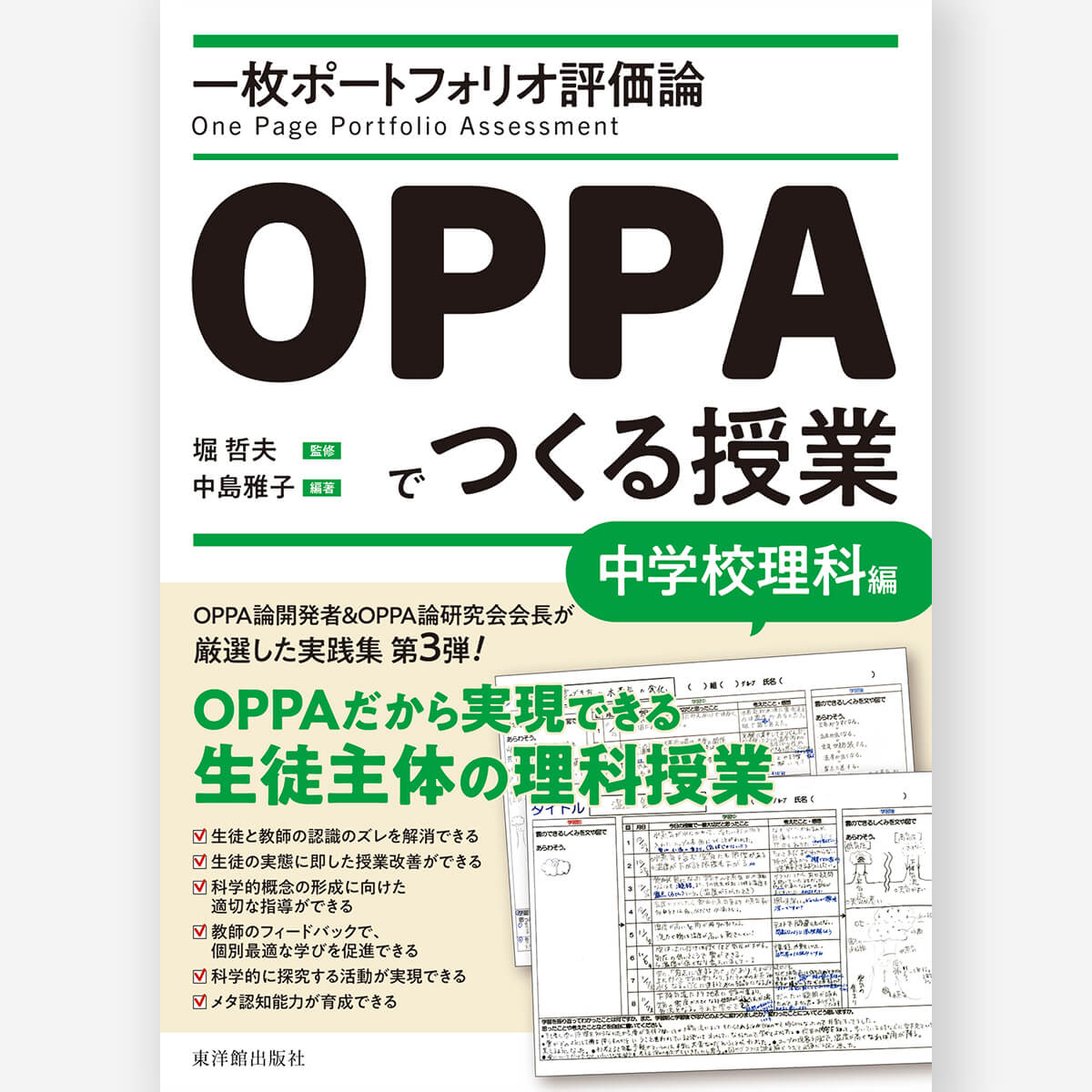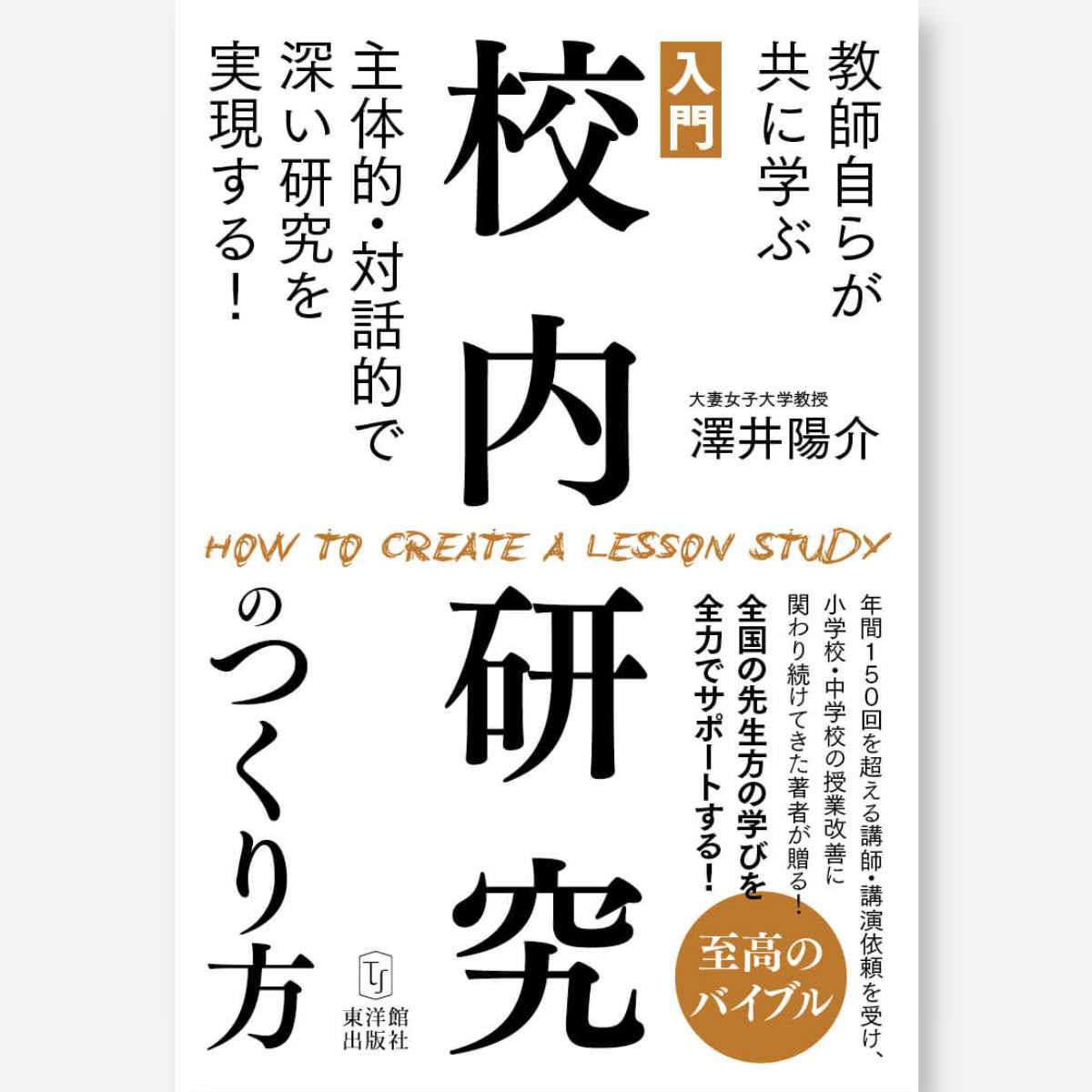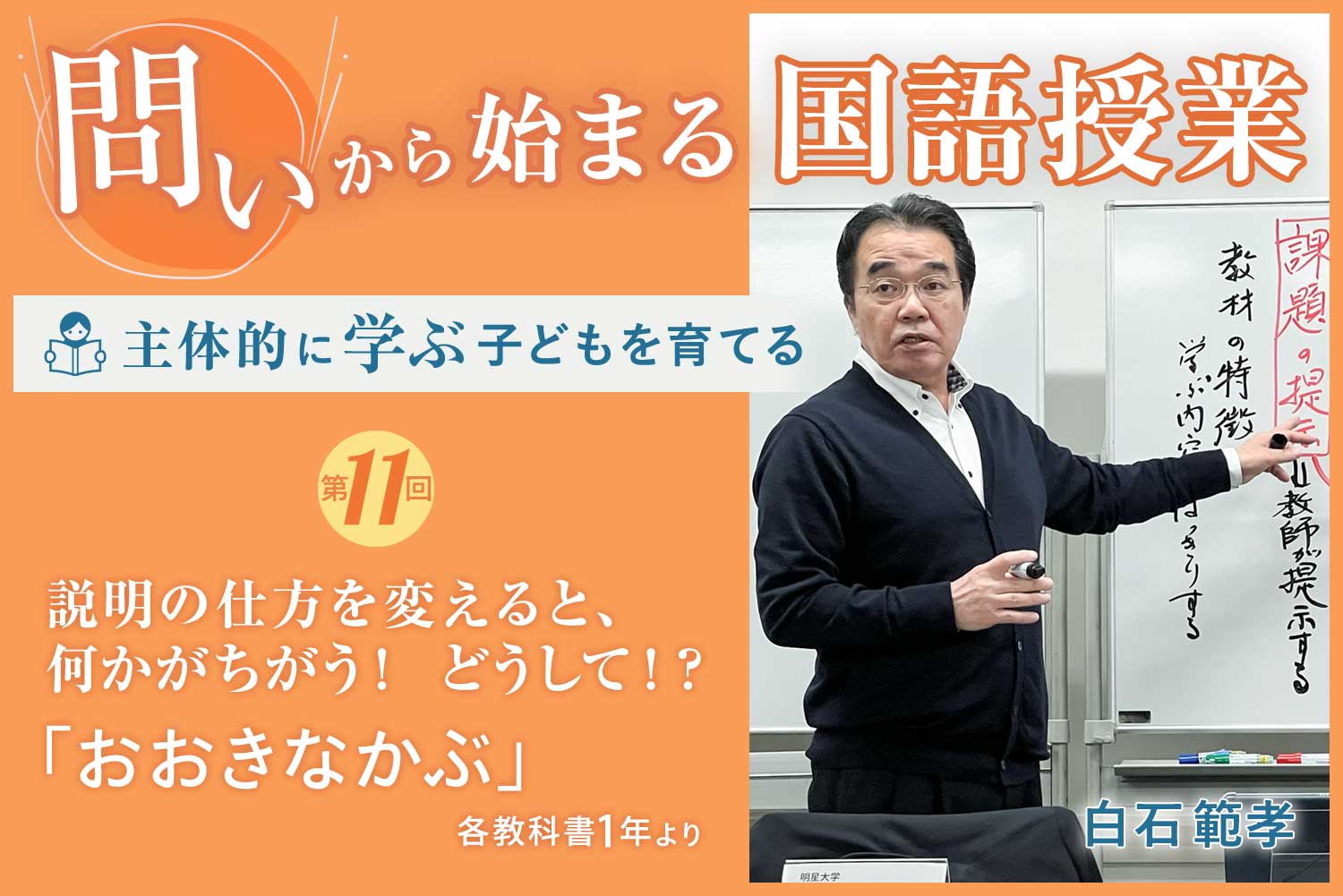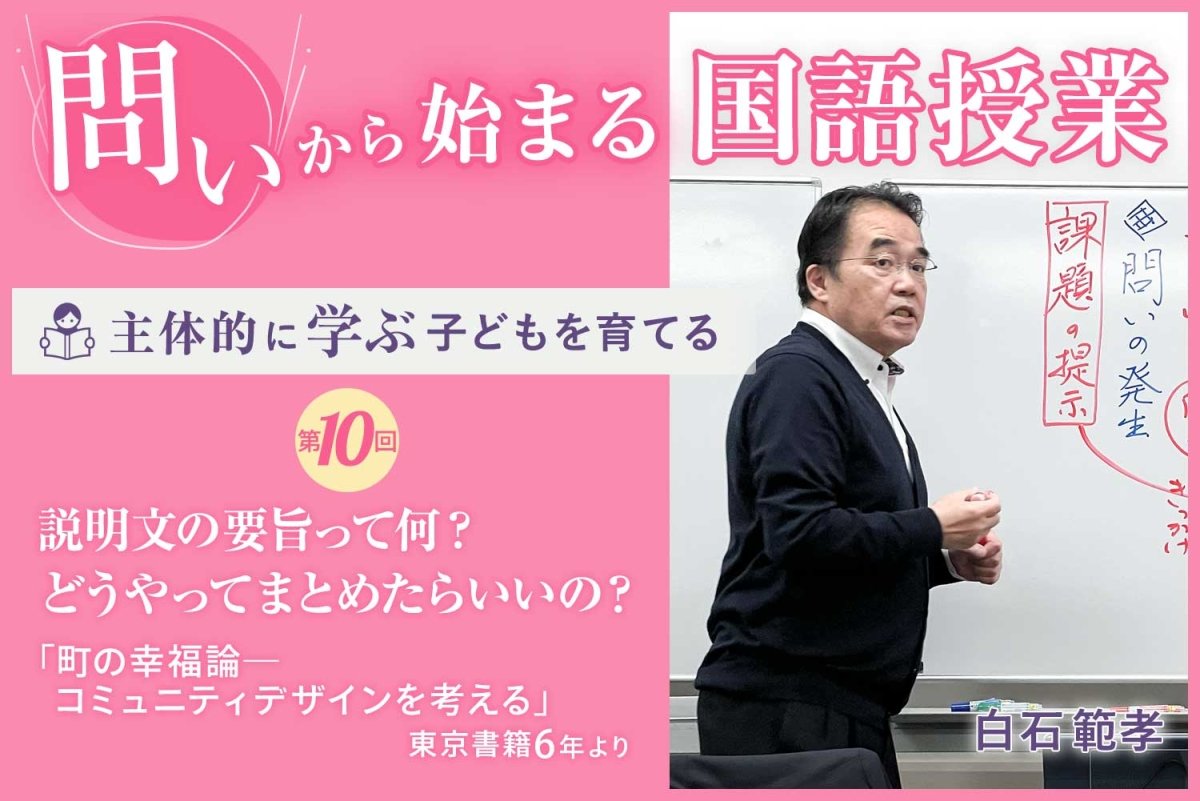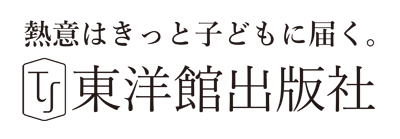急務の課題は公教育の再建
――『複雑化の教育論』のもととなった講演から約1年。この間に、教育関連で気になった出来事は?
いろいろと気になる報道はありますが、とりわけ大学教育が危機的であることが気になります。例えば、「大学ファンド」制度。認定を受けるには年3%の事業成長を大学は国に約束しなければならないという方針〔編注 1〕が話題になりました。大学に「稼ぐ」ことを求めて、稼ぎによって格付けするということになると、教育研究の方向が短期的な利益を出すことに限定されるし、教員の労働もさらに過剰になる。あらゆるレベルで教員が労働過剰になっているせいで、教員のなり手が減っていることも深刻な問題です。
――公教育が危機にさらされているように感じます。オルタナティブな選択をする保護者も増えていると聞きます。
公教育にはその時々の支配的な政治イデオロギーが深く関与するというのは日本の現実です。自治体の首長が変わると、地域の教育ががらりと変わるということが現に起きています。私立学校には建学の精神や独特の校風があって、教育内容が時の支配的な政治権力に直接影響されるということには抑制がかかります。ですから、保護者が政治の過剰を嫌って、子どもたちを私立学校に進めようとするとしても、それはしかたのないことだと思います。
ただ、私立学校で気になるのは、どうしても同質性の高い生徒たちが集まってしまうということです。学力や出身階層について同質性の高い級友たちと、中高一貫6年間、あるいは小学校からの12年間を過ごすということは、子どもの成長にとってあまりよいことではないと僕は思います。子どもは成長期にはできるだけ多様な出自の、多様な考え方をもつ友人と出会った方がいい。その方が成熟してゆく上ではよい環境だと思います。それに、私立に通わせるためにはそれなりの経済的な余裕が要ります。
個人的には、他にもいろいろ選択肢があります。「学校へ行かないで、高卒認定試験を受ける」というのもあるし、「通信制などのオルタナティブスクールに行く」というのもあるし「いっそ海外に行く」というのもあります。そういう選択は個人の前には開かれています。
ただし、それはあくまで個人レベルでの問題解決であって、制度的な問題の解決にはなりません。それに、進学について多様な選択肢を享受できるのは、ここでもやはり親に経済力がある場合です。貧しい家の子どもには、それほどの選択肢はない。だから、やはり公教育の再建が急務だと思います。
「政治」と「マーケット」の介入が公教育をゆがめている
――公教育の危機は、どのような要素からの影響が大きいのでしょうか。
「政治」と「マーケット」という2つのファクターが日本の公教育を壊している。それは間違いないと思います。
教育、医療、行政、司法などの制度は共同体が存続するために不可欠のものです。ですから、とにかく安定的に運営されていることが最優先します。政体が変わろうとも、経済システムが変わろうとも、これらの制度はそういう社会的変化とはかかわりなく継続的に管理・運営されなければならない。政権交代したからとか、株価が下がったからとかいうことで教育や医療の制度が軽々に変わっては困る。
でも、政治とマーケットはそういう安定的な制度が社会内に存在すること、それ自体に対して敵対的です。「変化しないもの」を許容しない。それが政治とマーケットの本質的な傾向です。とりわけ政治家は政治過程から相対的に自律的に機能している制度というのが嫌いです。ですから、「改革」を掲げる政治家はまず行政、医療、教育に手を突っ込みたがる。そして、わずかな社会的変化に即応して「ころころ変わる」制度に変えようとする。それが正しいと信じているんです。でも、選挙があるたびに一朝にして前の制度が放棄されて、また新しくなるというようなことは医療でも教育でも行政でも、本当はあってはならないことなんです。
一方、マーケットが医療や教育に首を突っ込んで来るのは、資本主義が限界に来て、もう金儲けのための「フロンティア」がなくなったからです。医療や教育は「それなしでは集団が維持できない制度」ですから、どれほど制度をいじりまわしても、機能不全にしても、破壊しても、最終的には税金であれ私財であれ、誰かが金を出してその制度を維持しようとします。ビジネスマンが医療や教育に首を突っ込むのは、それが絶対安全な「金儲け」の機会だからです。
教育と政治がかかわりを持つことはなかなか抑制できません。明治からあと、近代学制において、学校教育は「国家須要の人材」を育成するという国家目的に基づいて制度設計されていました。近代国家を立ち上げ、維持するために必要な人材を育成するという考え方自体は間違っていないと思います。ただ、その場合でも、長期的な視点で「どのように国力を高めるか」を考えるべきです。
多様な才能が、百花繚乱的に花開くような仕組みを作るというのが長期的には国力向上に最も効果的だと僕は思います。でも、そういう仕組みでは、教育現場に大きな自由裁量権を与えなければならない。反権力的、反体制的であることを恐れない元気のよい若者が輩出する。ですから、統治コストの最少化を優先的に考える政治家はそういう仕組みを採用しません。そうではなくて、たまたまその時に政権の座にある人間が、政権を安定させ、自分たちの支配を長期化するために、政権の安定のために「都合のよい人間」を作ることを学校教育に求め出します。上位者に無批判に従う、批判力のない、「イエスマン」を量産することを学校に命じてくる。そうなると、短期的には統治コストは低くなり、政権は安定しますが、次第に国力は衰えてくる。国は貧しくなり、国際社会でのプレゼンスが低下し、文化的生産力も衰える。それは世界のどこの国でも同じことです。
だから、学校教育においては、「国家須要の人材とは誰のことか?」という根源的な問いを繰り返し問わなければならない。具体的に言えば、そのときたまたま政権の座にある政治家が、自分にとって都合のよい国民を「国家須要の人材」であると定義することをどうやって防ぐか。それが公教育にとって死活的に重要な問題だと思います。
戦前は「教育勅語」によって国家が公教育に介入して、「天皇のために死ぬ国民」を制度的に量産しました。それによって日本は数百万の国民を失い、国家主権も国土も失いました。間違った教育が日本を滅ぼした。この前例を徹底的に反省して、二度と政治が教育に介入しないような自律的な仕組みを作るという決意から戦後教育は始まりました。けれども、その時にあったような緊張感が今の日本の学校教育にはもうまったく見ることができません。
ビジネスからの学校教育への介入も、政治の介入同様に、決してあってはならないものです。産業界はとにかく「高い能力を持ち、安い賃金で働き、上位者に逆らわない人間」を量産しろと言ってきます。これは営利企業である以上当然の要請です。でも、それはあくまで彼らの短期的な利益のために過ぎない。そういう人材がほんとうに必要ならば、企業内に教育機関を作って、自分たちがコストを負担して教育を行えばいい。でも、彼らは企業で人材育成コストを負担する気がありません。教育コストはすべて公教育に「外部化」しようとする。税金を使って自分たちに都合のよい人材を育成させようとする。「コストの外部化」は資本主義企業の基本ですから、彼らがそうすることを防ぐ理屈はありません。僕らにできるのは、「マーケットは学校に口を出すな」と繰り返し言うだけです。
政治の介入に関しては親たちも結構ナーバスになりますが、マーケットの介入については、保護者たち自身が骨の髄まで「資本主義的マインド」になっているので、「マーケットが介入することのどこが悪いのか?」と不審顔をされることがあります。教育というのは子どもに「付加価値」を付けていって、労働市場で高く売るためのものでしょう…と本気で思っている保護者は少なくありません。企業が望むような人材に育て上げることを学校教育に求めたりする。そういう人たちが「教育投資」というような言葉を平気で使う。マーケットのロジックや用語は親たちにも、子ども自身にも入り込んでしまっています。

公教育再建のためのジレンマ
政治とマーケットの介入をどうやって遠ざけて、公教育を自律的なものにするか。それが喫緊の課題なのです。でも、これはほんとうに困難な課題だと思います。
というのは、公教育への政治の介入を押し戻すためには、政治の介入が必要だからです。教育現場のフリーハンドに任せて、政治は教育に介入しないということを決定するためには、そういう政治決定を下す必要があります。「公権力の介入を排する」ためには「公権力の介入を要請する」という矛盾したことをしなければいけない。
だから、「政治の変化に期待する」というのは、学校教育にとっては諸刃の刃のリスクがあります。たしかに政治の変化がないとなかなか学校教育の自律性は回復できない。でも、政治の変化に期待するということは、政治の公教育への介入を受け入れるということです。僕たちはこのジレンマに苦しまなければならない。
マーケットの介入を防ぐことは、今の日本ではもう不可能だと思います。大人たちは、親も教師も、子どもたちに高い付加価値を付けて、労働市場に送り出すことが学校教育の目的だと心の底から信じている。その思い込みをどこかで引き剥がさないといけない。でも、どれほど言葉を尽くしても、たぶんわかってもらえないでしょう。
僕らにできることは、今の教育の現実を客観的に、ありのままに提示して、「今の教育はこんなふうになっています。このままでは日本はただ衰退するだけです。このままでいいのですか? これをどうしたらいいんでしょう?」と問いかけ、みんなで知恵を出し合うしかない。誰か力のある人に「正解」を出してもらって、それに従うというわけにはゆきません。市民全員が徹底的に「学校教育はいかにあるべきか」と問い続けなければ話は始まりません。公教育をここまで破壊するのに何十年もかけたわけですから、これをまた再建するためには官民一体となっても同じだけの歳月がかかると思います。

弱まる学歴主義と、強まる階層の固定化
――「格差社会」が問題視されて久しいですが、社会格差や学歴社会など、学校教育と絡めてどう見ていますか。
学歴に対する過剰な意味付けは今しだいに弱まっている気がします。子どもたちが有名になったり、お金を稼いだりするためのキャリアパスはいろいろと用意されていますから。
僕が子どもの頃、日本がまだ貧しかった時代は、貧しい家の子どもたちがキャリアを形成するためには高学歴しか手立てがありませんでした。プロ野球選手になる、歌手になるといったキャリアパスはよほど例外的な才能のある人にしか開けていなかった。キャリアを形成する上で一番フェアに開かれていたのが学歴でした。だから学歴社会になった。
「勉強さえできれば、何とかなる」というのが戦後日本の貧しい家の子どもたちにとってほとんど唯一の希望でしたから、学歴偏重になったことはある意味仕方がなかったと思います。もちろん、子どもたち一人一人に先天的な能力差がありますから、それだって決してフェアな競争ではないのですけれども、それでも家が貧しくても、身体が弱くても、学歴社会においては競争することができた。そういう点ではフェアでした。「学歴社会」は敗戦で貧しくなった日本社会が民主主義を採用した以上、必然的に登場してきたものだったと思います。
逆に、今は学歴の重みがしだいに軽くなっています。理由の一つは、多くの職業が世襲になったせいだと思います。政治家も世襲、経営者も世襲、芸能人も世襲。社会の上層部を占める職業ほど世襲が増える。「家業」を受け継ぐ子どもはキャリア形成では圧倒的なアドバンテージがあります。今ではもう「勉強ができる」というだけでは手が届く地位が限定されてきた。
学歴社会でなくなってきたというのは、別にそれで何か「よいこと」が起きたわけではありません。むしろ、生まれた段階でキャリアパスの割り当てが終わっていて、個人的努力で這い上がることのできる範囲が狭くなったということです。それだけ社会的流動性が失われて、階層が固定化したということです。
受験勉強へのモチベーションの変容
学歴が軽んじられるようになったもう一つの理由は「反知性主義」が広まったせいだと思います。「勉強なんかできてもしょうがない」ということを声高に言う人たちが、社会の上層部に増えてきた。「オレは勉強なんかできなかったけれど、こんなにえらくなった。だから学校の勉強なんか意味がない」ということを誇らしげにいう人がどんどん増えてきた。
戦後日本が学歴偏重であったのは、もちろん今言ったように「キャリアをめざす」ためには高学歴を手に入れることが合理的な道筋だったという事情もありますけれど、それと同時に「知性と教養」を高く評価する「教養主義」も大きくかかわっていたと思います。
僕は子どもの頃には、かなり真面目に勉強をしました。でも、それはいい大学を出て、いい会社に行って、出世して、高い給料をもらうというような生臭い目的のためではありませんでした。そういう「立身出世」は僕の勉強のインセンティブではなかった。僕が勉強を一生懸命やっていたのは、いい学校に行って、すばらしい先生に就いて、レベルの高い勉強をして、学友たちと熱く議論して…という教養主義的な動機にドライブされていたからです。そういう子どもは決して少なくなかったと思います。別に出世したり、金儲けをしたいから勉強するのではなく、勉強して知識や教養を身に着けたいという子どももたくさんいました。だから、受験勉強そのものは「無意味だ」と思いながらも、これを通過すれば、「知識と教養の場」に参入できると自分に言い聞かせることができた。
いまは、受験勉強を通じて、「知識と教養の場」に参入することができると信じている子どもはほとんどいないんじゃないかと思います。受験はただの「格付け」のための競争であって、受験勉強で高いスコアをとることが、その先の「知識と教養の場」への参入の資格になるというようなことを考えている子どもはほとんどいないんじゃないでしょうか。
学校教育がただ選抜と格付けのためにあるのだと思ってしまうと、あとは競争で相対的に優位に立つことしかすることがない。競争相手を1人でも減らせば自分が有利になる。自分の学力を上げることよりも、周りの競争相手の学力を下げることの方が、費用対効果がよいですから、学校教育を格付けに使うと、子どもたちの学力はどんどん下がって来るのは当たり前なんです。相対的な優劣だけが問題であるなら、全員が「勉強ができない」という状態のときこそ、わずかな学習努力で大きなアドバンテージが得られるからです。同学齢集団全体の学力が低下することが、相対的な優劣を競う環境としては、一番楽です。だから、いかにしてみんなが勉強に意欲をなくすようにするかに子どもたちが努力するようになった。今の子どもたちは無意識的にはほぼ全員がそうしていると思います。子どもたち同士の会話を横で聴いていても、おたがいの知的パフォーマンスを向上させるためのやりとりというのはまず聴くことがありません。ほとんどの会話は「そんなことを知っていても、学力向上には何の影響ももたらさない情報」のやりとりだけで構成されている。そういう話題の選択が無意識に行われている。
日本では、この10年間の政治家たちの知的劣化は目を覆わんばかりです。深い教養を感じさせる政治家の言葉というものを僕は久しく耳にしていません。逆に、知性にも教養にもまったく敬意を示さない政治家たちが教育についてうるさく発言している。その結果、日本の高等教育は先進国最下位に向けて転落し続けています。そのことに切実な危機感を持たないと日本という国にはもう先がないと思います。
編集部注
1「『年3%成長を約束』、大学ファンド支援の条件に 研究力向上確認も」朝日新聞DIGITAL(2021/12/24)
https://www.asahi.com/articles/ASPDS5QMWPDRULBJ019.html
教育を支える出版社として
1948年の創業以来、教育書の専門出版社として、主に学校教育に関わる出版活動を続けて参りました。学術書から実用書まで、教育書という分野において確かな地盤と実績を築いてきたという自負があります。
一方で、社会の大きな変化と、それに合わせた学校教育を含む教育情勢の変化も感じて参りました。創業前年の1947年には最初の学習指導要領が作成されました。当時はまだ「試案」という形で、戦争を省みる言葉とともに、子どもの興味や関心を大切にする児童中心主義の教育観が打ち出されました。
それから約70年が経ち、変わらない本質的な部分は現代に引き継がれつつも、全国の小中学校の9割以上に一人一台端末が配備され、授業風景が大きく変わろうとしています。学校から目を転じてみると、生産年齢人口の減少や科学技術の革新、地球規模での気候変動といった今まで人類が経験したことのない局面に直面しています。そのような変化の時代において、未来を生きる子どもたちのために、教育を支えるすべての人のために、何かまだできることがあるのではないだろうか――そのような思いから、本シリーズを新たに2022年より刊行いたします。


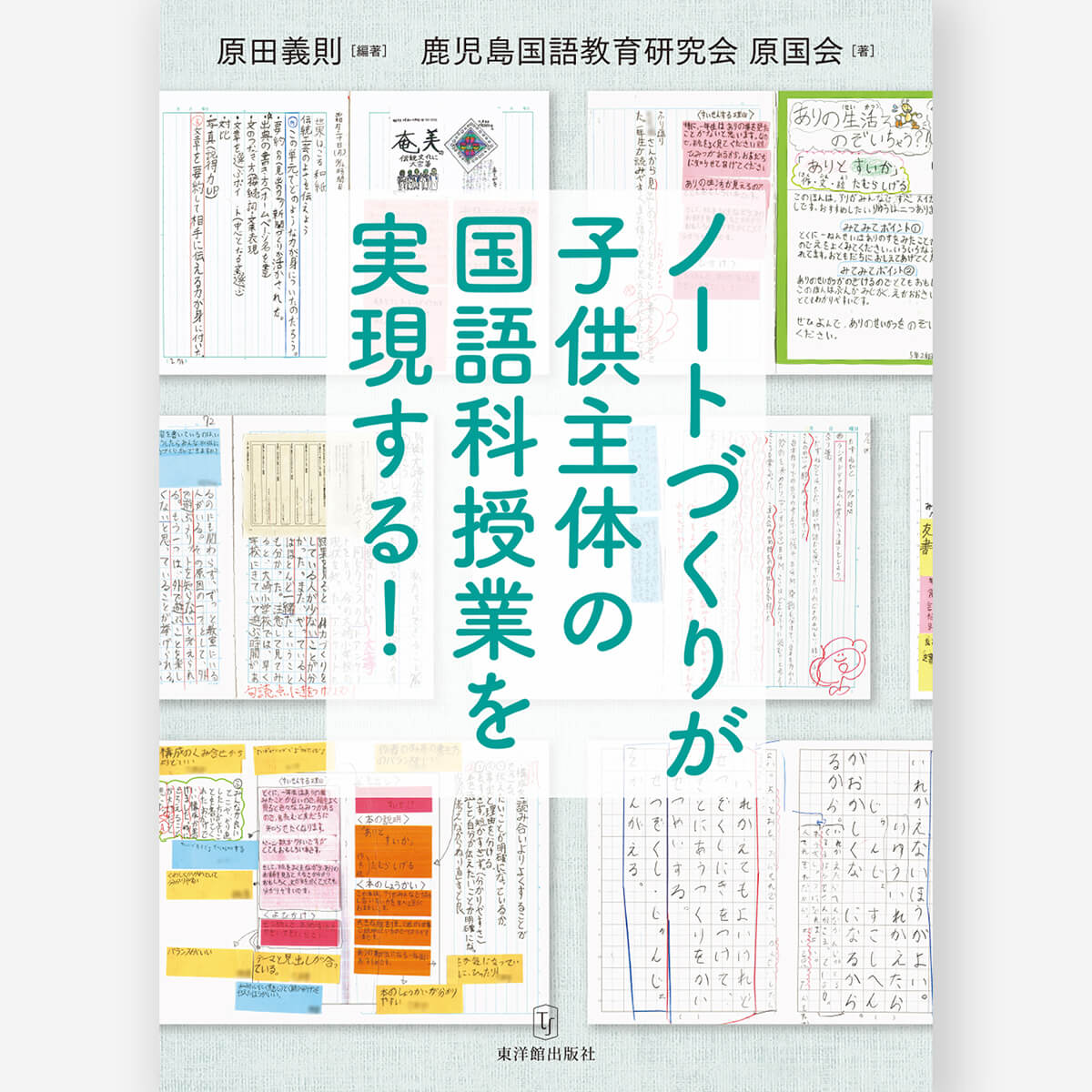



![[小中英語]学習者用デジタル教科書を活用するために知っておきたいこと―子どもを“真ん中”にした授業をつくる! - 東洋館出版社](http://www.toyokan.co.jp/cdn/shop/products/product-203055.jpg?v=1708564599&width=1200)