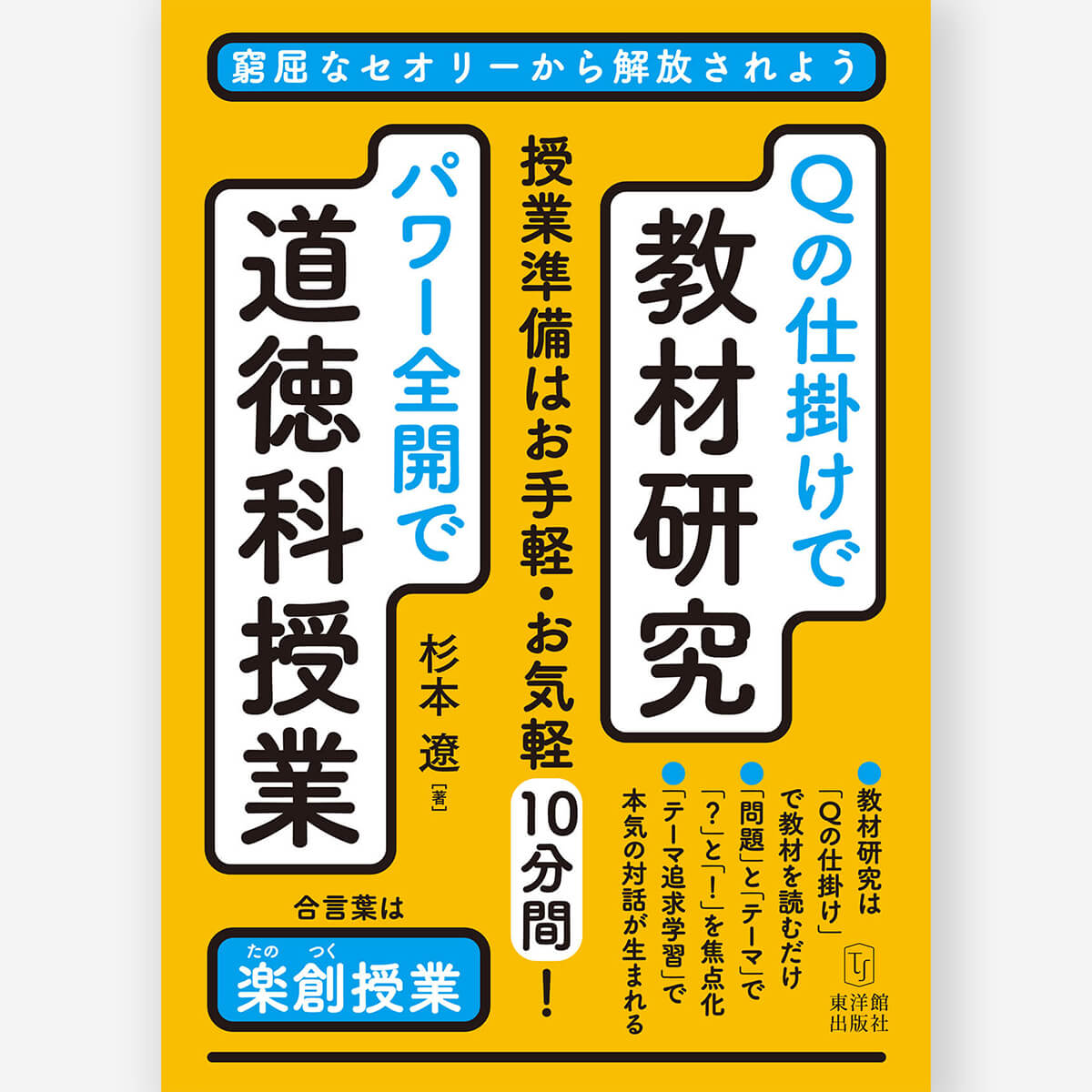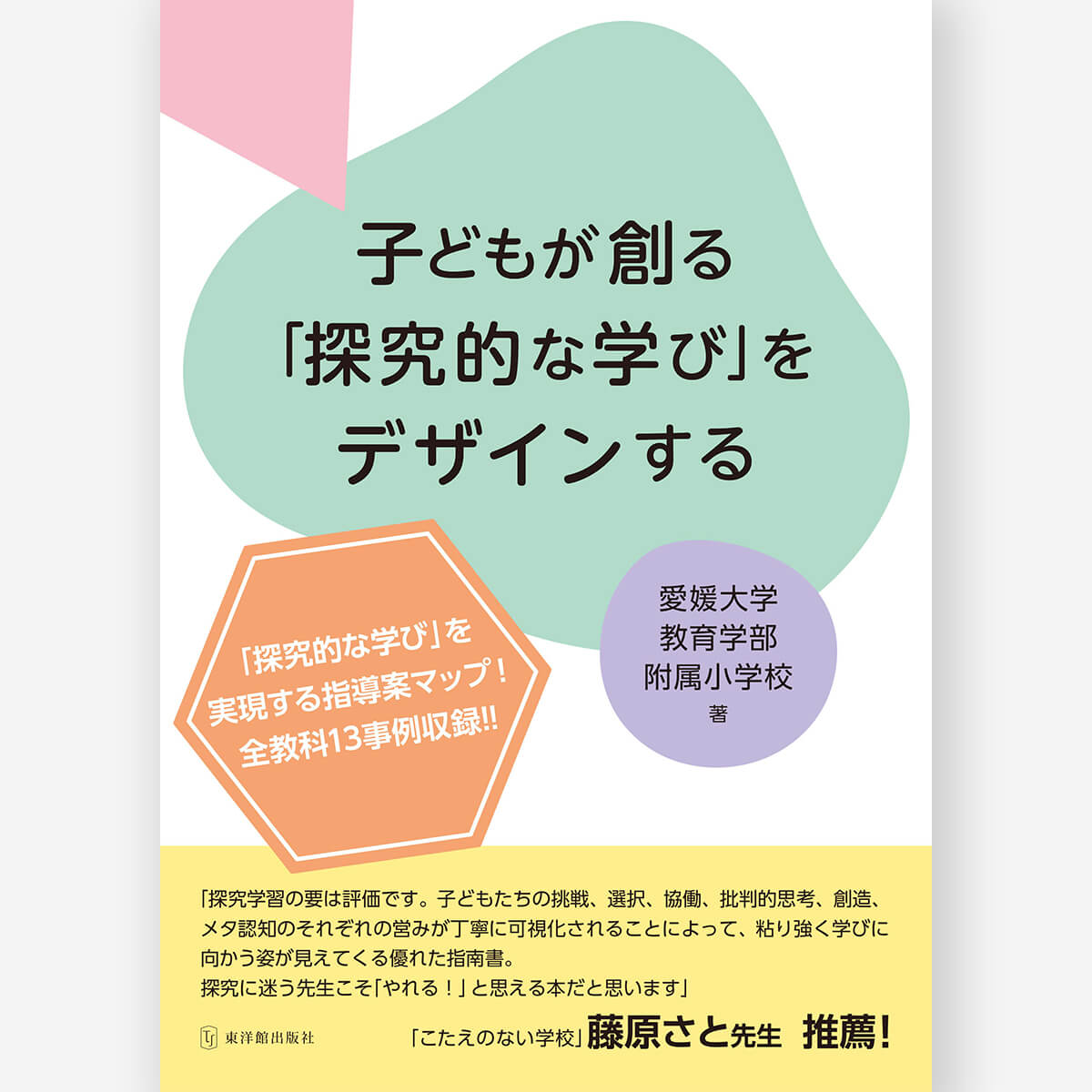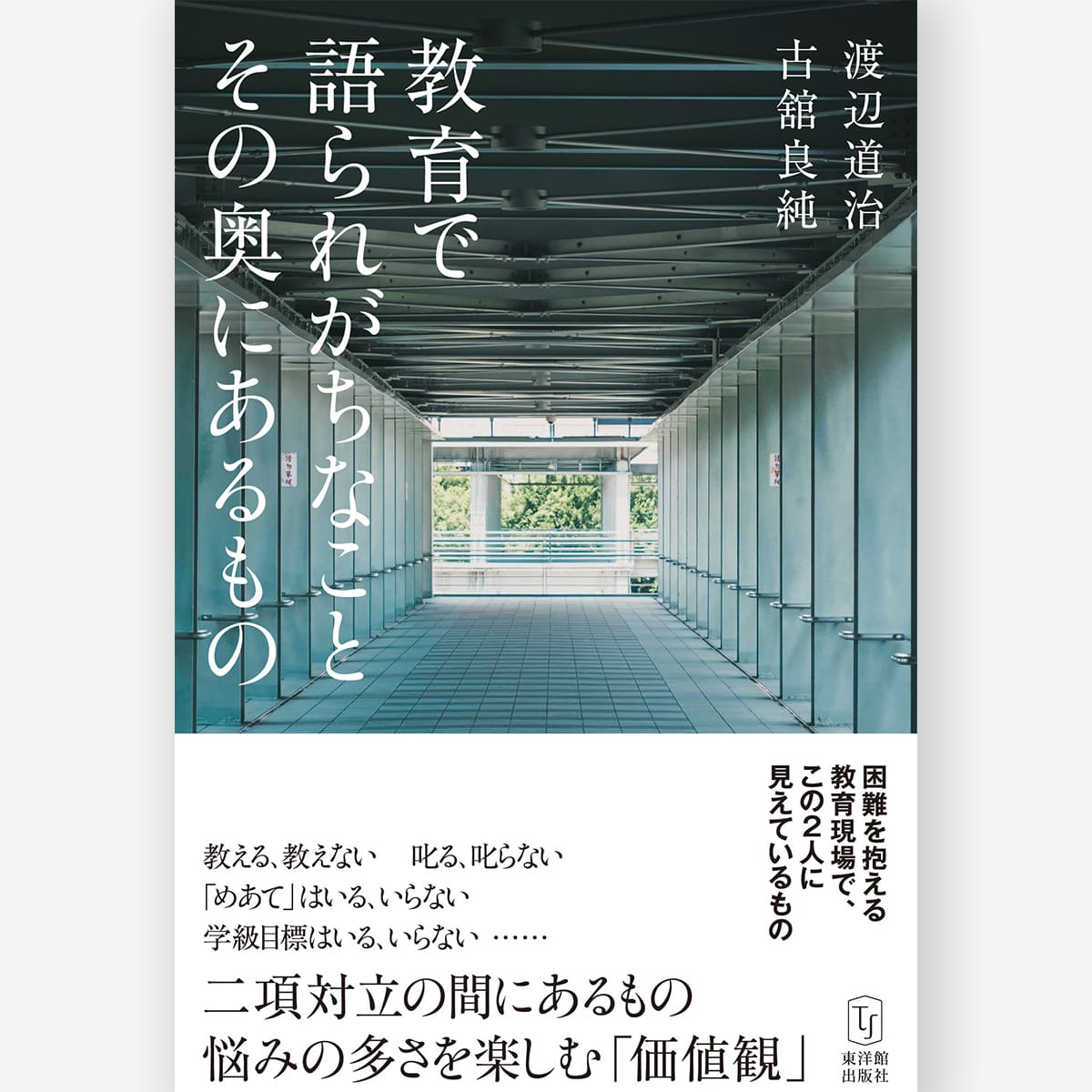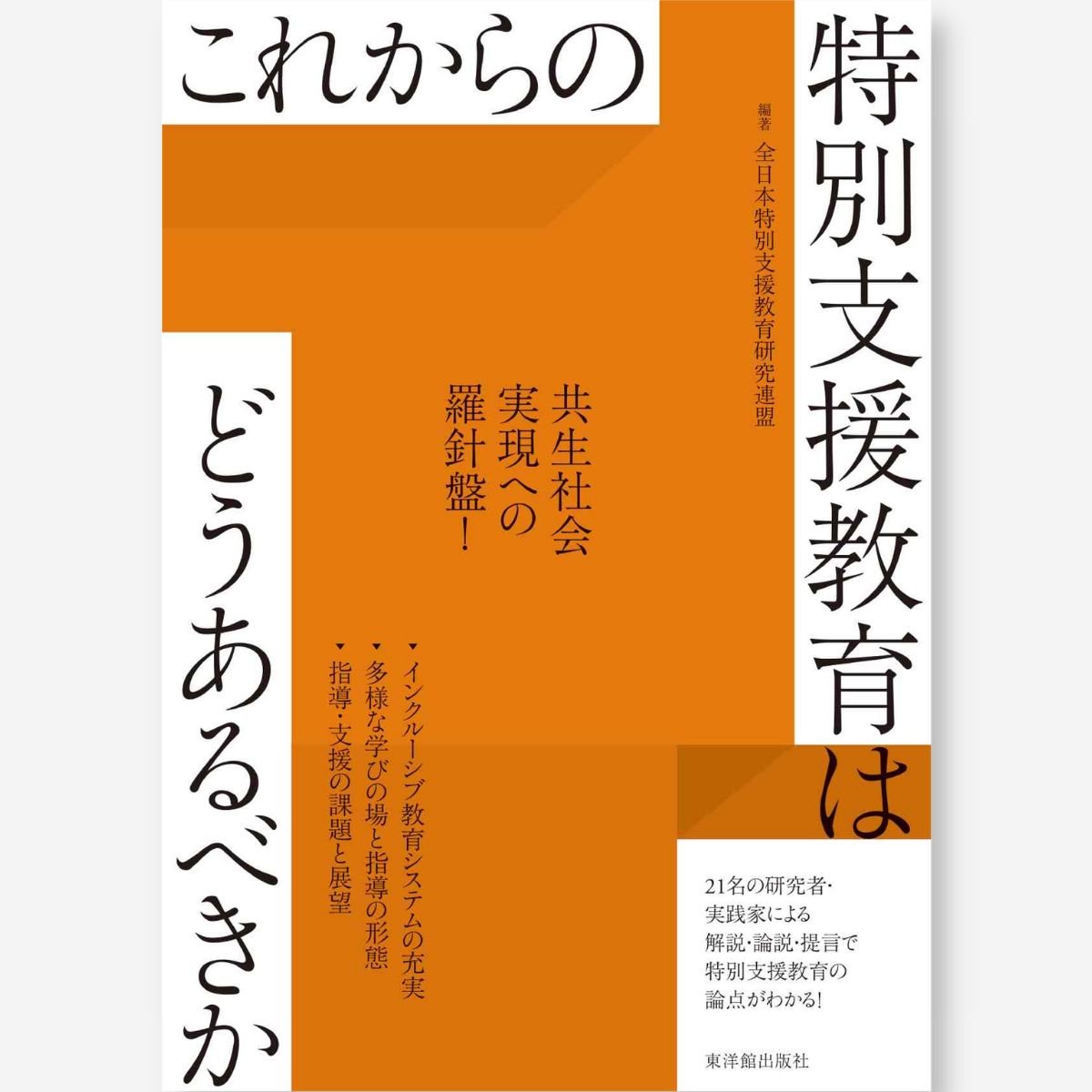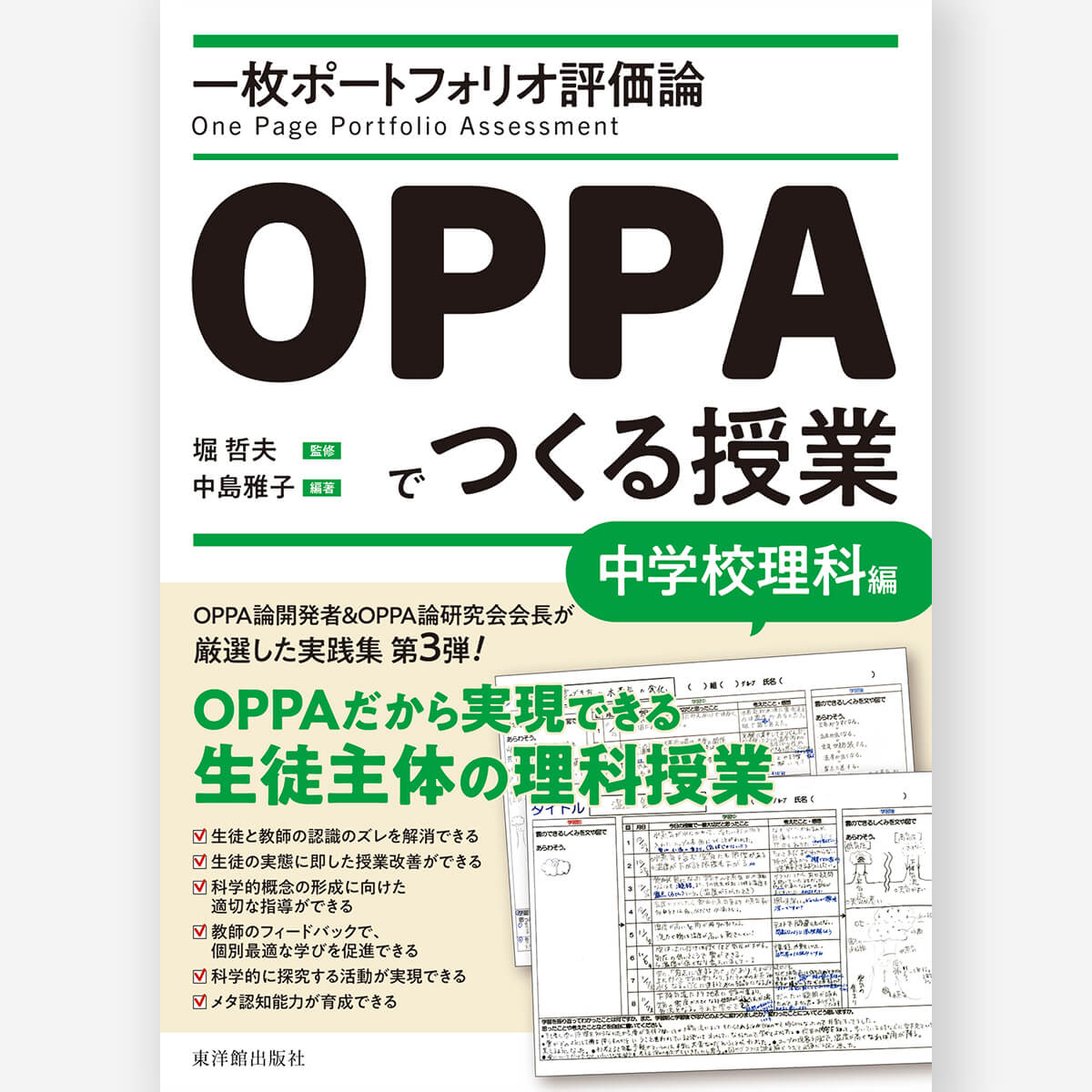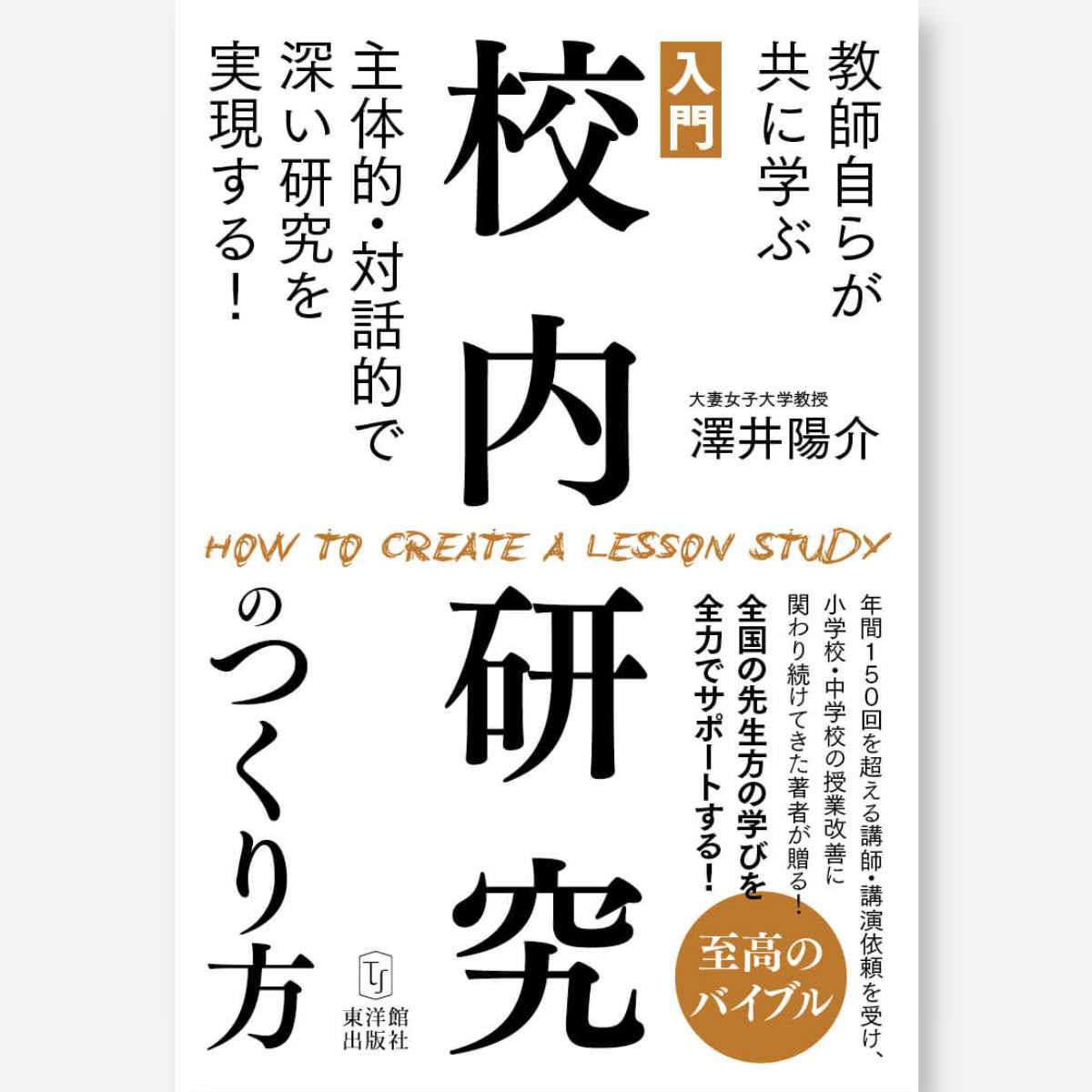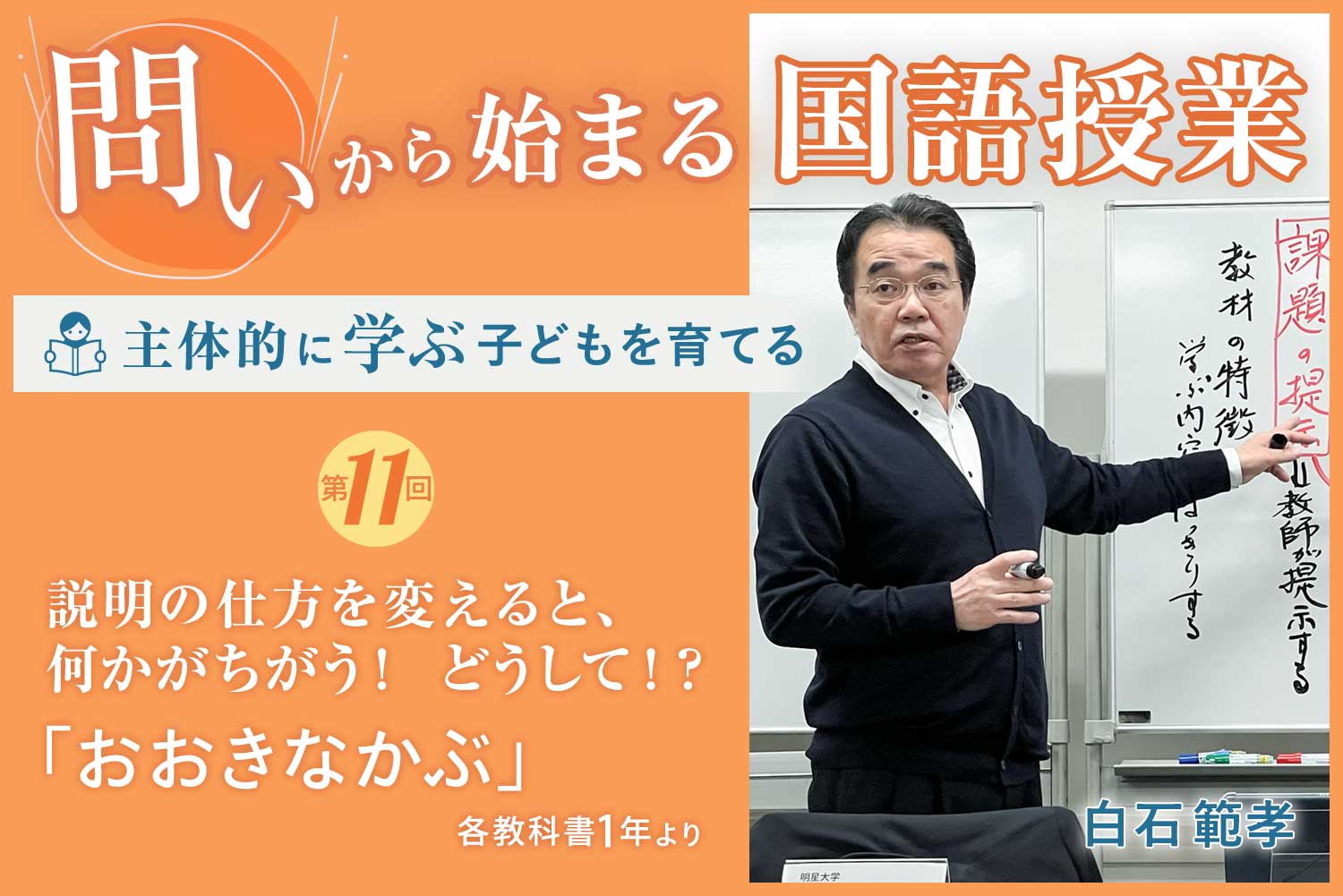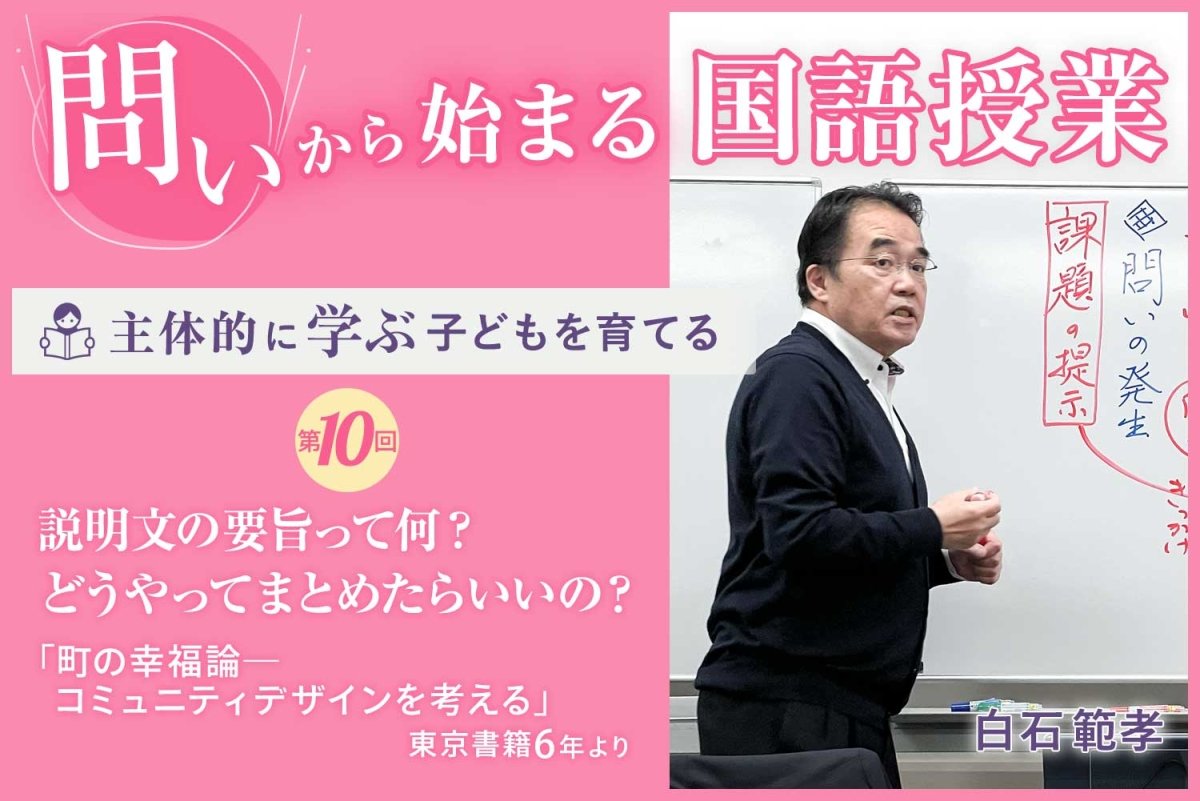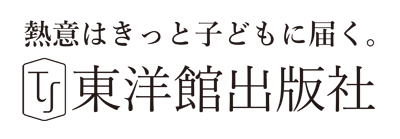子どもたちと共にたくらみ、新しいアイデアを一緒に生成する存在、“ジェネレーター”。今回はこのジェネレーターを紹介しながら、先生の“在り方”について具体的な事例をベースに考えていきます。
ジェネレーターとはどのような存在か、それを考える上でヒントになる言葉を紹介します。
『固定的な何かを見るのではなく、物事の生成・変化に向き合うことだ。』
『「つくることによる学び」や「創造的な学び」に対して、教師は一緒につくることに参加するジェネレーターとなることが重要となる。』
「ジェネレーター 学びと活動の生成」(市川力・井庭崇 共著、学事出版 2022)
小学校図画工作科の授業を例にすれば、先生が子どもたちにつくらせたい作品を提示し、それ通りに作らせることは、“固定的な何か”と言えるでしょう。
仮につくらせたい作品を想定していたとしても、先生が自らその制作の場に介入し、活動がリアルタイムに変化していくことを受け入れ、面白がっていく。これが、“物事の生成・変化に向き合うこと”と言えます。教師は一緒につくることに参加する、これがとても大切になってきます。
ジェネレーターの先生が図工授業を行うと?
具体的な図工の授業をベースにして、解説していきます。
例に挙げる題材は低学年の平面作品として実践されることの多い「おしゃれなカラス」です。制作手順はざっくり以下のとおりです。



と、こんな感じで制作します。 この題材も、実践する先生の“在り方”によって、かなり変わるのです。
上記の制作手順②にフォーカスし、わかりやすく3タイプの先生を例に解説していきます。
- A・教える意識の強い先生
- B・導く意識の強い先生
- C・ジェネレーターの先生
それぞれの特性が強い先生が授業を展開する場合、このようになると考えます。
A)教える意識の強い先生の場合
羽の形は予め決めて、事前に先生が描いたものを画用紙に印刷。子どもには、そこをカラフルに塗りつぶすように指示します。次に線に沿って、しっかりハサミで切るように指示。カラスに貼る羽の枚数も○枚と決め、伝達します。
B)導く意識の強い先生の場合
「どういう形がカラスの羽っぽい?」と全員に投げかけて、子どもたちのアイデアを造形に活かしていきます。羽の形を書いた後、色を塗る際も「どっちがいいかなあ」と対話しながら、または全体に問いながら、子どもたちに気づきと選択肢を提示します。“カラスの羽である”というゴールからは外れないように、子どもたちのアイデアを拡散・収束しながら、制作に活かしていきます。
C)ジェネレーターの先生の場合
Bの関わり方に加え、およそ“カラスの羽”には見えない、はみ出していく子どもがいたとしても、それを面白がります。「だったら、こういうのどう!?」とさらに教師自らがアイデアを提案したりして、制作に関わりはじめます。それを横でみていた別の子どもが「それいいね!僕もいいこと思いついた!」と、また別の“羽”とはちょっと違うアイデアが生まれていき、それがさらに別の子へと伝わっていきます。教師は「おしゃれなカラス」というテーマではじめたものの、結果的に全体的なテーマが変わってもいいとさえ思っています。
これらは、どれも極端な例として示しています。また、「あなたはこのうちのどれか?」という選択肢ではなく、ケースバイケースでその度合いは変化するでしょう。
みなさんがこの題材に取り組むとしたら、どんな“在り方”で関わりますか?
さて、上記のような極端な例で制作を進めていくと、作品はこんな風になるのではないでしょうか。
A)教える意識の強い先生の場合
作品1つに着目してみると、非常にクオリティが高く、「うちの子がこんな作品をつくれるなんて!」と保護者も驚くかもしれません。しかし、教室などで全員の作品が展示された場合、みんな同じような作品になっていることに気づきます。個々の差はほぼありません。
B)導く意識の強い先生の場合
作品1つに着目してみると、「あぁ、うちの子っぽいわ」と保護者は納得するかもしれません。教室などで全員の作品が展示されている場合、個々の作品に違いがあることに気がつきます。またクラス毎でも全体的な雰囲気に違いが生まれます。
C)ジェネレーターの先生の場合
作品1つに着目してみると、「これは一体なんだろう?」と保護者は困惑するかもしれません。全体テーマは「おしゃれなカラス」ではなく、「新種発見!?おしゃれな●●!」なんてテーマに変わるかもしれません。教室などで全員の作品が展示されている場合、個々の作品がまったく違うことに気がつきます。大きさもそれぞれで画用紙から羽らしきものがはみ出している作品も多く見られます。
これらは、僕が考える極端な例です。
Aの例は、制作過程よりも“作品”に重きが置かれています。
Bの例は、子どものアイデアを取り入れつつも課題としての方向性は外していません。
Cの例は、その場で生成されていくことを面白がり、それに乗り変化していくことそのものに向き合います。
教えるのではなく、変化していくことに向き合う
ここで再び、第14回でも紹介した上田信行先生のPLAYFUL THINKING[決定版](2020 宣伝会議)での一文を再掲します。
これまでの学校教育は、大人から子どもへ知識を伝達する「インストラクション(instruction)」が中心だった。〜中略〜 それに対して、今大きな潮流となっているのが、学びとは何かを体験し、その体験を振り返るプロセスを通じて自ら構築していくものであるという考え方だ。これをインストラクションに対して、「コンストラクション(construction)」という。知識とは他者から与えられるものではなく、自ら創り上げていくもの、つまり「創造するもの」であるという考え方だ。教育学では、このような創造的な学びのことを「コンストラクショニスト・ラーニング(構成主義的な学び)」と呼んでいる。
Aの例はまさに、大人から子どもへ知識を伝達する「インストラクション」です。
Bの例のように、子どもたちが自ら創り上げていくことを導いていければいいのですが、VUCA(予測困難)な時代において、それにも陰りが見えてきました。答えらしきモノ、ゴールらしきものがあれば導けそうですが、それが見えない。導き方が分からないのです。
今話題の探究学習。この答えのないこの取り組みに対して、先生方は皆悩んでいるのではないでしょうか。
そのヒントがこのCの例、ジェネレーターとしての「在り方」にあると思っています。教えるでも、導くのでもなく、その場で生成されていくことを面白がり、それに乗り変化していくことに向き合うのです。見通しを立てなくても、子どもたちと一緒になって、その場のなりゆきに乗って、面白がる。今、探究学習を楽しみながら実践している教育者たちは、総じてこのような特性をもっています。
ジェネレーターはなろうと思えば、誰でも、いつでもなれるはずです。そこが教科指導法や授業法、ファシリテーションのように様々な理論や技法を身につけることとの大きな違いです。ジェネレーターには、すでに身についていながらフタをしている感覚を取り戻すことで「自ずとなってしまう」のです。
僕はその感覚を取り戻すのに、図画工作科は最適だと考えています。今回紹介した授業例「おしゃれなカラス」をCのような例で実践するのは、正直あまりおすすめしません。そこで、この連載で何度も登場している図画工作科「造形あそび」の出番です!
ジェネレーターについてより深く知りたい方は、「ジェネレーター 学びと活動の生成」(市川力・井庭 崇 著 学事出版2022)をぜひ読んでいただきたいです。

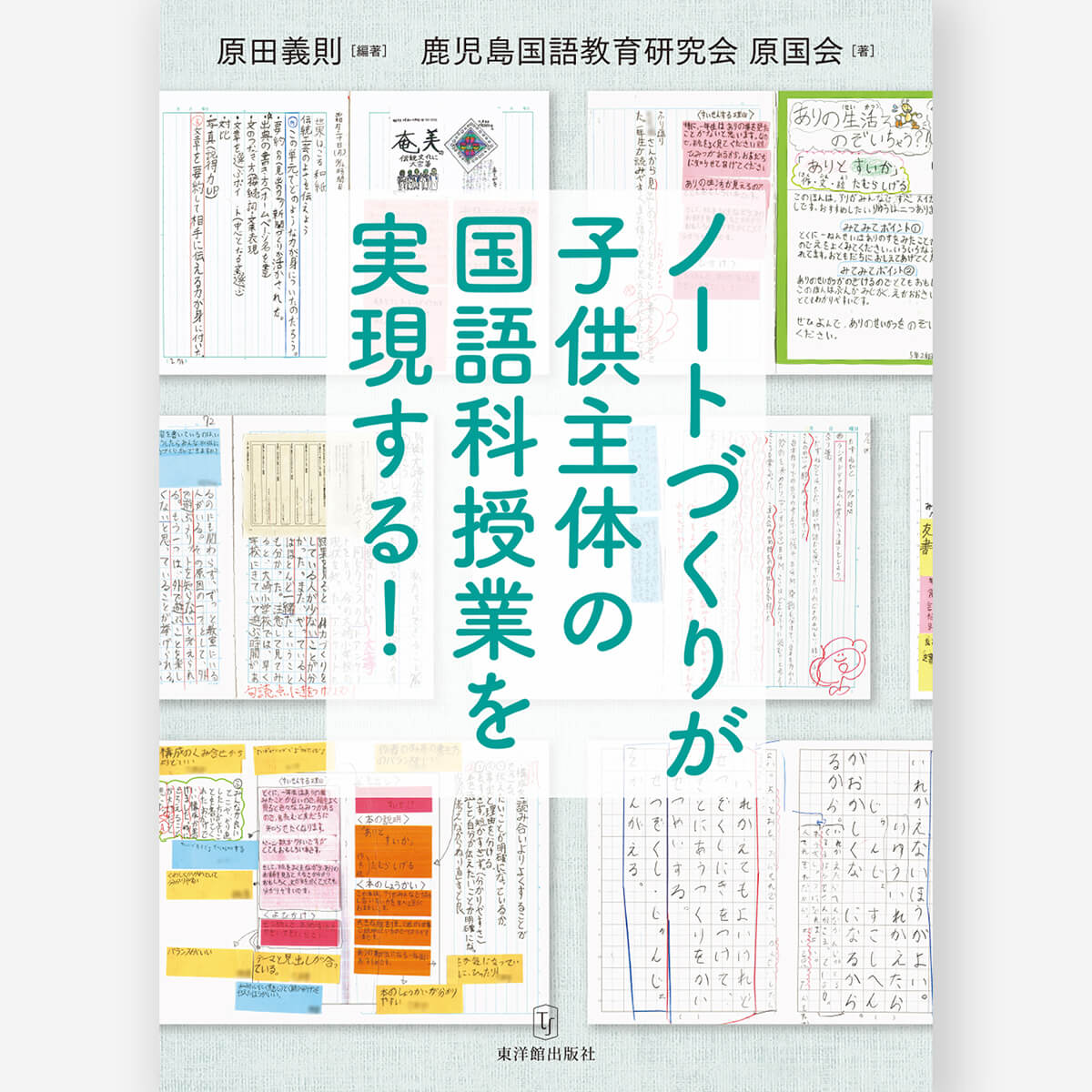



![[小中英語]学習者用デジタル教科書を活用するために知っておきたいこと―子どもを“真ん中”にした授業をつくる! - 東洋館出版社](http://www.toyokan.co.jp/cdn/shop/products/product-203055.jpg?v=1708564599&width=1200)