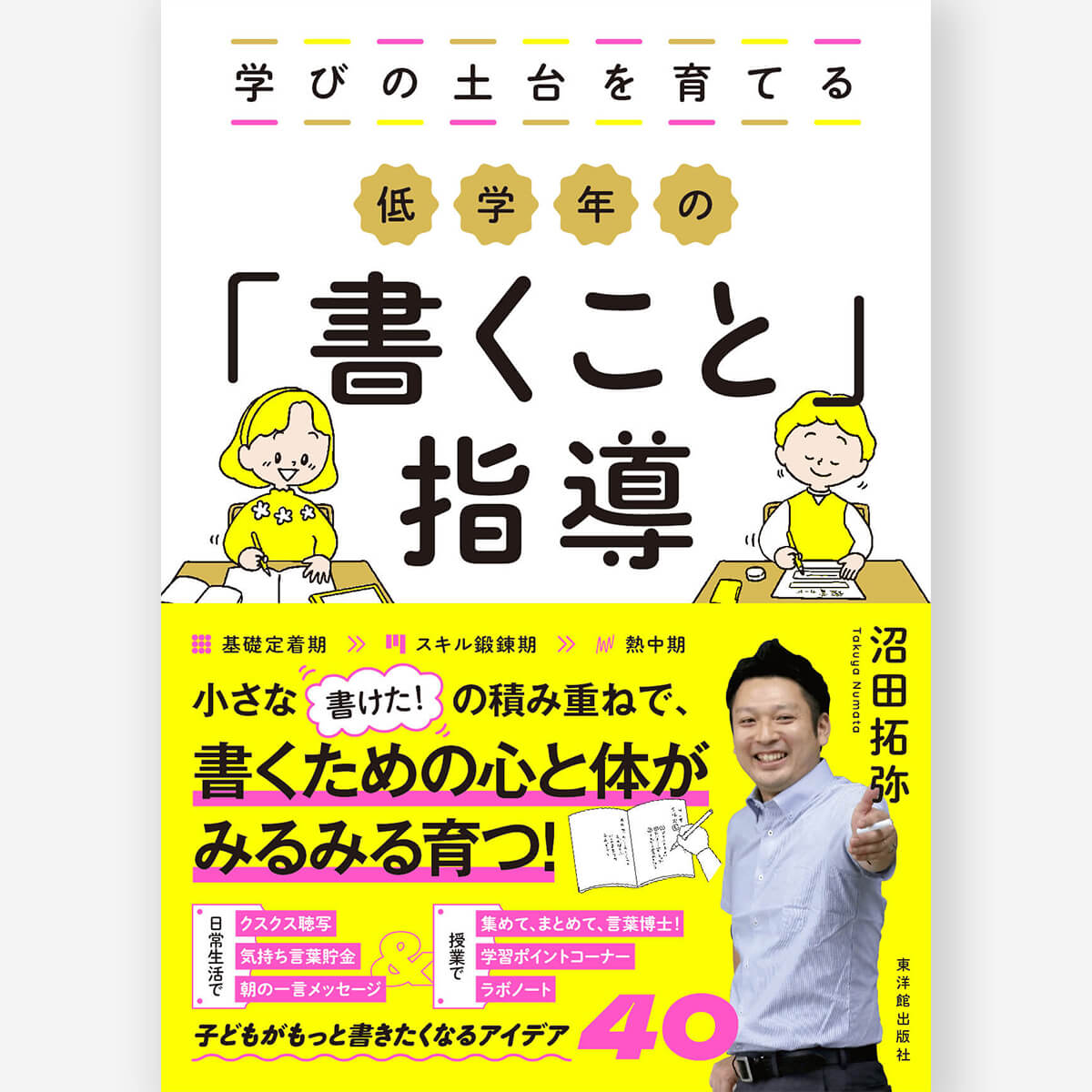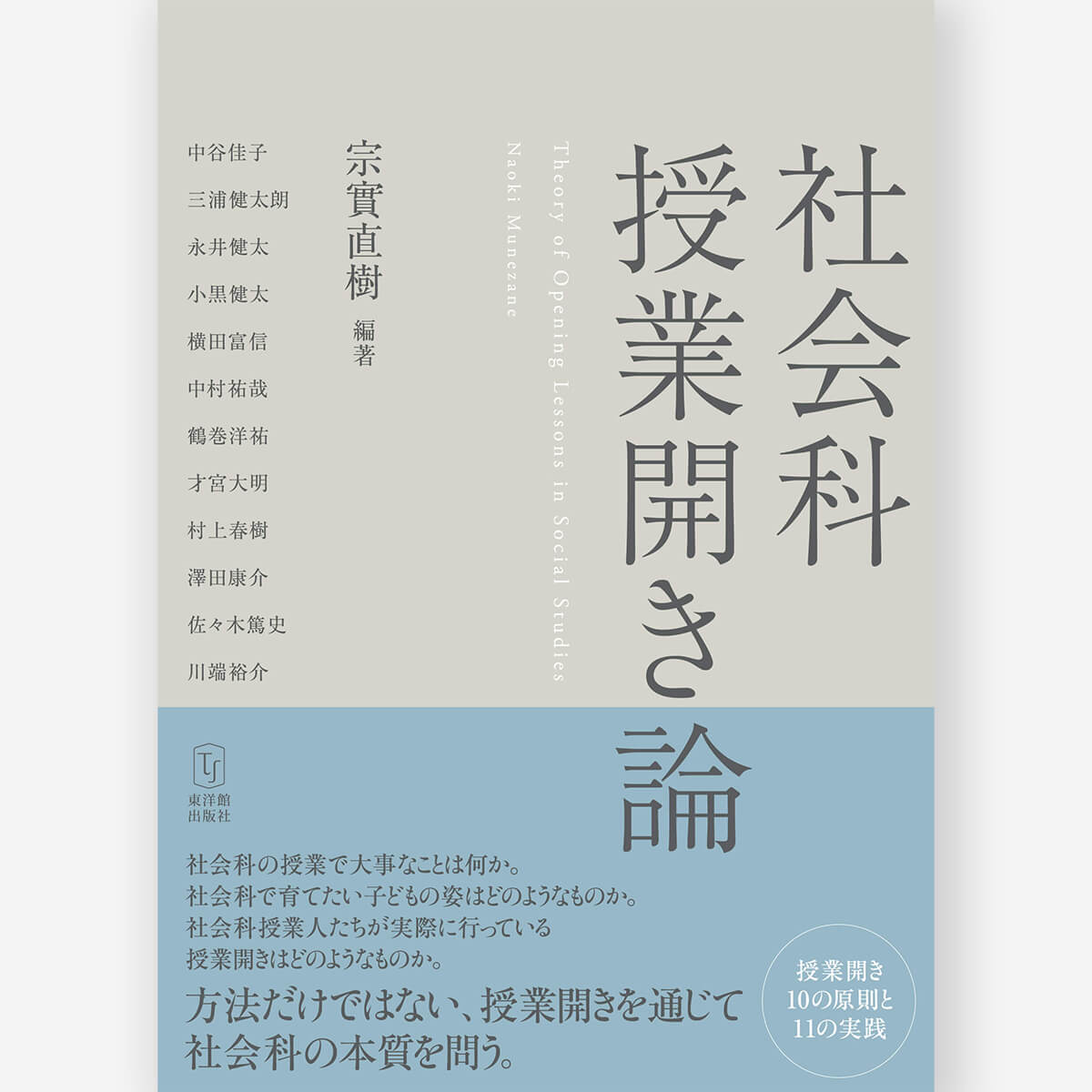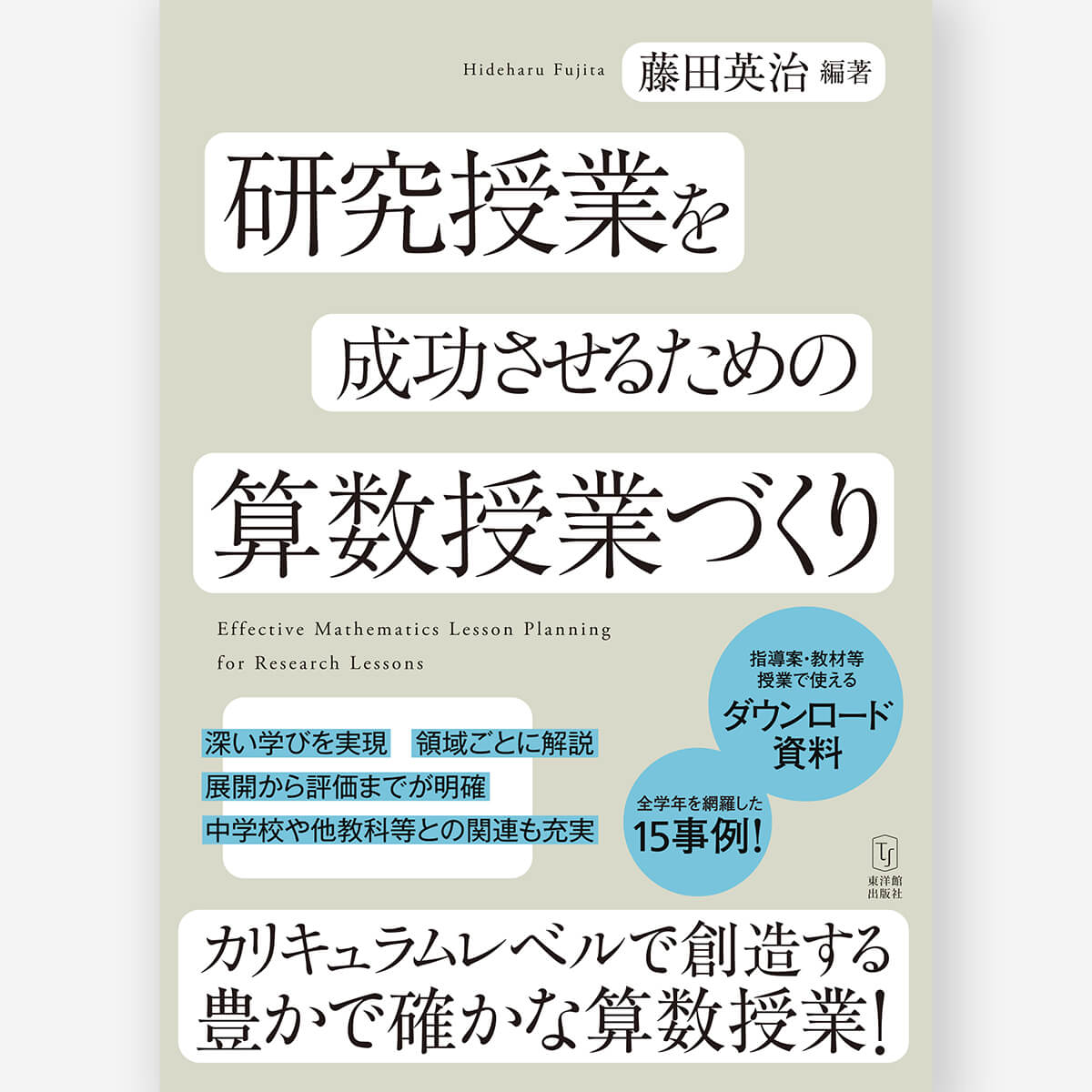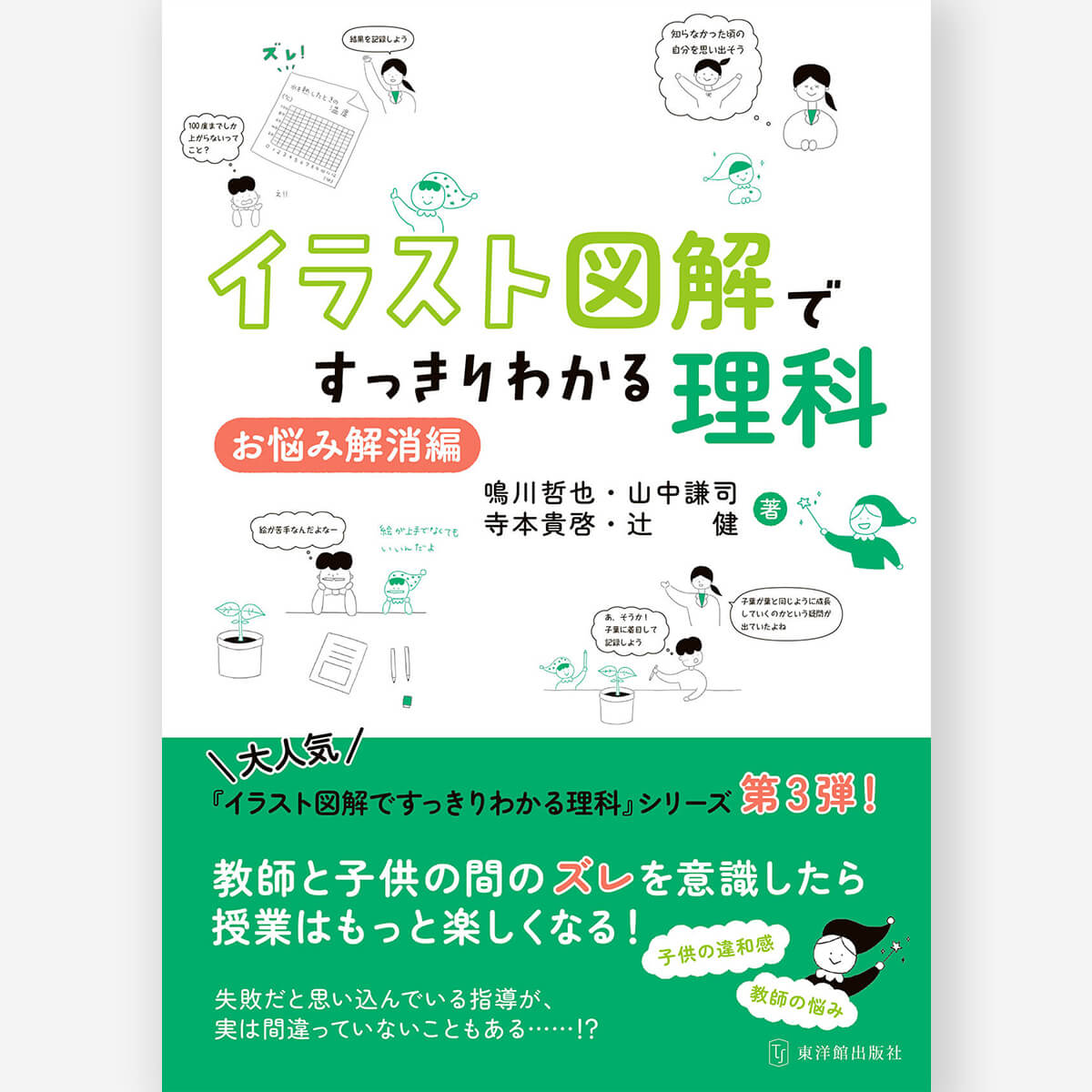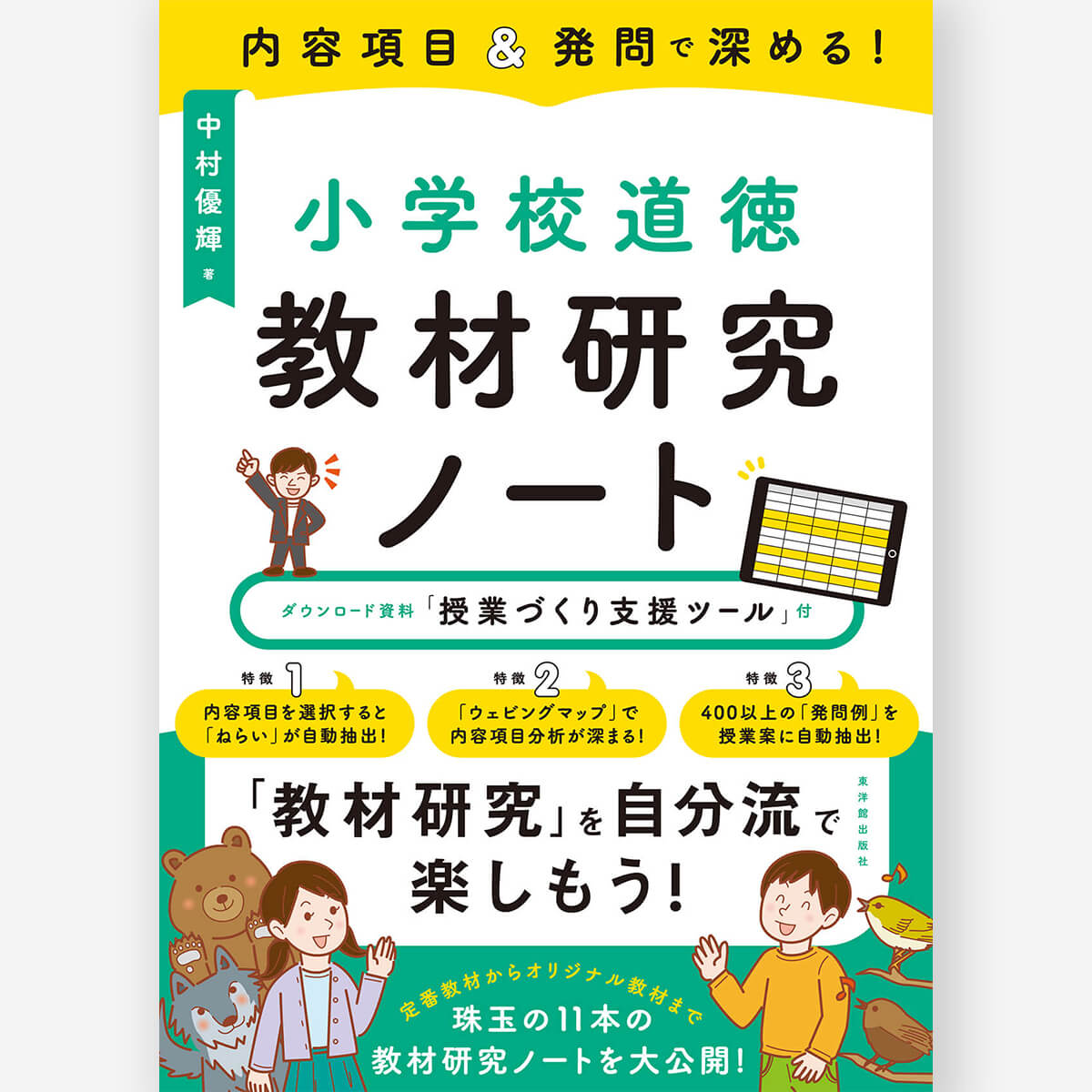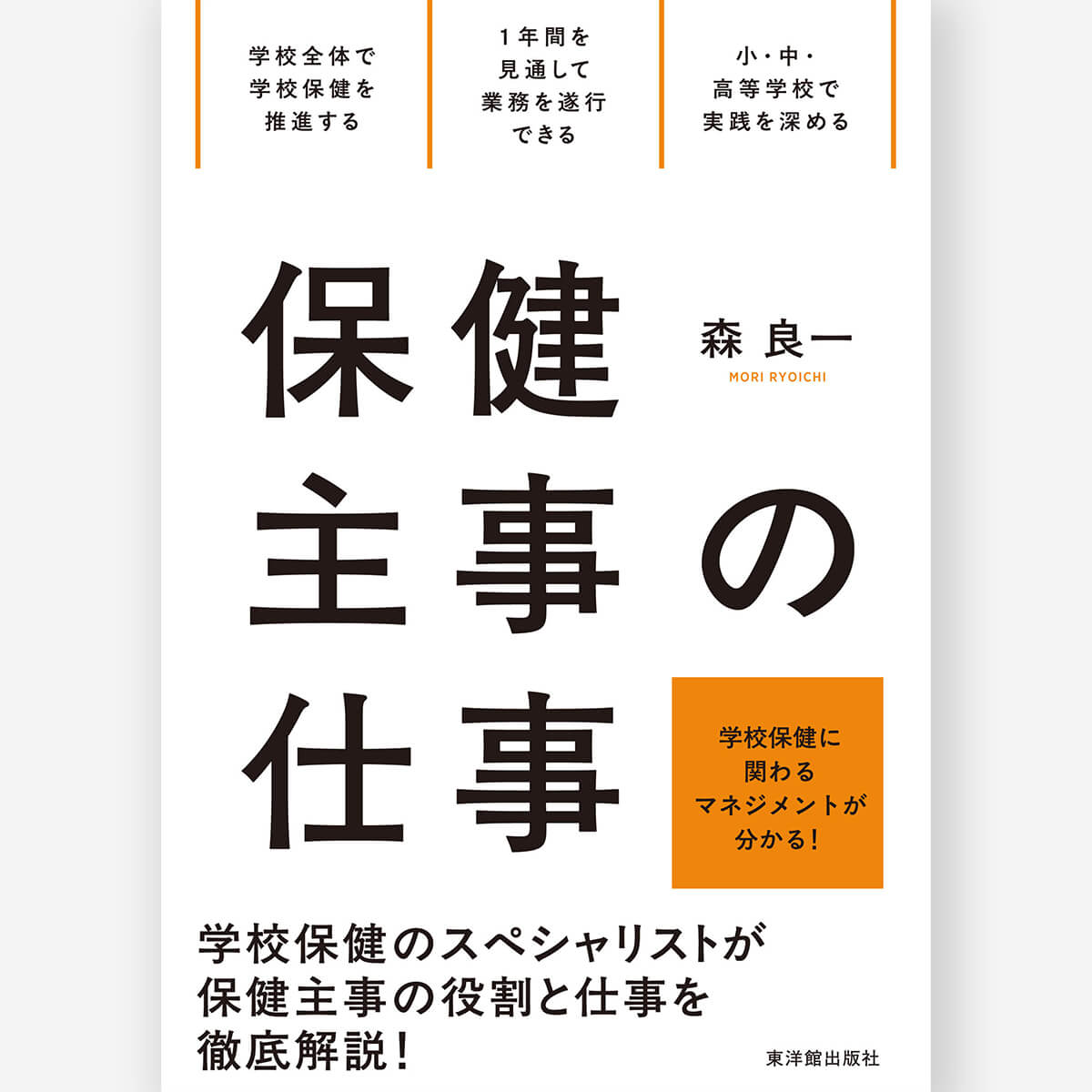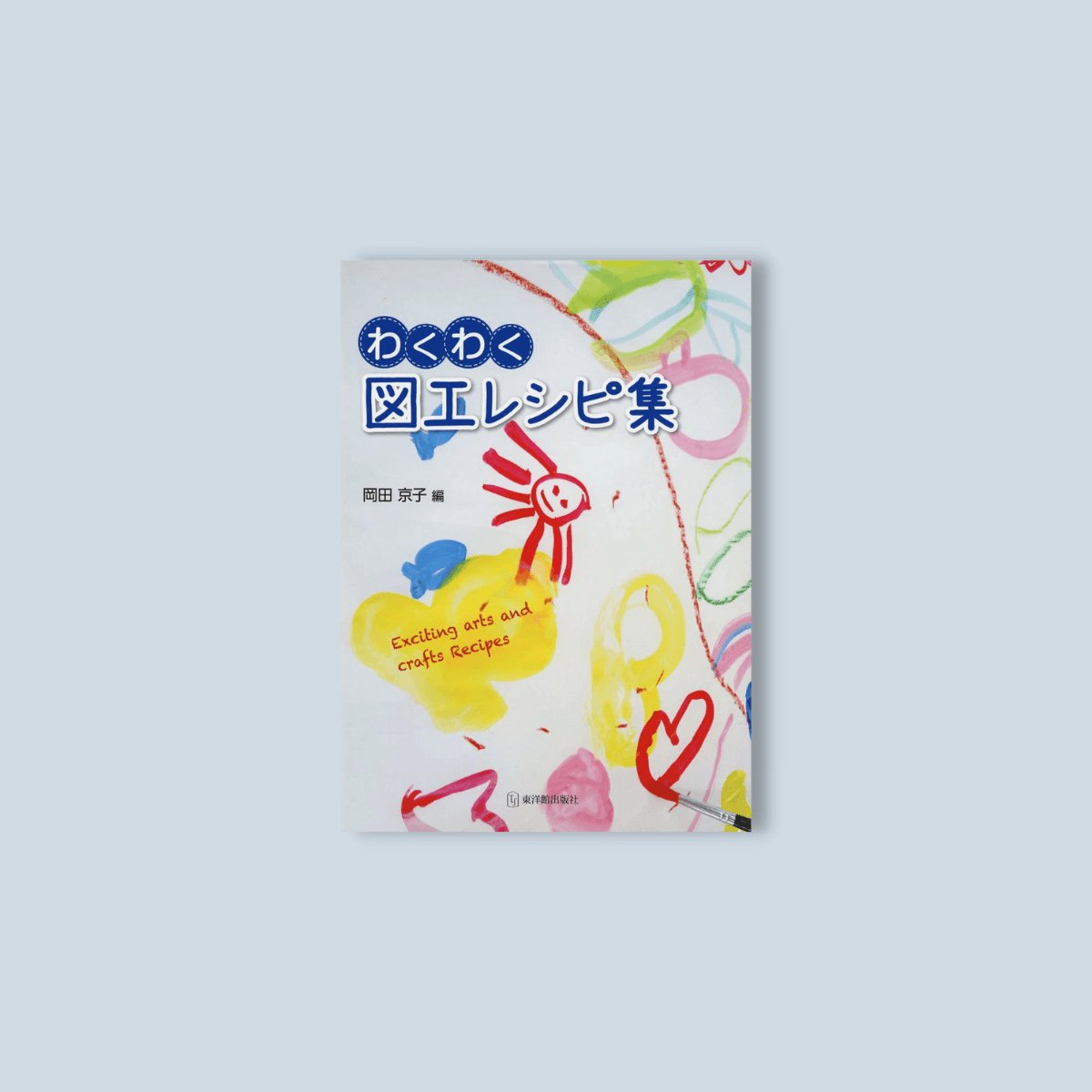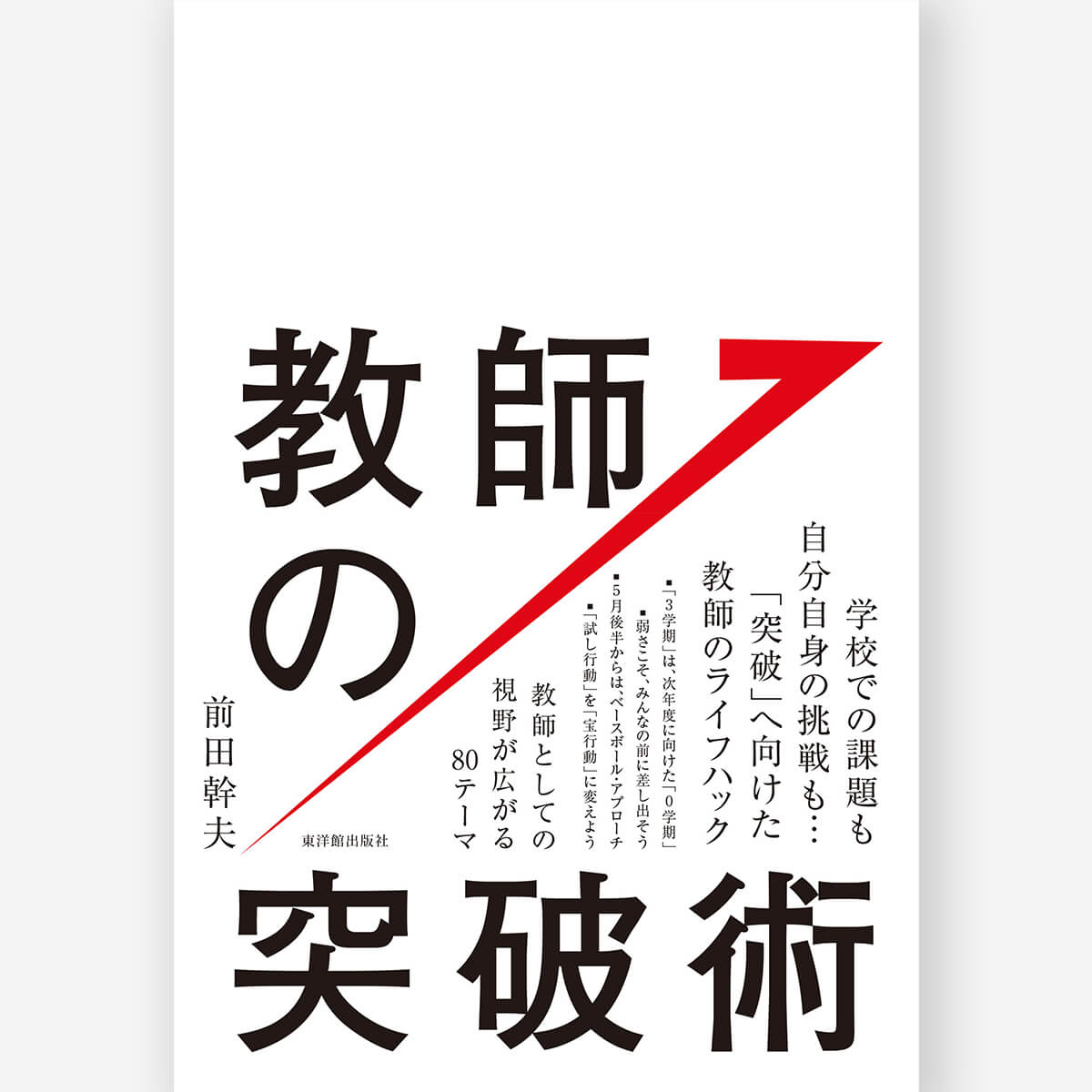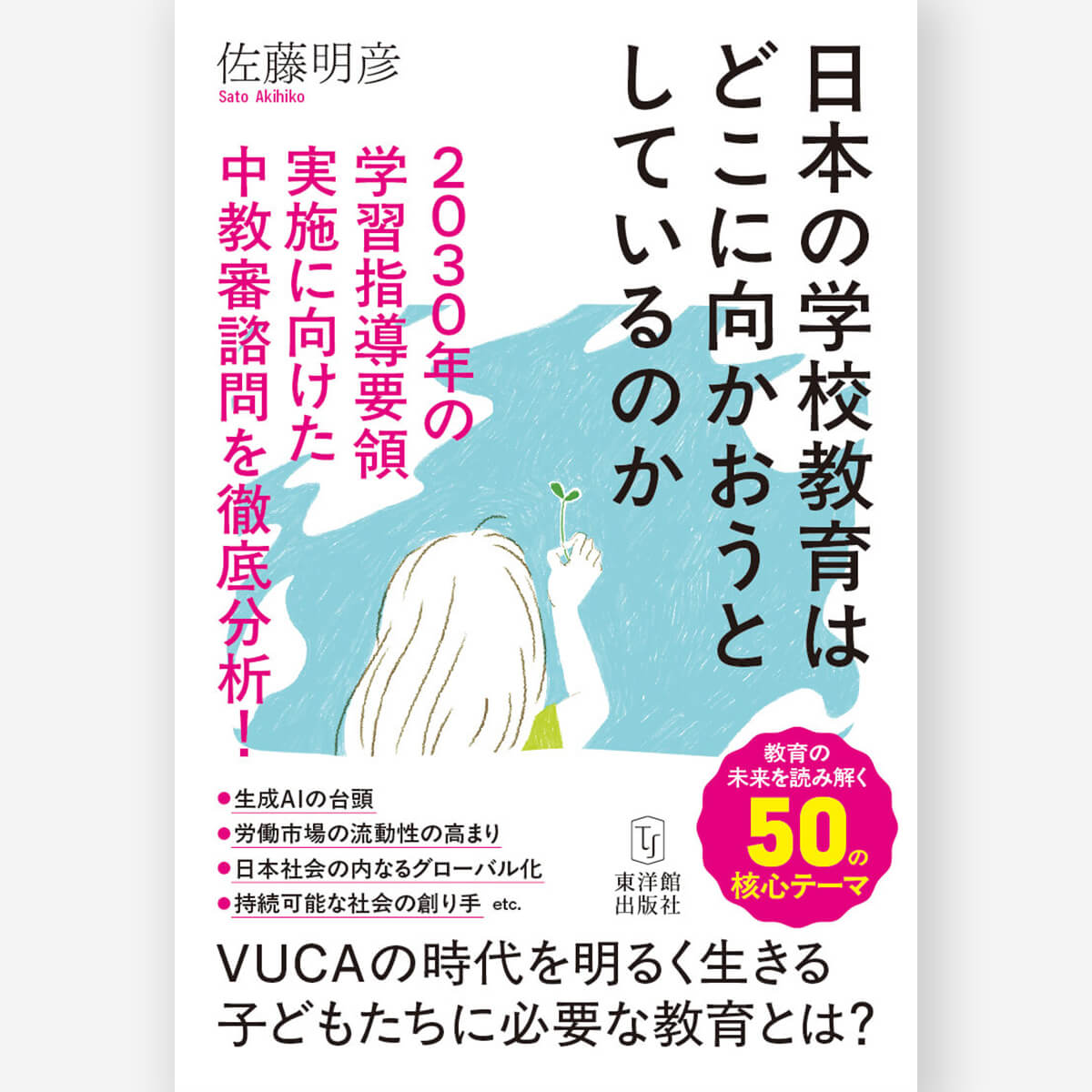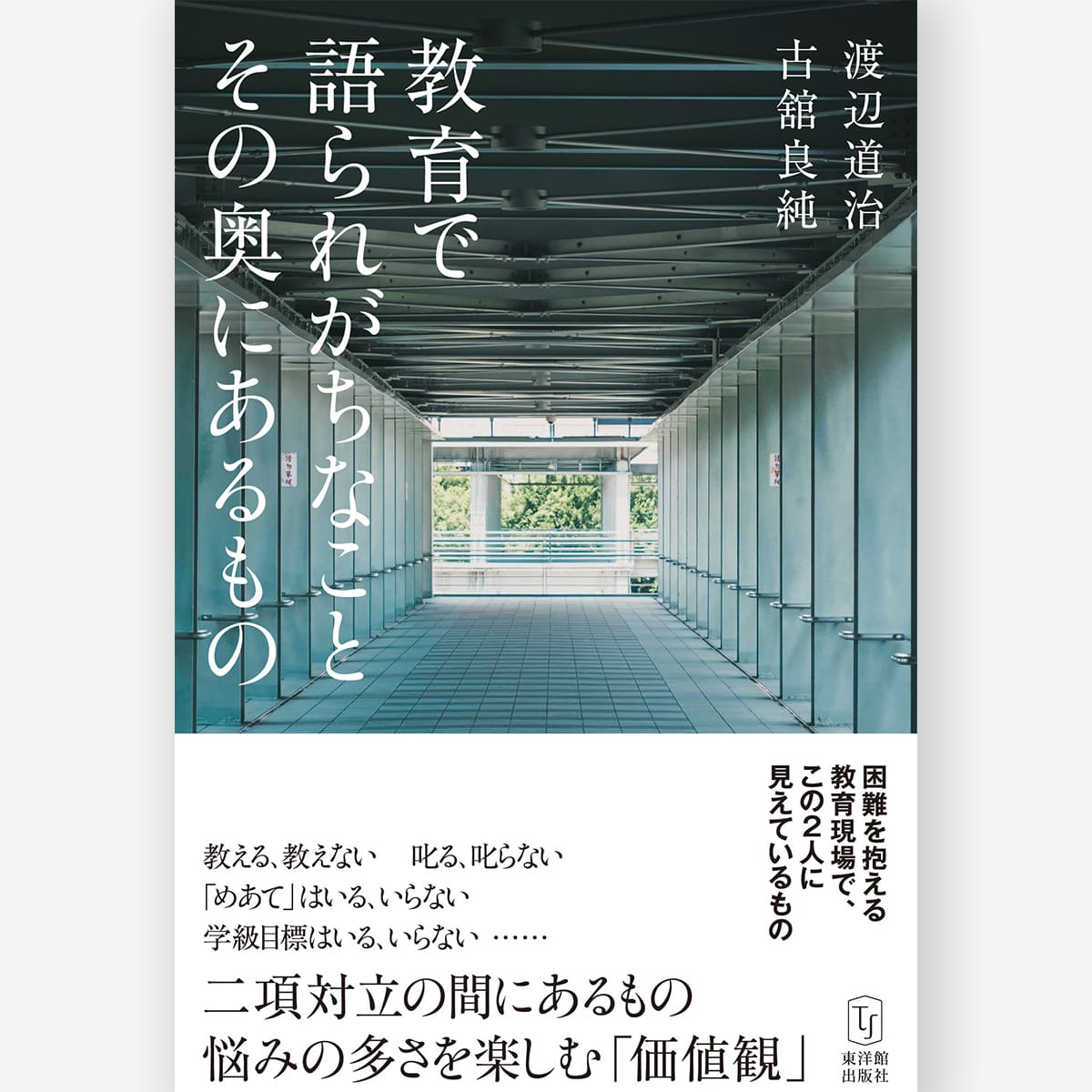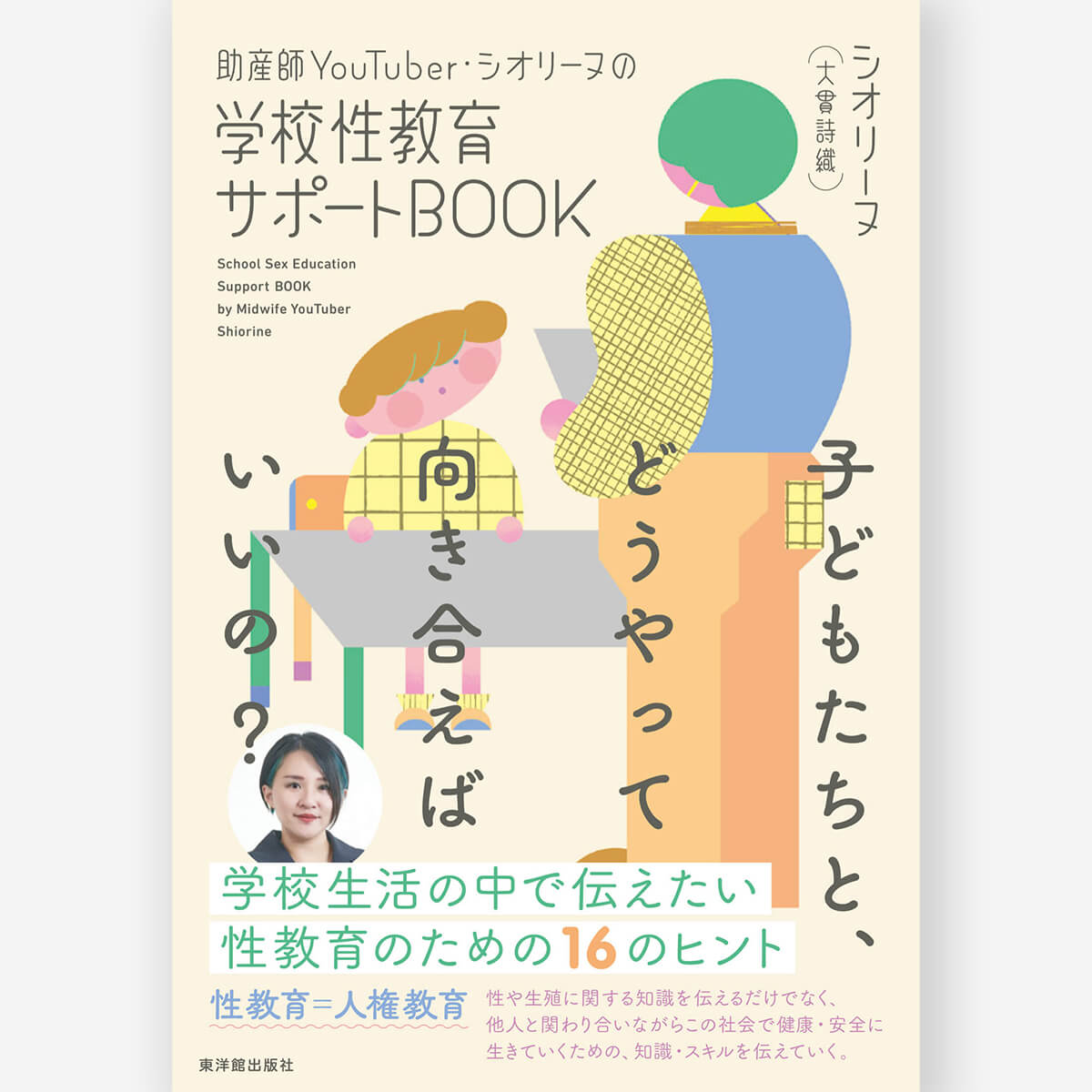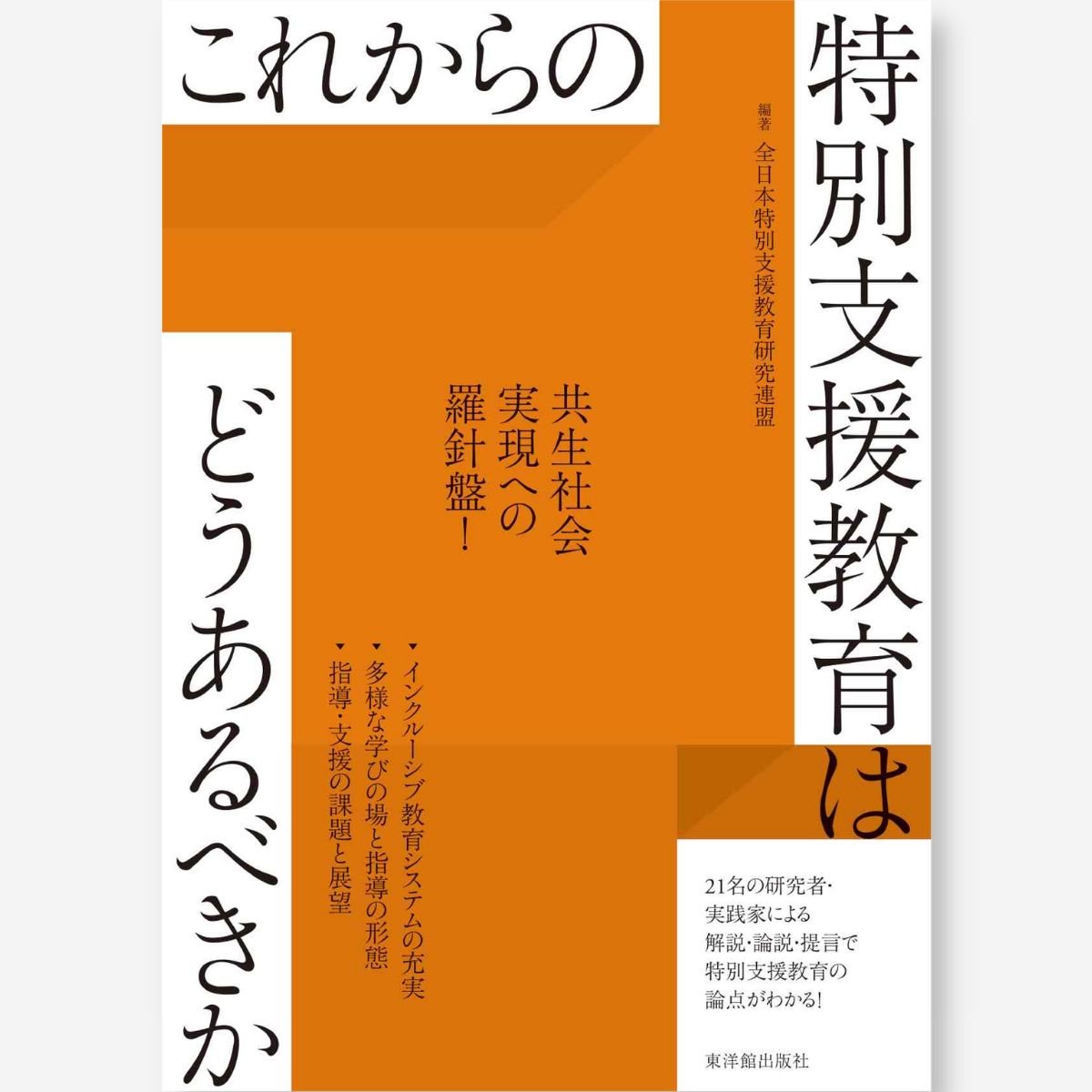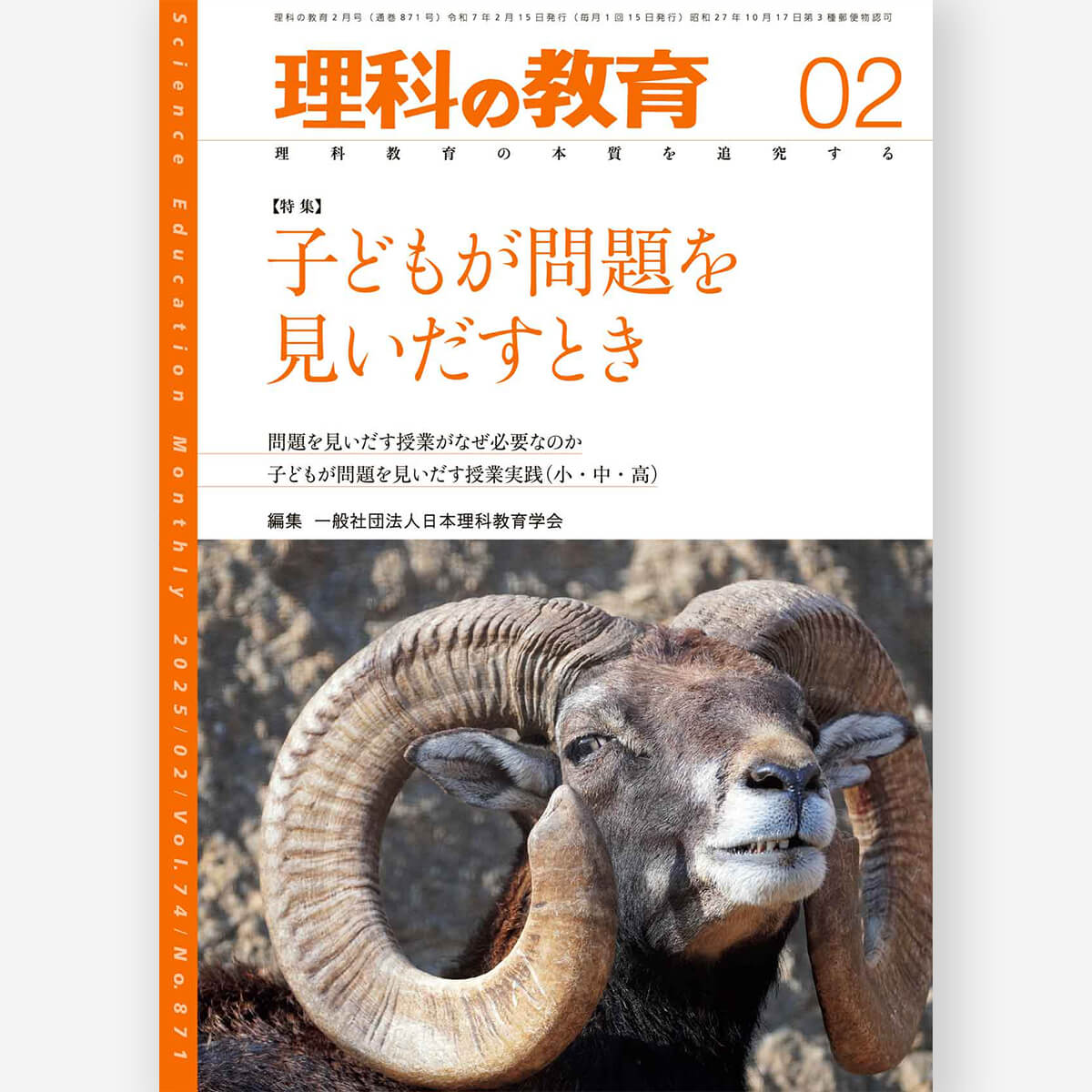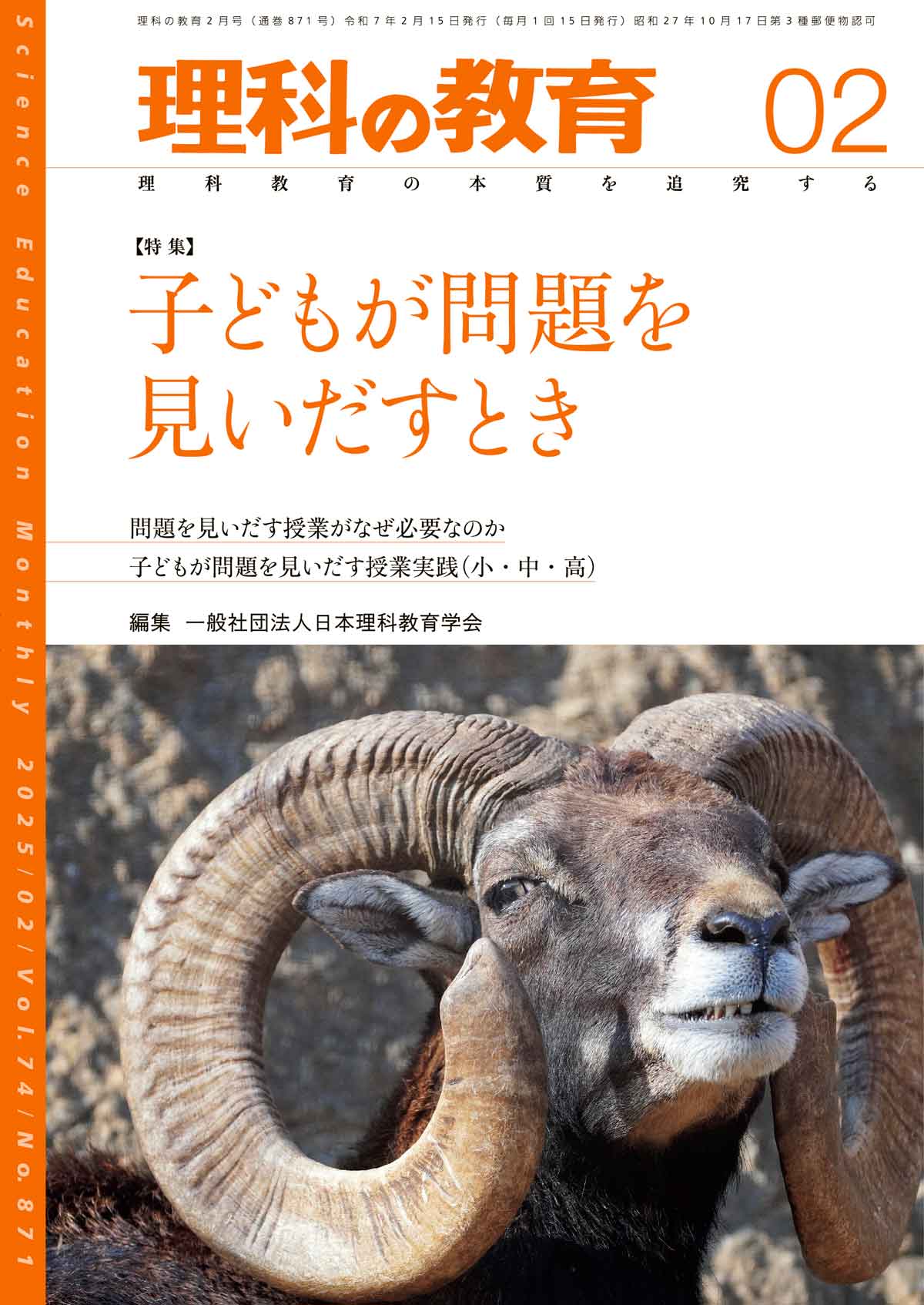令和7年2月号
通巻871号
2025/Vol.74
【特集】
子どもが問題を見いだすとき
■子どもが問題を見いだす授業がなぜ必要なのか
●子どもが問題を見いだすためにどこまで緻密に導入場面を考えるのか
-「注目」と「着目」で考え「導入場面の本質」を視覚化する「授業展開モデル」-
寺本 貴啓 5
●生徒はどのように問題を見いだすのか
-問題を見いだすきっかけと意欲の継続- 田代 直幸9
■子どもが問題を見いだす授業実践(小学校)
●やってみたいことを実現した先にある子どもの姿-第6学年「生物どうしのつながり・自然とともに生きる」- 中野 直人13
●「変数」に着目した問いを見いだす指導法
-変数を軸に体験活動から学習の文脈へと接続- 森川 大地16
●相互作用モデルから現象を捉える
-1人1実験から個別最適な学びの充実を目指して- 山口 義亮19
●自然に親しみ,問いを見いだす授業デザイン-第4学年「月と星」「ものの温度と体積」の実践を通して- 齋藤 照哉23
■子どもが問題を見いだす授業実践(中学校)
●中学気象単元での自己決定とメタ認知を活用して問題を表現化する指導
松本 浩幸26
●生徒が問題を見いだして課題を設定する授業づくり-中学校第3学年「遺伝の規則性と遺伝子」の実践を通して- 宮下 健太29
●中学校理科第3学年「運動とエネルギー」における課題設定
-ジェットコースターの設計を通じた課題設定- 藤本 博之33
●中学校理科でも実現可能な「問題を見いだす」学びの追究―自分の力で事象から問題を見いだし,探究可能な課題に変換する― 平澤 傑36
■子どもが問題を見いだす授業実践(高等学校)
●生徒が探究につながる疑問を見いだす授業の実践-実験結果の数値から疑問を生じる授業デザインの提案- 上村 礼子39
●高校生が問題を見いだすための教師の指導の工夫-通常の物理基礎及び物理の授業における電気に関する探究的な活動を通じて- 石川 真理代42
●生徒が問いを見いだすために何が必要か-疑問から問いへ変換する思考の順序性に基づく授業実践- 竹田 大樹45
連載講座
●『理科教育学研究』を授業に生かす
科学のテクスト読解による科学の学び
―小学校第6学年「燃焼の仕組み」の実践― 比樂 憲一 48
●生徒をひきつける観察・実験
ヒキガエルの幼生の血流,血球の観察 岡田 仁 50
●教材研究一直線
日本で南十字星を撮影する② 田中 千尋 52
●教材の隠し味
校庭の生物の観察「生物の声」~観察した生物になりきって
自己紹介,生物ミュージアムの開催~ 大久保 正樹 54
●Let’s Try!理科授業のDX
「1人1台端末」を活用して,「身近な樹木」と向き合う主体的な学びを!
縄 祐輔 56
●ダイバーシティ&インクルージョンを考える
日本語指導と教科教育の統合:外国ルーツの子どもたちの学びを支える方法
澤田 浩子 58
●概念構築を目指した探究型授業
~小学校4年生の電流の働きとの連結~豆電球の様子から
謎の4つの回路の配線を解明しよう「電流①」 荒尾 真一 60
●先生はサイエンスマジシャンNEXT
まさにエアコン!ゴム弾性の不思議 辻本 昭彦 62
会長候補者推薦について
63
オンライン全国大会案内
66
学会通信 68
次号予告 80
〈今月の表紙〉
ムフロン
学名:Ovis gmelini
偶蹄目ウシ科。
野生の羊の中では小型の種類。繁殖期になると,オスは大きな角をぶつけて争う。
表紙写真:片平久央
表紙・本文デザイン:辻井 知
(SOMEHOW)
Society of Japan Science Teaching
SCIENCE EDUCATION MONTHLY
2025/Vol.74/No.871
Occasions When Children Come Up With Good Questions
5 How Much Closely Should We Think of the Introduction Scene in Order For Students to Find Out Questions?
TERAMOTO Takahiro, Kokugakuin University, Tokyo
9 How Do Students Find Out Questions?: Clues to Coming Up With Questions, and Maintaining Interest and Motivation
TASHIRO Naoyuki, Tokoha University, Shizuoka
13 Children’s Behavior After Children Could Carry Out Something They Want to Try: “Making Connection Among Living Things, and Living With Nature” in 6th Grade
NAKANO Naoto, Elementary School Attached to Nara Women's University, Nara
16 Teaching Method of Finding Out Questions With Focus on “Variables”: Making a Connection, From Hands-on Activities To Learning Context, Centering on “Variables”
MORIKAWA Daichi, Nishitokyo Municipal Sakae Elementary School, Tokyo
19 To Grasp the Phenomena by Using Interaction Model: Aiming for the Promotion of Individually Optimal Learning From One Experiment Per Person
YAMAGUCHI Yoshiaki, Honden Elementary School, Osaka
23 Instructional Design For Children to Find Out Questions While Becoming Familiar with Nature: Practice of “Moon and Stars” and “Temperature and Volume of an Object” in 4th Grade
SAITO Teruya, Hiyoshi Elementary School, Kanagawa
26 The Use of Self-determination and Meta-cognition When Teaching the Weather Unit of Middle School Science
MATSUMOTO Hiroyuki, Iwamizawa Municipal Midori Lower Secondary School, Hokkaido
29 Lesson Planning For Students to Find Out Questions and Set Up Assignments: Practice of “Hereditary Regularity and Genes” in 9th Grade
MIYASHITA Kenta, Compulsory Education School Attached to Shimane University, Shimane
33 To Set Up the Assignment of “Motion and Energy” in 9th Grade: Setting the Assignment Through the Planning of Roller Coaster
FUJIMOTO Hiroyuki, Takenotsuka Lower Secondary School, Tokyo
36 Pursuit of Learning, For Students to “Find Out Questions” That Are Feasible Even on the Middle School Science Level: Students Manage to Find Out Question from Natural Phenomena By their Own Efforts, and to Transform Them Into Researchable Assignments
HIRASAWA Suguru, Iwate Board of Education, Iwate
39 Practice of Lessons, For Students to Find Out Questions That Lead to Inquiry-based Learning: Proposal of Instructional Design in Which Questions Arise From Values of Experimental Results
KAMIMURA Reiko, Tama Upper Secondary School, Tokyo
42 Improvement of Teaching, For High School Students to Find Out Questions: Inquiry-based Learning about Electricity in the Normal Classes of ‘Basic Physics’ and ‘Physics’
ISHIKAWA Mariyo, Toshima Upper Secondary School, Tokyo
45 What Is Needed For Students to Find Out Questions?: Educational Practices Based on the Sequential Order of Thinking Which Transforms Questions Into Problems
TAKEDA Hiroki, Keio Shonan Fujisawa Junior & Senior High School, Kanagawa
48 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom
50 Demonstrations to Attract Students
52 Hot Pursuit of Science Material Development
54 Tips to Spice up Instructional Materials
56 Let’s Try! DX in Science Lesson
58 To Consider Diversity and Inclusion
60 Inquiry-based Lessons Aimed at Constructing Conceptions
62 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>
目次英訳:柿原聖治
A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji