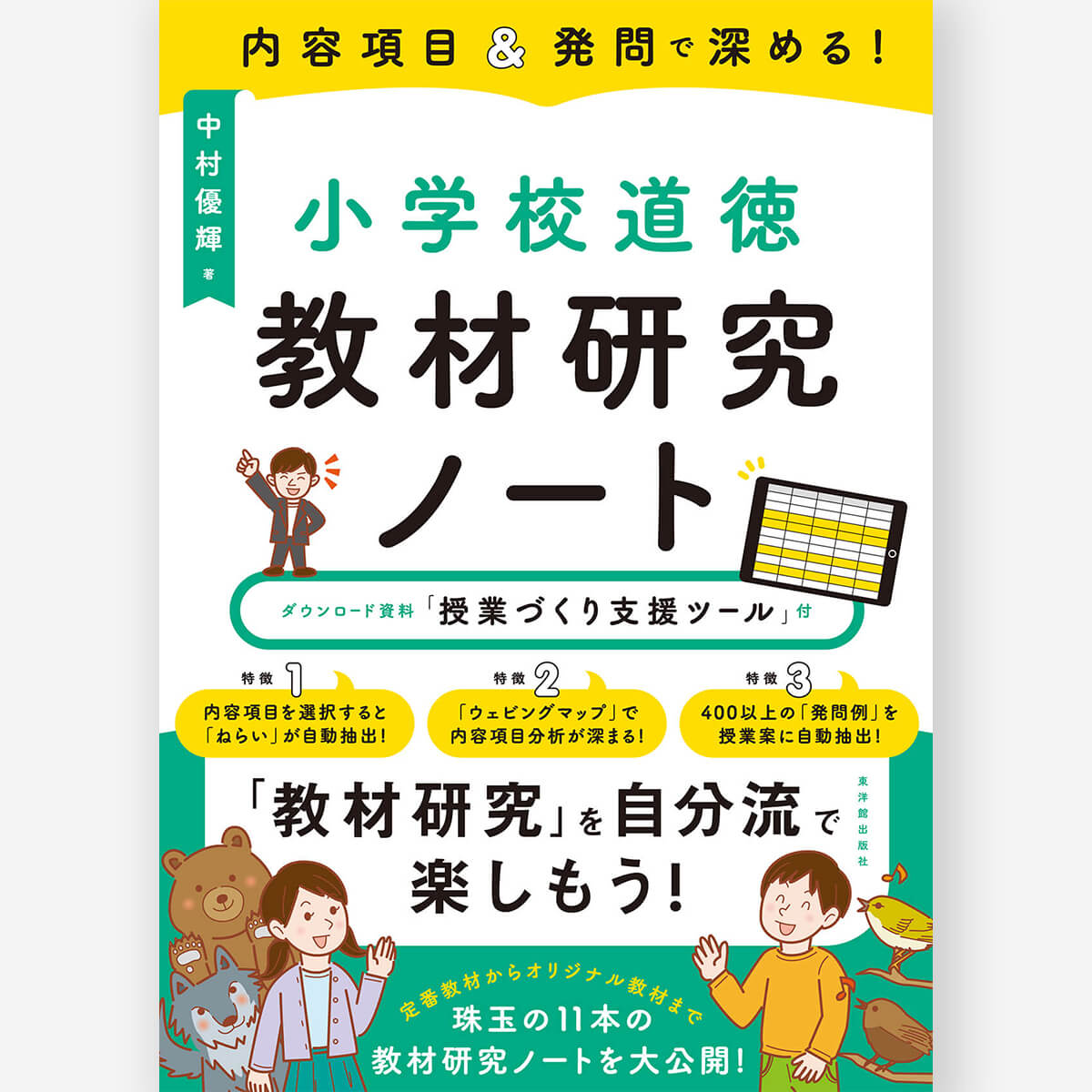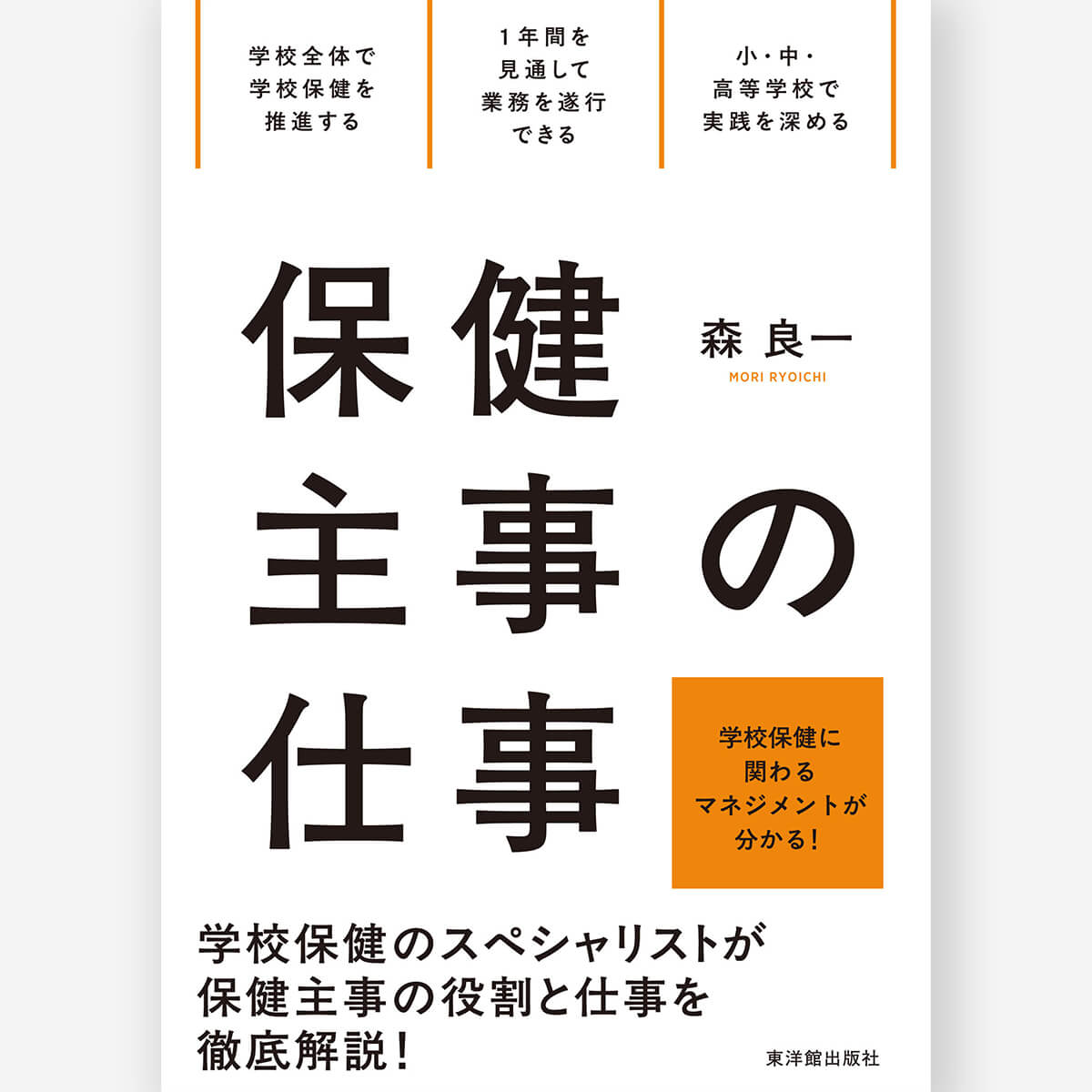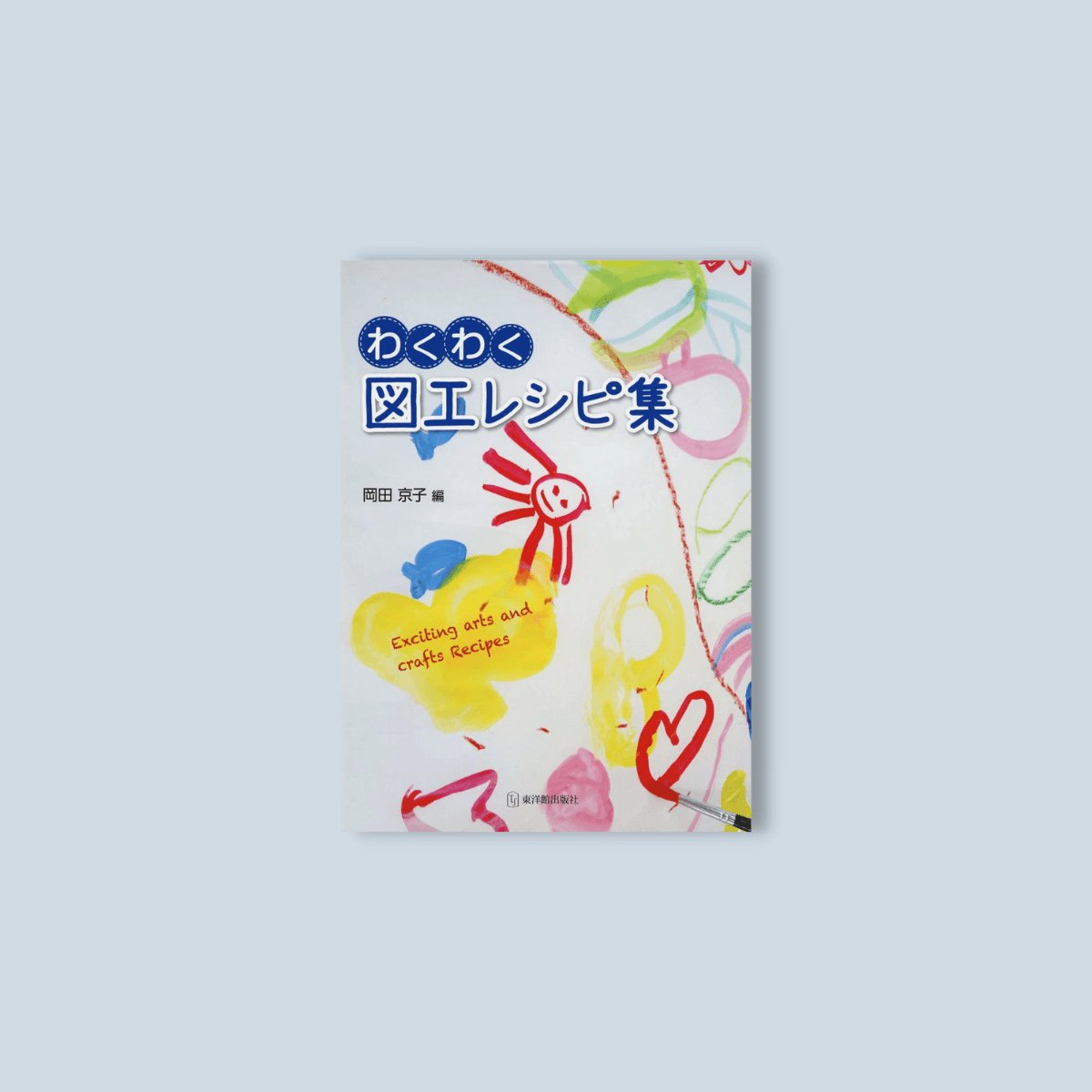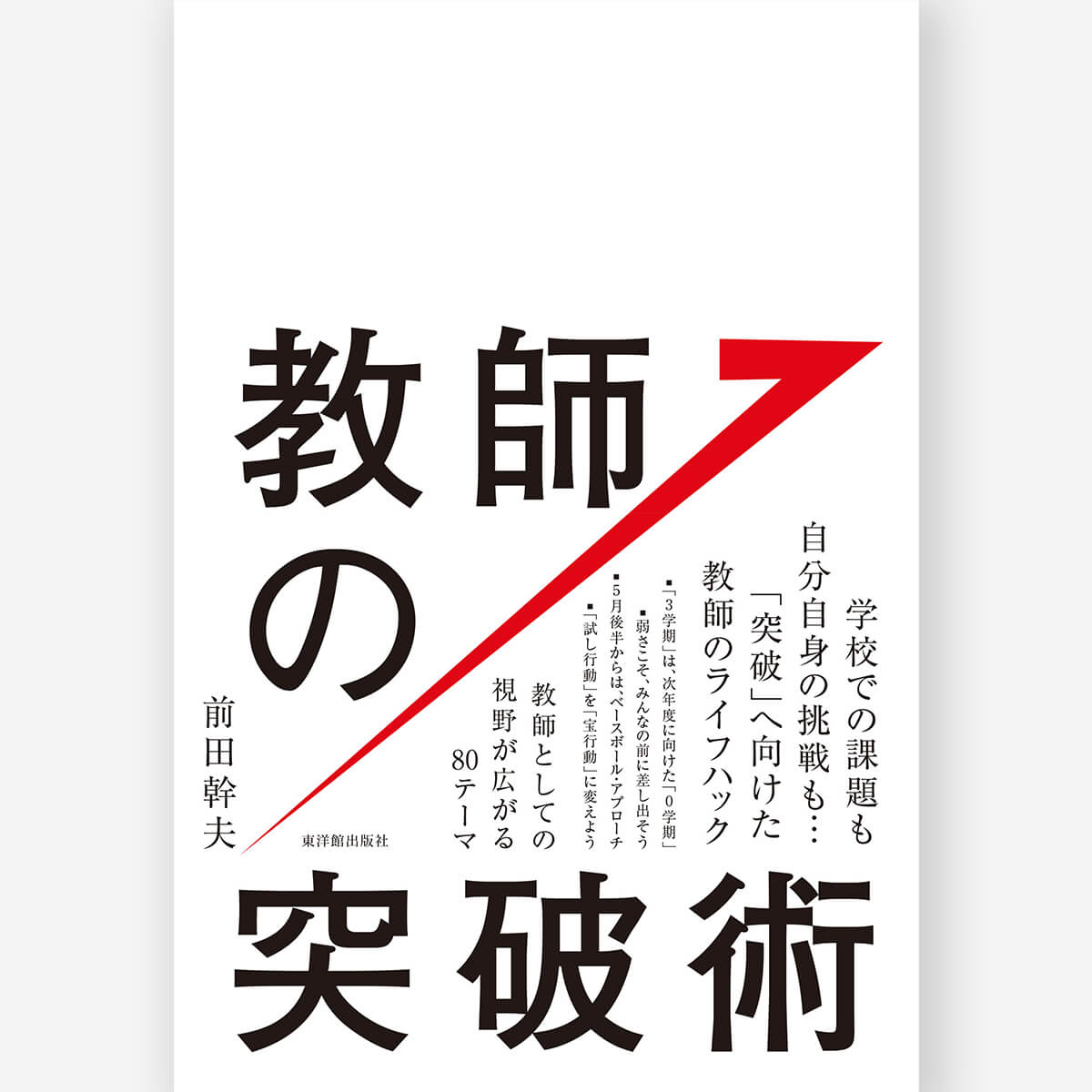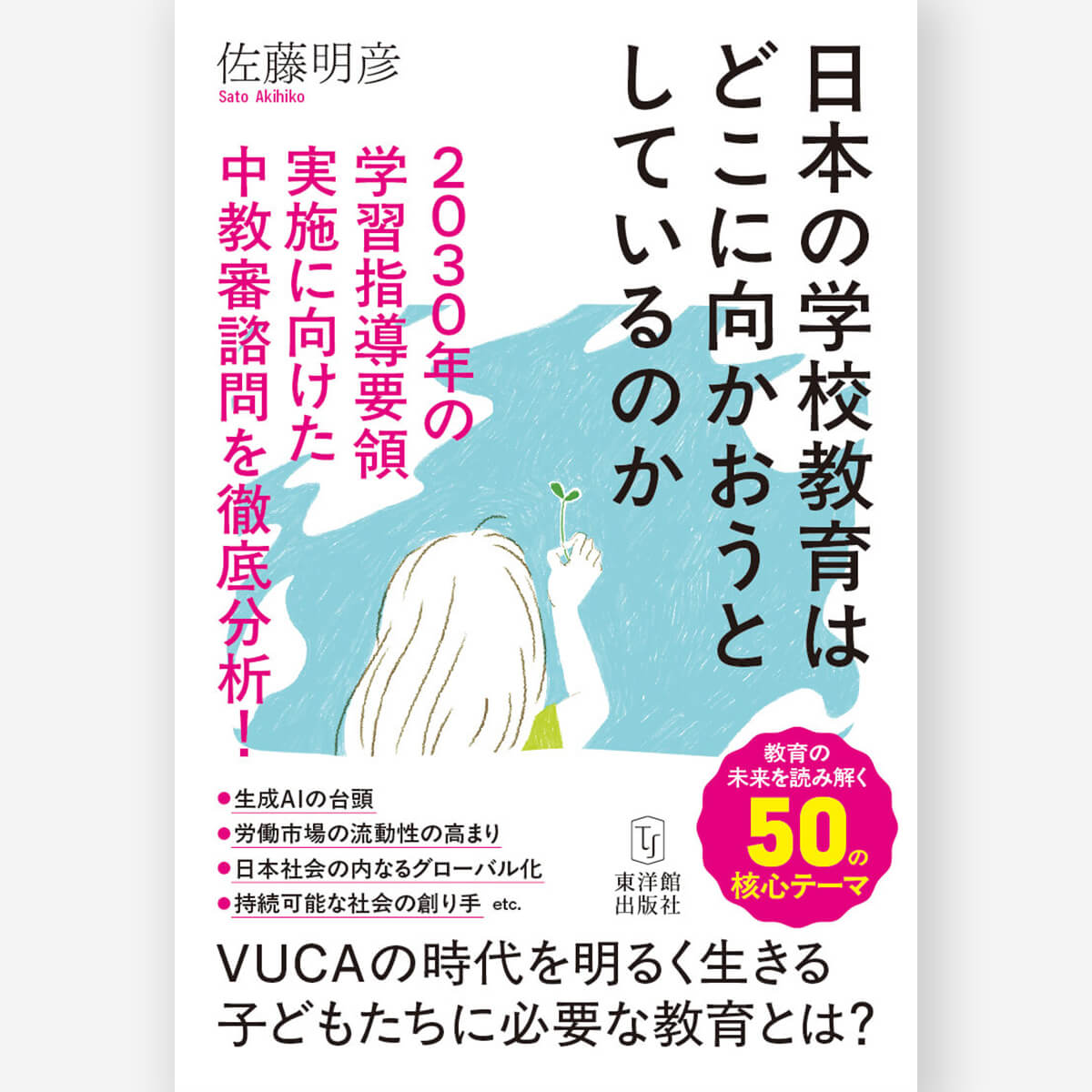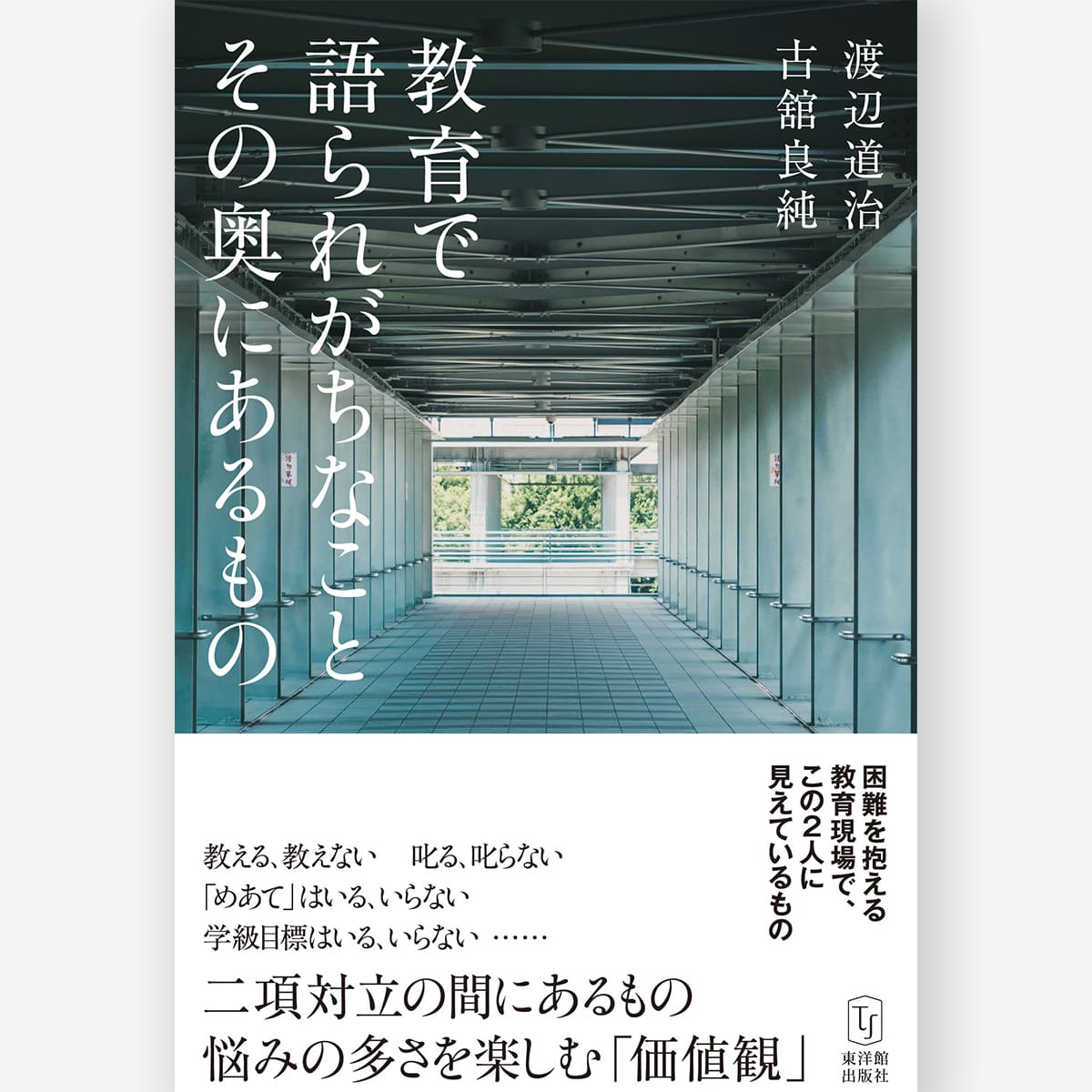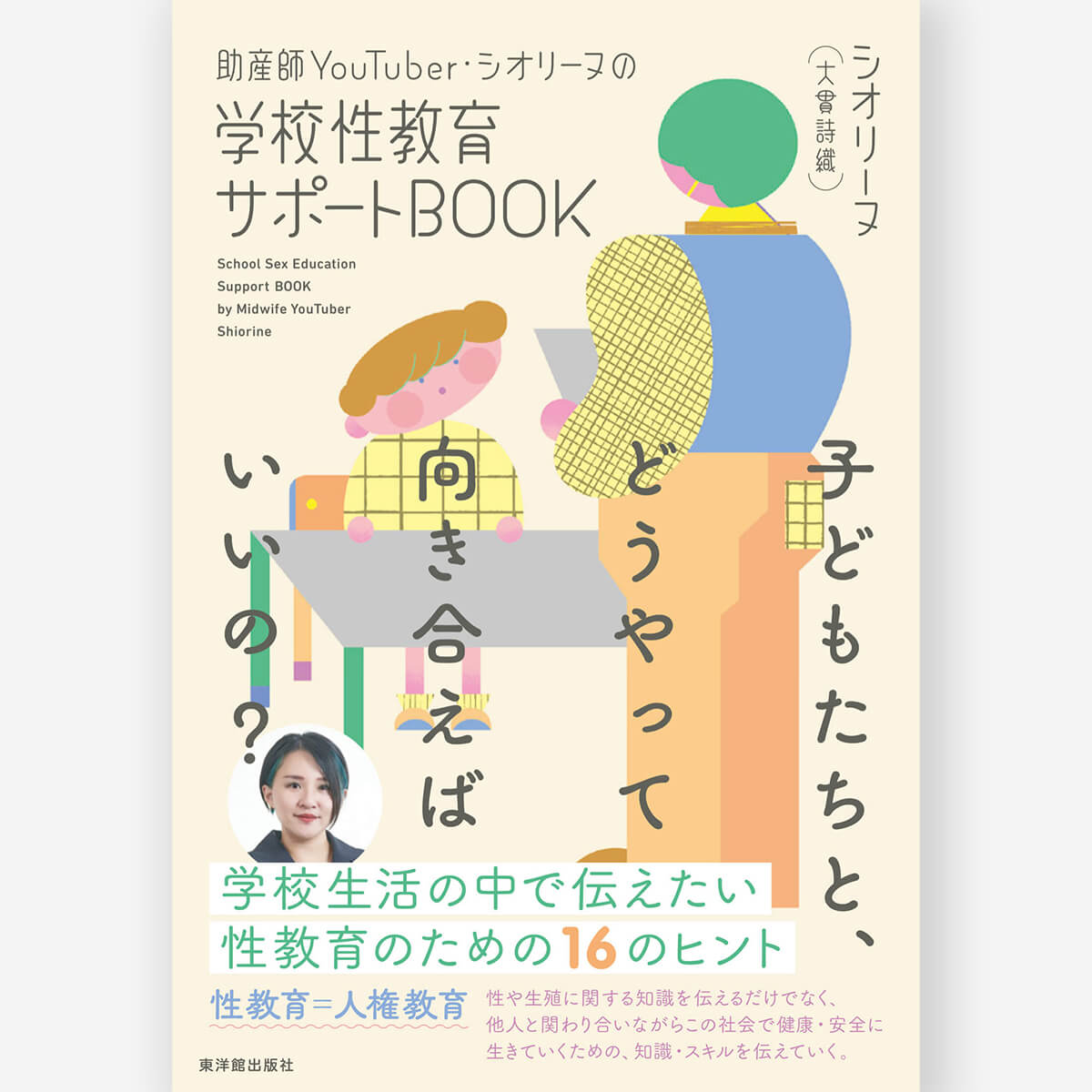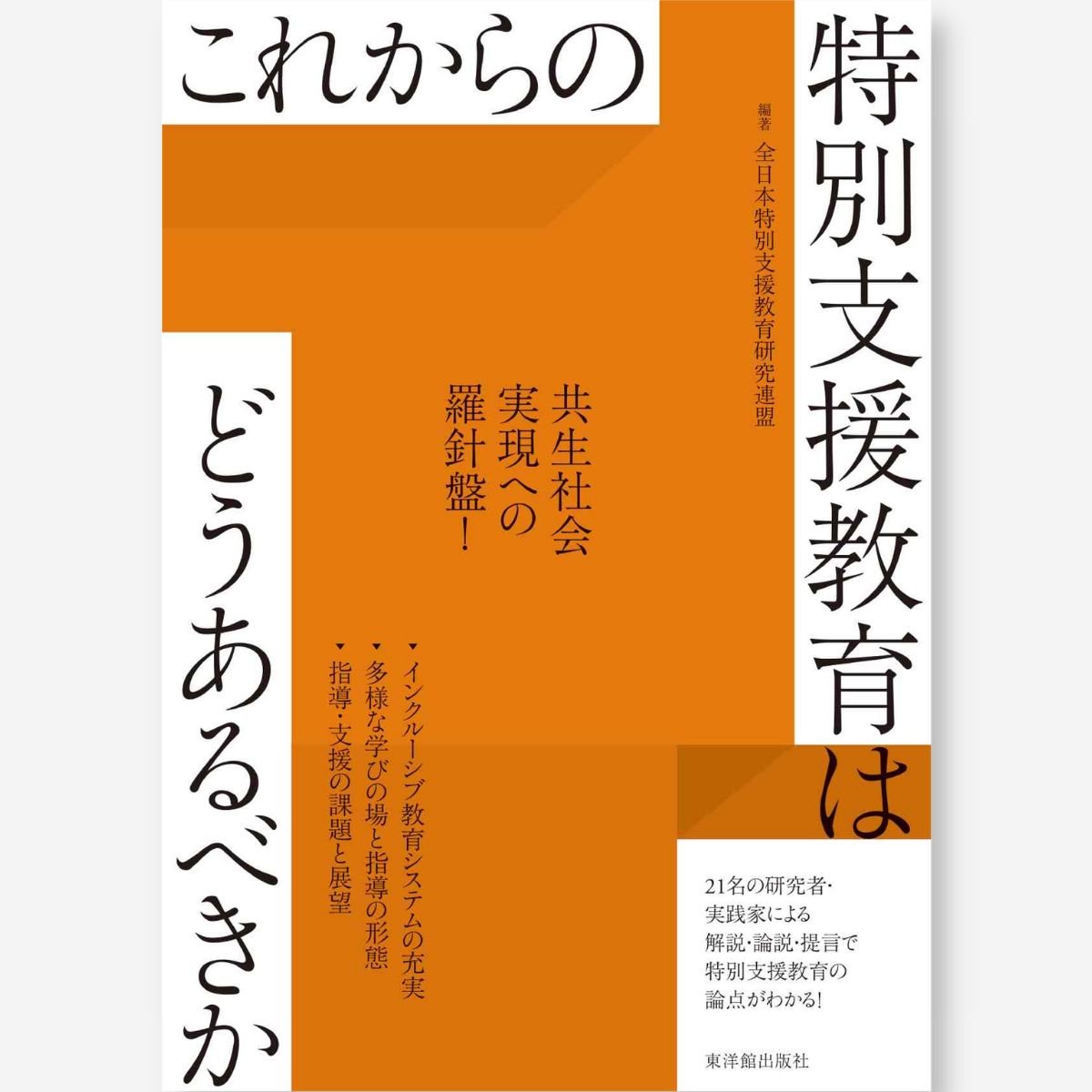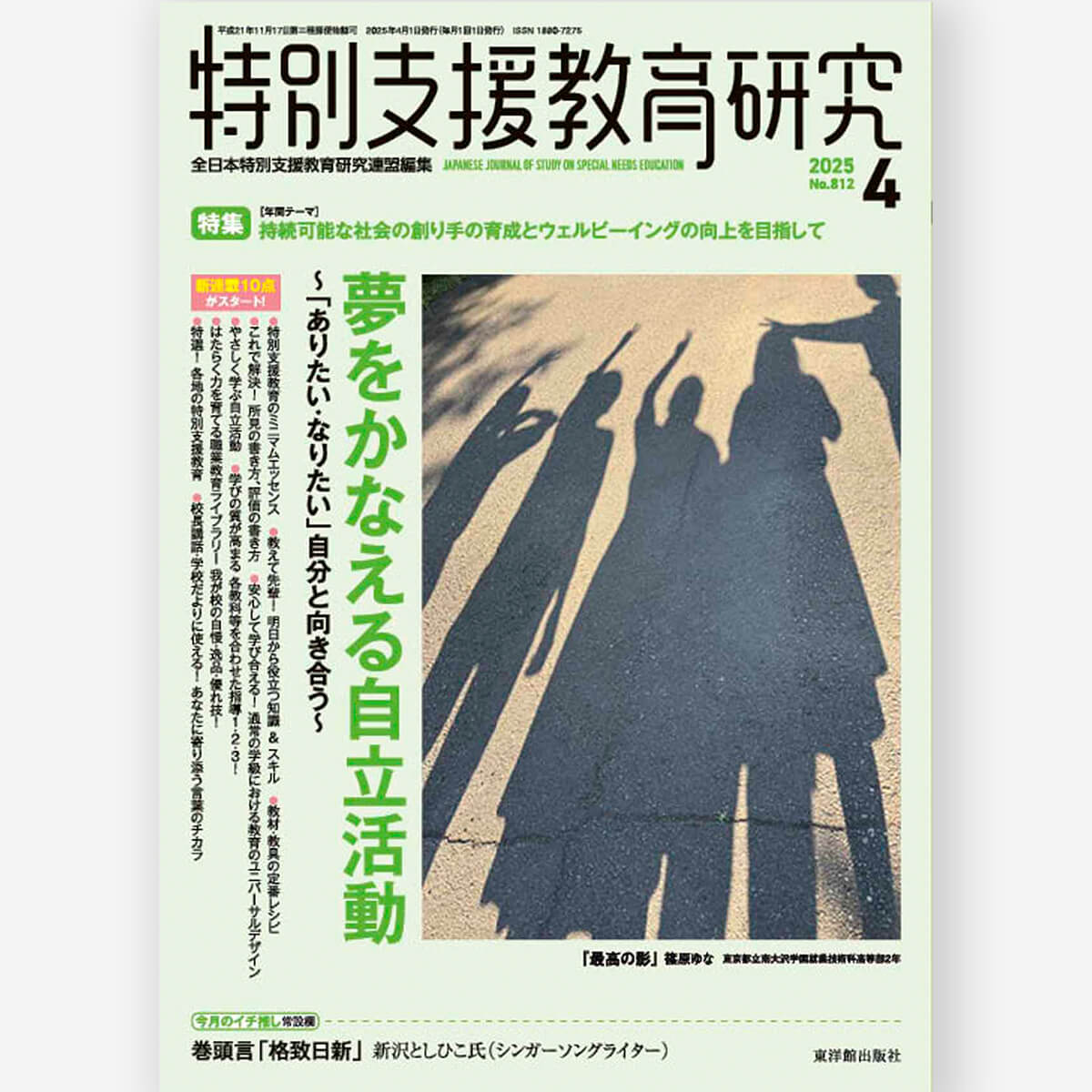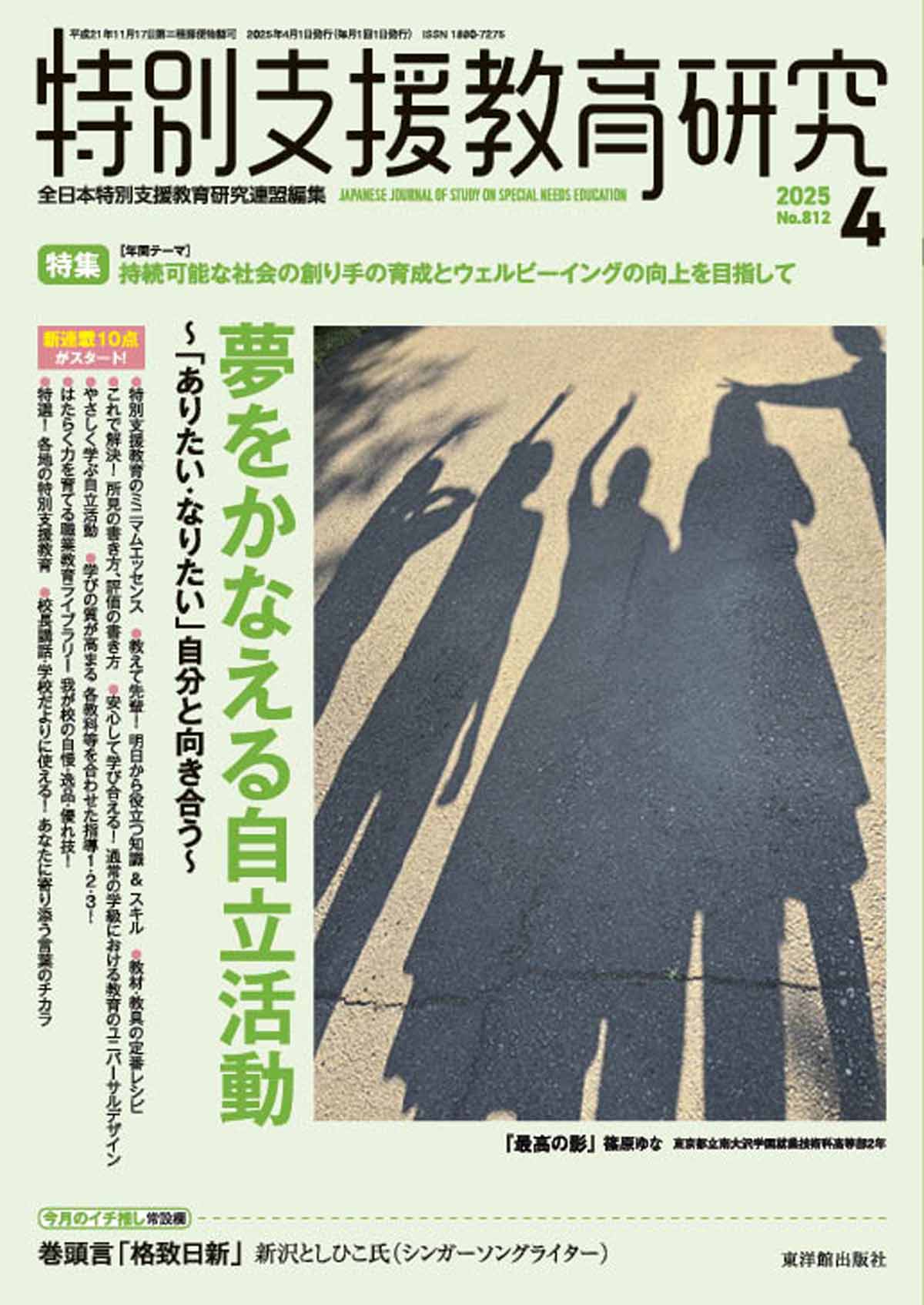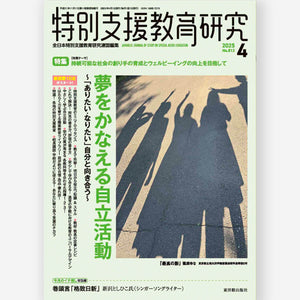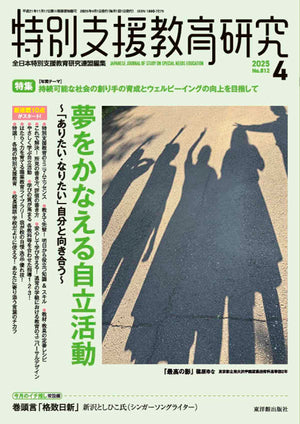レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
特集
夢をかなえる自立活動 ~「ありたい・なりたい」自分と向き合う~
本特集では、本人の「ウェルビーイング」や「ありたい・なりたい」という思いを大切にした「本人視点」から自立活動の指導の在り方について捉え直します。
近年、特別支援学校(知的障害)においても、自立活動の時間を週日課に位置付けて指導することが増えています。しかしながら、各教科等の指導において、自立活動の指導と密接な関連が十分に図られているとは言えない状況が散見されます。また、小・中学校の特別支援学級を含め、担当経験が浅い教員が増えており、自立活動の時間に「何をどのように指導してよいか分からない」という悩みもよく耳にします。
例えば、衝動性が強く、友達にすぐ手を出してしまうAさんがいたとします。その場合、Aさんには「衝動性を抑える」とか「問題と捉えている行動(以下、『問題行動』)を減らす」)ための指導が行われるでしょう。しかし、Aさん本人にしてみれば、「衝動性を抑えたい」とか「問題行動を減らしたい」とは思っていないかもしれません。本人視点に立つと、「本当は友達と仲よくしたい。でも、つい手を出してしまう」と思っているのかもしれません。
指導方法に着目すると、「手を出さないようにするためにはどんな技法が有効か」「問題行動を減らしていくためには、どのような指導計画が必要か」という考え方になりますが、それだけでは、自立活動が「子ども」ではなく「教師」が主語として進められることになります。しかし、自立活動の趣旨から考えると、「本当は友達と仲よくしたい」というAさんの願いを重視します。それこそ、「ウェルビーイング」や「ありたい・なりたい」自分の実現のためにも大切なことなのではないでしょうか。
自立活動においては、学んだことを各教科等の学習で生かすことや、学びの必然性を踏まえることなど、いわゆる「カリキュラム視点」が必要であり、何よりも「本人視点」に立って自立活動の指導を捉え直すことが不可欠です。本人視点とは、「ありたい・なりたい」という思い、そして本人にとっての「必要性」です。特別支援学校学習指導要領の「個別の指導計画の作成と内容の取扱いにおける留意事項」には、「興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうとともに自己を肯定的に捉えることができるような指導内容」「自己選択・自己決定する機会」「思考・判断・表現する力を高める指導内容」「学習の意味を将来の自立や社会参加に必要な資質・能力との関係において理解し、取り組めるような指導内容」の必要性を挙げており、自立活動の指導はまさに「自分ごと」の学びが重要であることが指摘できます。
以上を踏まえ、本特集では「どのような子どもの願いがあったのか」「どのようにして子どもの願いを捉えたのか」「どのように子どもが変容したのか」ということに視点を置いた事例を紹介し、自立活動の指導について再考する機会とします。

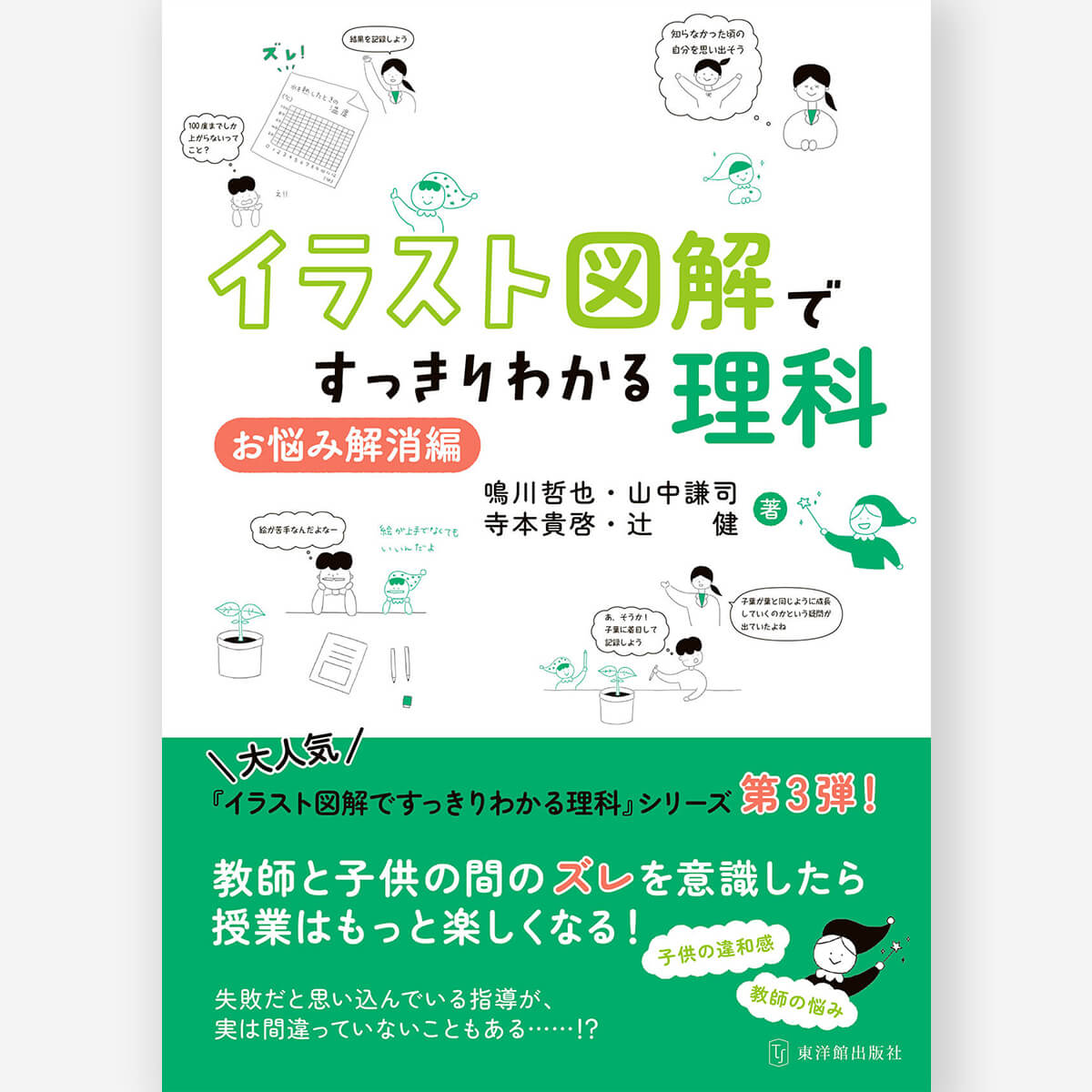
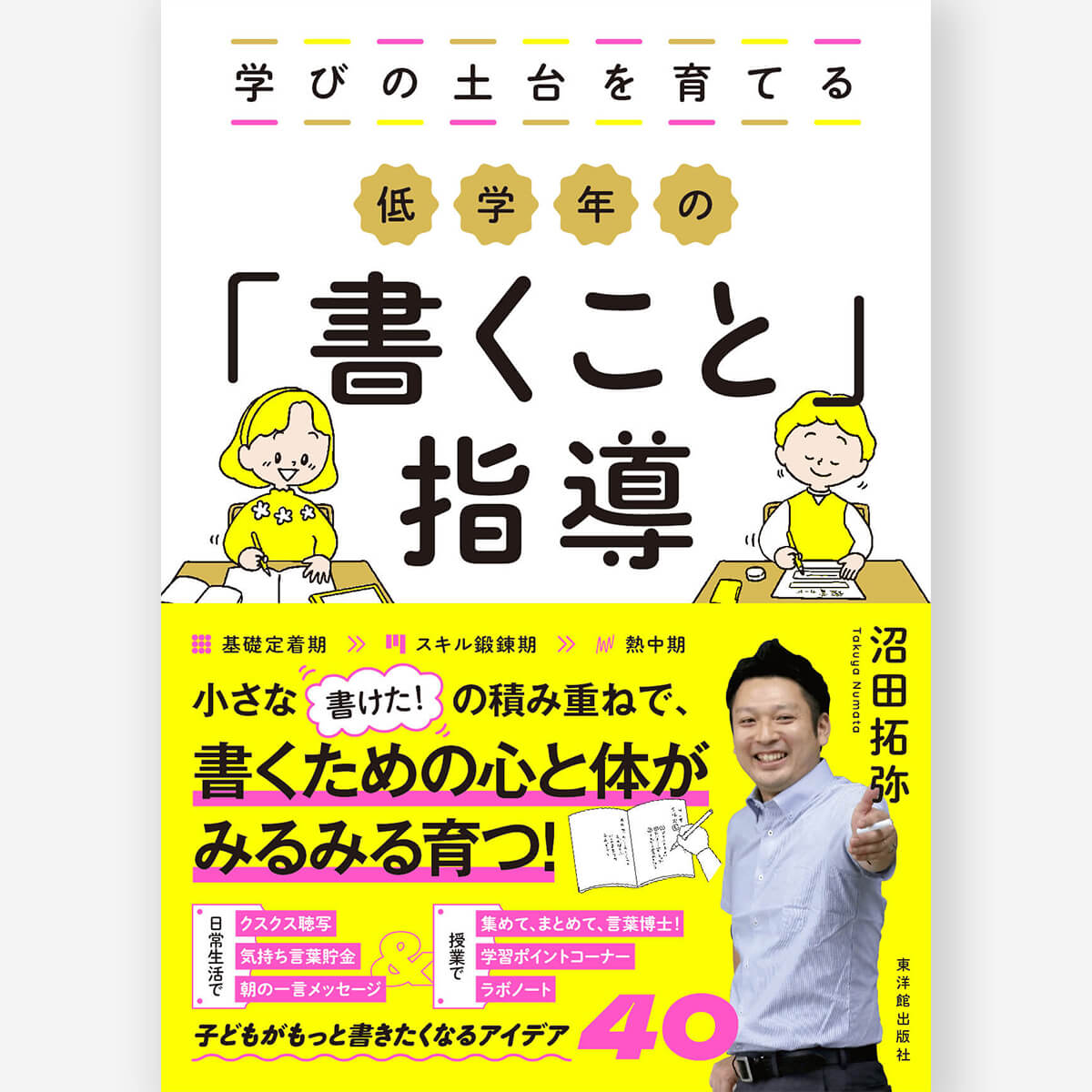
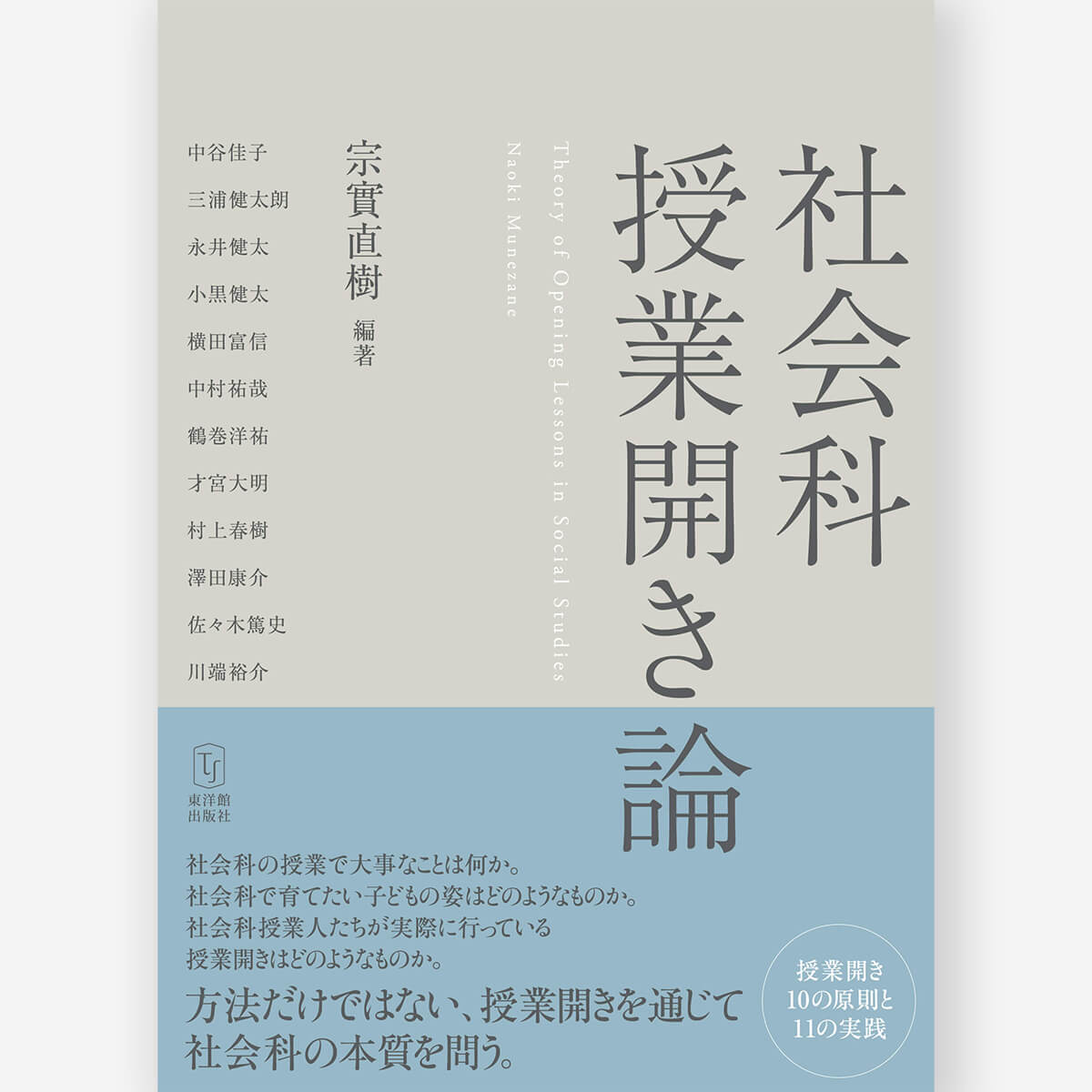
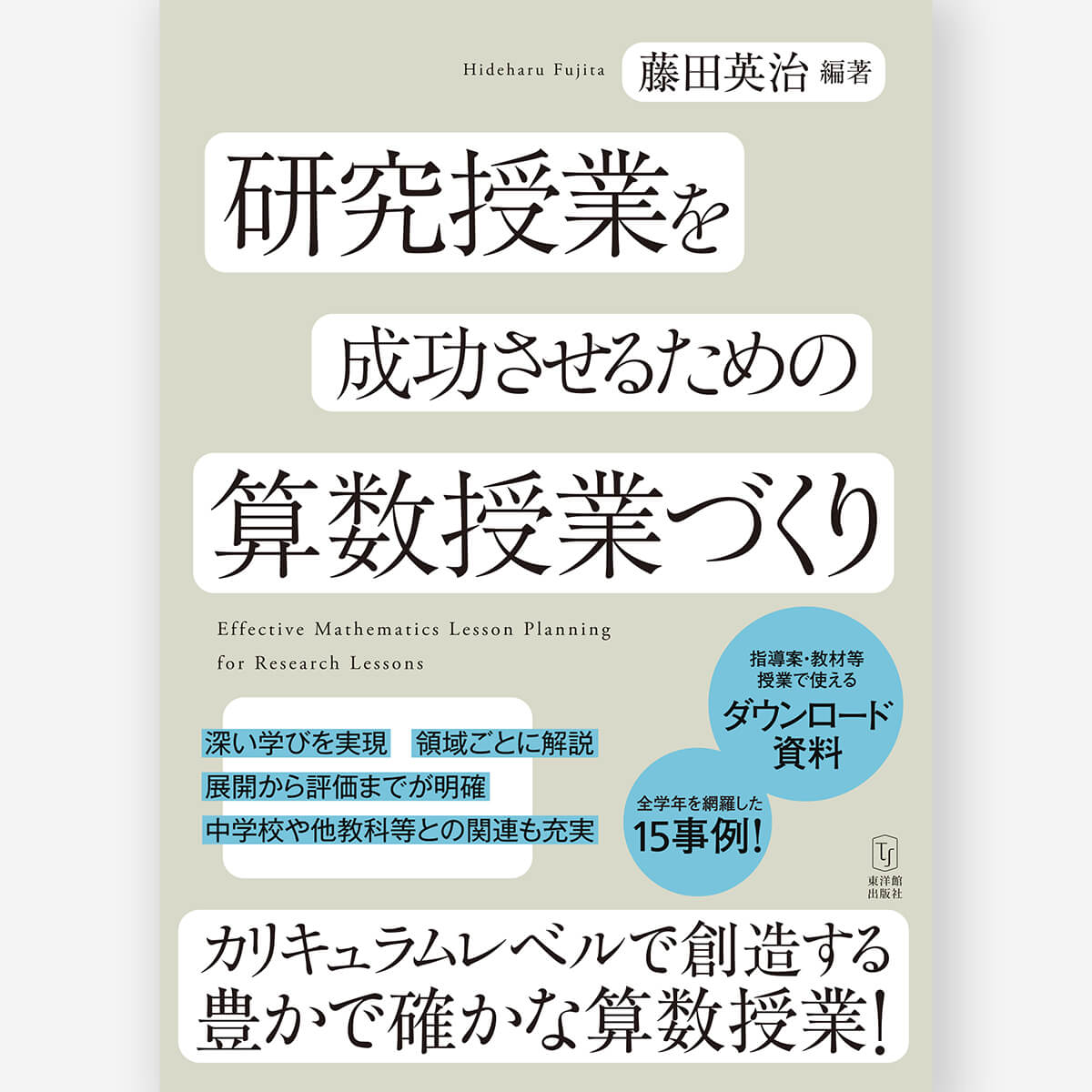
![[小中英語]学習者用デジタル教科書を活用するために知っておきたいこと―子どもを“真ん中”にした授業をつくる! - 東洋館出版社](http://www.toyokan.co.jp/cdn/shop/products/product-203055.jpg?v=1708564599&width=1200)